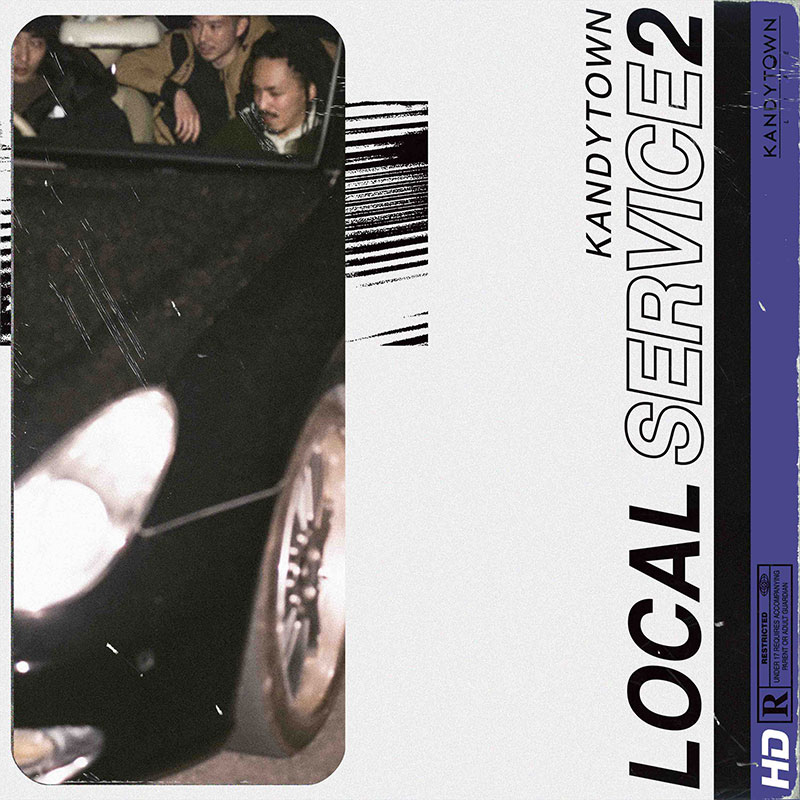現在はLAに暮らすラッパー、2010年代前半にいわゆるクィア・ラップの道を切り拓いた先駆者、ミッキー・ブランコが久しぶりに作品をドロップしている。『Broken Hearts & Beauty Sleep』と題されたミニ・アルバムで、レーベルは〈Transgressive〉、エグゼキューティヴ・プロデューサーとしてフォルティDLが関わっているようだ(シングル曲 “Free Ride” はフォルティとハドソン・モホークがコ・プロデュース)。アルバムとしては2016年の『Mykki』以来のリリースとなる。
だいぶポップに振り切れた印象で、ゲストもブラッド・オレンジなど豪華な面々が招かれている。70年代のクワイエット・ストーム(スムースなソウル。スモーキー・ロビンソンのアルバム名に由来)やクロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングからインスパイアされたそうだ。ミッキー・ブランコの新たな挑戦に注目を。
ラッパー、詩人、トレイルブレイザーのミッキー・ブランコが5年振りとなるオフィシャル作品をリリース。
フォルティDLのプロデュースによる9曲入りのミニ・アルバム『ブロークン・ハーツ・アンド・ビューティ・スリープ』、トランスグレッシヴより発売。
●ゲスト:ブラッド・オレンジ、ビッグ・フリーディア、カリ・フォー、ジャミーラ・ウッズ、ジェイ・キュー、ブルーノ・リベイロ他

2021.10.6 ON SALE
■アーティスト:MYKKI BLANCO(ミッキー・ブランコ)
■タイトル:BROKEN HEARTS AND BEAUTY SLEEP(ブロークン・ハーツ・アンド・ビューティ・スリープ)
■品番:TRANS522CDJ[CD/国内流通仕様]
■定価:¥2,400+税
■発売元:ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ
■収録曲目:
1. Trust A Little Bit (God Colony Version)
2. Free Ride
3. Summer Fling (feat. Kari Faux)
4. It's Not My Choice (feat. Blood Orange)
5. Fuck Your Choices
6. Love Me (feat. Jamila Woods and Jay Cue)
7. Want From Me (feat. Bruno Ribeiro)
8. Patriarchy Ain't The End of Me
9. That's Folks (feat. Big Freedia)
Mykki Blanco - "Free Ride" (Official Video)
https://youtu.be/Nbcjzaa75PI
Mykki Blanco - "Summer Fling" feat. Kari Faux (Official Visualizer)
https://youtu.be/MTY2nNQTZ7Y
Mykki Blanco - "It's Not My Choice feat. Blood Orange" (Official Music Video)
https://youtu.be/ul6j69EFjhU
Mykki Blanco - "Love Me" (Official Audio)
https://youtu.be/ZR_OweYhT-U

●ラッパー、詩人、トレイルブレイザーであるMykki Blancoは、デビュー・アルバム『Mykki』以来、5年振りとなるオフィシャル作品をリリースする。この9曲入りのミニ・アルバム『Broken Hearts and Beauty Sleep』は、Transgressive Recordsとの契約の一環としてのリリースとなり、FaltyDLがプロデュースを担当。スペシャル・ゲストとしてBlood Orange(Dev Hynes)、Big Freedia、Kari Faux、Jamila Woods、Jay Cue、Bruno Ribeiro等がフィーチャーされている。アルバムには、微妙なニュアンスを持ったジャンルをまたぐ楽曲が収録され、経験と成熟を持つ人間の反射的な知恵が示唆されている。ここでは、アーティストとっての新たな時代の到来を導き入れながら、人生と愛を念頭に置くだけではなく、これまで以上に大きな個人的なギャンブルが打たれている。
●Mykki Blancoはアメリカのラッパー、詩人、パフォーマー、活動家だ。2012年にEP「Mykki Blanco & the Mutant Angels」でデビュー。「Betty Rubble: The Initiation」(2013年)、「Spring/Summer 2014」(2014年)と2枚のEPを経て、2016年9月にデビュー・アルバム『Mykki』をリリース。クィア・ラップ・シーンのパイオニアとして知られ、Kanye WestやTeyana Taylor等とコラボレート。MadonnaのMVへ出演し、Björkとツアーを行なったりもしている。
More info: https://bignothing.net/mykkiblanco.html