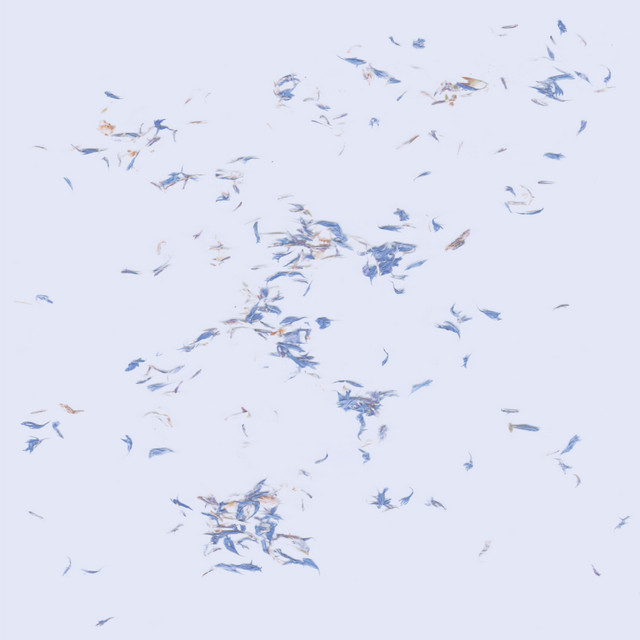MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Sound Patrol > 10 Selected Ambient / Downbeat Releases in 2020

2020年のほとんどを、僕はロンドンの自分のフラットで過ごした。コロナ禍による二回に及ぶロックダウン(都市封鎖)や、それに準ずる段階的外出規制によって、イギリスに住む者の行動はかなり制限されていた。2月までクラブやライヴ・ヴェニューへ行っていたのが別の世界の出来事のように感じられるほど、自分の生活スタイルも変わった。運動のため頻繁に外出するようになったり、自転車で遠出するようになったり、人混みへ注意を払うようになったり。自分が4年ほど住んでいる街を違った視点から見る機会が増えた。
今年自分が聴いてきた音楽を振り返ってみると、ダンス・ビートよりも、アンビエントやダウンビートと呼ばれる作品が多い。変わりゆく周囲の環境と自分との関連が放つ何かを理解するうえにおいて、頭やケツをバウンスさせる運動神経よりも、隙間がある音に消えていく感覚の方が研ぎ澄まされていくのかもしれない(と言いつつも、年末の紙エレで選んだエレクトロニック・ダンスたちには心底感動させてもらった。アンズのNTSレディオでのヘッスルオーディオ・スペシャルセットを聴くといまも涙が出そうになる)。
というわけで、今回のサウンド・パトロールは、いわゆるダンス系ではないものを10作品選んだ。もちろんここに載っていない素晴らしい作品もたくさんある。これは自分の独断で選んだ作品リストに過ぎないが、2020年という音楽シーンである種の停止ボタンが押された一年とはなんだったのかを振り返るきっかけになれば幸いである。2年前と同様にフィジカルで持っているものを中心に選び、以下、テキストと写真とともに掲載する。
Kali Malone - Studies For Organ | Self-Released

アメリカはコロラド出身で現在はストックホルムに拠点を置くパイプオルガン奏者、電子ミニマリスト、カリ・マローンの去年出たサード・アルバム『The Sacrificial Code』は、非常に多くの関心をひいた。この自主リリースされたカセット作品『Studies For Organ』は、去年作品のリハーサルとしてレコーディングされたもので、2017-18年の間にストックホルムとヨーテボリで録音されたと帯にはある。再生してみて驚いたのが低音の力強さである。その屋台骨の上でミニマルに展開されるメロディーは、スザンヌ・チャーニらシンセシストたちが描いてきたサウンドスケープと重なる部分があるかもしれない。不断なく動いていた旋律が変化をやめて持続のみに切り替わるエンディングに息を呑んだ。サラ・ダヴァチやカラーリス・カヴァデイルの活躍を鑑みるに、現代の電子音楽シーンにおけるパイプ・オルガンの存在感は増している。この「呼吸をしない怪物」が現在においてサウンドに内胞しているものを感じる機会が今後も増えていくのかも。
Alex Zhang Hungtai & Pavel Milyakov - STYX | PSY Records

まさかのコラボレーションである。LAのサックス奏者、アレックス・チャン・ハンタイ(aka ダーティ・ビーチズ)とモスクワの電子作家、パヴェル・ミリヤコフ(aka バッテクノ)がタッグを組み、後者が今年新設したレーベル〈PSY X Records〉からリリースされたのが、このアンビエント作品『STYX』だ。フォーマットはカセット(とデータ)で、テープはモスクワのミリヤコフから直接届いた(彼は今作のミックスとマスタリングも手掛けている。ミリヤコフは自身のプロダクション技術をサブスクライバーに提供する試みも最近スタートした)。オクターバーなどのエフェクターを駆使したミリヤコフのギターとAZHのサックスが、朝焼けのような美しいテクスチャーを生んでいる。モジュラー・シンセが作り出すアグレッシヴなグリッチとサックスの掛け合いなどもあり、単なるアンビエント作品の範疇にもとどまっていない。半透明の青いケースに包まれたカセット・ケースのデザインも秀逸。化学記号のようなシンプルなタイトルは、音の物質性へとリスナーを誘い込む。
Lisa Lerkenfeldt - A Liquor of Daisies | Shelter Press

オーストラリアはメルボルンを拠点に活動するリサ・ラーケンフェルドは、自身のデビュー・アルバム『Collagen』を、バルトローム・サンソンとフェリシア・アトキンソンが率いる〈Shelter Press〉から今年の8月に出していて、6月に先行する形で同レーベルからカセットでリリースされたのが今作『A Liquor of Daisies』である。アルバムは持続するシンセ、金属的テクスチャー、ディストーション・ドローンなど、手法面で多彩。それに対して、このテープ作は同じピアノのモチーフをループ+電子音というシンプルな構成ではあるものの、モチーフを変調させて驚きを生み、分厚い壁から高原を吹き渡る風のような音へと徐々に変化するエレクトロニクスが、39分48秒を永遠へと変化させる。この呼吸の長さが、LPよりもこのアルバムを特別なものにしている。ジャケットには「ゼロクライサム・ヴィスコサムへの詩、永遠のデージー(註:両方ともオーストラリアの花)、多様な祈る者たちと機械のためのプロポーザル」とある。なお、このカセットのバンドキャンプでの売り上げのすべては、ブラック・ライヴス・マター運動の一環として、オーストラリアのアボリジニ支援団体へと寄付された。
Jon Collin & Demdike Stare - Sketches of Everything | DDS

2月、僕はロンドンのカフェ・オトで二日に渡って行なわれたデムダイク・ステアのライヴへ行った。そのときのライヴ・リハーサルがカセットになった『Embedded Content』が素晴らしいというのは、別冊紙エレの家聴き特集でも書いた。その次の彼らのリリースになったのが、このランカシャー出身で現在はスウェーデンに拠点を置くギタリスト、ジョン・コリンとのコラボレーション作品『Sketches of Everything』で、さらに連作となる形でカセット『Fragments of Nothing』も出た。フォークやブルースを電子的に自由解釈したコリンのギターを、DSがリヴァーヴやエコーで空間にちりばめ、それがフィルターでねじ曲げられ、カモメの音が遠くへと運んでいく。ジャケットにはコリンの家族写真アーカイヴが借用されていて、ある種、記憶がテーマになっていることは間違いない。ここには憑在論的ホラーではなく、「ああ、昔こういうことがあったよね」という単純な回想が音になっている優しさがある。冒頭10分のなんと綺麗なことだろうか。
Pontiac Streator - Triz | Motion World

ポンティアック・ストリーターはフィラデルフィアを拠点に抽象的なビートとアンビエントを世界にドロップしている。その生態はアンダーグラウンドに潜っているため、サブスクにはコンピ参加以外作品がなく、流通が少ないレコードかバンドキャンプでその作品にアプローチするしかない。他にもいくつかグループでの名義があり、『Tumbling Towards A Wall』という傑作を今年発表した同じくフィラデルフィアのアンビエント作家ウラ・ストラウスとはアルバム『11 Items』を去年リリースしている。今作『Triz』はソロとしては2作目のアルバムにあたる。彼の作るビートは、LAのようにコズミックではなく、ロンドンのようなハードなホットさがあるわけでもなく、そのアンビエンスはベルリンのようにダークでグリッチィでもない。彼は自分の音を持っている。リズムはアメーバのように俊敏さ柔軟さを兼ね備え、ベースは鼓膜に息を吹きかけるように流れ、ベリアルのようにどこかから採取された音声が滑らかにこだまする。最後の曲名は “Stuck in A Cave” であり、抜けられない洞窟にいるものの、鳥の声が聞こえてくる。困難にいるときでも、想像力は外に向くことができる。ここには希望がある。
Experiences Ltd.

ベルリン拠点のプロデューサー、シャイ(Shy)はスペシャル・ゲストDJやフエコSとのゴースト・ライド・ザ・ドリフトなどの名義で活動している。彼は〈bblis〉や〈xpq?〉のレーベルを通して、いわゆるアンビエントやダウンテンポという既存ジャンルの両地点の間を漂う楽曲を紹介してきた。それに加えて彼が2019年に開始した〈Experiences Ltd.〉は、今年に入り、頭一つ抜けた力作を続々とリリースした。フィラデルフィアのウラ・ストラウスのウラ名義『Tumbling Towards A Wall』は、テープ・ループで劣化してくような淡いベールに包まれたテクスチャーを、ピアノなどのサウンド・マテリアルのループや重低音で色づかせ、3~5分ほどの長さの楽曲で8つの異なる光景を描いた傑作である。彼女がベルリン拠点のペリラ(Perila)と組んだログ(LOG)はよりクリアなテクスチャーのもと、肉声などを取り込み、異なる角度から静寂へとアプローチ。他にレーベルからは、ニューヨークのベン・ボンディや、日本のウルトラフォッグも参加しているプロジェクト、フォルダー(Folder)といったトランスナショナルな人選が続いている。2020年最後のリリースになったカナダのナップ(Nap)による7インチ「Íntima」は、90年代のアブストラク・ビートがよぎるなど、レーベルが今後もそのカタログを変形させていく可能性を示唆している。なお、レーベル・リリースのマスタリングの多くを手掛けているのは、デムダイク・ステアのマイルズ・ウィテカー。
Vladislav Delay | Bandcamp Subscription

今年僕が最も聴いたプロデューサーはヴラディスラフ・ディレイことサス・リパッティである。〈Chain Reaction〉諸作をコンパイルした『Multila』のリマスター、ソロ作『Rakka』とスライ&ロビーとの『500-Push-Up』、マックス・ローダーバウアーとの『Roadblocks』、ルオモ名義の『Vocalcity』リマスターなど、力強いリリースが今年は続いた。いま、彼はバンドキャンプで自身の作品のサブスクリプション・サービスを行なっている。この機会に彼のキャリアを聴き込んでみようと思い、僕は現在それをサブスクしている。月10ユーロでVD名義の作品ほとんど全てが非圧縮音源でダウンロードできるうえ、サブスク限定の音源発表も毎月ある。フィンランドの孤島に建つスタジオで、グリッチ・ノイズからフットワークにいたるあらゆる音像を、毎朝早起きしてリパティはせっせと作り、自然とジャズ、読書からインスピレーションを受けている(まるで村上春樹である)。あるインタヴューによれば、リパッティはオシレーターとフィルターでできることの限界に早い段階で気づいたらしい(といっても充実したユーロラックのセットを使用している)。そして向かったのはダブである。その可能性をミュージック・コンクレートやテクノ以外のリズムへ切り開いた点において、彼は当初つけられたベーシック・チャンネル・フォロワーという枠を超えて自身のスタイルを確立した。改めて、すごい作家である。グリッチの空間化を極めた『Anima』(2001)と高揚感溢れるリズム&サウンドの “Truly” のリミックス(2006)は同じ宇宙に存在しえるのだ。
Suzanne Ciani - A Sonic Womb: Live Buchla Performance at Lapsus | Lapsus Records

ブクラ・シンセサイザーを駆使し、電子音楽からピンボールの効果音に至るまで、70年代から歴史的な仕事をしてきたシンセシスト/作曲家、スザンヌ・チャーニ。彼女の昨今の電子音楽シーンにおける再評価は、デザイナー/DJ、アンディ・ヴォーテルが共同設立者に名前を連ねる〈Finders Keepers〉からの2016年作『Buchla Concerts 1975』にはじまる。それ以降、彼女はブクラ200eを抱え世界をツアーし、コンサートとトークによる教育を通し、いまもなお音を合成する意義を説いている。今作は2019年のバルセロナでのコンサートの録音であり、70年代にチャーニが使用していたシーケンサーを発展させた即興演奏を聴くことができる。往年のチャーニ作品で使われているアルペジエーターの旋律が、ステレオの左右を拡張せんとばかりに旋回し(オリジナルは左右ではなく四方の異なるスピーカーを使用したクアドロフォニック)、スネア化した短波ノイズが連打されるとき、客席から歓声が上がる。今作の開始と終わりには波の音がある。ただ理想化しているだけかもしれないけれど、あなたがブクラで作る波の音はなぜかとてもオーガニックに聞こえるんです、という2016 年のレッドブルミュージック・アカデミーの受講生の質問に、チャーニはシンプルに「それは複雑だからです」と答えている。楽曲が生む興奮に加え、独自の発振回路を持つブクラでオシレータとフィルターを入念に組み合わせて生まれる彼女の波の音は、自然を人間の側から思考する重要な事例でもあるのだ。
Drew McDowall - Agalma | Dais Records

70年代から90年代にかけて、コイルやサイキックTVの長年の共作者、あるいはそのメンバーとしても知られる、スコットランド出身で現在はブルックリンを拠点に置くドリュー・マクドウォル。近年はモジュラー・シンセを表現メディアの主軸においている。2年前に出た、同じくニューヨーク拠点のモジュラー・シンセシスト、ヒロ・コーネとのEP「The Ghost of George Bataille」が示唆していたかのように、ソロとしては5作目の『Agalma』は、数々の客演が目白押しになっている。ともに実験的シンセシストであるカテリーナ・バルビエリとロバート・アイキ・オーブリー・ロウとの共同作業において、逆行するサウンドや加工された肉声が、ハープなどの異なるマテリアルとともに、あらゆる方向から飛び交ってくる。先に書いたカリ・マローネの参加曲は、とぐろを巻くようなベースと左右の空間を埋め尽くすリードが、オルガンと奇怪に絡み合う。ヴァイオリンやダブルベースといった楽器も今作には多数散りばめられている。ノイズ/エクスペリメンタルの若手として知られるバシャー・スレイマン、エルヴィン・ブランディや、カイロのズリとの共作や去年のデビュー作『Dhil-un Taht Shajarat Al-Zaqum』で頭角を現したサウジアラビアのシンガー、ムシルマ(MSYLMA)らが参加したLP盤の終曲は、楽器とエレクトロニスのオーケストレーションとヴォーカルが圧巻のシンフォニーを見せる。ギリシャ語で彫像を意味する「agalma」が各楽曲の番号とともに割り振られた今作は、曲ごとに異なるサウンド・フォームを模索している。一貫して広がる暗さに引きずり込まれ、聴くことを止めることができない傑作だ(レコードは手に入れるタイミングを逃してしまった……)。
Burial + Four Tet + Thom Yorke - Her Revolution / His Rope | XL Recordings
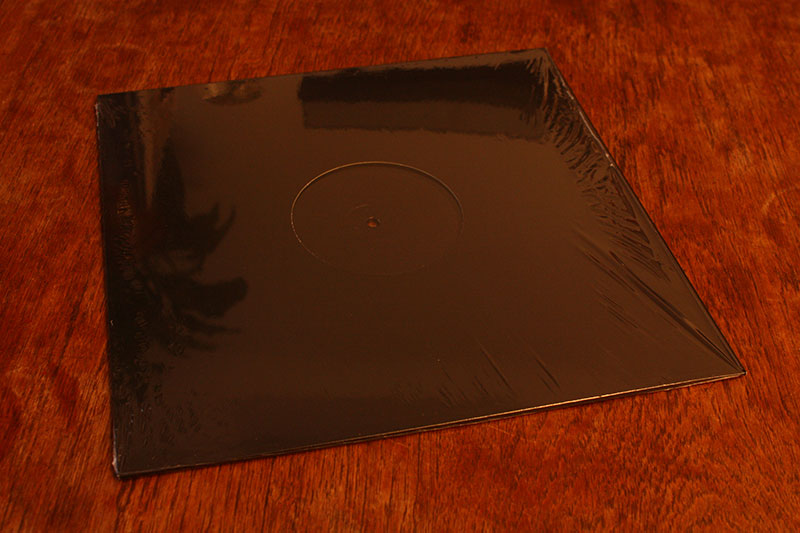
最後はウワサのアレ。ロンドンの三つのレコ屋がこの12インチの入荷を告知した翌日に在庫をチェックしたところ、すべての店舗ではソールドアウトになっていた。限定300枚だしな、と諦めていたところ、その一週間後にとあるレコ屋のサイトを眺めていたら、どういうわけか入荷していて入手することができた。フォー・テットが自身のレーベル〈Text〉から、それまでのデザインとは異なる黒ラベルで発表したベリアルとの最初のコラボ12インチ「Moth / Wolf Club」が出たのが2009年。そこにトム・ヨークが加わった「Ego / Mirror」が2011年、そして翌年には再び2人に戻って「Nova」をリリースしている。今回の曲調は前回のようにハウスではなく、減速したツーステップでもなく、いわゆるダウンテンポと括られるスローなビートになっている。これまでもそうであったように、今作にもベリアル的なクラックル・ノイズが散りばめられ、フォー・テット的な色彩を加える流浪のシンセ・リードがあり、どこからか現在に回帰してくるサンプリングが澄んだ情景を生む。ヨークの声はトラックの前面に出ているというよりは、キックによって区切られる間隔でこだましているかのよう。レコードのランナウト(曲とラベルの間)に「SPRING 2020」とあるので今年になって録音されたものなのだろうか。であるならば、ヨークの歌詞が放つ、犠牲がともなう革命、完璧な自己破壊といったモチーフは、パンデミックやブレグジットとも時代的に呼応しているのかもしれない。それが透き通るようなトラックのなかで鳴っている。2021年、この12インチ はどのように聴こえるのだろうか。
文・選盤・写真:髙橋勇人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE