MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Thom Yorke- Anima
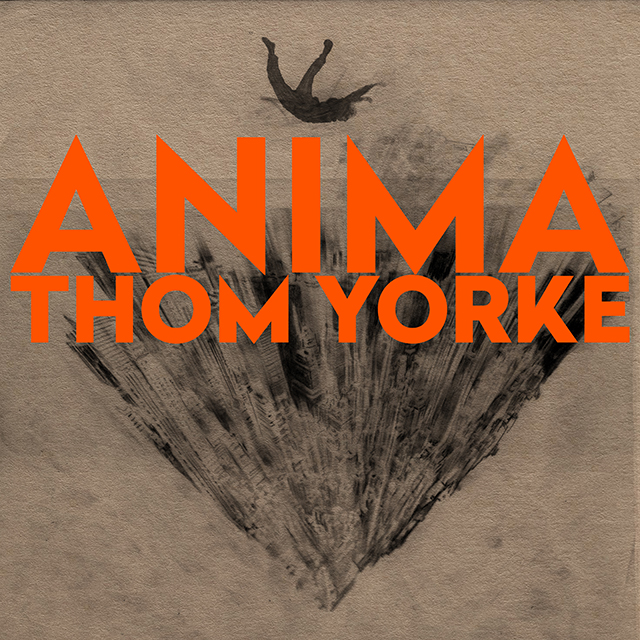
彼のことを見直したのは2017年だった。例のテルアヴィヴ公演をめぐるごたごたである。かの地で演奏することはパレスティナへの弾圧に加担することにほかならない、とイスラエルにたいする文化的ボイコットを推奨する団体「アーティスツ・フォー・パレスチナ・UK」がレディオヘッドを非難、5人それぞれに公演の中止を要請したのだ。それにたいしトム・ヨークは「ある国で演奏することは、そこの政府を支持することとおなじではない」と一刀両断、バンドはそのまま予定されていた公演を敢行する。ちなみに糾弾側にはロジャー・ウォーターズやサーストン・ムーアなども名を連ねていたのだけれど、もっとも手厳しかったのは映画監督のケン・ローチで、「弾圧する側に立つのか、弾圧されている側に立つのか」と容赦のない二択を迫った。
この混乱はアンダーグラウンドにまで飛び火し、翌2018年、「イスラエルにたいする学問・文化ボイコットのためのパレスティナ・キャンペーン(PACBI)」による協力のもと、ベンUFOやカリブー、フォー・テットやローレル・ヘイローなどが「#DJsForPalestine」というハッシュタグを共有、つぎつぎとボイコットへの賛同を表明していった(ちなみにフォー・テットはトム・ヨークとコラボ経験がある)。そのような対抗運動は「BDS(Boycott, Divestment, and Sanctions:ボイコット、投資引きあげ、制裁)」と呼ばれているが、かのブライアン・イーノもその強力な支持者である。
それらの経緯や各々の意見については『RA』の特集が詳しいので、ぜひそちらを参照していただきたいが、このボイコット運動の最大の問題点は、それがあたかもこの地球上に、「良い国家」と「悪い国家」が存在しているかのような錯覚を撒き散らしてしまうことだろう。イギリスやアメリカ(や日本)では大いにライヴをやるべきである、なぜならイギリスやアメリカ(や日本)はイスラエルとは異なり、そこに生きる「すべての」人間にたいし何ひとつ、いっさいまったく抑圧的なことをしない善良な国家だから──ある特定の国家のみを対象としたボイコット運動は、国家そのものにたいする疑念を覆い隠してしまう。
*
とまあそういう「音楽に政治を持ち込もう」的な混乱のなかで、いつの間にかその存在さえ忘れかけていたトム・ヨークのことを思い出すにいたったのである。彼の音楽について考えなくなってしまったのはいつからだろう、むかしはレディオヘッドの熱心なファンだったはずなのに──もちろんトム・ヨークはずいぶん前から果敢にエレクトロニック・ミュージックに挑戦し続けてきたわけだけど、どうにもロックの呪縛から逃れられているようには思えなかったというか、正直なところ『The Eraser』も『Tomorrow's Modern Boxes』もいまいちピンと来なかった。
ソロとして通算3枚目となる新作『Anima』は、しかし、素直に良いアルバムである。彼はようやくロックの亡霊を振り切ることに成功したのだろうか? ジョニー・グリーンウッドの活躍から刺戟を受けたのかもしれない。あるいは『Suspiria』のサウンドトラックを手がけたことがなんらかのトリガーになったのかもしれない。いずれにせよトム・ヨーク(とナイジェル・ゴッドリッチ)によるこの5年ぶりのアルバムは、彼が長年エレクトロニック・ミュージックを享受してきたことの蓄積がうまい具合に実を結び、ストレートにアウトプットされているように聞こえる。
今回の新作は、かつてツアーをともにしたフライング・ロータスがライヴでループを用いて即興していたことからインスパイアされているそうなのだけど、たとえばハンドクラップのリズムと「いーいー」と唸る音声がユーモラスに対置される冒頭の“Traffic”や、いろんな声のアプローチが錯綜する“Twist”といった曲によくあらわれているように、その最大の独自性はさまざまな音声とリズムの配合のさせ方に、そしてストリングスとシンセの融合のさせ方にこそ宿っている。
とくに素晴らしいのは後半の5曲で、ご機嫌なベースと崇高なコーラスのお見合いから、ライヒ/メセニー的なミニマリズムへと移行する“I Am A Very Rude Person”も、遠隔化されてふわふわと宙を漂うレトロフューチャーなブリープ音に、重厚なチェロとコントラバスが喧嘩を吹っかける“Not The News”も、虫の羽音を思わせる電子音の足下で強勢が複雑に変化し、次第にポリリズミックな様相を呈していく“The Axe”も、どれも細部を確認したくなって何度も聴き返してしまう。“Impossible Knots”におけるドリルンベース的なハットの反復と、そこから絶妙に遅れて爪弾かれる生ベースとの不一致もいい感じに気持ち悪くてクセになるし、“Runwayaway”のブルージィなギターのうえでぶるぶると震える声のサンプルはベリアルの発展形のようで、ポスト・ポスト・ポスト・ダブステップとでも呼びたくなる印象的なビートがそれを補強している(この曲もまたチェロとコントラバスがいい)。
あとはトム・ヨーク本人が歌うのをやめれば……と思う曲もなくはないけど、こういう素朴に良い内容のアルバムを送り出されると、もう彼のことを無視できなくなるというか、これからはまたしっかり彼の動向を追いかけていくことになりそうだ。
*
おまけ。アルバムのリリースから一月ほど経って“Not The News”のリミックス盤が登場、3年前にコラボを果たしたマーク・プリチャード、イキノックス、クラークの三組が存分に腕をふるっているのだけれど、それぞれかなりおもしろい解釈を聴かせてくれるので(とくにクラークがすごい)、そちらもおすすめ、というかマスト。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE