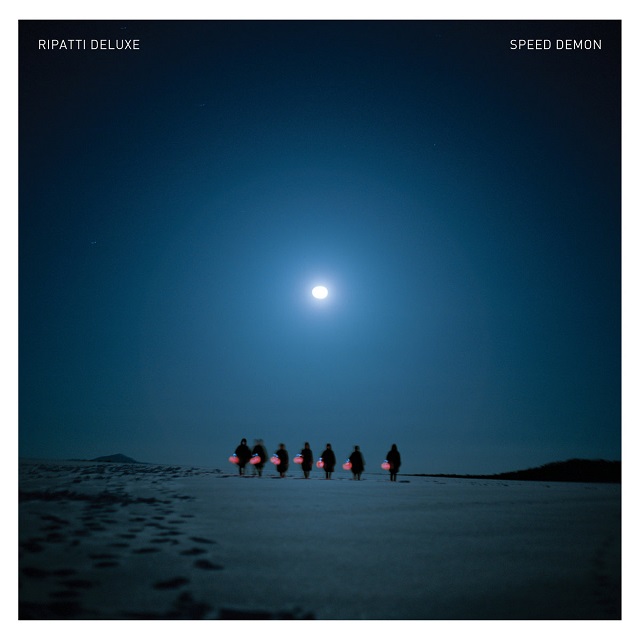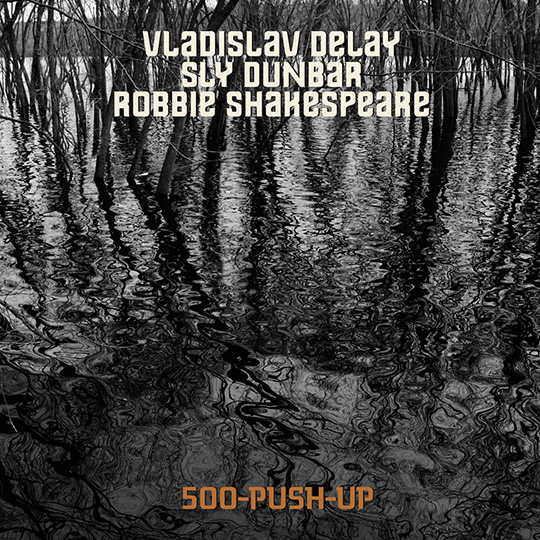MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Vladislav Delay- Rakka II
年末のサウンドパトロールでも書いたが、サス・リパッティ(1976-)ことヴラディスラフ・ディレイはバンドキャンプ上でのサブスクリプションを通して、自身の過去作の大部分と、新曲を毎月発表している。そこから見えてくる彼の経歴は実にユニークだ。VD名義の出世作となったベーシック・チャンネルの〈Chain Reaction〉から出した一連のシングルとその収集版である『Multila』(2000)や〈Mille Plateaux〉の『Anima』(2001)など、ダブ・テクノやグリッチ/アンビエント史の重要作は今日においてもその輝きを失っていない。2018年に出たコード9とベリアルの『Fabriclive 100』のミックスでも象徴的にプレイされていた “Otan Osaa” が入った『Demo(n) Tracks』(2004)を聴いてみても、サンプリング、グリッチ、低音そしてそこにダブを投入する才能が20代でここまで爆発していたのかと驚く。
グリッチやアンビエントに加え、リパッティの探求においてリズムもひとつの鍵である。彼はテクノよりもジャングルやD&Bを愛し、ルオモ名義で取り組んだハウスよりもUKGの2ステップを愛する男である(リズム&サウンドの “Truly” リミックス(2006)が良い例だろう)。彼はもともとジャズ・ドラマーで生粋のリズム・コンシャスであり、その腕はモーリッツ・フォン・オズワルドにも買われ、彼のトリオにも一時期参加することにもなり、近年では自らの即興演奏カルテットでもドラムを叩いている。このリズムへの好奇心はシカゴにも接続され、リパッティ名義でのフットワーク作も生まれた。三田格が言うように、ポーター・リックスやマイク・インクらと並び、リパッティはベーシック・チャンネルの影響を抜け出してオリジナルをやった少数派のひとりであり、このリズムをめぐる変遷がそのことを証明している。
研ぎ澄まされた感覚が10年代の〈Rastor-Noton〉からの諸作を生み、さらにはスライ&ロビーとの『Nordub』(2018)と去年の『500-Push-Up』に繋がっていく。これは彼の歴史のごく一部だが、そのキャリアを聴きまくった末にこうして昨年『Rakka』の続編である今作『Rakka II』が届けられたのだから、僕はこうして筆を取らないわけにはいかなかった。リリース元は引き続き、シェイプトノイズの〈Cosmo Rhythmatic〉。6月には絶好調の〈Planet Mu〉から、リパッティ名義でのアルバムもリリースされる。
デンシノオトが前作のレヴューで書いているように、『Rakka』シリーズはライフスタイルと多くの機材を売り払ったことによる転換を迎えて生まれたものだ。多くの人間がそうであるように、リパッティの人生は変化に溢れている。20代に多用していたドラッグをきっぱりとやめ、パートナーの電子音楽詩人 AGF と結婚し、子供ができ、2008年に拠点としていたベルリンを離れフィンランド北部に位置する人口約1000人のハイルオト島に移住。自分で木を切りスタジオまで建てている。そのなかでも音楽生活の比重を自然散策にずらすことによって生じた影響が重要だと本人は語っている。プレスリリースは、ここには彼がフィンランドの自然環境が持つ音楽構造によって制限されることのない、力(フォース)の描写があると予想している。ここにはスピリチュアルな解釈も可能かもしれないが、リパッティの言葉によれば、彼が身をおく環境は風が唸る音が非常に轟音で、それに耳が慣れた影響が『Rakka』にはあるだろうとも語っていた。
たしかに『Rakka』はラウドな音楽である。『II』を例にとれば一曲目の “Rakkn” は、吹雪のように細かいディストーションがかけられたドローンが両耳の聴覚を覆い、そこに左チャンネルのさらに歪んだノイズが定期的に回転し、高音域の反復がサイレンの警戒音のごとく聞き手の情動に作用。そのすぐ後に低音域のドローンがなだれ込んでくる。その後も多種多様なマテリアルが左右のスピーカーを飛び交っていき、轟音と音像にと圧倒されつつ、中盤からさらにキックの連打が打ち鳴らされる。いわゆるテクノ・マナーなど皆無で、音像は近年のSFのサウンドトラックのようでもある。とにかく、最小限かつマキシマムにエネルギーが解放されていく。
『I』と同様の機材セットアップで作られているため、『II』も前作に似た歪んだヴァイオレントなテクスチャーを部分として持っている。彼の重低音を支えてきたモーグシンセを売り払い、DAWのロジックをメインにし、同ソフトウェアに初期装備されている EXS24 サンプラーを多用した、と彼は答えている(ロジックは去年サンプラーのインターフェイスを刷新して、いまのヴァージョンはかなり見やすいのだが、リパッティが使用しているのはその前世代のものだろう)。ラップトップに取り込まれた音は、ラットやビッグマフといったギター・エフェクターに送り込まれる(彼はフィンランド人らしくメタルの影響も受けている。『Rakka』のラウドな縦ノリ感はそこにも通じる?)。生々しい歪みたちは、彼のスタジオのエコロジーの産物だ。マッシヴなサウンドだけではなく、“Rakas” のような穏やかな曲においても、そのテクスチャーは独自のナラティヴを持っている。
先ほど、彼のリズム・コンシャスについても触れたが、『Rakka』二部作もその延長線上にある。視界が開けた二曲目 “Raaa” において、太陽光のようなドローンを区切るようにキックはポリリズミックに鳴り、それと呼応するように、シンセの反復音は定期的にトリガーされる。ここにある言語は、間違いなくリズムだ。このリズムの迷宮は6曲の “Ranno” においてピークに達する。冒頭から断続するノイズの反復が時に遅延と揺らぎを含みつつ、ふたたびポリリズミックなキックが空間に介入していく。もちろんノイズやトーンの揺れは彼が愛するジャズのように即興的で詩的であるものの、このリズム構築は恐ろしいほどまでに細部までコントロールされている。
これらが自然環境における人間の制約から無縁のフォースを『Rakka』で描写していく。いわゆるジェネラティヴ・ミュージックは、音楽構造のパターン化をアルゴリズムの生成によって偶発的に乗り越えていく。また、ランダムに発信するLFOによってシーケンサーやフレーズを規則性がないかのように構築する手法もある。リパッティはそのようなランダム性による「開放」の描写を目指すのではなく、徹底的にコントロールされた複雑なリズムを経由して自由/自然の輪郭を炙り出そうとしている。気象や地質的な非人間的アクター、そしてそれを感じる人間が織りなすエコロジカルな連鎖反応ものとしても映る。トレッキング・シューズに覆われた旅人の足が、地図をロジカルにたどり、非ロジカルに広がる岩の上を進んでいく身体性。そこにもリズムはたしかにある。
『II』の表ジャケットは『I』の裏ジャケットを鏡写に反転させたもので、前作のピンク色に染められた入江は今作で緑に変わっている(入江の写真はリパッティの娘が撮影したもの)。この色彩と虚像関係の意図は不明だが、少なくとも、ここにはことなるモーメントがはたらいているようである。プレスリリースにあるリパッティの説明によれば、『II』は「希望とオプティミズムに満ちたロマンティックな夏のヴィジョン。一作目のブルータリストのヴァイブスのあと、嵐は過ぎ去り、空は晴れはじめている」とある。たしかに『I』の “Rakkine” で見られた視界を遮られた奈落の暴風雨のようなサウンドというよりは、『II』には終曲の “Rapine” のように、決して晴天ではないものの、彼方の空が晴れていくような感覚を覚えなくもない。いたずらに称賛される主体から切り離された対象ではなく、そこに参加することによって感じとられる恐怖にも希望にも転じる曖昧なグラデーションを保つアンビエンス。卓越したスタジオ・サイエンスを通して、ヴラディスラフ・ディレイが今日の我々に提示するのは、そのような自然像である。
髙橋勇人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE