「まったく国民に自粛を押しつけといてさ」、いきつけのクリーニング屋の親仁は吐き捨てるように言った。「あいつらは好き勝手やってんだよ、とんでもないよね」。昨年末のことである。かれこれ10年以上世話になっている個人経営の店の、もう白髪さえ頭にまばらなこの爺様とは、いままでずっと天気の話しかしてこなかったから、突然の政治的憤怒にはフイを突かれる格好となった。ええ本当にそうですねと、そのぐらいの言葉しか返せなかったが、あんな温厚な年寄りさえも怒っているのだと念を押された思いだった。
このところニュースは、失業者、ホームレス、そして自殺者について報道している。コロナ第三波に対してとくになんの対策もなく、意味のある支援策も解雇防止策もないまま、だらだらと非常事態宣言がでたばかりだ。ニュースはそして最近では、トランプの信じがたい暴力的な脅しを報じている。この一大事に、他の先進国と違って我が国の政治リーダーはコメントすらできないようだが、まあ、ワシントンの議事堂における支持者たちの暴動では、警察の対応がBLMデモとは明らかに違っていることを世界に見せてしまったと。その点でもBLMの成果はあったと言えよう。だが、あの憎しみや怒りは、ぼくがアリエル・ピンクのCDをたたき割って捨てたところでは、とうてい消えはしない根深いものであることを知らしめてもいる(ジョン・ライドンに関しては……紙エレ年末号をどうぞ)。
さっきからテレビの画面では飲食店の店主たちが悲鳴をあげている。一家の稼ぎ手がまたひとり職を失っているときに自助(自分でなんとかせぇ)を第一とする菅政権は、就任以来中小企業の事業再構築をうながしているが、これは中小企業の何割かの淘汰を意味している。こんな与党を前に野党はいまもって存在感を示すことができず、その支持率は一向に上がらない。いま、目の前にあるのは幻滅ではない、絶望だ。
バズライトイヤーの髪型をしたおまんこ野郎が
労働者たちを呼びつける
自分の将来について考えたほうがいい
自分の首のことを考えたほうがいい
仲間を作ることやクソな髪型について考えたほうがいい
俺は25セントのパスタと
スミノフの温かいボトルの夢を叶える
“Fizzy”
ポップ・ミュージックにできること。気張らし。慰め。逃避。夢。熱狂。ダンス。カオス。笑い。快楽。幻覚。励まし。内省。趣味の競い合い。性の解放。愛の増幅。社会参加。孤独な魂に寄り添うこと。批評。罵倒。失意。絶望。悲しみの共有。挑発。炎上。攻撃。ヒーローはいつだって私をがっかりさせる。異議申し立て。疑問。気づき。目覚め。言いたくても言えないことを言うこと。頭のなかの革命。
俺はなぜ、穿いているブーツの二の次なのか?
俺はなぜ、着ているコートや髪型の二の次なのか?
俺はなぜ、自分の車の二の次なのか?
腕時計やジーンズ、ポロシャツよりも下
“Second”
スリーフォード・モッズは、間違いなくいまもっとも面白いバンドのひとつである。その立ち振る舞い、音楽性、言葉、ユーモア、見た目、政治的スタンス、勇気、ぶち切れ方……スリーフォード・モッズは怒りにかまけて理想を忘れるようなことはしない。ものごとは昔よりも複雑化している。だからスリーフォード・モッズは走っているが、ただ走っているわけでも、考えてから走っているわけでもなく、調査し、挑発し、不条理を受け入れて、真剣に考えながら走っている。ザ・KLFが、ポップ・ミュージックがその随所に渡って市場化され、金が神となった現代を見据えながら象徴的な意味合いとして100万ポンドを燃やしたのだとしたら、そのがんじがらめの資本主義リアリズムのなかで目一杯ジタバタして、泥にまみれてもがいているのがスリーフォード・モッズだ。彼らは、地元の保守的なコミュニティにも、居心地良さそうなリベラルのコミュニティにも属さない。言うだけ言って、やるだけやってやろうという腹づもりなのだろう。
また、いまのような時代ではスリーフォード・モッズには希少性という価値まである。パンク・アティチュードはほかにも、たとえばシェイムのような若いバンドやストームジーのような賢明なるMCにもあるのだろう。だが、ジェイソン&アンドリューというふたりのおっさんがそのなかで際だった存在であることは間違いない。昨年もロックダウン中にUKで起きた介護者への国民からの讃辞に対して、こうした美談は政府の怠惰を隠蔽すると発言したことで、当たり前だが物議を醸し、また、「階級の盗用」だとアイドルズを大批判したビーフはファット・ホワイト・ファミリーまで巻き込んでの騒ぎとなった。
それで、まあ、スリーフォード・モッズは進化しているのだ。新作『スペア・リブズ(Spare Ribs)』には、まずはサウンド面の変化がある。『オースタリティ・ドッグズ(Austerity Dogs)』の頃のモノクロームな煉獄ループに比べると音色も多彩で、曲もずいぶん親しみやすくなっている。セックス・ピストルズやストゥージズの幻影も霞んではいるが、ドイツの冷たいエレクトロや後期ザ・スペシャルズ風な内省とメランコリーもあったりで、曲のヴァリエーションが増えている。とはいえ、ジェイソンの激怒するヴォーカリゼーションとアンドリューのミニマルなトラックが古き良きロックに回収されることはない。
UKのモッド・カルチャーとは、本来の意味を思えば60年代回帰のレトロ志向のことではないはずだ。あれはモダンな(新しい)ものを好み、たとえば最先端のUSブラック・ミュージック(ないしはUK移民の音楽=レゲエ)を愛好する尖った文化だった。ノーマティヴな社会に溶け込みながら、人とは違った趣味を持ち、人とは違った方法で自分をしっかり着飾る文化。ジェイソンも服が大・大好だが、彼はウータン・クランに触発されたあくまで現代のモッドである。ポップ・ミュージックにできること。いまリアルに起きていることのレポート。
ここにアンセムなどない
あるのはコンクリート
チップス
汚れたソーセージ
3ポンドの花束
“The Wage Don’t Fit ”
スリーフォード・モッズはイギリスのノッティンガムの、ジェイソン・ウィリアムソンいわく「レイシストだらけ」の保守的な街で誕生した。2006年のある日のこと、パジャマ姿のまま近所に発泡酒とチョコバーを買いに行ったときにアイデアが閃いたという。ちなみにその名前だが、彼らがスリーフォードという土地に縁があるわけではない。ただその響きが良かったから採用したという。
ジェイソンは、他人の曲をループさせたトラックに自分のラップをかぶせるという初期スリーフォード・モッズのやり方で地元のスタジオエンジニアと4枚のCDR作品を出している。昔はストーン・ローゼズやオアシスが好きだったというジェイソンだが、彼が自分のパートナーに選んだのは地元のDJ/プロデューサーで、ソロでは荒涼としたエレクトロニカ作品を多発しているアンドリュー・ファーンだった。長身で痩せこけたアンドリューと5枚目のCDR作品を作ると、2013年には正式なアルバムとして『オースタリティ・ドッグズ(緊縮財政の犬たち)』をリリースする。時代をみごとに捉えたその勇敢で独創的な音楽はWire、NME、ガーディアン、Quietusなどなど、イギリスの有力メディアからいたってシリアスに、そして知的に評価され、翌年の『ディヴァイド・アンド・イグジスト(分断と出口)』にいたってはマーキュリー賞にもノミネートされた。(いまではブリストルの巨匠マーク・スチュワートからロビー・ウィリアムスのようなセレブにまで愛される人気バンドになったが、曲の歌詞でNMEをバカにしたので、同メディアが選ぶ最悪なバンドの1位にもなっている)
スリーフォード・モッズはその後3枚のアルバムを出している。2015年の『キー・マーケッツ』、2017年には〈ラフトレード〉から『イングリッシュ・タパス』、2019年には自分たちのレーベル〈Extreme Eating〉から『イートン・アライヴ』。再度〈ラフトレード〉からのリリースとなる『スペア・リブズ』は、昨年話題となったベスト盤『オール・ザット・グルー』を挟んでのアルバムで、ロックダウン中に録音された。まるでDAFのようなエレクトロなミニマリズムとともに『スペア・リブズ』はこんな風に、失意と疲弊感からはじまる。この気持ちは我々日本人もシェアできるのではないだろうか。
俺らみんなが保守党に疲れている
そのせこさにやられている
浜辺はファックされ、波もないから
ここじゃもう誰もサーフィンしない
“The New Brick”

イーノは全然好きじゃない。彼は、俺のハマってる連中の多くにすごく影響してきた人なわけだ。でも俺自身は一切影響を受けてない。彼にはまったく興味を惹かれたことがないな。だってさぁ、あのみてくれだぜ(笑)。
■新作、とても楽しませていただきました。音楽的にヴァリエーションが増えたことで、歌詞がわからずとも楽しめます。ある意味アクセスしやすい作品だなと。
JW:(うなずきながら)うん、それは間違いない。
■ロックダウン中に『スペア・リブズ』の録音に取りかかったそうですが、最近はどんな風に過ごされていますか?
JW:うん、なんとかやってる。ポジティヴであろうと努めているし……かなり妙だけどね、ただじっとして、働かずにいるってのは。いやだから、ギグをやれないわけでさ。でも──うん、俺たちは大丈夫だよ。とにかくいまは、他の多くの人びとに較べりゃ自分たちの状況はずっとマシなんだし、常にそれを思い起こすようにしなくちゃいけないな、と。
■日々、読書や映画鑑賞に明け暮れているとか?
JW:(笑)いやぁ、俺は読書が苦手でさ。マジにからっきしダメな読み手だよ。もっと本を読めればいいなとは思うけど、ほら、自分はものすごく──これ(と携帯をカメラにかざす)の中毒なわけで。
■おやおや。
JW:(携帯スクリーンを猛スピードでスクロールするふりをしながら)ピュッピュッピュッピュッ! 始終そんな感じで、何か見て「おっ、すげえ!」みたいな。わかるだろ? うん、よくないのは自分でもわかってるんだけど。それ以外だと、俺は子持ちだから、父親業だね。子供の面倒をみて過ごしてる。そうやってとにかく心持ちの面で忙しさを保とうとしているし、クリエイティヴな面で言うと、アルバム(=『スペア・リブズ』)以来、自分は実際何もやってないな。それでも何やかんやと時間はふさがっているし、きっとそれは親だと忙しいってことだろう。
■あなたがフランクフルト学派やマルクーゼを読んでいるとどこかの記事で見かけたんですけど、それは本当ですか? たしか『一元的人間』を読んでいる、とのことで。
JW:ああ、とてもいい本だ。あれは助けになったというか、本当に影響された。そうは言っても1、2章かじった程度だけどね、(顔をしかめながら)すごく、すご〜く難解でおいそれと読めない本だから。ただ、あれを読んだおかげで自分はものすごくこう──目覚めさせられたっていうのかな。この……国による支配ってものから、資本主義の抑圧から、我々は決して自由になれない、という観念を意識するようになった。彼らがこちらを欺き、資本主義の経済モデルに一生貢献し続けるように我々をだます、その様々なやり方からね。
■でもほんと、その管理・抑圧からは逃れられないですよね。たとえば、こうしていま素晴らしいテクノロジーを使って取材していますが、これですら資本主義モデルに準じた一種の社会的なコントロールじゃないかと感じることがありますし。
JW:うん……。だけど、と同時に俺はそれを気に入ってもいるんだ。金を使うのは好きだし、高価なスニーカーを買うのも好きだ。外食するのも、いい服を着るのも好き、と。だから俺はまた、そのモデルを自らに割り振ってもいるっていう。
■先ほど言ったように、まずは音楽的に以前よりもヴァリエーションが増えたと思います。そこは意識されましたか? 様々なヴォイスやサウンドがミックスされていますし、ギターを弾いているのはあなたですか?
JW:ああ。
■ギターを弾くのは本当に久しぶりだったと思いますが、どんな気分でした?
JW:たしかにずっと弾いてなかったけど、まあ、とにかく音楽の方がギターをいくらか必要としていると思えた。アンドリューは“Nudge It”でギターを弾いたし、俺は“Thick Ear”で弾いてる。だからときおり……そう、とにかく今回はギターが必要だって風に自分には感じられた、ギターをちょっと加えようと思ったっていう。だから、以前の自分ほどギターっていうアイディアに敵愾心を抱かなくなっているんだよ。
[[SplitPage]]モッズというのはいつだって真実を伝える連中だった。だから俺は自分のバンドに「モッズ」の単語を含めた。自分たちもその同じ流れに沿っている、俺はそう思ったから。
■スリーフォード・モッズのサウンドスケープを拡張するというのは──『Key Markets』以降、確実にその幅は広がってきていましたが──意識的でしたか? スリーフォード・モッズの音楽はそぎ落とされたミニマルなものになりがちですが、今回はもう少し聴き手に緩衝材を与えている気がします。
JW:ああ、そこは確実にそうだ。思うに、俺は……どう言ったらいいのかな、これまでよりもう少し層の重なった、もうちょっとカラフルなものにしたかったんだ。
■ちなみに、アンドリューがひたすらチープな機材を使って音楽を作っていますが、それは高価な機材でしかモノを作らないことへの反論なのでしょうか?
JW:そうは言っても、ここ数年で奴の機材の幅は間違いなく以前より広がったと思うけどね。でも、あいつは以前「ACID」っていうソフトを使ってビートを作っていたはずで、っていうかいまも使ってる(笑)。だから、そうね、あいつはこう……効果音だとか、奇妙なサウンドだのに入れ込んでるんだよ。で、それらを入手するのには、そんなに大枚はたかずに済むわけじゃない?
あいつのいま使ってるセットアップも、かつてに較べりゃずいぶんでかくなった。ただ、それでもあいつはいまだに、歌にビート/音楽を組み込む際は最小限の要素みたいなものにしか頼らない。あいつも近頃じゃ、いくつか良質な機材の一式をいつでも使えるよう、手元に揃えたがるようになってるけども。
■スリーフォード・モッズはある意味、音楽を作ることに、音楽界にインパクトを与えるのに大金を費やす必要はないという、その好例じゃないかと思うんですが。
JW:そうそう、その必要はまったくない。俺たちはそういうのに興味なし。とにかく俺たちは大抵ミニマルにまとめているし、アンドリューはそれにうってつけなんだ。というのもあいつの音楽は、たとえばソロでやってるExtnddntwrk(=extended network)にしても、どれも一種の音のランドスケープ、サウンドスケープ郡みたいなことをやっているし、やっぱりミニマルなわけで。だからほんと、あいつのやることはそこと完璧にマッチするんだ。
■Extnddntwrk名義の作品は、じゃあよくご存知なんですね。彼のアンビエントな側面もお好きですか?
JW:ああ、もちろん! 好きだしいいと思う。もっとも、あれは自分が普段聴くような類いの音楽じゃないけども。だから、そんなに聴かないけど、ちゃんと評価はしてる(笑)。
■ ちなみにアンビエントの巨匠イーノに関してはどんな印象をお持ちですか?
JW:ファンではないな。(苦手そうな表情を浮かべて)全然好きじゃない。でも彼は、俺のハマってる連中の多くにすごく影響してきた人なわけだよね? テクノだとか、エレクトロニカ全般なんかに多大な影響を与えてきた人だとされているけれども、俺自身は一切影響を受けてない。彼にはまったく興味を惹かれたことがないな、うん、それはない。だってさぁ、あのみてくれだぜ(と、頭を丸めた坊主頭のジェスチャーをする)? でかい頭で、すげえ妙なルックスでさ。フハッハッハッハッ……!
■(苦笑)。いや、イーノはあなたと同じようにコービン支持者ですし、政治的には共感できるんじゃないかなと。
JW:(真顔に戻って)ああ、うんうん、それはもちろんだよ。だから要は、俺はあの手のミュージシャンにエキサイトさせられることはまずない、ってこと。いつだってもっとこう、ストリート系な、「ウギャアアアァァッ!」みたく騒々しいバンドなんかの方に感心させられるっていうか、そういうのなら「おう、よっしゃ!」とそそられるっていうさ。
■2020年にはこれまでのキャリア総括盤『All That Glue』も出しましたし、自分たちを振り返る時間もあったかと思います。
JW:(うなずいている)
■あらためてスリーフォード・モッズの原点を、あなたが友人のサイモン・パーフと2006年か07年あたりにこのプロジェクトをはじめた、その当初のコンセプトを教えていただけないでしょうか?
JW:あれは本当に……いま君たちが耳にしているもの、そのごくごくベーシックなヴァージョンだったんだ。当時の俺たちは他の人間の作った音楽をループして使っていた、という意味でね。
■(笑)無断サンプリングしていた。
JW:(苦笑)そう! で、俺はとにかく……そのループにシャウトを被せていただけで。個人的な実体験の数々、酔っぱらった経験や失敗談、アルコールとドラッグへの依存、セックスとか、まあ何でもいんだけど、そういった事柄すべてについて語っていた。いまやそこは変化したけどね、それとは別のことを俺は歌ってる。ただ、それらは人生のなかのごくちっぽけな立ち位置/存在の観察だ、というのは常にあって。で、それが念頭にありつつも──うん、昔の自分の怒号ぶりを思うと、いまよりもうちょっと早口でまくしたてていたしラウドだったし、たまに自分で制しきれなくなることもあり、実はそんなによくはなかった、みたいな? だからとにかく、いまやっていることと基本的には同類の、でもその初期ヴァージョンだった、という。
■スリーフォード・モッズは、モッズと言いながらいわゆるモッズ・サウンドではありません。ポール・ウェラー的なネオ・モッズ、あるいはスモール・フェイセズといったタイプの音楽ではないわけですけど、そもそもなぜ「モッズ」を名乗ることにしたんでしょう?
JW:それは、俺たちは基本的に──いやまあ、俺自身はモッズ的なものには入れ込んでるんだけどね。あれは常に俺の興味をそそってきた。で、俺のモッズ観は、あれは他の何よりも際立つことができるものだ、ということで。もしもバンドがモッズなるものをばっちりモノにできれば、そいつらは他の何よりも抜きん出ることができる、みたいな。というのも、モッズ(モダーンズ)というのはいつだって真実を伝える連中だったし、クリエイティヴィティに対してもっとずっと正直なアプローチをとってきた連中なわけで。だからなんだ、自分たちのバンド名に俺が「モッズ」の単語を含めたのは。自分たちもその同じ流れに沿っている、俺はそう思ったから。
■で、今回のアルバムの“Nugde It”の歌詞は興味深いなと。
JW:へえ、オーケイ。
■あれはスリーフォード・モッズの現在の立ち位置を歌っていると思いますよね。で、スリーフォード・モッズに対する評価に対しても苛立っているように読めるのですが、もしそうだとしたら、これはどういうことなのでしょうか? ちょっと説明をお願いできますか?
JW:あの曲で言わんとしているのは、異なる生い立ちを持つ連中がいかにして、実際にその経験がないくせに自分たちとはバックグラウンドが違う者たちの物真似をしているか、ということだね。そうやって物真似することで、彼らは自分たちをもっとエッジーに、あるいは実際より興味深いものに見せようとしている、という。で、多くの場合、人びとはその点に気づいてすらいないわけ。そういった連中は、自分たちがやっているのは本当はなんなのかすら考えずに、他の人びとのユニフォームを借り着してるっていう。俺は、それってマジに無礼な侮辱だと思う。かつ、その物真似を鵜吞みにして支持する人間が山ほどいるって事実、それに対しても本当に怒りを感じる。そういうことをやってるバンドのいくつかは、とんでもなく人気が高いわけだろ? というわけで、あの曲で取り上げているのはそういうことだね、「階級見学ツアー(class tourism)」みたいなものについてだ。
(※ここでジェイソンの話しているのは、上流・中流・下層と階級が分かれる英国で、上位に位置する人間が不思議がりときにバカにする意味合いで一時的に=物見遊山で立ち寄るごとく下層階級のファッションやスラングやカルチャーを真似する行為を指す。「貧民見学ツアー」を意味するpoverty safariというタームもある)
だから、お前さん自身は繫がっていない、お前さんには実体験の一切ない、そういう人びとだったり彼らの生き様をお前は物真似しているんだろうが、と。お前がそれを利用するのは、そうやって真似ることで自分をパワフルに見せたいだけだろ、と。
■──それは、アイドルズみたいなバンドのことですか?
JW:ああ、まったくねぇ! うん、そう。
■ソーシャル・メディア他であなたと彼らとのビーフが広まりましたよね。先ほどもおっしゃっていたように、アイドルズはいますごい人気ですけれども──
JW:(苦虫をかみつぶしたような表情で)ああ。
■あなた自身は彼らの言うことは信じていない、と。
JW:信じないね。なんて言えばいいのかな、「学が足りない/ちゃんと勉強してない」っていうの? 一元的で浅薄だし、中身がまったくない。とにかくやたらポーズばっか、と。で、いまって本当にひどい時期なわけだし、「自分は生きているんだ」と実感できるような何かを求めるわけだろ。これは俺個人の思いだけど、ああしたかっこつけやポーズから、俺はそういう感覚を受けないんだ。
■ちなみに、主にCD-R作品を出していた初期のことをわたしは「スリーフォード・モッズMK.1」あるいは「Ver.01」と捉えているんですが──
JW:ああ、うん。
■で、アンドリューが加入し、いわば「スリーフォード・モッズ Ver.02」がはじまった、と。そのブレイク作である『オースタリティ・ドッグズ』以降とでは、音楽への向かい方はどう違っていますか?
JW:うん、変化したね。絶対にそう。だから……質問は、俺の音楽に対する姿勢がどう変化したか、ということ?
■ええ。基本は変わっていないと思うんですが、『オースタリティ・ドッグズ』を境に、それ以前に較べてもうちょっとプロっぽくなった、「これは自分たちのキャリアだ」と考えはじめたんじゃないかと。そこで、音楽作りや作詞へのアプローチは変化しましたか?
JW:ああ、なるほど。うん、変化した。それは、さっきも話に出たマルクーゼみたいな人の考えだとか、現代世界に対する様々な類いの批評等に触れたことが影響しているんだと思う。
それと同時に、俺自身のなかで育ち続けている、「自分はこの世界のどこに位置してきたのか」みたいな意識/目覚めもあるんだ。自分という存在はこの世界でどんな意味を持ってきたのか? 自分は自分にとってどんな意味があるのか? 自分は何を学んできたんだろう? と。ぶっちゃけて言えばケアしているのは唯一それだけ、ほんと、成功と物質的な豊かさに伴うあれこれがひたすら重要な世界のなかで、自分はこれまでどんな人間として生きてきたのか、そうしたすべてをひっくるめたあれこれが、『オースタリティ・ドッグズ』を作った後で、よりはっきりしたものになりはじめていった。
■それだけヘヴィになった、とも言えますね(苦笑)。
JW:ああ、もちろん! そりゃそうだって。歳を食えば食うほど、たくさんのことがかなり、こう……だから、ドラッグだのセックスだの、そんなんばっかの人生なんざもうご免だ、タイクツなんだよ! って風になり出すもので。それらがやがて問題になってくるし、となると自分の人生からその要素を取り去るよう努力する他なくなる。いや、セックスは残しておいていいな、タハッハッハッハッハッ! ただまあ、ドラッグ摂取/飲酒等々の問題面は取り除こうぜ、と。
アルコールとドラッグのツケは、最終的に非常に大きく俺に回ってきたから。あれを乗り越えるのには本当に長くかかった。で、そうしていったん克服してみると、この世界は自分にどんな意味を持つのかという面に関して、これまでとは違う物事が作用してくるようになって(※数年前からジェイソンは飲酒もドラッグも断っている)。
というわけで、スリーフォード・モッズに備わったメッセージはある意味『オースタリティ・ドッグズ』以降も変わっていないんだけど、ただそのコンテンツは常に変化し続けている。

■スリーフォード・モッズは、マルクス主義者やフランクフルト学派を研究するような知識人からも評価されていますよね。個人的には興味深く思っているのですが、こうした左翼的な分析に関しては、あなたはどんな感想をお持ちでしょうか?
JW:彼らの分析には大いに賛成だ。もっとも、自分を左翼人だとは思っちゃいないけどね。でも、右翼じゃないのは間違いない。
■(笑)それはありがたい!
JW:(爆笑)。うん、ああした分析は好きだよ。インテリの立場にいる人たち、おそらく俺も興味を抱くであろう、そういう人びとが俺たちのやっていることをすごく気に入ってくれてるのはいいことだと思ってる。
[[SplitPage]]彼らの分析には大いに賛成だ。もっとも、自分を左翼人だとは思っちゃいないけどね。でも、右翼じゃないのは間違いない。
■オーウェン・ジョーンズの『チャブ』は読んでいると思いますが、あの本は好きですか?
JW:もちろん読んだ。すごく気に入ったね。あの本もまた、俺が政治に関してもっと建設的なフォルムみたいなものへと浮上していく、その助けになったもののひとつだ。
■“Elocution”では誰かの偽善性を批判しているようですが、具体的に誰とかあるのでしょうか? それとも音楽シーンに対する観察?
JW:ああ、うん、あれは……だからこの国の音楽シーンじゃ、マジにがっくりさせられる、そういう手合いはいくらでも跡を絶たないわけで。
■(爆笑)
JW:ハッハッハッハッハッ! なんかこう、そういう連中がどこからともなく次々に湧いてくる。っていうか、ほぼ毎年出てくるな。本当にシャクに障りイラつかされる、そういうアクトが毎年かならず、1、2組は登場する。
■(苦笑)なるほど。
JW:で……あれはほんと、そうした連中をあれこれ組み合わせたコラージュだね。連中は社会正義を謳った色んなキャンペーン活動のフロントを張るわけだけど、たまに「こいつら、自分たちのキャリアを向上させるのが目的でこういう活動をやってるんじゃないの?」という印象を抱かされることがあって。音楽そのものの力じゃ勢いが足りないからそれをやってる、と。才能が平均以下のミュージシャンの多くは、人気者のポジションを狙うなかで、大抵はネットワーキングに頼るものなんだ。各種音楽賞だの、なんであれそのとき焦点の当たっている、メディアに取り上げてもらえる問題に対するキャンペーン活動を通じて、という意味でね。だから連中は多くの場合、自分たちの地位を向上させるために、そのメカニズムに相当に依存しているわけ。
そうは言っても、彼ら自身は自分たちがどういうことをやっているかに対する自覚がないのかもしれないよ? ただ──そういうのにはウンザリなんだって。そんなんクソだし、お前らの音楽は特にいいわけでもない。こっちにはそれはお見通しなのに、それでもお前は「音楽をケアしてます」って言うのかよ、と。まあ、彼らもたぶん少しは気にかけているんだろうな。けど、それ以上にお前が気にしているのは自身のキャリアだろ、っていうさ。
■そこはミュージシャンにとっての難問ですよね。たとえば『スペア・リブズ』が売れてあなたたちがさらにビッグになったら、「ソールドアウトした」と批判する人は出てくるでしょうし。
JW:ああもちろん! っていうか、その批判を俺たちはこれまでも受けてきたし、いまですらそうだ。ただ、俺たちがかっこつけた気取り屋ではないこと、セレブではないっていう事実、そこは人びとだって俺たちからもぎ取れない。俺たちは常に、自分たちのままであり続けてきたんだしさ。
■“Glimpses”や“Top Room”はロックダウン中の情景を歌っていますよね? で、“Glimpses”ですが、これは曲調こそパンク・ソングなのですが、歌詞がずいぶん抽象的というか詩的に思いました。ここにはどんな意図があるのでしょうか?
JW:“Glimpses”ね。あれは……もっとこう、子供を連れて近所の公園に出かけると、みたいな話だね。で、行ったもののCOVIDのせいで公園は封鎖されてた、と。それと、消費主義についての歌でもある。それがいかに……だから、とあるスニーカーの宣伝をちょこっとやっただけでそのスニーカーをタダで5足もらえる奴もいる、と。ところがこちらは、その同じスニーカーを買うのに500ポンドだのなんだの、大金をはたくことになる。となると、こっちはほとんどもうなんの価値もない人間だ、ってことになるよな。商品そのものの話ではなくて、マネーのことだよ。
でもいずれにせよ、俺たちだってみんな、そこは承知しているわけで。誇示的消費(=conspicuous consumption。富や地位を誇示するための消費)なんて、別に目新しいものでもなんでもないんだし。で、俺としてはある意味、その点をあそこで論議したかったんだけど──うん、果たしてそのふたつの意味合いをあの曲でちゃんと表せたか、それは我ながらよくわからないな。あれはとてもいい歌だし、すごく気に入ってる。ただ、曲のメッセージという意味では、まだほんの少し、言葉が足りないのかもしれない。
■2014年のガーディアン紙の取材であなたはスリーフォード・モッズの音楽の根幹には「怒り」があると話しています。いまでも「怒り」はモチベーションだと思いますが、それはあの頃とまったく同じ「怒り」がいまも持続している感じですか?
JW:うん……だから、俺の怒りのほとんどは、他の人びとに対して感じる苦々しさや嫉妬、うらやましさから派生したものなんだよ。それとか他人をおいそれと信じないところだったり、政府に対する軽蔑もその主な要因になっている。で、その点は変化していないと思う。それらのアイディアから、俺はいまだにこうしたエネルギーのすべてを得ているわけで。ネガティヴィティにシニシズム、そして自己批判もあるけど、そうしたものからエネルギーを得ている。
というわけで、そこはいまだに継続中だな。ただ、思うにほんと唯一、自分にとって重要なことという意味で……自分にどうしても語れないのは愛だなぁ。愛というのは、(歌にして)宣伝するよりも(苦笑)、実際に体験する方がずっといいアイディアだと俺は思っているから。だからまあ、ポジティヴィティがほとんど存在しない、ポジティヴさがわずかな隙間にちょこちょことしか見出せない状況で、常にポジティヴなことばかり語るのは、どうしたって興味深いこととは思えないだろう。
■トランプやボリス・ジョンソンのような右派ポピュリストは、新自由主義によるグローバリゼーション(安価の移民労働)と「Austerity」(福祉予算のカット)によって追いやられた労働者たちの心情にうまくコミットしていましたが、コロナによって、例えばトランプが選挙に負けたように、右派ポピュリズムにほころびが出てきています。しかし、それでも日本では、コロナを企業社会の新自由主義的な再編の機会として捉えている向きもあり、ますますやばい状況になりそうです。イギリスも失業者がハンパないと報道されていますが、そうした社会不安や追い詰められていくメンタリティの問題、見えない恐れの感覚は今回のアルバムに大きな影響を与えていると感じたのですが、いかがでしょうか?
JW:そうだと思うよ、うん。もちろん。だからこの、自由がみるみる奪われていくという実感に、疎外感に……日常的に同じ経験を繰り返しているなという感覚。終わりがどうにも見えてこないフィーリングに、いったい何を信じればいいのかわからないという感覚。情報よりもむしろ、「これは大丈夫だ」と思える自分のいい本能/直観に常に頼らなくてはならない状況だとか。正確な情報ってのは、誰にでもすぐ入手できるものであるべきだというのに。うん、そういったことが作品に影響したね。──と言いつつ、と同時にこれは……パンデミックが襲った際の人びとの振る舞い方とそこから生まれた結果というのは、資本主義システムの下では人びとはそう振る舞う以外にないんだし、いずれにせよそれと同じ結果になる、ということでもあって。だから今回の作品にしたって、ずっと継続している物語のエピソードのひとつというか、『オースタリティ・ドッグズ』以来俺たちが語り続けてきたこと、そのなかの一話なんだ。
というわけで、俺はその面はあまり述べたくなかった。この試練だって、後期資本主義のまた別の一面に過ぎないんだし、あまねく広がった腐敗の現れであり、遂に本当に真剣な決断を下さなくてはならない地点にまで達した文明の側面なんだから。自分たちは何を信じるのか、そして自分たちはどう振る舞っていくのか、そこについて人類はシリアスな決断を下さなくちゃならないところまで来ているわけでさ。うん、そうした思いはたしかに、アルバムにある程度までは影響を与えた。おっしゃる通りだ。
ネガティヴィティにシニシズム、そして自己批判もあるけど、そうしたものからエネルギーを得ている。というわけで、そこはいまだに継続中だな。ただ、思うにほんと唯一、自分にとって重要なことという意味で……自分にどうしても語れないのは愛だなぁ。
■たとえば、ビリー・ノーメイツが参加した“Mork n Mindy”なんかはそういう気味の悪い不安をうまく捉えた曲だと思いましたが、あの曲はあなたの子供時代を反映したものらしいですよね?
JW:ああ、そうだ。あの曲は俺が子供だった頃についての歌で、そうだな、あれと“Fish Cakes”の2曲は、子供時代について歌ってる。自分の子供時代や、子供のときはどう思うんだろうといったことを考えるようになりはじめて……。俺は生まれつき、難病の二分脊椎症(spina bifida)を患っていてね。11歳のときに脊椎の大手術を体験したんだ。
■ああ、そうだったんですか。
JW:うん。でも、当時は二分脊椎症だったとは知らなくて、今年の夏に(コロナの影響で)ジムが閉鎖され、自宅の庭でエクササイズ中に背中を怪我して、はじめてそうだったと知った。で……うん、そのおかげで、手術を受けた頃に引き戻されたね。あれは、かなりエモーショナルな時期だったから。というわけであの頃を思い返したし、子供だった自分のことをまた考えるようになって。それにもちろん、いまの自分には子供もできたし、彼らの子供時代と自分自身の子供時代とをしょっちゅう比較するようにもなったわけ。だから……あの曲はアルバムに入れたかったんだよ、子供時代を考えれば考えるほど、自分のなかに色んな思いがたまっていったから。
■ビリー・ノーメイツは今年アルバムを出しましたが、あなたも1曲参加していますよね。彼女は抜群だと思いますが、あなたは彼女のどんなところを評価していますか?
JW:やっぱ、あの声だよね。それと、彼女の曲の書き方も。彼女は本当に、すごく、すごく才能があるし……うん、ちゃんとした、本当にオリジナルな人で。それに、彼女を聴いていると自分の頭にかつてのグレイトなシンガーがたくさん思い浮かぶんだ。とくに、過去の優れたソウル・シンガーの数々を思い起こす。音楽という概念を実践する面でも非常に腕の長けた人だし……とにかく彼女には、どこかしらすごくソウルっぽいところがあるんだよなぁ。と同時に、80年代っぽいところもかなり備えていて。そうした点が、ほんといいなと思う。
■Amyl and the Sniffersのエイミー・テイラーも参加していますが、今回なぜ女性シンガー2名とコラボしようと思ったんでしょう?
JW:俺たちも女性の存在を求めていたんだよ、だから、ほら……全般的に、女性が欠けてるわけだしさ(苦笑)。
■(笑)テストステロン値が高過ぎる、と。
JW:そう(笑)! 野郎が多過ぎだって。ハッハッハッハッ……ぎゃあぎゃあ騒いでる男どもが多過ぎる(苦笑)。
■アルバム名は「肋骨」で、女性はアダムの肋骨(=リブ)から作られたと旧約聖書にありますよね。それで女性が必要だったのかな?と。
JW:ああ〜! たしかに! なるほどねぇ。(笑)いや、そういうわけじゃないけど、でも実に古典的なポイントだな、それって。そういう風に自分が考えたことはなかったけどさ。
■このアルバム・タイトルを知ったときに、イギリスで70年代に発刊されたフェミニスト雑誌『Spare Rib』を思い出したんですよ。その書名はもちろん、聖書の「女性は男性の一部である」という発想を茶化したもので。
JW:うん、うん(うなずく)
■とはいえ、このタイトルの「スペアリブ」は、まさしく我々のことを指しているわけですよね。一本くらいなくなっても平気なあばら骨、いわば使い捨てライターのように取り替え可能な存在、という。
JW:イエス! でも……君がそうやってアルバムの概要をまとめてくれた方が実際よりはるかに面白いかもな、クハッハッハッハッ!
■(笑)ふざけないでください。全部、ちゃんと考えてるんでしょ?
JW:いやいや、そうやってあれこれ言われると、俺は「違う」って言い出すっていうね! アッハッハッハッハッァ〜……!
(ひとしきり笑った後で真顔に戻って)いや、うん、そうだよ。あのタイトルは基本的に、俺たちの政府は2020年のはじまり以来人びとをどんな風に扱ってきたか、ということで。無駄死にした死者の数──だから、あれだけ(コロナで)死者が出たけど、そのある程度までは防げたはずだった、俺はそう思っていて。そこで考えさせられたんだよ、政府は経済モデルに貢献している人民の生命よりも、その経済モデルを維持することの方に心を砕いているんだな、と。いやもちろんこれは、政府側はその点を意識してそうやっている、という意味ではないんだ。ただ、世のなかには常に、この経済モデルに貢献する人間たちが絶え間なく流入してくるわけでさ。ということは、この経済モデルを保存するためにだったら、政府の側には20万人であれ百万人の命であれ、たまにちょっとばかり人口を削ってもなんとかなる、そういう余裕があるってことだよ。
で、2020年のはじめからイギリスの公衆に対しておこなわれてきた安全対策の数々を考えれば考えるほど──わかるだろ? 英政府は(人民よりも)経済モデル維持の方をもっとケアしてきたんだな、という印象を抱くわけ。だから、政府の考え方は「肋骨をいくつか取り除いても、身体そのものはなんとか機能するからOK」みたいなものにはるかに近い、と。ということは、俺たちはみんなスペアリブだってことだよ。でも……このタイトルは、イギリスではおなじみな、中華料理のテイクアウト・メニューにもちなんでいて。
■ほう。
JW:わかるかな、スペアリブ? イギリスじゃどこでもお目にかかるありふれた食い物なんだけど(※ばら肉を骨付きで揚げたりバーベキューした、イギリスのお持ち帰りチャイニーズの定番料理)。ある意味、そこにも目配せしているタイトルだし、子供時代とも繫がっていて。
■……あなたはよく、食べ物について書きますよね?
JW:うん。
■どうしてですか?
JW:当たり前だろ、それって。
■「スペアリブ」はもちろん、これまでも「マックフルーリー」とか「イングリッシュ・タパス」とか。あなたは身体を鍛えていて、大食いしなさそうですけど、歌詞には食べ物や食べることに関する妙な執着があるように感じるんですが(笑)?
JW:いやとにかく、多くの人間が食えるのってそれくらいなわけじゃない? たとえば……ひとり分のチップス、その人が手に入れられるのはそれだけ、みたいな(※チップスはフライド・ポテト。日本のそれより厚めにカットされていてボリュームがあるにも関わらずひと袋200〜300円程度なので、本来は副菜であるチップスを主食代わりにする人もいる)。それとか、食べられるのは卵サラダサンドだけ、とか。だから、それって人びとはいかに……んー、あまりお金がない状態にいると、そういう安くてしょうもない食べ物でも美味く感じて大事に味わえる、そこに落ち着くんじゃないかと思う。それに、俺とアンドリューがふたりで話すのって、ほんと、食い物についてばっかだし。
■(笑)マジですか。
JW:いやだから、そこはまた……さっき言われたイングリッシュ・タパスだとか、マックフルーリーだとか、まあなんでもいいんだけど、そうやって俺が歌で取り上げてきたことって、俺がそういった食い物を食ってる日常の周辺で起きた色んなことを表象するものでもあるんだよ。それは子供時代の話も同様で、ガキの頃はとんでもなくひどいものを食わされてたよなぁ、みたいな文句をね(笑)。その手の話はしょっちゅうやってる。
■表題曲の“Spare Ribs”の歌詞にエイフェックス・ツインが出て来ますが、お好きですか?
JW:うん、彼はいいんじゃない? いやだから、あの歌詞で彼の名前を持ち出したのは、あの曲で歌っているのは──
■──知ったかぶりの、マウントしたいタイプ?
JW:(顔をしかめて)うんうん、あの手合いはね〜、ほんと、もう……
■(歌詞を引用して)「エイフェックス・ツインや/スペインのアナキストについてえんえん語ってる奴」と。
JW:うん、そうそう! だからさ、ああいう難しそうなことをぺらぺら触れ回ってる連中って、いざ「それってどういうことですか?」と突っ込まれると、実はそれをよく知っていないのがバレるっていう。となると、やっぱ思うよね、お前は常に「自分はこの手の世界にどっぷり浸かってますよ、熟知してます」って雰囲気を醸してきたのに、なんで自分の言ってきたあれこれをよく知らないんだい?と。
■“Fish Cakes”で繰り返されている「At least we lived」という言葉に込められている感情は、やはり絶望感なのでしょうか? すごく悲しい曲だなと思いますし、「少なくとも自分たちは生きたんだから」という一節にあなたが込めたのもそういう思いなんでしょうか。
JW:うん、ある意味、そうなのかもしれない……。うん、そうした悲しみをあの曲で伝えたかったのかもね。というのも、俺が子供の頃は……いや、そんなに悲しい子供時代だったとは思わないな。それよりもこう、とにかく退屈だった。狭く限られていたし、周囲にも大して何もなくて。しかも大人たち、当時接することになった大人のほとんどは、子供たちよりもひどい状態で。だから、とにかく何もかもがつまらなくみじめだと思えたし、憂鬱に映った。そこを歌にしたいなと。それらの体験を曲に含めたいと思ったんだ。それをやるのには、本当に苦戦したけどね。というのも、俺はあれを哀れっぽい曲には、聴き手に憐憫の情を掻き立てるような曲にはしたくなかったから。そうではなく、あの情景を表に見せたかっただけで。
■今年亡くなったアンドリュー・ウェザオールから受けた影響についてお話しいただければ。Two Lone Swordsmenの“Sex Beat”(ガン・クラブのカヴァー)には影響を受けたという話は読みましたが、それ以外で彼について思うことがあればお願いします。
JW:TLSのアルバム『From the Double Gone Chapel』(2004)で、彼らは──あれはたぶん4枚目か5枚目だったはずじゃないかな? あれを聴いて、俺の抱いていた……シンガーが歌う際のいいバッキング・サウンドとはどういうものになり得るか、そこについての考え方を部分的に変えさせられた。いいサウンドってのは何かという、その見方をね。あの雷みたくゴロゴロと鳴るベース・ラインに、あのアルバムでのアンドリュー・ウェザオールの歌い方に……それにキース・テニスウッド。彼とは知り合いで、たまに話す間柄だよ。本当にいい人だけど、うん、彼の用いたプロダクションの手法だとか。そういや、彼もブライアン・イーノの大ファンなんだよな。彼に「あのアルバムであなたが影響されたのは何だったんです?」と尋ねたら、「ブライアン・イーノにめっちゃ影響されたぜ!」って答えが返ってきて、俺は「クソッ、そうなのか!」みたいな(笑)。
■(苦笑)それはもう、あなたもイーノを聴かないと。意地を張らず、諦めて聴きましょう。
JW:(笑)あー、そうだねぇ、聴かないと……。ともあれ、うん、そういう話で。それに、アンドリューとも2回くらい実際に会ったことがあって。ほんと、イイ奴でね。本当にナイス・ガイで。全然──お高くとまったところや自己中心的なところのまったくない、じつに愛すべき人だった。だからうん、そこはものすごく感銘を受けたよね。でも、それだけじゃなく、彼の佇まいも印象に残ったな。ほら、あのタトゥーだったり……着る服を通じて自己表現する彼のやり方だとか、あれは無類のものだったっていう。ああいうことをやる人は決して多くなかったし、そこからも本当に影響された。とにかく、「自分の頭で考えろ」っていうこと。もっとも、その点については、他の人たちからも俺は多く学んできたんだよ。ただ、アンドリュー・ウェザオールはそのなかでもグレイトな人物のひとりだと思ってる。
■ウェザオールには「彼のスタイル」がありましたよね。そこが、他の人とは違っていたんだと思います。
JW:(うなずく)ああ。
■来年の抱負をお願いします。
JW:それは……やっぱ、またライヴをやることだよね。俺たち、日本にぜひ行きたいと思ってるし。
■ぜひ!
JW:うん、ほんと、日本に行けたらいいなと思ってる。とにかく日本で演奏するだけでいいんだ。そうやって向こうに行って……ギグをやって守り立てることで、『スペア・リブズ』にふさわしいだけのことをちゃんとやってあげたいな、と。いまは視界も開けた状態なわけだし、うん、もっと後になってからではなく、できれば早めにそれを実現したいと思ってる。
■アルバム音源も好きですが、あなたたちのエネルギーはライヴだと一層パワフルなので、日本でのショウが実現するのを祈っています。というわけで、本日はお時間いただき、ありがとうございました。
JW:こちらこそ、ありがとう。
★了
(2020年12月17日取材)


 Jam City
Jam City







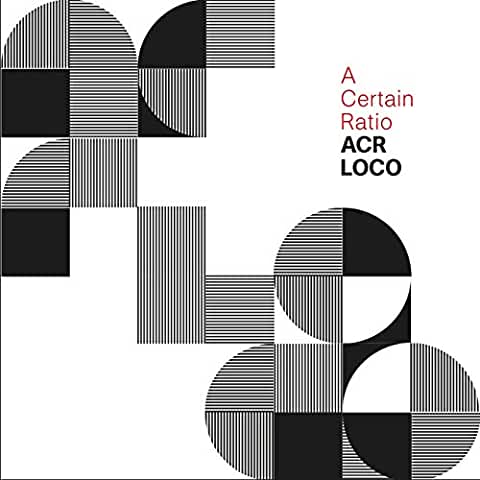
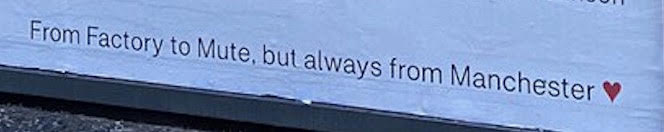


 デニス・ジョンソンとACR。
デニス・ジョンソンとACR。




