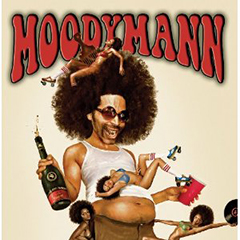MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Moodymann- Moodymann
結論から言えば、本作『Moodymann』はここ最近のムーディーマンのなかでは抜きんでている。まず何よりもこれは『Black Mahogani』以来の大きなリリースであり、ここ数年のベスト盤的な内容で、彼の集大成でもある。これからムーディーマン(デトロイトの、カルト的な人気をほこるハウス・ミュージックのDJ/プロデューサー)を聴きたいという若い方がこの文章を読んでいたら、迷うことなく本作を手にするがいい。
というか、このところのムーディーマンは、2012年の『Picture This』をのぞけば、長くもなく短くもないミニ・アルバムをヴァイナルのみの限定盤としてリリースしている(2008年の『Det.riot '67』、2009年の『Anotha Black Sunday』、昨年の『ABCD』……)。これらはすべてが予約で売り切れるほどの競争率なので、本当に好きな人/レコードのためには努力を惜しまない人しか聴いてないと思われる。今回もアナログ盤(12曲)に関しては予約でショートしているが、数週間後にCD(27曲)も出た。要するに、『Moodymann』は久しぶりに手に入れやすいアルバムで、『Picture This』からの再録(アンプ・フィドラーとのまったく素晴らしい“Hold It Down”)、2008年のホセ・ジェイムス“Desire”のリミックス、CDにはくだんの限定盤からの数曲も再録されている。さらにCDにはEPで発表した曲もいくつか再録していて、ラナ・デル・レイ“ボーン2ダイ”のリミックスまで入っている。CDはお買い得だ。
ムーディーマンは同郷のアンドレスとも似て、ハウス・リスナーのみならずヒップホップのリスナーの耳も惹きつけている。彼のリズム&ブルースのセンスゆえに、ハウス・ミュージックという枠組みを超えて、幅広いリスナーにアピールしているのだろう。現代のような音楽が売れない時代に、こと洋楽への関心が弱まっている日本において、ハウスを扱っているすべての輸入盤店で発売直後に「SOLD OUT」とするムーディーマンの人気は、異例中の異例だ。
昔、シカゴでハウス・ミュージックが生まれたとき、熱狂した多くのダンサーたちが「教会みたいだ」などという科白でその感動を表したエピソードは知られている。アフリカ系アメリカ人の教会は、──筆者も1度だけ行ったことがあるが──、宗教の現場というより共同体の集会場だ(デトロイトにおいては、奴隷制時代に奴隷を逃がす隠れ家でもあった)。大勢で歌って踊って、それもかなりハードに踊って、神父は、今週は寄付金を公園の壊れたブランコの修繕に使ったとか、建設的な報告する。そうした身近な人びとの集まっているにおいが、そしてデトロイトは破産したというニュースとは裏腹のファニーなアーバン・フィーリングが、尽きることのない地元愛が、果てしないセクシャルな衝動が、ファンキーな笑いが、ムーディーマンの音楽には注がれている。ラナ・デル・レイのリミキサーに抜擢されたほどの人物だが、基本、アンダーグラウンドの音楽家なので、誰しもが彼にアクセスできるわけではない。しかし、それでも彼の音楽は大衆音楽であり続ける。大衆は必ずしも多数を意味しない。むしろ多数の専制に逆らっている、少数派を大切にするという意味において「民衆」の音楽だと言えよう(……数日後には憂鬱な都知事選だ)。
そして、おっさん節の道化たアートワークが時代錯誤でどんなにダサかろうと、この音楽は──勝ち負けの音楽ではなく──共同体の音楽なので、おおらかに受け止められる。アホだなーと笑っても、音楽がうまいので、文句は言わせない。『Moodymann』の、ハウスから広がる多彩な展開(R&B、ファンク、ジャズ、8ビートの速いピッチの曲などなど)は、彼のキャリアを顧みれば自然な成り行きだ。それは成熟するデトロイト・ハウスの現在でもある。1曲、ファンカデリックの名曲“コズミック・スロップ”をがっつりサンプリングしている曲がある。そして、CDの中面の写真に写っている彼のスタジオのシーケンサーの上には、プリンスの『1999』のカセットが、どーんと、意味ありげに、結局のところこれが彼にとっての最良のポップ作品のひとつであると主張するかのように、置いてある。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE