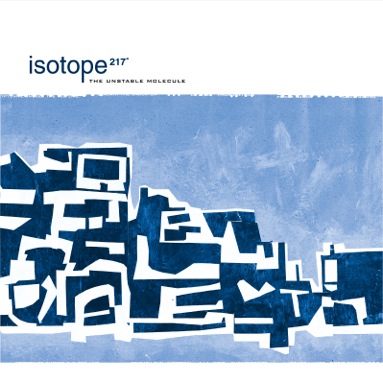DJテイがビートを作り、同時にラップをはじめたのは11歳のとき、つまり小学時代のことだった。16歳になると彼は地元のクルー、故DJラシャド、DJスピン、トラックスマン、DJアールらのTeklifeに最年少メンバーとして加入する。
シカゴのジューク/フットワークが発見されてから、そろそろ10年が経とうとしている。昨年はジェイリンの素晴らしい『ブラック・オリガミ』があって、今年はまずはDJテイの『スティル・トリッピン』というわけだ。DJテイの名は、OPNが3曲も参加したDJアールの『オープン・ユア・アイズ』でもクレジットされているが、わりと早いうちから〈ハイパーダブ〉がEPを出しているので、Teklife期待の若手がいよいよ同レーベルからの初アルバムを発表ということでシーンでは盛り上がっている。
DJテイは、18歳のときに最初のアルバムを自主で出しているのだが、そのタイトルは『オーヴァードーズ・オン・テックライフ』という、若気の至りに尽きるタイトルを冠している。そして今回は、『スティル・トリッピン』、「まだぶっ飛んでるぜ」というわけだ。
とはいえ、『スティル・トリッピン』は23歳の若さにまかせてぴょんぴょん跳びはねるというよりは、音楽的にじっくり聴かせる側面を持ち合わせているアルバムだ。ヒップホップ色も強く、ことトラップからの影響も見せてはいる。もちろん、ここ10年で発展したシカゴの革新的なダンスのビートはある。
しかしたとえばカナダの女性シンガー、オディール・ミルティルをフィーチャーした“Same Sound”における優雅なソウル・テイスト、テンポを落とした“9090”や“Anotha4”におけるドリーミーな叙情、ニュージャージーの女性DJ、UNiiQU3を招いての活気溢れる“Gimme Some Mo”、女性シンガーのファビ・レイナをフィーチャーしたチルアウト・トラックの“I Don't Know”……。
アルバムには多様性があり、DJペイパルやDJメニーたちに混じって、シカゴのダンスバトルには女性陣もいるんだよと言わんばかりに女性たちも参加し(サンプリングではなく実演として)、早熟なDJテイの音楽的な才能はいろんな意味で光っている。なかでも“Trippin”は最高の出来の曲のひとつ。
うーん、日本語の「フットワーク」という文字がデザインされたジャンバーも格好いいです。そしてフットワークらしいすばしっこい動きを見せる“Need It”や“I'm Trippin”──。
「トリップ」という言葉には、もちろん「旅をする」という意味も含まれているわけだが、じっさいにこうしてロンドンの〈ハイパーダブ〉から新作がリリースされているのであり、シカゴのフットワークはいまも世界を旅行中なのだ。シカゴがこの「旅」を止めたことはない。ハウス・ミュージックが生まれたときからずっと、シカゴはいまもなお、アンダーグラウンド・ダンス・ミュージックの王国である。