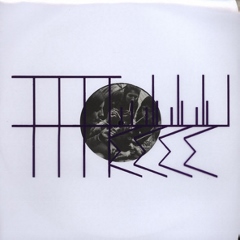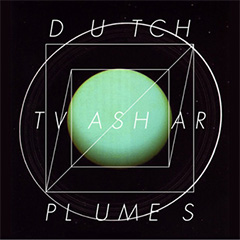MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Reviews > Album Reviews > Helm- Hollow Organ
最近誰の家に遊びに行ってもレコード棚にPANの音源がチラ見できることにヘソを曲げている僕は、その都度持ち主に対して「なんでみんな2~30ドルも出してPANの12インチ買うのかなー』等と嫌味を言っている。だって正直僕も好きだから。アートワークにアーティストのピックアップ、リスナーへの裏切り加減、と悪い印象がない。それでいてレーベルの実態もはっきりしない。そりゃあ気になるよ。
バーズ・オブ・ディレイ(Birds of Delay)は2000年代後半にロンドンを拠点としながら精力的に活動をおこなっていたハーシュ・ノイズ・ユニットだ。彼らのサウンド、また活動範囲やリスナーはかなりUSノイズ・シーンに食い込んだものであったと言える。どことなくスカルフラワーを彷彿させ、サイケデリックとも感じられるハーシュの嵐は、多くのUSノイズ・ファンを恍惚とさせた。しかし当時からポップなセンスを兼ね添えたユニットであったといまさらながら思う。
片割れのスティーヴン・ワーウィックはバーズ・オブ・ディレイ時代とまったくほぼ同じセットアップ、具体的にはクソ・カシオトーンとループペダル、そしてなぜかマラカスによる人力ハウスを展開するヒートシック(Heatsick)にてサンフランシスコを拠点にブレイクしている。先日、LAにて行われた〈ノット・ノット・ファン〉10周年イヴェントのトリもおおいに盛り上がり、ひと一倍盛り上がる汗ダクのブリット・ブラウンを見ながら爆笑していた。そしてスティーヴンがバーズ・オブ・ディレイにおける光であったとすればヘルム(Helm)のルーク・ヤンガーは影だ。
ヘルムは聴者に強烈な印象を残すサウンドではない。それでいて異常なまで中毒性が高い。同じく〈PAN〉からの前作『サイレンサー(Silencer)』そして本作『ホロウ・オルガン(Hollow Organ)』どちらも僕にとってBGMとして針を落とす頻度の高いレコードだ。サンプリングとモジュラー・シンセによる漆黒のマテリアルが剃刀の上に見事なコンポジションを成している。昨今のノイズ上がりの(クソ)テクノと一線を画すのはそのサウンドが破壊的ではなく圧倒的に繊細かつ空虚だからだ。トライバルなパーカッションに金属音、ミニマルなシンセサイズにノイズと、トレンドな素材を用いつつも誰よりも器用に展開し、緊張感をもって扱っている。いままでのグラハム・ランキン(Graham Lamkin)によるアートワークを考えれば、それはUSノン・ミュージックからの影響とも捉えられるし、いずれにせよドローン化するテクノ、ゴスやEBM、コンテンポラリー、ノイズの絶妙な着地点を計算しつつもそれが嫌味に聴こえないのが不思議だ。
サウンドシステムが劣悪な状況での記憶だが、ライヴでの退屈さには改良の余地はあれど、この手のサウンドではもっとも洗練された部類であることは間違いない。
倉本諒
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE