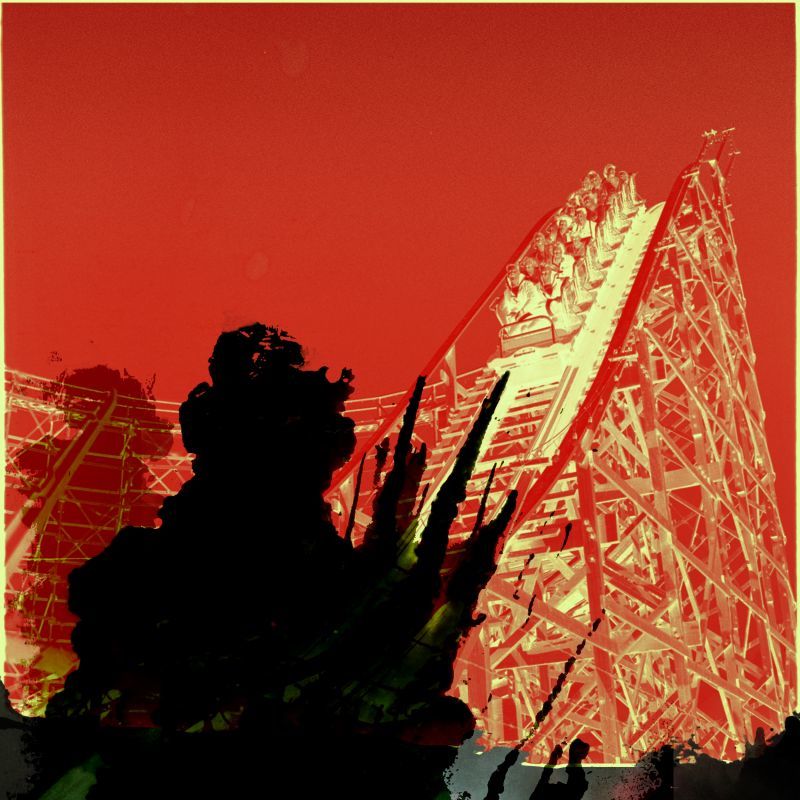MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > PANICSMILE- REAL LIFE
私はパニックスマイルの中心人物というよりバンドそのものというべき吉田肇が拠点を地元福岡に移すと耳にはさんだとき、東京のオルタナティヴ・ミュージック界の損失の大きさに嘆息を禁じえなかったが、よく考えると(考えんでも)、んなもんは東京偏重の感傷主義にすぎないのであって、現に吉田が地元に戻ってからもパニックスマイルは活動を継続し、こうして7年ぶり9作目のアルバムをとどけてくれた、そのタイトルを『Real Life』という、11曲入りのコンパクトディスクは1990年代後半以降の日本のアンダーグラウンド・シーンがいかなる変遷を経て2020年代初頭にかくあるかの証言である。なんとなれば私にはパニックスマイルの音はつねに現在を意味する、いまこの場を指さしている。
昨年刊行した『ele-king』24号の特集「オルタナティヴ日本!」のランキングには選出されたものの、ウェブ媒体には初登場だろうから簡単に来歴をご紹介すると、パニックスマイルは90年代初頭に福岡で活動を開始し、向井秀徳、ミスカズアキと共同で運営にあたったレーベル〈HeadacheSounds〉などでの自主活動を経て、98年同レーベルよりファースト『E.F.Y.L』を世に問うとともにメンバー全員で上京。翌年の2作目『We Cannot Tell You Truth, Again.』はホッピー神山の個人レーベル〈God Mountain〉がリリース元だった。余談になるが、〈ゴッド・マウンテン〉はホッピー神山と大友良英、フリクションのレックとデッドエンドの湊雅史によるオプティカル8を筆頭に、今堀恒雄と外山明、菊地成孔らのティポグラフィカ、内橋和久とナスノミツルと芳垣安洋のアルタード・ステイツや竹久圏と早川俊介のキリヒトなど、ジャンル無用で強度重視な展開をみせ、管見によれば、勝井祐二と鬼怒無月のまぼろしの世界とともに90年代オルタナティヴを代表する名個人レーベルであり、そのラインナップに念願叶って名を連ねた当のパニックスマイルは、しかしリズム隊のふたりがあいついで脱退するという憂き目をみていた。メンバー4人のうちふたりがあいついでバンドを去ったのである。のこった吉田はギターの保田憲一をベースにコンバートし、所属していたバンドを辞めた直後の石橋英子をドラムに誘い、ほどなくジェイソン・シャルトンがギターで加入し、それにより現時点でパニックスマイル史上最長となる陣容が整った。2001年の3作目『10songs, 10cities』こそ過渡期の記録の面持ちだったが、次作『Grasshoppers Sun』(2002年)で格段の飛躍を遂げた彼らはパニックスマイルのスタイルというべきものを確立する。その内実を簡便に要約するのは至難の業だが、ポストパンクのサウンドテクスチャとオルタナのリズムコンストラクションの複合的曲解からくる不協和音や変拍子が材料なのにそれでつくった建物は存外しっかりしているというか、とくに4作目は保田と石橋のリズム陣がたがいちがいの方向にすすもうとする2本のギターを接着し、さらに石橋英子のヴォーカルが全体を衣のように包みこむ新たな語法への確信がサウンドに宿っていた。
やがてパニックスマイルは水を得た魚になった。5作目の『Miniatures』は前作で彼らの表現を知悉したBOAT~NATSUMENのAxSxEの音づくりも奏功し、前作よりハードな質感で凝縮した音の塊が飛び交う快作となった。私が彼らのライヴに接するようになったのもこのあたりだったか。当時は『Miniatures』1曲目の “101 Be Twisted” がしばしば幕開けを飾っており、イントロのカッティングから一気呵成に雪崩れこむパニックスマイルの合奏風景はいまも瞼の裏に焼きついて離れない。おりしも2000年代なかごろ、インターネット前後の聴取環境の変化で音楽状況も地殻変動をきたしており、バンドという活動形態はむろんのこと、ロックなる形式もその中身もひとしく問い直しに迫られていた。オルタナティヴとは「もう一方」を意味する対向概念だが、それが形容する文言を完全に否定するのでなく、形式の潜在性を炙り出し次の道筋を提案する。すなわちオルタナティヴのあとにロックとつづけば、ここでいうロックとはロックのかたちをした新しいなにかであり、なにが飛び出すかわからなくてわくわくするシロモノを意味していた、すくなくとも1990年代なかばくらいまではそうだった(はずだ)が、いかに堅牢な概念やコミュニティといえども季節とともに移ろうのは世の理(ことわり)であるとみなすのは、しかし時代の趨勢になびかなかったものの存在をみえにくくする。
シーンの牽引車にして孤塁の守り手──などといわれてもありがた迷惑にちがいないが、2000年代後半のパニックスマイルにはそのことばがあたらずとも遠からずのたたずまいがあった。アンサンブルは成熟し曲の書き方もこなれていった。石橋英子の歌と多彩さは新しい武器だったが、それが生み出した可能性の余白が吉田肇のソングライティングセンスをひきだしてもいた。保田とジェイソンは異能の両輪であり、それらのパートが噛み合ったのが6作目の『Best Education』である。本作を『ele-king』24号が選出したことはすでに述べたが、執筆者のイアン・マーティンは選評で本作の魅力をバランス感覚にもとめている。つづめると「聴きやすいポストパンク版のキャプテン・ビーフハート」となる評言はおそらくこのアルバムの吉田とジェイソンのギターのからみに1969年のマジック・バンドの面影をみるからだろうが、本作の魅力は細部の記号性のみならず、聴きやすさ、親しみやすさ、ぶっきらぼうなポップさとでもいいたくなるものを総体で全力であらわす点にもあった。4曲目の “Pop Song (We Can Write)” はそのような姿勢への韜晦とも諧謔ともつかない内容だが、作中でくりかえす「ポップソング」の「ング」の歌いまわしに吉田肇の歌い手としてのクセになる魅力を再発見したのも本作だった。その点で『Best Education』の名は体をもあらわしており、ライヴもひきつづき充実していたが、3年後の『A Girl Supernova』でこのラインナップは幕引きを迎えることになるのである。メンバーの個人的な事情もからんだ決断だったと記憶しているが、コンセプトを練り編曲に凝った『A Girl Supernova』(2009年)を聴き直すと4人でできることはやり尽くしたのが実情だったのではないか。
おりしも2000年代も終わりにさしかかったあたり。同時多発テロ、イラク戦争、リーマンショックとつづいたあの10年のあいだ世界は翻弄されっぱなしだった。では音楽はどうだったのか。ことにオルタナティヴな音楽は。インターネットで聴き方は変わったが、アーカイヴへのショートカットは懐古趣味を亢進させはしても、オルタナティヴな音楽を志向するものにはヒントの糸口になるどころか、還流する無限とも有限ともつかない情報をもてあますばかり。バンドという形態の機動性よりロックなるフォーマットの受動性に焦点があたったのもこの時期だったか。つまるところオルタナティヴ・ロックもオルタナという型に嵌まった、と。
吉田肇にそのような反問や煩悶ともつかないものがあったかは知らない。とまれ2010年が転機だったのはまちがいない。彼らはその年の早春、渋谷 O-Nest、秋葉原グッドマンにつづく3月28日の下北沢シェルターの自主企画をもって2000年代をしめくくった。さらに3年後、パニックスマイルは吉田とともにバンドにのこったベースの保田がギターにまわり、松石ゲルとDJミステイクをリズム隊に加えた新ラインナップで8作目『Informed Consent』を世に問うた。お家芸といえる変拍子と複合リズムはプリミティヴさを増し、とらえようではバンド史上もっともビーフハート度の高いこのアルバムで心機一転、反転攻勢に出るかと思われたパニックスマイルだったが、ここから彼らは短くない期間口を噤んでしまう。初期には1~2年のスパンだったアルバムのリリースはこの時点で3~4年と間遠になっていたものの、『Informed Consent』から本作までは7年かかっている。むろん手をこまねいていたのではない。吉田とドラムの松石がのこり、新たにギターで中西伸暢が、ベースには元イースタンユースの二宮友和が加わりラインナップは一新、それにより体質も刷新した。具体的には幾多のリフレインでモザイク模様を組み上げる従来の手法から個々メンバーの資質を活かす方向性に舵をきったというか。特筆すべきはベースの存在感で、奏法や音色の多彩さは音楽性の幅を生み、作品の厚みにつながっている。他方、吉田の手になる楽曲のオブセッシヴな歌詞や緊張感の高さは据え置きで、彼ら一流のぶっきらぼうなポップセンスはいくぶんかまろやかに仕上がっている。収録曲に目を転じると、トシちゃんのヒット曲をもじった “Hattoshite Bad” にはじまり、ポエトリーリーディング風の “Hands Free”、ギターのフレーズも印象的な “Best Hit Kiyokawa” ときて、全員が明後日の方向に走り出すかのごとき “I Wanna Be Strong” などは自家薬籠中のものの趣だが、幕引きの “Living In Wonderland” では4管を客演に迎え新領域に踏みこんでいる。パニックスマイルはかつて石橋英子の在籍時に彼女の演奏するフルートをとりいれたこともあったが、今回の管の間欠的なフレーズに耳を傾けると、その執拗な反復は装飾的効果よりむしろ構造を志向しているのがわかる。基本形をふまえながら新機軸を打ち出すこのやり方は結成当初からほとんどゆらがないが、表層的な飛躍より歩幅を確認できる前進を好む彼らのスタンスは煽情的なジャーナリズムの見出しよりむしろ、ことばの真の意味でのオルタナティヴに奉仕しつづける。すなわち音楽のありうべき場所(オルタナティヴ)をさししめすのである。
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE