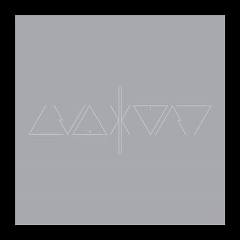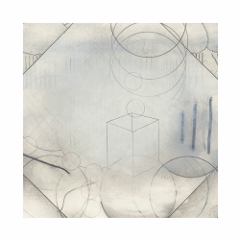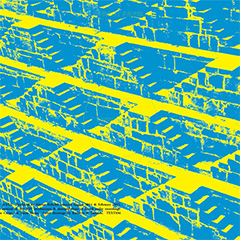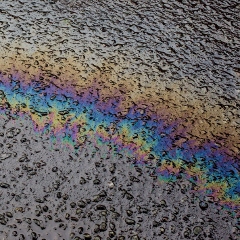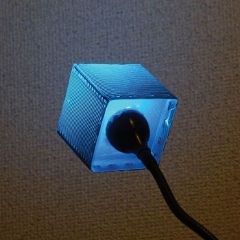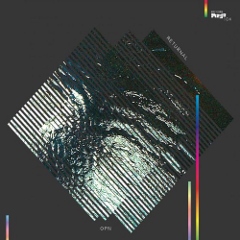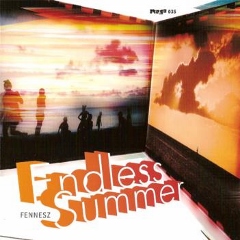MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > Electronica “New” Essential Discs- ──エレクトロニカの“新”新世紀、シーンを書き換える16枚の注目作
Electronica “New” Essential Discs
──エレクトロニカの“新”新世紀、シーンを書き換える16枚の注目作
文:髙橋勇人、デンシノオト、野田努、橋元優歩 Nov 10,2015 UP
「こういうひとつの括り方に抵抗を感じる人がいるのはわかっているが、なかば強引にでも括った方が見えやすくなることもある。もともと踊れもしないテクノ(エレクトロニック・ミュージック)を、しかし前向きなニュアンスで言い直したのがエレクトロニカ(ないしはえてして評判の悪いIDM)なるタームである」
「2010年に〈エディションズ・メゴ〉からOPNが『リターナル』を出したときは、この手の音楽がエレクトロニカというタームを使って解釈されることはまずなかったが、しかし、エイフェックス・ツインが華麗な復活を遂げて、かたやEDMが全盛の今日において、エレクトロニカ新世紀と呼びうるシーンが拡大するのはなんら不思議なことではない」
(本特集巻頭言より)
──とすれば、フロアにもベッドルームにも収まらない今日的なエレクトロニカとはどのようなものか。ディスク・レヴューで概観する。
シーンに現れたときにはマスクを被り謎の存在だったアコード。彼らはマンチェスター近郊を拠点に活動をするシンクロとインディゴによるテクノ・ユニットだ。プロジェクトをはじめるにいたってエイフェックス・ツイン、セラ、シャックルトンといった面々を念頭に置き、この作品においてはその影響がジャングルやダーク・アンビエントを通して噴出。そのリズムをアタマで理解しようとすると複雑で脳の中枢が熱くなり、体で捉えようとすると妙なダンスが生まれる。また今作の後半にはフィスやリージスといったプロデューサーたちのリミックスを収録していて、特にハクサン・クロークによる「数多くの証人」と題された曲がトんでいる。前半の楽曲すべてをひとつにリフィックスしてまとめたもので、家でもフロアでも聴けないような音の暴力が10分続き、ド派手なSF映画のようにそれが突如パッと終わる。(髙橋)
思えば、転換期は2010年だった。アクトレスで言えば『Splazsh』の年。その後も『R.I.P』、そして『Ghettoville』へと着実に我が道を進んでいる。UKクラブ・カルチャーから生まれたモダン・エレクトロニカを代表する。(野田)
エレクトロニカとは、いかに工夫するか。リチャード・D・ジェイムスにとってのそれは機材の選び方にも関わっている。高価なモジュラー・シンセや最先端のデジタル環境を賞揚するわけではない……という話は佐々木渉に譲ろう。『Syro』から続く3作目は、アシッド・サウンドの最新型。(野田)
日本においてこのエレクトロニカ・リヴァイヴァルの風を敏感に感じ取ったひとりが、アルビノ・サウンド。詳しくはインタヴューを参照。(野田)
音楽作品において、これほど強烈なヴィジュアルは、久しぶりである。若く敏感な感性は、なんとも妖しい光沢を発しているこのヴィジュアルに間違いなく手を伸ばすだろう。アルカはそういう意味で、現代のハーメルンの笛吹き男である。(野田)
好き嫌い抜きにして、フォー・テットの功績は誰もが認めざる得ないだろう。最新作は2曲収録。メトロノーミックなドラミングの上を、エキゾティズムを駆り立てるように、インド人の歌のサンプリングが挿入され、叙情的な展開を見せる1曲目。そして静かにはじまり、多幸的な協奏のなか、心憎いドラミングでエンディングを用意するもう1曲。見事、というほかない。“ストリングス・オブ・ライフ”のカヴァーも素晴らしかったし。(野田)
〈リヴェンジ(RVNG Intl.)〉からの『ムーヴメント』(2012年)がクラブ・シーンにも届いたこともあって、新作は名門〈4AD〉からのリリースになったサンフランシスコ出身のホーリー・ハーンダン。簡単にいえば、ローレル・ヘイローとは対極にいるプロデューサーで、彼女の女性らしい“声”がこの音響空間では重要なファクターとなっている。「R&Bエレクトロニカ」とでも言ったらいいのかな。(野田)
https://www.youtube.com/watch?v=nHujh3yA3BE
ブルックリンの新世代電子音楽マスターが、2013年にOPN主宰〈ソフトウェア〉からリリースしたアルバム。デトロイトの高揚感と、ハウスの優雅さと、ミニマル・ダブの快楽性と、00年代以降のアンビエント/ドローンの浮遊感を、ポスト・インターネット的な情報量と感性で(再)構築。4/4のテクノ・マナーと、雲の上を歩いているようなスモーキーな感覚が堪らない。あの〈オパール・テープス〉などからも作品をリリースしている。(デンシノオト)
ザ・バグことケヴィン・マーティン、イラストレイターとしても活躍するキキ・ヒトミ、詩人でありテクノ・アニマルでマーティンと共演したこともあるロジャー・ロビンソンによるスーパー・ダブ・トリオが、電子音楽化クリスチャン・フェネスと組んだ意外作。家(に籠る)系アカデミシャンを、ストリートの知性派ギャングが外へ引きずり出したらどうなるのか? いや、ここでの実験はその逆だろうか。〈ハイパーダブ〉からのリリース作で聴けるスモーキーで力強いダブステップは押しやられ、フェネスの繊細な残響プロダクションがバグのラフさをときに助長し、ときに漂白する。リズムがもう少しあってもいいかなと思う気もするが、両者のバランスを考えれば納得もできる。インテリジェント・ダブ・ミュージック。(髙橋)
ローレル・ヘイローが2010年に何をやっていたかと言えば、〈ヒッポス・イン・タンクス〉からチルウェイヴ風の柔らかい作品を出していたのだった。が、ヨーロッパを経験してからは、彼女の音楽は遠近法のきいた音響のダンス・サウンドへと変容した。2013年に〈ハイパーダブ〉から出した12インチ「ビハインド・ザ・グリーン・ドア」に収録された“スロウ(Throw)”なる曲は彼女の最高作のひとつで、ピアノとサブベース、パーカッションなどの音の断片の数々は、宙の隅々でささやかに躍動しながら、有機的に絡み、全体としてのグルーヴを生み出す。テクノへと接近した新作においても、立体的にデザインされた小さな音の断片とサブベースが、独特のうねりを創出している。凡庸のテクノとは違う。女性アーティストに多く見受けられる甘い“声”(ないしは女性性)をいっさい使わない硬派による、素晴らしい作品だ。(野田)
サクラメントのプロデューサー。2012年にアルバム『ファンタスティック・プラスティック』でデビューして以来、ヒップホップに軸足を置きつつもしなやかに音楽性を変容させ、翌年の『オルタネイト/エンディングス』ではジャングルを、そしてこの『パターン・オブ・エクセル』ではアンビエント・ポップを展開。2015年はジョーイ・バッドアスのプロデュースで話題盤『B4.DA.$$』にも参加するなど、時代にしっかりと沿いながらもジャンル性に固執しない無邪気さを発露させている。自らが「ピュア・ベイビー・メイキング・ミュージック」と呼ぶもうひとつのペルソナ、ファースト・パーソン・シューター(FPS)名義ではチルウェイヴに同調。クラムス・カジノやスクリュー、ウィッチ・ハウスとも隣り合いながら、まさにFPS(一人称視点のシューティング・ゲーム)──主観性が先行する世界をドリーム・ポップとして読み替え、2010年前後のリアリティを提示した。(橋元)
〈テクトニック〉や〈Keysound〉といったレーベルからリリースを重ねてきた、UKのグライム・プロデューサー、ロゴスのファースト・アルバム。マムダンスとの『プロト』(Tectonic, 2014)ではUKハードコアの歴史を遡りフロアを科学する内容だったのに対して、こちらはリズム・セクションを可能な限り廃して、空間に焦点を当てたウェイトレス・グライムを前面に出し、そこにアンビエントの要素も加えた実験作。グライムの伝統的なサウンドである銃声や叫び声のサンプリングと、尾を引くベース・キックがフロアの文脈から離れ、広大な宇宙空間にブチまけられているかのような様相は恐怖すら覚える。「グライムを脱構築していると評された」本作だが、本人は大学で哲学を学んだ経験から「ロゴス」の名前を採っているとのこと。(髙橋)
Sndのマーク・フェルも長きにわたってこのシーンを支えているひとり。2010年以降はコンスタントに作品を出している。これもまたミニマルを追求した作品で、NHKコーヘイとも共通するユーモアを特徴としている。(野田)
NHKコーヘイは、本当にすごい。〈ミル・プラトー〉〈スカム〉〈ラスターノートン〉と、そのスジではカリスマ的人気のレーベルを渡り歩き、ここ数年は〈PAN〉、そしてパウウェルの〈Diagonal〉からも12インチを切っている。もちろん彼にとっての電子音楽は大学のお勉強ではない。それは感情表でもなければ研究でもない、おそらくは、意味を求める世界への抵抗なのだろう。2015年の新作では、素っ頓狂なミニマルを展開。小さなスクラッチノイズのループからはじまるこの反復の、どこを聴いても物語はない。タイトルは、あらためて言えば、NHK『番組』。(野田)
この1曲目から2曲目の展開を、大音量で聴いていない人は……いないよね? いい、1曲目、そして2曲目だよ。そうしたら、最後まで聴いてしまうだろう。(野田)
OPNが錯視家なら、パテンは詐欺師。「D」とだけしか名乗らないロンドンの“ミステリアスな”プロデューサーによるセカンド・フル。煙に巻くようなタイトルやアートワーク、あるいは言動によって、アブストラクトなダンス・トラックにアートや哲学の陰影をつけてしまうスリリングなマナーの持ち主だ。〈ノー・ペイン・イン・ポップ〉から最初のアルバムを、〈ワープ〉から本作をリリースしたという経歴は、〈エディションズ・メゴ〉と〈メキシカン・サマー〉をまたぐOPNが同〈ワープ〉と契約したインパクトに重なり、当時のインディ・シーンにおける先端的な表現者たちがいかに越境的な環境で呼吸をしていたのかを象徴する。とまれ、Dは人気のリミキサーにして自身もレーベルを主宰するなど才能発掘にも意欲的。彼の詐術とはまさにプロデューサーとしての才覚なのかもしれない。(橋元)
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE