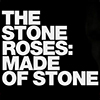MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Regulars > アナキズム・イン・ザ・UK > 第34回:This Is England 2015
『The Stone Roses:Made of Stone』日本公開用パンフのためにシェーン・メドウズにインタヴューしたとき、「わたしは『This Is England』シリーズの大ファンです。『This Is England 90』はどうなってるんですか」などという素人くさい質問をぶつけてしまったことが含羞のトラウマとなり、『This Is England 90』には複雑な想いがあった。が、あれから早くも2年の月日が流れ、わたしは自宅の居間でイカの燻製を食いながら当該作を見ていた。
(このシリーズの歴史を説明するとそれだけで連載原稿が終わってしまうので、ここではすっ飛ばす。知りたい人は拙著『アナキズム・イン・ザ・UK』のP136からP145とか、あるいはネット検索すれば日本語でもそれなりの量の情報は手に入るし、こういう映像もある)
*******
『This Is England 90』は、チャンネル4で4回終了(最終回だけ長編の1時間半)のドラマとして放送された。ストーリー展開は『This Is England 86』に似ている。サブカル色濃厚、時代ジョーク満載の1回目で視聴者を大笑いさせつつノスタルジックな気持ちにさせ、2回目までそれを引っ張り、3回目でいきなりダークな方向へ走りはじめて、4回目はずっしりへヴィ。という、メドウズ進行の王道だ。
わたしが前述の質問をしたとき、メドウズは「90年は俺のストーン・ローゼスへの愛が最高潮に達していた年だったから、そうしたことが何らかの形で『This Is England 90』にも出て来る」
と答えたが、たしかにローゼスは主人公たちの物語の壁紙として梶井基次郎の檸檬のように黄色いアシッドな光を放っている。(ウディが『Fool’s Gold』のイントロを歌うシーンは今シリーズのハイライトだ)
『This Is England 88』の最後で復縁したウディとロルの間には2人目の子供が生まれているし(1人目はウディの子供ではなく、ミルキーの子供だった)、ロルや妹のケリー、友人のトレヴは給食のおばちゃんとして働いていて、専業主夫になったウディやミルキー、カレッジをやめたショーンらのために子供たちの給食を職場からくすねているという、相変わらず底辺っぷりの著しい元ギャングたちの姿で本シリーズははじまる。
1990年はマーガレット・サッチャーが首相官邸を去った年だ。
それはわたしがけしからんフーテンの東洋人の姉ちゃんとしてロンドンで遊んでいた年でもあり、周囲にいた(やはりけしからん)若者たちが、サッチャーが官邸を去る日の模様をテレビ中継で眺めながら、「私はこの官邸に入った時よりもこの国を明らかに良い状態にして去ることができることに大きな喜びを感じています」というスピーチを聞いて、「私はこの国を無職のアル中とジャンキーの国にして去ることができることに大きな喜びを感じています。おほほほほほほ」とおちょくっていたことをよく覚えているので、メドウズがあの時のサッチャーの映像を『This Is England 90』の冒頭に持ってきた理由はよくわかる。
「サッチャーを倒せ」「サッチャーはやめろ」と日本の現在の首相ばりに嫌われていたサッチャーは90年に退任した。ほなら労働者階級の若者たちも幸福になればいいじゃないか。が、彼らは全然ハッピーにならない。むしろ、不幸はより深く、ダークに進行して行く。
ロルの妹のケリーは、ドラッグに嵌って野外パーティで輪姦される。さらに父親を殺したのは本当は姉のロルだったと知って家出し、ヘロインに手を出してジャンキー男たちのドラッグ窟に寝泊まりするようになる。
一方、ロルの父親殺害の罪を被って刑務所に入っていたコンボの出所が間近に迫り、ロルとウディが彼の身柄を引き取るつもりだと知って、ミルキーは激怒する。黒人の彼には右翼思想に走っていた白人のコンボに暴行されて死にかけた過去があるからだ。「レイシストと俺の黒人の娘を一緒に暮らさせるわけにはいかない」と憤然と言うミルキーに、「お前だって俺の最愛の女を妊娠させたじゃないか。出産に立ち会ってたらお前の(黒人の)赤ん坊が出て来たんだぞ。それでも俺はお前を許したじゃないか。コンボを許せ」とウディは言うが、ミルキーの気持ちは変わらない。
コンボは刑務所でキリスト教の信仰に目覚め、改心して子羊のような人間に生まれ変わっている。しかしミルキーは出所してきた彼に大変なことをしてしまう。
というストーリーの本作は、1作目の映画版に話が回帰する形で終了する。
一方でロルとウディがついに結婚するというおめでたい大団円もあり、ミルキーがコンボに復讐するというのも大団円っちゃあ大団円だが、こちらは真っ暗で後味が悪い。
結婚式の披露宴にはケリーも戻って来て、みんなが幸福そうに酔って踊っている姿と、ひとり別室でむせび泣いているミルキーの姿とのコントラストで最終回は終わる。ふたつの全く異質な大団円を描いて終わったようなものだ。なんとなくそれはふたつの異なる中心点を起点にして描いた楕円形のようでもあり、おお。またこれは花田清輝的な。と思った。
それはサッチャーがいなくなっても幸福な国にはならなかった英国を体現するようで辛辣だが、同時にそれでもそこで生きてゆく人びとを見つめる温かいまなざしでもある。
*******
以前、うちの息子の親友の家に行ったときのことである。
うちの息子の親友はアフリカ系黒人少年であり、その父親は「黒人の恵比須さんみたいな顔で笑うユースワーカー」としてわたしのブログに以前から登場しており、拙著『ザ・レフト』のコートニー・パイン編のインスピレーションにもなった。
彼には4人の息子がおり、長男はもうティーンエイジャーなのだが、うちの息子を彼らの家に迎えに行った折、長男の友人たちが遊びに来ていた。で、十代の黒人少年たちはソファに座ってゲームに興じていたわけだが、恵比須さんの長男がこんなことを言っていた。
「いやあいつはバカっしょ。しかも赤毛。しかもレイシスト。粋がって『ニガー』とか言いやがるから、俺は言ってやったね。『ふん。女も知らねえくせに。ファッキン不細工なファッキン童貞野郎』って」
「おー、言ったれ、言ったれ」みたいな感じで2人の友人は笑っている。
と、エプロン姿でパンを焼いていた恵比須顔の父ちゃんが、いきおい長男の方に近づいて行って、ばしこーんと後ろ頭を叩いた。
「痛えー、何すんだよー」
と抗議する長男にエプロン姿の恵比須は言った。
「どうしてそんなファッキンばかたれなことを言ったんだ」
「だってあいつファッキン・レイシストなんだよ」
「そういうことを言ってはいけない」
「ふん、あんなアホにはヒューマンライツは適用されない。あいつは最低の糞野郎だ」
「俺はPCの問題を言ってるんじゃない。レイシストに同情しろなんて言ってないし、糞野郎は糞野郎だ」
血気盛んな十代の黒人少年たちの前に仁王立ちしたブラック恵比須は言った。
「だが、俺たちの主張を正当にするために、俺たちはそんなことを言ってはいけないのだ」
きっと彼は黒人のユースワーカーとして何人もの黒人のティーンにそう言って来たんだろう。ロンドン暴動の発端となったトテナムで長く働いたという彼の言葉にはベテランの重みがあった。少年たちはおとなしく食卓について父ちゃんが焼いたコーンブレッドを食べ始めた。
わたしと息子もタッパーにコーンブレッドを詰めてもらって持って帰った。ブラック恵比須は竿と鯛を持たせたくなるぐらいにこにこしてエプロン姿で手を振っていた。
*******
元右翼のコンボが黒人のミルキーの指図で殺されたことを暗示するような『This Is England 90』のラストシーンを見ながら、ブラック恵比須とミルキーは同じぐらいの年齢だと思った。
1990年はもう四半世紀も前になったのだ。児童への性的虐待や近親相姦や殺人やレイプやドラッグ依存症は、まあ人間が生きてりゃそういうこともあるさー、お前らがんばれよ。と登場人物たちに乗り越えさせているメドウズが、レイシズムだけはそう簡単に乗り越えられない業の深いものとして最後に浮き立たせている。
この認識を持って、この諦念に立脚して、それでもこの国の人たちはレイシズムに向き合ってきた。というか、向き合うことを余儀なくされてきたのだ。これは四半世紀経ったいま、移民・難民の問題として再び浮上している。
ここに来て本作を見る者は、これは2015年のイングランドの話だと気づくのである。
おまけ。もう一つの『This Is England 90』
(マーガレット・サッチャーVS ジェレミー・コービン。これも25年前だが、2015年の話でもある)
Profile
 ブレイディみかこ/Brady Mikako
ブレイディみかこ/Brady Mikako1965年、福岡県福岡市生まれ。1996年から英国ブライトン在住。保育士、ライター。著書に『花の命はノー・フューチャー』、そしてele-king連載中の同名コラムから生まれた『アナキズム・イン・ザ・UK -壊れた英国とパンク保育士奮闘記』(Pヴァイン、2013年)がある。The Brady Blogの筆者。http://blog.livedoor.jp/mikako0607jp/
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE