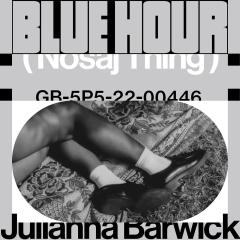MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Nosaj Thing - ノサッジ・シング──アンビエントで繊細な美学をもった新作を語る
取材に入る直前。インタヴュー・カットを撮りたいので、最初の数分だけ照明を落とさせてもらいますと、そう伝えた。「大丈夫、暗いほうが好きだから。暗いのはいい」。その返答は、まさに彼の音楽を体現していた。どこか内省的で、しかしけして感情を爆発させることはない音楽。映像喚起的で、光よりも影のほうを向いてしまうタイプの、マシン・ミュージック。
バックグラウンドは00年代後半の西海岸にある。いわゆるLAビート・シーンが彼のスタート地点だ。当地のDJ/プロデューサー/エンジニアであり、レーベル〈Alpha Pup〉の主宰者でもあるダディ・ケヴが、ビートメイカーにフォーカスしたパーティ《Low End Theory》を開始したのが2006年。そこでケヴがノサッジ・シングの(のちにファースト・アルバム『Drift』に収録されることになる)“Coat Of Arms” をヘヴィ・ローテイションしたことが、彼のその後の飛躍につながった。
とはいえデイダラスやフライング・ロータス、ティーブスといったあまたの才能ひしめくムーヴメントの渦中、やはりノサッジ・シングの音楽はどちらかといえば控えめに映るものだったのではないだろうか。以下に読まれる「日中はヒップホップのアーティストのプロデュースを手がけて、夜はアンビエント・ミュージックをつくって自分の世界に籠もる」との本人の弁は、まさに彼の音楽の特徴をよくとらえている。間を活かし、表面的な華やかさよりも、ある種の静けさや落ち着きのなかに独自の雅を展開していくこと。2010年代に入りチャンス・ザ・ラッパーやケンドリック・ラマーといった大物をプロデュースしたり、トラップの感覚とエレクトロニック・リスニング・ミュージックを折衷する『Fated』や『Parallels』といったアルバムをつくり終えた今日でも、その軸はまったくブレていない。
むろん、変化している部分もある。この秋リリースされ、年明けにアナログ盤の発売を控える5枚目のアルバム『Continua』に色濃くあらわれているのは、マッシヴ・アタックやトリッキーといったブリストルのサウンド、かつてトリップホップと呼ばれた音楽からの影響だ。
最たる例はジュリアナ・バーウィックを迎えた “Blue Hour” だろう。この曲がまたとんでもなくすばらしいのだけれど、驚くなかれ、ふだん声をあくまでひとつのサウンドとして利用している彼女が、ここでは歌詞を書き明瞭に歌っている。ゲストに新たな試みを促す力が、ノサッジ・シングの「暗い」トラックには具わっているにちがいない。
バーウィックはじめ、ほとんどの曲にゲストが招かれている点も大きな変化だ。サーペントウィズフィートやトロ・イ・モワ、パンダ・ベアなどなど、多彩かつジャンル横断的な面子が集結しているが、なかでも注目しておきたいのは今年素晴らしいデビュー・アルバムを送りだしたコビー・セイと、ele-king イチオシのラッパー=ピンク・シーフ。ここでもまたノサッジ・シングは、普段の彼らからは得られない、声の抑揚やムードを引きだすことに成功している。
ほの暗く、静けさを携えながらも、内にさりげない光彩を潜ませた音楽──それは、激動の一年を締めくくろうとしているわたしたちリスナーが、じつはいちばん欲しているものかもしれない。間違いなく、すごくいいアルバムなので、ぜひ聴いてみてほしい。
マッシヴ・アタックやポーティスヘッド、トリッキー、アンクルとか。そういったものにインスピレーションを得ました。
■NYにいる友人から聞いた話では、いま物価の上昇がすごいらしいですね。レストランにふたりで入ると以前は50ドルで済んだところが100ドルはかかるようになったそうです。LAはどんな具合でしょうか? NYはパンデミックで仕事を失った人も少なくなく、さらに追い打ちをかけるように物価高になり、ホームレスや精神不安を抱えるひとも増え、治安も悪くなったと聞いています。
NT:やっぱりLAも同様にインフレがひどくなりました。とくにガスの料金がすごく上がっていてみんな苦しんでいます。ホームレスにかんしては、LAはここ10年くらいずっと問題視されてきていましたので、パンデミックの影響というよりも、ひとつの社会問題としてつねに存在していました。個人的には、パンデミックのときはたまにゴッサム・シティ(『バットマン』で描かれる、荒廃した治安の悪い都市)に住んでいるような気分になりましたね。
■新作は最終的にはとてもムーディーで、ある意味では心地よい音楽にまとまっていますが、背景には気候変動など未来への不安や、あなた個人の家宅侵入被害といった、いくつかの重たいテーマが潜んでいるようですね。今回は5年ぶりの新作で、12人ものゲストを迎えたアルバムです。どのようにこのプロジェクトがはじまり、進んでいったのかを教えてください。
NT:前のアルバムを2017年にリリースしたんですが、そこからどういう方向性にいくかを考えるのにしばらく時間を要しました。どのように自分の次のアルバムをつくりあげていくか、すごく悩みましたね。パンデミックは世界じゅうの人びとにとって難しい時期だったと思うんですが、自分にとってその時間は貴重なものだったと考えています。というのもこの数年間、5~7年はずっとツアーをしたり、他のアーティストのプロデュースを手がけたりしてきて、そういった経験を自分の世界にどのように落としこむかを考えていたので、自分にとってはある意味とてもポジティヴな時間でした。
今回のアルバムそのものは、とてもシネマティックなものだと思っています。僕は85年に生まれたんですけど、90年代半ばの音楽をとくによく聴いていたので、そういった音楽を自分なりに解釈して取りこむことにチャレンジしました。たとえばマッシヴ・アタックやポーティスヘッド、トリッキー、アンクルとか。そういったものにインスピレーションを得ました。とはいえ、ノスタルジックになりすぎないよう、細心の注意を払いました。
それと、今回のアルバムはこれまででもっともコラボレーションを全面に打ちだしたものになっています。ぼくはもともとすごくシャイな人間ですが、今回参加してくれたアーティストたちには個人的に知っていたわけではないひとも何人かいて、そういうひとたちにも連絡をとって参加してもらうようにお願いしました。だからさまざまなスタイルをうまくミックスすることができたアルバムだと思います。

日中はヒップホップのアーティストのプロデュースを手がけて、夜はアンビエント・ミュージックをつくって自分の世界に籠もる──そういうような棲みわけをしてきました。
■あなたの音楽はビート・ミュージックでありながら、ある種の静けさや暗さを携えていて、アンビエントにも通じる部分があるように感じます。過度にハイテンションになる音楽ではなく、こういったサウンドができあがるのには、あなたの性格や生い立ちも関係しているのでしょうか?
NT:LAで育って、さまざまな音楽やカルチャーに触れる機会があったことは大きかったと思います。東京も同じような感じですよね。自分の世界をクリエイトするなかで、アンビエントをつくることは一種のセラピーのように感じています。これまでいろんなアーティストとセッションをしたり、プロデュースをしたりしてきましたけれど、たとえば日中はヒップホップのアーティストのプロデュースを手がけて、夜はアンビエント・ミュージックをつくって自分の世界に籠もる──そういうような棲みわけをしてきました。それこそブライアン・イーノがさまざまなジャンルの音楽をプロデュースしていて、ロックからアンビエントまでいろいろやっていましたが、歳を重ねるうちに彼のようなことをやりたいと思うようになりましたね。
■エレクトロニカ的だけれどもヒップホップやR&Bでもあり、新作にはあなたが好きな音楽がいろいろ詰まっています。なかでもやはりヒップホップの要素は大きいように感じましたが、いかがでしょう? とくにピンク・シーフはエレキングが好きなラッパーのひとりですので、参加しているのが嬉しかったです。彼の魅力はどういうところにあると思いますか?
NT:ピンク・シーフには、とても新鮮で近未来的な印象を抱きました。彼のレコーディングは私のスタジオでおこなったんですが、とても面白かったことがあって。アルバムのアートワークに使われている写真はエディ・オットシェールというロンドンの写真家によるものなんですけど、この写真には両面があるんです。表に「両面を見て」と書いてあるんですよ。表では、道の真ん中に人が座っています。裏返すと、その道の反対側も写されているんです。ひとつの作品で道の両面を写したものなんですね。
その写真をスタジオでピンク・シーフに見せたところ、彼は「わかった」と言って20~30分でリリックを書き上げました。そして彼はレコーディングをはじめて、楽器も演奏したんですけど、すごく長いテイクをひとつだけ録って、「できたよ」って言ったんです。追加で録音することもなく、ほんとうにワンテイクで終わらせちゃったんです。スタジオで彼に初めて会って、いきなりレコーディングがはじまって、すぐに終了したというそのプロセス自体が、自分にとってはかなり衝撃でしたね。
その後「足すものはほとんどないけど、スクラッチだけ足したい」と伝えると、Dスタイルズの曲をスクラッチしてくれました。自分が10代の頃によく聴いていたDJグループで、当時はスクラッチにハマっていたので、とても嬉しい経験でした。
序文:小林拓音、質問:野田努(2022年12月27日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE