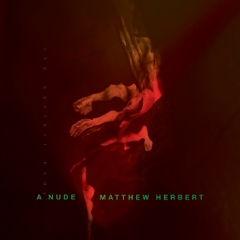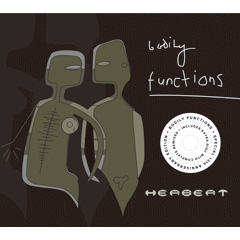MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Matthew Herbert - ハーバートの新作は馬の骨を用いた実験的アンサンブル
interview with Matthew Herbert
ハーバートの新作は馬の骨を用いた実験的アンサンブル
馬は、猫なんかよりもはるかに深く人間とつながっている。人間と多くの関係をもったナンバーワンの動物なんだ。
ユニークなることばは日本では「風変わりな」「奇抜な」といったニュアンスで使われることが多い。本来の意味は「唯一無二」だ。マシュー・ハーバートのような音楽家がほかにいるだろうか? ハウス、ジャズ、フィールド・レコーディングにコラージュ、コンセプト、メッセージ──どれかひとつ、ふたつをやる音楽家はほかにもいる。ハーバートはそれらすべてを、30年近いキャリアのなかでずっと実践してきた。しかも、シリアスなアーティストが陥りがちな罠、深刻ぶった表情にはけっしてとらわれることなく。ハーバートこそユニークである。
90年代後半、彼はまずミニマルなテック・ハウスのプロデューサーとして頭角をあらわしてきた。トースターや洗濯機といった家にあるモノの音を用いた『Around The House』(98)、人体から生成される音をとりいれた『Bodily Functions』(01)などの代表作は、彼が卓越したコラージュ・アーティストでもあることを示している。ビッグ・バンドを迎えた『Goodbye Swingtime』(03)はひとつの到達点だろう。政治的な言動で知られる言語学者チョムスキーの文章がプリントアウトされる音をサンプリングしたりしながら、他方で大胆にスウィング・ジャズ愛を披露した同作は、ブレグジットに触発された近年の『The State Between Us』(19)にもつながっている。
ここ10年ほどを振り返ってみても、一匹の豚の生涯をドキュメントした『One Pig』(11)、ふたたび人体の発する音に着目した『A Nude』(16)などコンセプチュアルな作品が目立つ一方、『The Shakes』(15)や『Musca』(21)では彼の出自たるダンスの喜びとせつなさを大いに味わうことができた。パンデミック前は意欲的にサウンドトラックにも挑戦、尖鋭的なドラマーとの目の覚めるようなコラボ『Drum Solo』(22)もあった。彼の好奇心が絶える日は永遠に訪れないにちがいない。

Matthew Herbert × London Contemporary Orchestra
The Horse
Modern Recordings / BMG / Silent Trade
この唯一無二の才能が新たに挑んだテーマは、馬。気になる動機は以下の発言で確認していただくとして、ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラと組んだ新作『The Horse』ではサウンド面でも新たな実験が繰り広げられている。馬の骨はじめ、全体としてはフィールド・レコーディングの存在感とフォーク・ミュージック的な気配が際立っているが、自身のルーツの再確認ともいえるダンス寄りの曲もある。コンセプトとサウンドの冒険が最良のかたちで結びついた力作だと思う。
もっとも注目すべきはシャバカ・ハッチングスの参加だろう。ほかにもセブ・ロッチフォード(ポーラー・ベア)やエディ・ヒック(元ココロコ)、シオン・クロスと、サンズ・オブ・ケメット周辺の面々が集結している。2010年代に勃興したUKジャズ・ムーヴメントのなかでも最重要人物たるハッチングスまわりとの接続は、長いキャリアを有するハーバートが現代的な感覚を失っていないことの証左だ(ハッチングスが若いころに師事した即興演奏のレジェンド、エヴァン・パーカーの客演も大きなトピックといえよう)。
ちなみに本作で馬との対話を終えた彼は現在、バナナに夢中だという。スーパーやコンビニなど、いまやどこにでも安価で並んでいるバナナ。その光景がグローバリゼイションと搾取のうえに成り立っていることを80年代初頭の時点で喝破したのが鶴見良行『バナナと日本人』だった。どうやらいまハーバートもおなじ着眼点に行きついたらしい。早くも次作が聴きたくなってきた。
彼にお願いしたことは、「フルートを演奏した世界初のミュージシャンになった気持ちを想像しながら演奏してくれ」ということだけ。彼が参加してくれたのはほんとうに光栄なことだった。シャバカ・ハッチングスというミュージシャンはつねに疑問を持ち、考えている。
■新作のテーマは「馬」です。音楽と馬との関わりでまず思い浮かべるのは、ヴァイオリンの弓が馬のしっぽからつくられていることです。つまりクラシック音楽の長い歴史は、馬なくしては成り立ちませんでした。また音楽以外でも馬は、移動手段としての利用をはじめ、人間と長い歴史を有しています。今回馬をテーマにしたのはなぜなのでしょう?
H:じつは最初から馬を選んだわけじゃないんだよ。馬のほうからぼくを選んでくれたんだと思う。最初のアイディアは、なにか大きな生き物の骸骨を使ってレコードをつくるといういうものだった。そこで eBay でいちばん大きな骸骨を検索したんだ。ティラノサウルス・レックスとか、恐竜のね。でもそれはなくて、購入することができるいちばん大きな骨は馬の骨だったんだ。だから馬の骨を買ったら、数週間後にものすごく大きな箱がスタジオに届いてさ(笑)。「なんてことをしてしまったんだろう」とそのときは少し後悔したよ(笑)。でもぼくはその骨格から楽器をつくりはじめて、それで音楽をつくりはじめた。そしたらどんどん馬の魅力に夢中になっていったんだ。馬や、馬にまつわる物語にね。馬は、猫なんかよりもはるかに深く人間とつながっている。人間と多くの関係をもったナンバーワンの動物なんだ。そこで、馬は自然界と人間の関係の謎を解き明かす鍵であり、その関係をあらわすとても素晴らしい比喩になると思った。そんな成りゆきで、今回のアルバムを作るに至ったんだよ。
通訳:そもそもどうして骸骨を使いたいと思ったのでしょう?
H:正直、それは覚えてない。そのアイディアを気に入ったのはたぶん、骨というものが多くの動物が共有するものだからだったと思う。骨は見えないけれども私たちのなかに存在しているものだから。毎回レコードをつくるたびにぼくにとって重要なのは、その作品制作をとおしてなにかを学ぶことなんだ。自分が知らないことに触れ、それを学び、そしてそれをオーディエンスを共有することがぼくの野心なんだよ。
■以前は「豚」をテーマにしたアルバムを出していますよね。それと今回の「馬」とは、テーマのうえでどう異なっているのでしょう?
H:豚の場合、あれは一匹の豚の人生の旅路がアルバムの大きなテーマだった。その豚が生まれてから食べられるまでの人生を記録したのがあの作品。そして、その豚が食べられた瞬間にその記録はストップするんだ。その記録はある意味ドキュメンタリーのようなもの。ある一匹の豚のドキュメンタリー、あるいは物語なんだよ。僕は、あの一匹の動物の一生のほとんどすべてを知っていた。その豚が生まれたときも、食べられたときもその場にいたし、旅の間中ずっと一緒だった。でも今回の馬についてはなにも知らないんだ。競走馬であること、ヨーロッパ生まれであること、そしてメスであることだけは知っているけど、知っているのはその3点のみ。だから今回のアルバムはほとんどその馬の死後の世界のようなもので、その馬の霊的な旅、幻想的な旅、神聖なる旅といった感じなんだ。馬の骨を手にしたときからすべてが未知だった。つまりぼくにとってこのアルバムはドキュメンタリーではなく、探検や未知の世界であり、かなり抽象的な作品。この馬は数年前に亡くなったんだけれど、ある意味アルバムをつくることで、その馬のために死後の世界を作ったようなものなんだ。
■非常にさまざまな音が用いられていますが、制作はどのようなプロセスで進められたのでしょうか? リサーチと素材の収集だけでかなりの時間を費やさなければならないように思えます。
H:そう。かなり大変だったね。今回はレコードの制作期間が半年しかなかったから、骨組が届いてから完成するまではとても早かった。最初はなにをどうしたらいいのかわからないままアルバムづくりをスタートさせて、まずヘンリー・ダグに脚の骨を使って4本のフルートをつくってもらったんだ。そのあと骨盤からハープをつくってもらい、サム・アンダーウッドとグラハム・ダニングに骨を演奏できる機会をつくるのを手伝ってもらった。そうやってできあがった新しい楽器の演奏方法を発見しながら素晴らしいミュージシャンにそれを演奏してもらったんだ。とにかく即興で音を演奏し、ストーリーをつくっていった。今回はカースティー・ハウスリーという監督と一緒に作業をしたんだ。彼女はイギリスの有名なシアター・カンパニー Complicite で多くの演劇を手がけている。そしてもうひとり、イモージェン・ナイトというムーヴメント・ディレクターとも一緒に作業した。ぼくと彼女たちの3人は、ドラマツルギー(戯曲の創作や構成についての技法、作劇法)について考え、物語の構成や内容について考えることにかなり長い時間を費やし、この馬の骨にまつわるストーリーと、音楽にまつわるすべての可能性について話しあったんだ。最初のアイディアがエキサイティングであったと同時にすごく厄介だったし、時間も限られていたから、けっこう途方にくれてしまってね。そこでカースティーとイモージェンが物語の構成を考えるのを手伝ってくれたんだ。

アウトサイダーやエキセントリックなひとたち、もしくはシーンの端っこで面白い音楽を作ってきたひとたちをこのレコードに招き、ここで彼らに自分の居場所を見つけてほしかったんだよ。そして彼らをこの空間で祝福したかったんだ。
■今回の制作でもっとも苦労したことはなんでしたか?
H:もっとも苦労した、というか大変だったのは、その馬に対して誠実で忠実な作品をつくること。ぼくはその馬のことをなにも知らなかったから、自分が知らないものについて音楽をつくるというのはかなり難しいことだった。まるで、会ったこともないだれかのプロフィールを書くようなものだからね。もうひとつは、骨という唯一残されたその馬の一部に魂を見出すこと。骨はぼくが持っているその馬のすべてだったから、もちろんぼくはその骨に敬意を払いたかった。でも骨というものに魂を見出すことが最初は難しくてね。生きているものと違って、骨はカルシウムと炭素とシリコンでできている。骨はもう生きていないわけで、生き物の遺骨と魂の関係とは何かを考えるというのが、ぼくにとってはすごく複雑だったんだ。
■“The Horse’s Bones And Flutes” では、馬の骨からつくられたフルートをシャバカ・ハッチングスが演奏しています。彼はサックス奏者ですが、日本の尺八などさまざまな管楽器を探究しています。また彼はアフリカの歴史を調べたり、非常に研究熱心です。彼の探究心について、あなたの思うところをお聞かせください。
H:最初に今回の件を依頼したとき、彼は「無理だね。俺には演奏できないよ」と言ったんだ。でも、もちろん彼は才能あるミュージシャンだから、10分後には完璧にフルートを演奏していた。そこでマイクをセットし、ひたすら彼に演奏してもらい、2時間かけてそれを録音したんだ。そしてその演奏をとにかく聴きまくりながら、僕らはたくさん話をした。僕が最初に彼にお願いしたことは、「フルートを演奏した世界初のミュージシャンになった気持ちを想像しながら演奏してくれ」ということだけ。そこから2時間の即興演奏ができあがり、ぼくがそのなかからとくにいいと思った部分をいくつか取り出し、曲をつくりあげたんだ。ぼくは彼の探究心が大好き。だからこそ彼を選んだし、彼が参加してくれたのはほんとうに光栄なことだった。シャバカ・ハッチングスというミュージシャンはつねに疑問を持ち、考えている。音楽というものはときに超越を意味するものだと思うんだ。そして、考えるということと降伏することのあいだにはとても複雑な関係がある。彼はかなり興味深い視点やヴィジョンを持ってるんだ。演奏や即興をやっているときはとくにそう。彼は演奏しているときつねに考え、つねになにかを創造しながらも、そこには同時に自由が存在する。彼のなかではそのアンバランスが成り立っていているんだよ。自由で好奇心旺盛でありながらなにかを達成しようとするのはすごく難しくて複雑なことだと思う。でも彼はそれをとてもうまく表現できていると思うね。
質問・序文:小林拓音(2023年6月23日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE