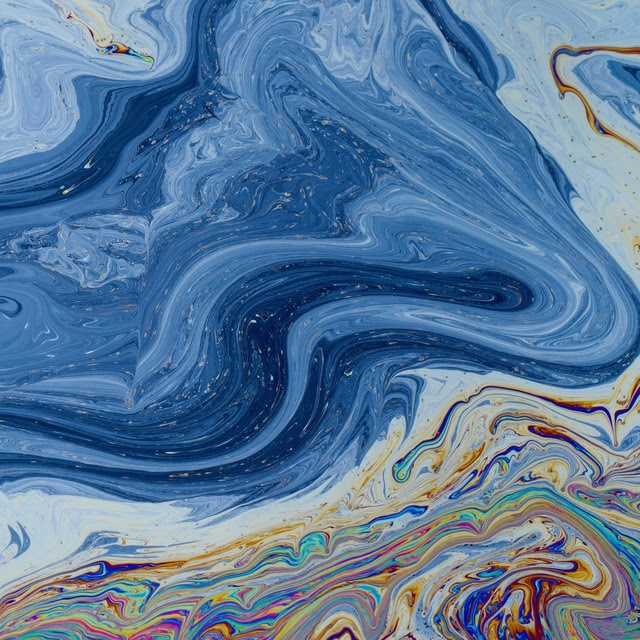イタリア出身で現在はベルリンを拠点に活動しているシェイプドノイズことニーノ・ペドーネが、2015年以来となるフルレングス『Aesthesisis』をリリースする。レーベルはラスティやソフィーなどの作品で知られるグラスゴーの〈Numbers〉で、マーク・フィッシャーの言う「ハードコア連続体」を意識した作品になっているようだ。〈NON〉のマイシャや、ここ数週間しょっちゅう名前を見かけるジャスティン・ブロードリック、ラビットや元コイルのドリュー・マクドウォールも参加している。
なお、シェイプドノイズはこれまで〈Opal Tapes〉や〈Type〉といったレーベルから作品を発表してきており、マムダンスやロゴス(彼も今年『TMT』のインタヴューで「ハードコア連続体」について語っている)、マイルズ・ウィテカーとのコラボ経験もある。他方で彼はエイフェックス・ツインのお気に入りアーティストでもあり、リチャードは最近の《Field Day Festival》などのフェスで彼の曲をかけている。さらに付け加えるなら、ニーノは〈Repitch〉というレーベルの運営にも関わっており、スリープアーカイヴやソートなどの12インチを送り出してもいる(そのサブレーベルの〈Cosmo Rhythmatic〉からは今度、シャックルトンの新プロジェクトがリリース)。
とまあこのように、アンダーグラウンドで陰日向なく重要な活動を続けている彼だけに、今回の新作も要注目です。

artist: SHAPEDNOISE
title: AESTHESIS
label: Numbers
catalog #: NMBRS62
release date: 8 October 2019
Tracklist:
01. Intriguing In The End feat. Mhysa
02. Blaze feat. Justin K Broadrick
03. Elevation
04. Rayleigh Scattering
05. The Foolishness Of Human Endeavour
06. CRx Aureal
07. Blasting Super Melt
08. Unflinching
09. Moby Dick feat. Drew McDowall & Rabit