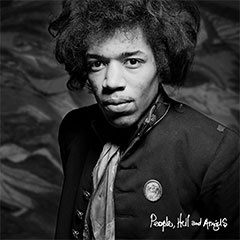MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > David Sylvian- Died In The Wool
2年前のある日、湯浅学氏に電話した。
「湯浅さん、デビシルの新作聴きました?」
「聴いたよ、あれおもしろいね」
「演奏とシルヴィアンの歌はギリギリの絶妙な緊張関係にありますね」
「シルヴィアンはデレク・ベイリーといっしょにやってからなー。その影響かもな」
「でもちょっとなつかしかったスね」
「なにが?」
「『歯のはえたケツの穴』みたいじゃなかったですか? あのころ湯浅湾も即興ノイズをバックに歌ってましたよね」
「デビシルはあんなデタラメじゃないからな。......そういうこといったり書いたりすると、良識あるひとに怒られるか狂人あつかいされるから、いったり書いたりしないようにしようぜ」
湯浅さん、もうしわけない。約束を破ってしまった。
みなさんのおっしゃるとおりシルヴィアンの『マナフォン』はデタラメではない。
ベイリー~カンパニーの圏域のフリー・インプロヴィゼイションと、コーネリアス・カーデューの――つまり現代音楽の――の系譜に連なるAMMのメンバーに、クリスチャン・フェネス、大友良英や中村としまるや秋山徹次などの日本の即興演奏家の演奏(そこには2000年代の日本の即興シーンの問題意識が反映されていたのはいうまでもない)をプロツールスのマトリクスに配置することで、ベイリーが固執したイデオム(ストック・フレーズ)から完全に自由な即興を、ハードウェアのメモリとソフトウェアのファンクションをかりて"作曲"に置き換えた『マナフォン』は音響(派)とダンス・カルチャーの挟み撃ちにあったアヴァン・ミュージックがメタな視点をふくむコンセプトを前景化しはじめた動きとも無縁でなかった。というより、『マナフォン』はそれらの命題に深入りすることなく、別の場所に回路を拓いたとみるべきで、その意味で、〈samadhisound〉以降のシルヴィアンの隠遁者めいたイメージに似つかわしい孤高をあらためて感じさせた。
『マナフォン』の日本盤にはボーナス・トラックが1曲入っている。英国在住の日本人作曲家、藤倉大の"Random Acts Of Senseless Violence"のリミックスがそれだが、藤倉のヴァージョンはシルヴィアンの歌に複数の楽器が散発的に同期する、文字通りランダムな原曲にストリングスを加え、それぞれのエレメントを時空間上に再配置することで、全体を整理し直している。機能美を追究したリミックス=解体~再構築の図式ともちがう、変奏と呼ぶべき解釈がそこではおこなわれていたが、密室の作業を思わせるシルヴィアンのどこか切迫した原曲に較べ、藤倉の音楽は開かれている。シルヴィアンは他者の音を彼の歌に密着させたが、藤倉は外から音を操作した。このあざやかなコントラストはあたりまえのリミックスではほとんどあらわにならない。これに気をよくしたシルヴィアンはこの方法論を拡張し、作業は最終的に『ダイド・イン・ザ・ウール』にまとまった。"Random~"リミックスを再録したアルバムの半分は前作の"変奏"。のこりはアウトテイク(のリメイク)と新曲である。
「『マナフォン』のリミックスを作る考えは僕にはまったくなかった。『ブレミッシュ』に較べると、『マナフォン』を作るのは感情面ではるかに疲れることだったと言うと驚く人もいるかもしれない。完成した後に、また曲に向かう気持ちは残っていなかったし、『オンリー・ドーター~ブレミッシュ・リミキシーズ』の時と同じアプローチがうまく作用するとは思えなかった。『ダイド・イン・ザ・ウール』は漸進的に出現した」シルヴィアンはライナーノーツでこう語っている。
シルヴィアンは気をよくしたわけではなかった。むしろ精も根も尽き果てていた。後につづく文章によると、漸進的にシルヴィアンを駆り立てたのは進行中の藤倉大とコラボレーションだった。そのとき、ポピュラー音楽史に独自の地位を確立したミュージシャンと、クラシックの作曲家の3年に渡る共同作業は数曲に実を結びつつあった。
変奏はいずれも前作を更新している。目的がそもそもちがうのだろう。歌に弱音の即興の断片をオーヴァーラップさせた『マナフォン』のモンタージュ的な構造に『ダイド・イン・ザ・ウール』はフレームをあてはめている。1曲目の"Small Metal God"ですでに、『マナフォン』では音の素描ともいうべき簡素な即興が歌をとりまいていたが、『ダイド・イン・ザ・ウール』の藤倉大の変奏は音が明確な意味をもつと語るようである。意味とは体系であり、歴史とか学習とか、もっといえば歴史の学習とかをふまえた音であると、私は思う。依然、シルヴィアンと藤倉大の対比はあざやかである。そこに本作のもうひと組のコラボレーターであるノルウェイのエリック・オノレ&ヤン・バングのラップトップ・インプロヴィゼイションが加わるとコントラストに階調がうまれる。『マナフォン』の曲名に名前のみえる19世紀の詩人、エミリー・ディッキンソンの詩を歌った"I Should Not Dare""A Certain Slant Of Light"のポップな曲調はアルバムのフックでもあるが、モノクロームのアナーキズムといいたくなる手法で自身の音楽に静かに裂け目を作った前作を、優美に、しかし大胆に編み直した本作へ橋渡す役割を担っている。エリック&ヤンとの比較において藤倉のコントラストがいっそうきわだつのはシルヴィアンの慧眼というほかない。前作のオクラだしである"Anomaly At Taw Head"の60年代の武満徹を彷彿するエレメントを点在させた空間構成、"Snow White In Appalachia"のロマンティシズムといった動的な魅力はアルバムの中盤で顕著になる。最終的にそれは、ニューヨークでシルヴィアンと藤倉が行った二度目のセッションで録音した"The Last Days Of December"に落としこまれるのだけれど、バス・フルートの重音(マルチフォニックス)が軋むように低く唸り、弦のドローンが時間の後ろ髪を引くこの曲は単(淡)色の『マナフォン』の世界に色彩を加えた『ダイド・イン・ザ・ウール』の次の彼の方向性さえ照らすように思えてならない。
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE