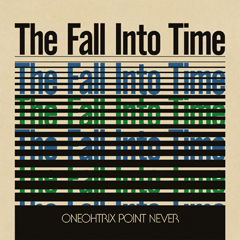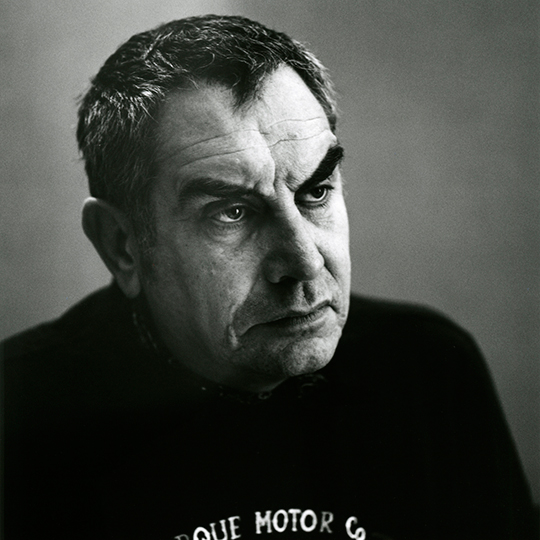何をきいても、きくだけ野暮になるのだ──。リズムボックスの規則正しいビートを無視して、右に左に奇妙に揺れながら、モリッシーを彷彿させるヴォーカリゼーションでオーディエンスを威嚇するハネス・ノーヴィドは、強くひとを惹きつけながらも近寄りがたいような緊張感をみなぎらせている。若く固く純粋で、土足で入ってくるものを許さない。こんなにロマンチックでドリーミーな曲なのに……いや、そうした曲でこそ彼の憮然とした表情と固い動作は美しく、聴くものの胸を打つ。
4月某日、原宿のアストロホールでは、彼の一挙手一投足が意味を持ち、熱を生み、ひとびとの心を煽っていた。煽るといってもそれは威勢のいい掛け声やメッセージによってではない。そこで歌われていた言葉は、君に会いたいとかそんなような、きわめてささやかな、あるいは内省的なものにすぎない。音はきわめてロマンチックなシンセ・ポップ、生硬なポスト・パンク。
そしてハネスはといえばリズムにもメロディにも、ホールの空気にすら乗ろうとしない。散漫に客を眺め、どうでもいいことのように歌い、拍を外して動く(踊るというより動き)。それは、自分の外にあるものすべてに向けての威嚇や挑発であるようにも感じられるし、ガーゼにくるまれた、純粋で傷つきやすいものを想像させもする。──わたしたちを強い力で陶酔させ、高揚させ、我を忘れようとさせていたものは、そんな繊細な姿をしていた。
ロックにこんなふうにひりひりとしたものを聴き取るのは久しぶりだった。素晴らしく攻撃的で、ピュアで、ロマンチック。小器用なリヴァイヴァリストたちではない。ロックが説得力を失う時代を真正面から踏み抜いて、ブリリアントな曲を聴かせてくれる。ラスト・フォー・ユースは本当に特別なバンドだ。年長者が聴けば、なんだ、ニューオーダーやジョイ・ディヴィジョンのミニチュアじゃないかと言うかもしれないが、残念ながらそんなことは知らない。わたしたちが見ているのはそれではなく「これ」なのだ。そして、そこにいた人たちみなが切実に、かけがえのないものとして「これ」を感じていたからこそ、異様なほどの熱が生まれていた。わたしたちはいまここに、2016年にいるのだ。
ラスト・フォー・ユース。ハネス・ノーヴィドを中心とする3人組。「いいバンドがいる地域」として数年来注目を浴びているコペンハーゲン・シーンの顔ともいえる存在だ。活動を開始した2009年当初はハネスの一人シンセ・プロジェクトともいえるスタートだったが、2014年の前作『インターナショナル』から現体制になっている。自分たちでレーベル活動も行う一方で、彼ら自身のアルバムはイタリアのノイズ・レーベル〈Avant!〉やエクスペリメンタルなサイケ・レーベル〈セイクリッド・ボーンズ〉などからもリリースされており、実際のところ、後者のように2010年代のシーンを賑わせたレーベル経由で世界に広く知られるところとなった。
 Lust For Youth Compassion Sacred Bones / ホステス |
先月、彼らは新作『コンパッション』を携えて来日した。先に述べた様子を思い浮かべていただければおわかりかと思うが、筆者が言葉でたずねるべきことなど本来なにもない。そこには、語らずにすべてを伝えてしまう、ハネス・ノーヴィドという名の心があるばかりだった。ライヴのあとに取材していたら、質問が変わっていたか、あるいは何もしゃべれなかったかもしれない……。
しかしともかくもお伝えしよう。彼らはわずか30分足らずのインタヴュー中、注意力のない男子中学生のようにずっとふざけていたけれど、それはおたがいへの照れ隠しのようにも見えた。不真面目なのではない。真面目だからこそ言葉を接げないのだ。嬉々としてロックがアーティストの口からプレゼンされねばならない時代は不幸である。ジャケットには点字がならんでいる。
■Lust For Youth / ラスト・フォー・ユース
スウェーデン出身、ハネス・ノーヴィドによるシンセ・ポップ・プロジェクト。2011年にデビュー・アルバム『ソーラー・フレア(Solar Flare)』を発表。2011年に発表した2作め『グローイング・シーズ』はメンバーの脱退がありソロ・プロジェクトとして発表されたが、2014年リリースの前作『インターナショナル』よりマルテ・フィシャーとローク・ラーベクがラインナップに加わっている。自身のレーベルからの他、イタリアのノイズ・レーベル〈Avant!〉や、つづく作品はUSの〈セイクリッド・ボーンズ〉等からもリリースされている。2016年4月にニュー・アルバム『コンパッション』を発表、同月来日公演を行った。
掘り下げて掘り下げて、だんだんポップになっていった(笑)。 (ハネス・ノーヴィド)
■ラスト・フォー・ユースは、歌詞が英語であることがほとんどですよね。スウェーデン語で歌わないのはなぜなんですか?
ローク:僕らの中でも2つの母国語があるからね。スウェーデン語とデンマーク語。でも世界から見れば、両方合わせてもごく少数の人数が話している言葉にすぎない。そんな中でより多くの人とコミュニケーションをしたいと思ったら、よりビガーな言葉を使うほうがいいよね。そして、僕らが知っているビガーな言葉といえば英語しかないんだ。
マルテ:英語はデンマークでも小さな頃から学校で教わるからね。
ハネス:音楽的な点からいっても、英語はいちばん通じやすいよね。ポップ・ミュージックの言葉だと思う。
マルテ:前のアルバム(『インターナショナル』2014年)は、イタリア語の曲が入っていたり、スウェーデン語の曲が入ったりもしているから、使ってはいるんだよね。でも歌うことにおいては圧倒的に英語ということになるかな。
■なるほど。〈アヴァン・レコーズ(Avant! Records)〉からいくつかリリースがありますね。『サルーティング・ローマ(Saluting Rome)』(2012年)あたりはずいぶんダークで、ノイズやインダストリアル的な要素も強いかと思いますが、そこからくらべて現在はずいぶんポップなかたちになったとも言えるかと思います。そうなったことに何かきっかけや理由はありますか?
ハネス:あの頃も十分ポップだったと思うよ。
ローク:いや、最初につくっていたテープなんて、ただのノイズだったじゃん(笑)。
マルテ:ハネスがひとりでつくっていた頃でしょ? 初めて聴いたとき、「マジで?」って思ったもん。ほんとにこれをポップとして解釈することかできるのかなって。
■ははは。とくにハネスさんだと思いますが、そういうノイズ・ミュージックに最初に触れたのは何がきっかけだったんですか?
ハネス:ウルフ・アイズ(Wolf Eyes)から入って、掘り下げていったかな……。10代の頃だから、何がきっかけだったかなんてあまり覚えてないんだけど。で、掘り下げて掘り下げて、だんだんポップになっていった(笑)。
僕にとってシンセ・ポップとか80年代の音楽のイメージは、「パンクのショウの後でかかってた、みんなで踊れる楽しい音楽」なんだ。(ローク・ラーベク)
■それがラスト・フォー・ユースのポップの真実なんですね(笑)。一方で、ニュー・オーダーに比較されたりするように、ポスト・パンクだったりシンセ・ポップのような音楽は何が聴きはじめだったんでしょうか。それから、みなさんの国の同世代にとってそれらはポピュラーなものなんですか?
マルテ:いまでこそかからないけど、あの頃はラジオとかでかかっていたよね。ニュー・オーダーとかは。
ローク:僕にとってシンセ・ポップとか80年代の音楽のイメージは、当時僕が好きで通っていたパンクのショウ、それが終わったあとに飲みにいくところでかかってるって感じかな。パンクのショウではみんな暴れたりしていたけど、その後クラブのダンスフロアなんかに行くと、そっちから打ち上げで入ってきた男子がテーブルの上にのぼって、シャツを脱いで騒いだりしていた。そういう、みんなで盛り上がって楽しい時間を過ごしたっていう思い出が、あの手の音楽を聴くとよみがえってくるよ。「パンクのショウの後でかかってた、みんなで踊れる楽しい音楽」なんだ。
■そうはいっても、みなさんは80年代当時がリアルタイムではないですよね。たとえばニュー・オーダーならどのアルバムから聴きはじめたんですか?
ローク:僕は映画『ブレイド』(1998年)のサントラとして収録されている“コンフュージョン”のリミックスだね。完全にレイヴの音楽って感じで……ニュー・オーダーの曲ですっていう感じではないけど、ニュー・オーダーの最初の思い出とかインパクトといえばそれなんだ。
マルテ:僕は「ブルー・マンデー」かな。ラジオでよくかかってたよ。
ハネス:僕は「クラフティ(Krafty)」(2005年)かな。その後は『ムーヴメント』に出会うまで気にならなかった。
■私もそのアルバムが最初だと思います(『ウェイティング・フォー・ザ・サイレンズ・コール』2005年)。同世代ですね(笑)。でも、“ブルー・マンデー”がラジオでよくかかってたというのはなんなんでしょうね。さすがにオリジナルが出た当時じゃなさそう。
マルテ:そうだね。僕は32歳だから。
■それは生まれたかどうかくらいですね。
実際には仲はいいんだよ。メディアが言うように、みんなオシャレな服を着て、みんなハンサムで、みんな才能があって……なんてことはないし、そうやって十把ひとからげにされるのは違和感があるっていうだけで。
■コペンハーゲンのバンドについて、英米のメディアや日本でも話題になったりしたんですが、実際にシーンを呼べるようなつながりとか盛り上がりはあるんですか?
ハネス:僕らとしては、あまり「シーン」という実感はないんだけど、それぞれのバンドに友だち関係っていう結びつきはあると思うよ。
ローク:長くやっているバンドも多いから、そこには自然に友情みたいなものはできてくるかな。
■なるほど。でもメディアがそう言っているだけってことでもない?
ローク:まあ、間違いなくコミュニティ的なものはあると思うよ。でも、(お菓子を食べてふざけあいながら)僕らが集まってやることなんてこんなことばっかりで、音楽の話なんてしてないよ(笑)。そんなふうに騒がれる前にとっくに僕たちのコミュニティはできてしまっていたから、いまさらって感じはあったけどね。だから「みんな仲がいいんでしょうね」っていうような質問を受けると、あえて「いや、仲良くないよ」「きらいだよ」って言いたくなっちゃうんだ。
でも実際には仲はいいんだよ。メディアが言うように、みんなオシャレな服を着て、みんなハンサムで、みんな才能があって……なんてことはないし、そうやって十把ひとからげにされるのは違和感があるっていうだけで。それぞれに個性があるし、みんな音楽以外の興味も大きいから。
マルテ:それにみんなの音楽性もどんどん広がっているから、まとめて語るのはますます無理が出てきているだろうね。
■基本的にはパンクとかロックとかって音楽が多いんですか? クラブ・ミュージックみたいなものとは混ざっていない?
ハネス:バンドが多いのは間違いないね。
マルテ:でも、テクノもわりとある気がするな。たしかに僕らのまわりではないけど、でもいろんな音楽があるよ。なんでも。ユニークなことをやっている人も多いし、そういう人たちもゆるやかにつながっているとは言えるんじゃないかな。
ミニマリズムを愛する感覚とか、歴史の古さとか。日本への共感みたいなものはあるよ。(マルテ・フィッシャー)
■へえ。たとえばハネスさんはゴーセンバーグご出身かなと思うんですが、ゴーセンバーグは一時期、エレクトロニックなバンドやユニットがいくつも出てきて注目されていましたよね。JJとか、エール・フランスとか、タフ・アライアンスとか。彼らなんかとは交流があるんですか?
ハネス:ゴーセンバーグは以前しばらく住んでいただけなんだけどね。いや、友だちじゃないよ彼らは。じつは僕らのイヴェントに来たいってタフ・アライアンスのメンバーが言ってきたときに、断ってしまった経緯があるんだよね。僕は彼らが好きなんだけど、僕の友だちが、ああいう人たちを呼ぶのは日和ってるみたいなことを言って断ってしまったことがあって。
じつのところスウェーデンの音楽はそんなにマジメに聴いてないんだ。スウェーデンは昔から、自分たちがいちばんの音楽の国だっていうようなことを外に向けて言ってきた。たしかに90年代にそういうことはあったかもしれないけど、いまはそんなことないと思うし、とにかくスウェーデンの人っていうのは、視線が内側に向いていて、外の音楽に対して無知なんだ。僕はそう思う。
マルテ:でもやっぱり、ポップ・ミュージックは強いよね。アバにはじまってさ……。あと、音楽の学校がすごく充実しているんだよ。デンマークだって、普通の学校に通っていてもけっこう音楽の教育はしっかりしていると思う。
■北欧……と一括りにするわけにはいきませんけど、スウェーデンもデンマークも、福祉国家であり、合理的で進歩的な考え方を持つ国というふうなイメージがありますけれども、実際にみなさんもそう感じますか?
ローク:合理的っていうのはどうかなって思うところもあるけど、ほかの2つはそうだね。美意識みたいなところでは、スカンジナビアは日本と共通するところがあるんじゃないかって思うよ。
マルテ:そうだね、ミニマリズムを愛する感覚とかね。あとは歴史の古さとか。日本への共感みたいなものはあるよ。
基本的には音楽で生活できている人が多いよ。ただ、ひとつ言えるのは、音楽でリッチになっているやつはいない(笑)。(ローク)
■なるほど、意外なものの造形が似ていたりもしますからね。……でも、若い人が絶望していたりしないんですか?
ハネス:それは世界中、みんなそうだと思うよ。
■ははは、それは反論しにくいですね。
ローク:未来ってことを考えると、すごく恐ろしい場所のような気がする。もしかするとすごく楽しいこともいっぱいあるのかもしれないけど、不安の方が大きいよね。
ハネス:だから考えないでおくことにしたほうがいい。
■あはは。金言です。でも、みなさんやお友だちは、みんな音楽で食べているんですか? それとも何か別に職業を持ちながら?
ローク:基本的には音楽で生活できている人が多いよ。個人差はあるけど。ただ、ひとつ言えるのは、音楽でリッチになっているやつはいない(笑)。なんとかやっていけてるってだけでね。
ハネス:僕らは例外だけどね。
■では、いま聴いている音楽で刺激的だと思うものはどんなものですか?
マルテ:ブリアルとか。
■へえ、意外なようで、みなさんにも相通じるようなダークさがあるかもしれませんね。
ローク:僕はコペンの仲間がつくっているのを聴くだけで手一杯だよ。
ハネス:僕も。
Lust For Youth “Sudden Ambitions”
ゴシックは嫌い。(ローク)
■なるほど、音をシェアしているんですね。ところでLFYの作品は近年は〈セイクレッド・ボーンズ〉から出てたりしますけど、あのレーベルにはどんな印象を持っていますか? みなさんはカタログの中ではやや異質ですよね。
マルテ:たしかに僕らは異色かもしれないね。でもそれがいいことだとも言える。
ハネス:僕は同じくらいの規模の別のレーベルからのリリースの経験もあるけど、いい感じなんじゃないかな。必ずしも有名レーベルではないけど、おもしろいバンドのものを出してると思う。僕らからデヴィッド・リンチまでね(笑)。あとファーマコンとか。
■ファーマコンはいいですよね。〈セイクレッド・ボーンズ〉の中には、特異な形でではありますけど、ゴシックの要素もあると思います。みなさんは自分たちの音楽の中にゴシックを感じることはありますか?
ローク:ゴシックは嫌い。
ハネス:ははは。
ローク:でも時間はかかったけど、僕らの音楽を理解してくれるレーベルが出てきたことはうれしいことだよ。僕も自分でコペンハーゲンでレーベルをやっているわけだし、やろうと思えば自分たちでも出せるけれど、そんな中で出そうと言ってくれる人がいるわけだから、いいことだよね。
■そうですね。こうやってお会いしてみると、みなさんずいぶんやんちゃな印象なんですが、曲のなかで歌われていることはわりとどれもラヴ・ソングというか。それがちょっと意外でした。これはわざと意識しているというか、ポップ・ソングは恋愛を歌うものというような考えがあったりするんですか?
ローク:やんちゃはいまだけだよ(笑)。
ハネス:嘘をつくのがうまいというだけじゃないかな。
マルテ:曲の雰囲気にインスパイアされて歌詞を書くことが多いから、それで影響されるのかもしれない。曲自体がそんなムードを持ってるんだよ。
ローク:それがまあ、ゴスが嫌だっていうことにつながるんじゃないかな。もちろんラヴ・ソングを書いている人が恋愛をしているかといえばそうとは限らない。ゴスのひとたちもきっとそうで、彼らがつねにメランコリックでウィザラブルな自分たちを演じていて、それを見て周りの人も同じ気分になってしまうということがあるんだとすれば、僕たちも自分たちの世界を曲で提示して、聴く人たちをそんな気分にさせているということなのかなと思うよ。
点字って、つねづねおもしろいものだなって思ってたんだよ。デザイン的にとっても美しいものなのに、それを読める人には見えなくて、見える人には読めなくて、っていうのがね。(マルテ)
■世界といえば、ジャケットの点字のモチーフはどこから?
ローク:まず、もとになる風景はあったよ。ハネスとマルテは同じアパートに住んでいたことがあって、そこが今回のレコーディングの場所でもあるんだけどね。それで、煮詰まってくると海を眺めて──海の色か空の色かちょっと区別がつかないような色をしてたよね──それを眺めて散歩したりしてたんだ。いい気分転換になった。
マルテ:で、点字については、僕がツアー中に飲んでいた薬があるんだけど、それについていた点字がヒントになってるんだ。その海か空かわからない色みたいに、何かがはっきり見えないひとのための字を使うというのは、おもしろいと思って。点字って、つねづねおもしろいものだなって思ってたんだよ。デザイン的にとっても美しいものなのに、それを読める人には見えなくて、見える人には読めなくて、っていうのがね。
■それは、音楽も似たようなところがあるかもしれませんね。
マルテ:その通りだね。