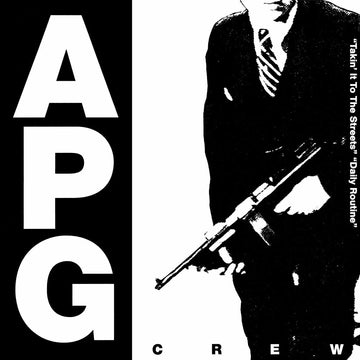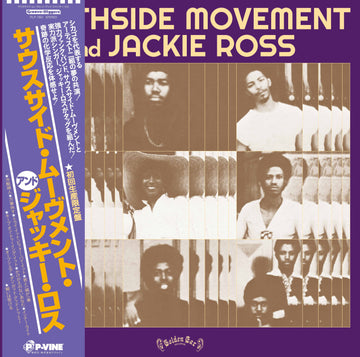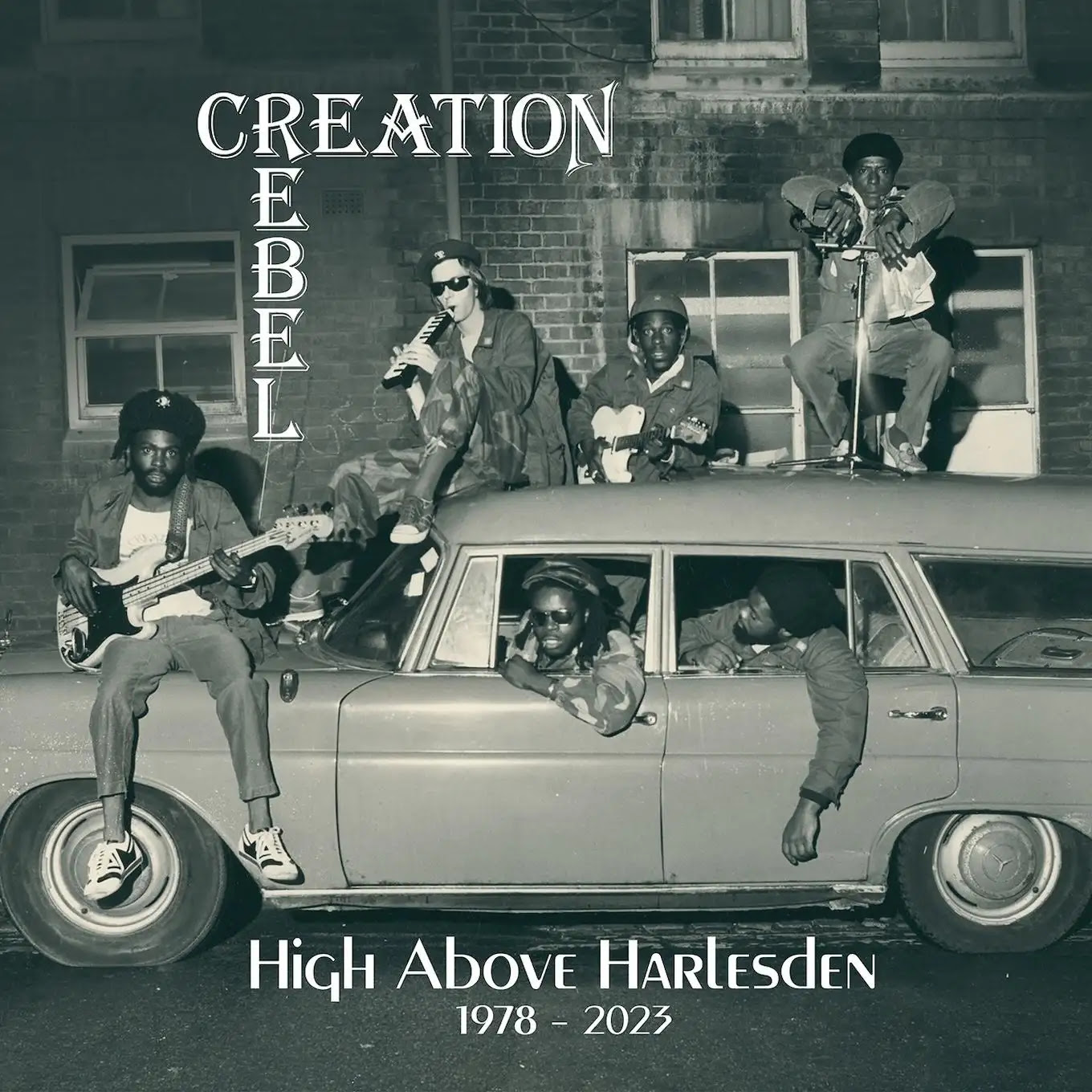ドアーズを初めて聴いたのが中3で、その後の2~3年で、すごいスピードでいろんな音楽を吸収した。レコードやラジオで。そして、ハードなもの、他にないもの、この二つが自分は好きなんだとわかった。
灰野敬二さん(以下、敬称略)の伝記本執筆のためにおこなってきたインタヴューの中から、編集前の対話を紹介するシリーズの2回目。今回は、高校時代からロスト・アラーフ参加までの1969~70年頃のエピソードを2本ピックアップする。ロック・シンガー灰野敬二の揺籃期である。
ちなみに本稿がネットにアップされる頃、灰野は今年2度目のヨーロッパ公演(イタリア、ベルギー、フランス)へと旅立っているはずだ。
■ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン
■灰野さんが高校時代からドアーズやブルー・チアの熱心なファンだったことは有名ですが、当時、特に好きだったミュージシャンとしては他にはどういう人たちがいたんですか?
灰野敬二(以下、灰野):高校の学園祭では “サティスファクション” などを歌ったんだよ。先輩たちのバンドのシンガーとして。学園祭のためだけの即席バンドね。3年生のギタリストはジェフ・ベックに似ていた。その他にも、ビートルズやナインティーンテン・フルーツガム・カンパニー(1910 Fruitgum Company)の “サイモン・セッズ Simon Says” とか歌った。当時流行っていたロックやポップスの曲ばかり。先輩から声をかけられて参加したバンドだし、曲も先輩たちが決めていたからね。でも、“テル・ミー” と “サティスファクション” を10分ぐらいずつやった時は、普通の演奏をバックに、ドアーズ “When The Music's Over” を意識したストーリーテリング的ヴォーカルにしたんだ。あと、俺はテイスト(Taste)の「シュガー・ママ Sugar Mama」(69年のデビュー・アルバム『Taste』に収録)をやりたいと言ったの。でも、誰も知らなかった。俺は『Taste』の米盤を持ってて、特にロリー・ギャラガーのギターが大好きだったから。
ギターに関しては、もちろん最初はエリック・クラプトンやジミ・ヘンドリクスなどを熱心に聴いていたけど、ロリー・ギャラガーはそういったブルース・ロック・ギタリストとはどこか違うと感じていた。変だなと。曲の作りが、ロックでもブルースでもカントリーでもない。リフも他のギタリストとは全然違う。理論ではなく直感としてそう思った。たとえば、ジミヘンやクラプトンの音楽が五つの要素から成っているとすると、ギャラガーは七つの要素で成っている。だから、飽きない。バロック音楽的要素も感じたりして。で、当時の自分の中でギャラガーは最高のギタリストになった。ちょっと後、渋谷ジァン・ジァンなどに日本のバンドのライヴを観に行くとみんなでクラプトン大会とかやってて、フーンと思っていた。当時から日本のロック・シーンはそんな感じだったんだ。
Taste “Sugar Mama”
今の若い世代は音像ではなく音響に関心を向けがちだけど、そのあたりは世代格差を感じる。センスという言葉で音の加工を重視するけど、俺はそういうのは好きじゃない。ロックを感じない。
■17才でロリー・ギャラガーの特異性をしっかり感じ取れたってのはすごいですね。
灰野:とにかくいつも “違うもの” を探し求めていたから。ドアーズを初めて聴いたのが中3で、その後の2~3年で、すごいスピードでいろんな音楽を吸収した。レコードやラジオで。そして、ハードなもの、他にないもの、この二つが自分は好きなんだとわかった。ジミヘンもクラプトンもカッコいいけど、彼らはやはりロックの優等生なの。ギャラガーだってもちろん優等生だけど、そこにとどまらない、更に何か違うものがある。
■アイリッシュという属性も関係してたんでしょうね。
灰野:そうそう。彼の表現の根底には反イギリスの感覚がある。ヤマトの人間が持ちえないセンスをアイヌや沖縄の音楽家が持っているように。俺はお前たちとは違うぞ、俺たちにも目を向けろ、という意志を感じる。彼の音楽の中にあるカントリー・テイストも、ルーツはアイリッシュ・フォークだし。
■ロリー・ギャラガーの他には?
灰野:デビュー時のレッド・ツェッペリン。高校1年の冬だったと思うけど、パック・イン・ミュージックの火曜日、福田一郎さんが、日本盤はまだ出てなかったツェッペリンの1st『Led Zeppelin』(欧米では1969年1月リリース)の “You Shook Me” をかけたのを聴いてショックを受け、翌日か翌々日、日本の発売元だと思われる日本グラモフォンに電話した。「ツェッペリンのファン・クラブを作ってくれ」と。それぐらいこのデビュー・アルバムにはずっと、ものすごい愛情を持ってきた。“You Shook Me” の最後の部分のギターとヴォーカルの掛け合い、俺はあれでヴォーカリゼイションに目覚めたの。ブルー・チアのグルーヴ感とロバート・プラントのヴォーカルが、ミュージシャンとしての自分のスタート地点になったと思う。ドアーズの演劇的表現は別にして。
Led Zeppelin “You Shook Me”
とにかく “You Shook Me” はショックで、パック・イン・ミュージックを聴いた後、寝られなくなった。当時はまだ高校を辞めてなかった頃で、翌日学校から戻るとすぐにお金を握りしめて渋谷ヤマハに駆け込んだ。当時あそこは6時15分が閉店で、学校から帰宅してから急いで行くとだいたい6時ちょい前ぐらいに着く。だから、試聴している時間などない。幸い、盤はあり、それを大事に抱えて帰宅したのを憶えている。米盤で、3000円近くした。当時は英盤はなかなか入ってこなかった。
日本の発売元が日本グラモフォンだとどうやってわかったのか……はっきり憶えてないけど……当時の日本ではいいバンドの発売元はだいたいグラモフォンだったから、勘で電話したんだと思う。でも、電話に出た人はツェッペリンのことを知らず、話がまったく通じなかった。もしわかっている人が出ていたら、俺は日本のツェッペリン・ファン・クラブ会長になっていたかもしれない。だいたい、当時はヤードバーズやキンクスだって、日本ではあまり知られてなかったからね。
ツェッペリンは今でも1stが一番好きだね。というか、2作目以降は関心がなくなった。1stはアヴァンギャルドでしょう。今の若い世代は音像ではなく音響に関心を向けがちだけど、そのあたりは世代格差を感じる。センスという言葉で音の加工を重視するけど、俺はそういうのは好きじゃない。ロックを感じない。
“You Shook Me” を聴いて、音楽や歌や声に対する概念が自分の中で変わったと思う。ああいうことをしてもいいんだ、なんでもありなんだ、と。あと、ロックじゃないけど、ヴォーカリゼイションのヒントということだと、パティ・ウォーターズも大きかった。今はもうロバート・プラントは嫌いだよ。歌がヘタだから。声を出すことと歌うことは違う。「歌」ではなく「ヴォイス」と呼ばれることを俺が嫌いなのは、ヴォイスの人たちは歌がヘタだから。歌は、ずっと歌い続けていかないと上手くはならないんだ。
声を出すことと歌うことは違う。「歌」ではなく「ヴォイス」と呼ばれることを俺が嫌いなのは、ヴォイスの人たちは歌がヘタだから。歌は、ずっと歌い続けていかないと上手くはならないんだ。
■錦糸町の実況録音
音楽家になる決意を固めた灰野敬二が高校を中退したのは1969年、高校2年の2学期。17才になって間もなくの頃だ。そして、ロスト・アラーフに参加するのが70年7月。その間に灰野が短期間参加したバンドが錦糸町を拠点とする実況録音である。
■狭山の高校を中退してからロスト・アラーフに参加するまでの1年ほどは、どういう活動をしていたんですか?
灰野:中退したちょっと後、69年の秋だったと思うけど……都内の高校に通っていた中学時代の級友から「友人のロック・バンドがシンガーを探しているんだけど、会ってみないか?」と誘われたんだ。彼は中学時代に俺に最初にビートルズを教えてくれた友人で、高校に入ってからも地元でのつきあいが続いていた。
で、さっそくそのバンドのドラマーの実家の倉庫でバンドと対面した。川越の高校生とは違い、格好からして全員すごく洗練されてて、ギタリストなんて3才ぐらい年上に見えたし、最初、ちょっとナメられている感じもした。で、その彼からいきなりポール・バターフィールド・ブルース・バンドの “絶望の人生 I Got A Mind To Give Up Living”(66年の2nd『East-West』に収録)を歌ってみてくれと言われてね。当時、ポール・バターフィールド・ブルース・バンドなんてちゃんと聴いている人はほとんどいなかったし、いきなり “絶望の人生” を歌ってくれと言われて驚いたけど、俺はちゃんと歌えた。最初の一節を歌っただけで、ナメた態度だった彼ら3人は「オーッ!」とびっくりした。結局その倉庫で2回ぐらい練習した後、メンバーの一人が通っていた高校の学園祭に出たんだ。その時一緒に出ていた別のバンドのシンガーが俺のヴォーカルを絶賛してくれたのはよく憶えている。彼は俺以上の長髪で、レッド・ツェッペリンの大ファンだった。
The Paul Butterfield Blues Band “I Got A Mind To Give Up Living”
■そのバンドとはその後も一緒にやったんですか?
灰野:いや、それっきりだったと思うけど、その学園祭を見に来ていた人から声をかけられたんだよ。高橋さんというドラマーだった。「自分たちは錦糸町界隈でブルース・バンドをやっているんだが、歌ってくれないか?」と誘われて、会いに行った。まだバンド名がないそのグループのメンバーは皆、俺よりもちょっと年上で、俺が加入してから実況録音というバンド名をつけた。彼らは当時、フリートウッド・マックのカヴァーなどをやっていた。皆、ピーター・グリーン好きで。でも、俺がグランド・ファンク・レイルロードやMC5を歌いたいと提案したら、面白そうだからやろうということになった。その時のベイスが、70年代にカルメン・マキ&OZに参加した川上シゲ(川上茂幸)だよ。
■その実況録音というバンドが、初めて参加したプロのバンドですか?
灰野:一応形の上ではギャラが発生するバンドという意味では、そういうことになるね。実際はギャラなんてなかったけど。
実況録音はビアガーデンやゴーゴー喫茶などで演奏していた。鶯谷とかの怪しい店で。俺が実況録音で歌っていたのは、1970年の前半の半年足らずだったと思うけど、どの場所でもたいていは、一回演奏しただけで、あるいは途中で止められて、もういいと帰されていた。客が全然踊れないし、いつも俺が絶叫していたから。実況録音はロック・バンドと名乗っていたけど、彼らにしてみればロックでもなんでもなく、ノイズだったわけ。でも、メンバーも、もっと普通に歌えとかは一度も言わなかった。俺は一番年下なんだけど、彼らは常に俺に興味を持ってくれてたし、ソウルフルで礼儀正しい奴、という見方をしてくれていた。とてもいい関係だった。俺はライヴが終わると川越まで帰れないから、よく川上が泊めてくれたんだ。
客席からバンバン物が飛んできたので「かかってこい、この野郎!」と怒鳴り返した。結局、客がどんどん帰ってゆき、4ステージやることになっていた最初のステージで俺たちはクビになった。
■実況録音の音を録音したものは残ってないんですか?
灰野:いや、まったく。もしかしたら、どこかにあるのかもしれないけど……あったとしても、俺が怒鳴っている声とかが入っていると思う。いつも「ヤメロー!」とか野次る客と怒鳴り合いをしてたから。銀座のソニー・ビルの屋上ビアガーデンでやった時のことはよく憶えている。1曲目でグランド・ファンク・レイルロードの “Are You Ready”(69年のデビュー・アルバム『On Time』に収録)をブルー・チア風にやったら、客席からバンバン物が飛んできたので「かかってこい、この野郎!」と怒鳴り返した。結局、客がどんどん帰ってゆき、4ステージやることになっていた最初のステージで俺たちはクビになった。もちろんギャラももらえなかった。ビートルズの “And I Love Her” とか、当時のビアガーデンの定番曲を普通にやっていればいいものをね(笑)。
Grand Funk Railroad “Are You Ready”
実況録音のメンバーとはその後は長いことつきあいが途絶えたままだった。川上がOZなどメジャーで活動していることは知っていたけど、俺的にはOZは違うという認識だったし。でも、彼らとは数年前に再会したんだよ。ネットで調べて、ギタリストでリーダーだった伊藤寿雄さんを見つけた。伊藤さんたちは、今でも年に一度ぐらい集まってライヴをやってて、俺も彼らのライヴを観に行った。2019年の正月には、普段は錦糸町で惣菜屋をやっている伊藤さんの家に招かれて、食事もしたし。伊藤さんには俺のライヴも観てもらった。俺がギターを弾くなんて彼は知らなかったからびっくりしていたけど、「ロックだな」と言われて、うれしかった。
ちなみに、このインタヴュー後の2022年7月2日、灰野は《三様》なるライヴ・イヴェント(高円寺 ShowBoat)で52年ぶりに伊藤、川上と一緒にステージに立った。伊藤がスタンブル・ブルース・バンド(Stumble Blues Band)のギタリストとして、川上が川上シゲ with The Sea のベイシストとして、そして灰野が川口雅巳とのデュオとしてそれぞれのライヴをこなした後、最後に、伊藤・川上・灰野 +サポート・メンバーという形で実況録音の同窓会ライヴが繰り広げられた。ステージ上で時折笑顔になる灰野を私が観たのは、後にも先にも、その時だけである。

2022年7月2日高円寺 ShowBoatでのライヴ