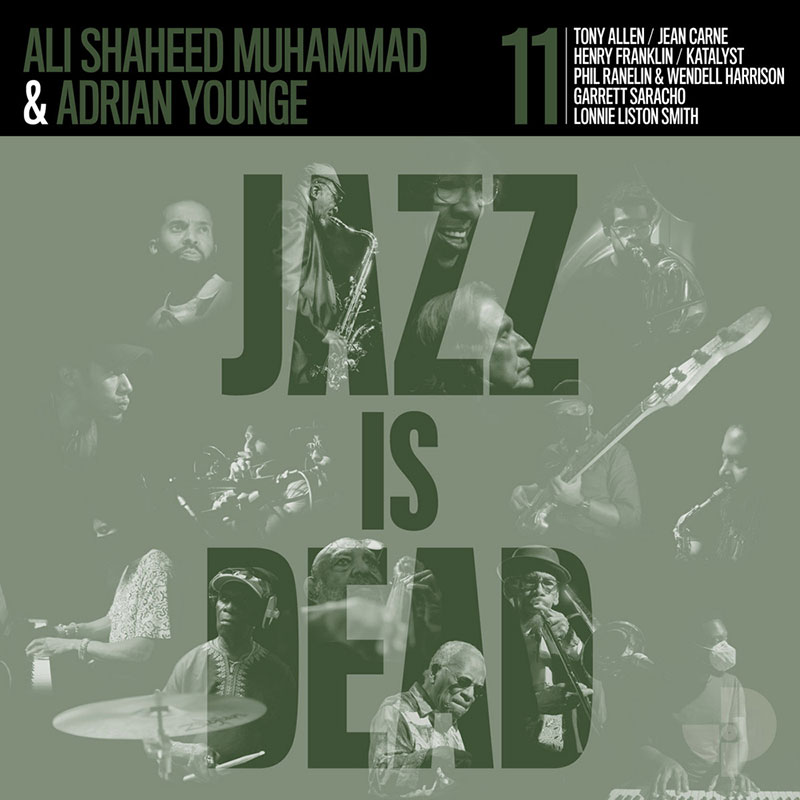ブライアン・リーズ、フエアコ・S以外にもいくつかの名義を持つこのアーティストのキャリア、そのサウンド・スタイルは一貫したものもありつつも、そのスタートとなった2010年代というディケイドは端的にいって前半後半で異なる。2010年代初頭、キャリア初期には朋友アンソニー・ネイプルズのレーベル〈Proibito〉を中心に、このフエアコ・S名義も含めていくつかの名義でディープ・ハウス・トラックをリリースしじわりじわりと知名度をあげた。どちらかと言えばダンサブルな12インチを主体にしたアーティストであったと言ってもいいだろう。その後、ひとつ転機となったのはやはりフエアコ・S名義のファースト『Colonial Patterns』だろう。初期のシングルのハウス路線をその後のアンビエント・タッチの作品へとつなげたその音楽性で、やはり OPN の〈Software〉との契約ということもあり、より広い層へと名前を広げていった作品となった。以降、どちらかと言うと、アルバム・サイズの作品で大きく注目される感覚で、2016年のセカンド『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』は、2010年代のダブ・アンビエントの金字塔ともなった作品だ。さらにディケイドの後半は、クラブ・トラックスというよりも、後述する活動を含めてより幅広いカッティング・エッジなエレクトロニック・ミュージックを牽引する存在であり続けている。
この2010年代後半から現代の彼の活動ということで言えば、自身も含めた、その周辺のアーティスト・コミニティというのがひとつ強い印象を持って浮かび上がってくる。抽象度のさらに高いダーク・アンビエントなペンダント名義、そしてペンダント名義をリリースした主宰レーベル〈West Mineral Ltd.〉からは彼の朋友とも言えるアーティストたちの作品を次々とリリースしている。またこのアーティストの連なりはさらにスペシャル・ゲスト・DJ(Special Guest DJ)主宰の一連のレーベル〈3XL〉とその傘下〈Experiences Ltd. / bblisss / xpq?〉のリリースへとつながっていくのだ。自身の参加するゴーストライド・ザ・ドリフト(Ghostride The Drift)のようなプロジェクトも含めて、この一団でそれぞれコラボ・ユニットなどを形成し、どこか匿名性が強くミステリアスな印象を受ける。リリースされるサウンドも雑多で、ダブ・アンビエントからIDM、ベース・ミュージック~ダンスホール~ジャングル、さらにはブルータルなメタルコアのような作品まで、エレクトロニック・ミュージックのレフトフィールド・サイドを突っ走っていると言えるだろう。
そんななかで2022年の春にリリースされたフエアコ・Sの『Plonk』は驚くべく完成度でまたもやシーンを驚かせた。エコーの霧が晴れたクリアなエレクトロニック・サウンドは、どこかDAW~グリッチ流入前の1990年代の実験的なテクノの、言ってしまえばリスニング~アンビエント・テクノにおける「リズム」の冒険を現代へと引き寄せたという感覚がある。いや、そう感じるのは古い人間だけで、彼が言うように現在の音楽がそうした傾向を持っていると考えた方がいいのかもしれない。ともかくそうした断片的な流れ、要素が、彼の才能を通して新たにシーンに提示されたということだろう。フエアコ・S名義のアルバムは、現代のところ毎回サウンドががらりと変わっている。それは彼のアーティストとしての進化の発表の場ということなのかもしれない。2020年代のエレクトロニック・ミュージックのシーンを占う上でも、またひとつ分岐点となりそうな作品だ。
今回はコロナ禍を経て、4年ぶりとなる待望の来日公演直前に、シーンの新たな流れの推進力となるかもしれない新作の話題を中心に、通訳の方に質問を託したのだった。
オウテカの存在は大きくて、1990年代後期と2000年代初期のIDMや電子音楽全般に影響を受けている。
■ベルリンを活動拠点にされているようですが、音楽制作に関して影響はありましたか?
ブライアン・リーズ(Brian Leeds、以下BL):2019年から2021年までの、パンデミックのほとんどの期間中はベルリンに住んでいたけれど、実は2021年の末に地元のカンザスシティに戻ってきたんだ。カンザスでは家族と自然の近くにいられることを楽しんでいたけれど、今回の日本のツアーの後に、フィラデルフィアに引っ越すよ。
■新作『Plonk』は、ラストの “Plonk X” こそアンビエントですが、ホエアコ・S名義としてはある意味でパーカッシヴで新たな境地へと至った傑作だと思っています。まず、アブストラクトな『Plonk』というタイトルはどこからきたのでしょか?
BL:タイトルの『Plonk』(日本語で「ポロンと鳴る音、ドスンと落ちる音」などの意味)は、アルバムのサウンドを端的に説明するのにちょうど良かったんだ。アルバムのプロジェクトのいちばん初期のファイルを保存するために付けた名前で、自分の中でその言葉が引っかかっていたんだよね。“Plonk” というワード自体が、今回のアルバムを上手く言い表す機能をしていると思う。あと、これまでのアルバムがすごく長い名前になりがちだったから、その流れを断ち切るためでもあったんだ。
■『Plank』の、特に、3、4、6、8のようにパーカッシヴなサウンドは、前作の『For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)』とも、また初期の同名義でのハウス・サウンドとも違った印象を持ちます。強いて言えば最初期のオウテカなど、93年ぐらいの、まだDAW登場以前の実験的なテクノを彷彿とさせます。こうしたスタイルの楽曲はなにか、意図があったものでしょうか? それともたまたまデキたパーツから膨らませていったものなんでしょうか?
BL:うん、オウテカの存在は大きくて、1990年代後期と2000年代初期のIDMや電子音楽全般に影響を受けている。ただ、そういった音楽からの影響はアルバムにはっきり出ていると思うけれど、自分はラップをよく聴いていて、それも確実に今回の作品に関係しているね。
■今回のリズムの打ち込みに関して、例えばスケッチに使っている入力機材などが影響を与えたとか、そういったテクノロジーの部分での影響はありますか?
BL:このアルバムはDAWの FL Studio 20 だけで作った。コンピュータのみの制作は制約があるけれど、自分にとってはいちばん強力な機材でもある。アルバムの中のメロディやパーカッションの多くでランダマイザーを取り入れている。今回のアルバムのテーマでもある自動車や自動車工場、メカニックといったものの影響に立ち返って、人間味のある要素を取り除いて、機械自身が語るようなサウンドにしたかったんだ。
■今回は同名義の以前の作品のような深いダブ・エフェクトがかかったサウンドとも違ったクリアな音像が印象的です。こうした変化はどこからきたものでしょうか?
BL:ダブの要素や音響のフィデリティ(忠実度)にはいつも興味があって、特にロウな音質に惹かれるのかもしれない。でも今回のアルバムでは新しい方法を探求して、いままでとは違う制作のプロセスを試したいという気持ちが強かった。普段聴いたり、DJでかけたりする大半の曲から確実に影響を受けている。うまく成功したかどうかはわからないけれど、正しい方向に向かって間違いなく一歩進み出せたと自分では思っているよ。

今回のアルバムのテーマでもある自動車や自動車工場、メカニックといったものの影響に立ち返って、人間味のある要素を取り除いて、機械自身が語るようなサウンドにしたかったんだ。
■SIRE.U の参加、そもそもヴォーカル曲には驚かせられたんですが、彼の起用はどのような経緯で?
BL:Sir E.U は、自分が昔リリースしたことのある〈Future Times〉から作品をリリースしていて、今回自然とフィットするように感じたんだ。彼は幅広いタイプのトラックでもラップができる人で、その才能にも興味があった。今回僕が用意したトラックでも、素晴らしい仕事をしてくれたと思う。今後は、自分の作品でも誰かのレコードのプロデュースでも、もっとヴォーカリストと一緒に曲を作ってみたいね。ラップでもポップでもなんでも。
■逆に前作との境界線にあるような “Plonk VII” “Plonk X” などのアンビエント曲も印象的です、アルバムの選曲にはわりと時間などをかけたんでしょうか? なにかコンセプトなどがあればお教えください。
BL:これらのアンビエントなトラックを一緒に含んだのは、自分の過去と現在の橋渡しをするためでもある。自分の過去の作品との繋がりをリスナーに与えながらも、これからの未来に対して同意を促すような役割を果たしているんだ。
■『Plonk』直前には ペンダント名義のアンビエント・アルバム『To All Sides They Will Stretch Out Their Hands』がリリースされていますが、本作との関係性はあるんでしょうか? 例えばそれぞれしっかりとサウンド・コンセプトを作って別々のタイムラインで作ったのかとか、作っているうちにそれぞれ振り分けていったとか。
BL:『To All Sides~』は、ペンダントの最初のアルバム(『Make Me Know You Sweet』)を作った2017、2018年と同時期にできていたんだ。かなり時間が経って古くなっているから、いまの自分との繋がりはもはや薄れたといえるね。曲を作るときは、基本どのプロジェクトのためのものかは把握しているよ。ペンダントではダークな一面を、ホエアコ・Sではメロディックで、遊び心に富んだ一面を表現している。自分にとってホエアコ・Sはジャンルに縛られずフィーリングを重視するプロジェクトで、ペンダントはダーク・アンビエントってところだね。
■『Plank』のリズム・アプローチの変化のひとつに、ゴーストライド・ザ・ドリフト(Ghostride The Drift)などの周辺アーティストとのコラボからの影響ありますか?
BL:確かに影響を受けているし、他の人との音楽制作自体もそうだね。他のアーティストとのコラボレーションと、自分が聴く音楽、そしてDJをすること、これらの組み合わせが『Plonk』にいちばん大きな影響な影響を及ぼしている。
■あなたのレーベル〈Western Mineral〉とスペシャル・ゲスト・DJことライアン・フォール(Ryan Fall)の〈3XL / Experiences Ltd. / xpq?〉といったレーベルは、あなたのカンザス時代からの仲間=Rory O’Brien、Exael、Ulla Straus and Romeu といったアーティストとともにひとつのシーンというかコミニティを作っているような印象を受けます。彼らとのコラボレートはやはりあなたにとってとても良い刺激になっていますか?
BL:もちろん、僕の友達と彼らの音楽は、いままでの創作にすごく影響を与えているし、今後も進化し続けたいと思っている。計り知れない才能があって、作りたい音楽を限りなく追い求める意欲を持った友達に出会えてラッキーだったよ。彼らの音楽にはすごく遊び心があるし、インスピレーションをもらえるんだ。
■ちなみにスペシャル・ゲスト・DJは、アメリカ時代からのつながりですか?
BL:Shy(スペシャル・ゲスト・DJ)とは、当時のパートナーの Naemi(exael)を通じてだね。彼らが2013年ごろにカンザスシティを訪れた時に知り合った。そのとき Shy はシカゴに住んでいたんだ。
■また今回はアンソニー・ネイプルズとジェニーのレーベル〈Incienco〉からのリリースとなりましたが、彼のレーベルは、あなたやDJパイソン、そしてアンソニー自身のようなエポックメイキングな作品をリリースするアーティストばかりです。アンソニーのそうした審美眼に関して、あなたの印象をお教えください。
BL:アーティストたちが本当にやりたいことを表現できるようなレーベルの運営に情熱をそそぐアンソニーとジェニーには愛をささげたいね。大きなレーベルと契約する代わりに、自分の音楽をリリースしたがっている友達がいてくれるのは嬉しい。僕にとってはつねに個人的な繋がりが大切なんだ。
■ちなみにさきほどあげたオウテカのような90年代初期の実験的なテクノで好きなアーティストはいますか?
BL:オウテカ、モノレイク、パン・ソニック、ヴラディスラヴ・ディレイ、T++ だね。だけど『Plonk』に関しては間違いなく、もっと新しい音楽からインスピレーションを受けているよ。
ペンダントではダークな一面を、ホエアコ・Sではメロディックで、遊び心に富んだ一面を表現している。自分にとってホエアコ・Sはジャンルに縛られずフィーリングを重視するプロジェクトで、ペンダントはダーク・アンビエントってところだね。
■あなたの初期のハウス作品にはベーシック・チャンネルのようなダブ・テクノとセオ・パリッシュのようなローファイなハウスのハイブリッドのような印象を受けます。このふたつのアーティストはあなたの音楽に影響を与えていますか?
BL:ベーシック・チャンネルは、自分の音楽性に最も影響を与えているもののひとつだね。セオ・パリッシュはそれほどかな。カンザスシティに住んでいて、ハウス・ミュージックに興味があったときは彼の影響を受けてたけれど。最近あまりハウスは聴かなくなったんだ。
■上述のアーティスト、影響を受けた作品としてあげるとすれば?
BL:たくさん選びたいのはあるけれど、最初に挙げるならベーシック・チャンネルの「Radiance」だね。
■ジャマイカのルーツ・ダブは聴きますか? もしお気に入りの作品があればお教えください。
BL:いや、ルーツ・レゲエはあまり興味がないね。どちらかといえば、ダンスホールやラテン・ミュージックを現代的に解釈した人の音楽からインスパイアを受けることが多いかな。
■あなたはつねに、カテゴライズを拒むようにエレクトロニック・ミュージックに新たな道を作り続けています。それと同時に初期の作品や今作には、ダンス・ミュージックへの愛情も感じることができます。こうしたアーティスト像はあなたが考えていることとマッチしますか?
BL:確かに、過去の音楽は現在の自分に影響している。だけどそれを従来の形でそのまま焼き直すというよりは、新しい方法を通して音楽への愛やリスペクトを伝えようとしているんだと思う。だから過去の音楽だけにフォーカスするのではなく、いまの新しい音楽を聴くことで、そのためのアイデアを多く得ることができるんだ。
■生涯で最も衝撃的だったDJは誰でしょう?
BL:とても答えづらい質問だから、最近感動したセットで、自分の世界の中で踊れたDJをふたり選ぶよ。Djrum と Barker だ。
Huerco S. 来日情報
■熊本公演
EVEN

2022年6月17日(金)
開始:22時
料金:3500円(1ドリンク付)
Line up:
Huerco S. from KC
egg
IWAKIRI
Kentaro
jpn
■東京公演
Sustain-Release presents 'S-R Tokyo 2.0'

2022年6月18日(土)Day1
開始:10:00pm~6:00am
料金:DOOR ¥4,500 / W/F ¥4,000 / GH S MEMBERS ¥4,000 / ADV ¥3,250 / BEFORE 23 ¥2,500 / UNDER 23 ¥2,500
Line up:
-STUDIO X
Aurora Halal (NY)
Huerco S. (KC)
食品まつり a.k.a Foodman -Live
Lil Mofo
-CONTACT
Kush Jones (NY)
YELLOWUHURU
DJ Trystero
Kotsu
-FOYER
Hibi Bliss
suimin
k_yam
Loci + sudden star
T5UMUT5UMU

2022年6月19日(日)Day2
開始:4:00pm~11:00pm
料金:DOOR ¥3,000 / W/F ¥2,500 / GH S MEMBERS ¥2,500 / ADV ¥2,250 / BEFORE 17 ¥2,000 / UNDER 23 ¥2,000
Line up:
-STUDIO X
Hashman Deejay & PLO Man (VBC / BE)
-CONTACT
Mari Sakurai
ASYL
DJ Healthy
https://www.contacttokyo.com/schedule/sr-tokyo2-day1/
■愛知公演
DENSE#

2022年6月24日(金)
料金:Door 3000YEN / Adv 2500YEN / U25 2000YEN(0時までに入場のみ)
Line up:
HUERCO S
KURANAKA aka 1945
live:
CRZKNY
dj:
DJ UJI
Karnage
abentis
Good Weather in Nagoya
■大阪公演
2022年6月25日(土)
料金:BEFORE 0:00 : 2000yen DOOR : 3,000yen
開始:23:00
Line up:
Huerco S. (West Mineral Ltd.)
and more