COVID 19がパンデミックになり4ヶ月が過ぎた。NYでは、人は普通に外に出ていて、マスクをしているだけで普段と変わりない。公園、ビーチには人がぎっしり、レストランやバーも、アウトサイドシーティングは人がぎっしり。
https://gothamist.com/news/coronavirus-updates-july-18

地下鉄やバスも人はたくさん乗っていて、6フィートのソーシャル・ディスタンスが取るのが難しいときもたくさんある。が、COVID 19はまだ猛威を振るっている(夏になれば勢力は弱まる、という見解は大きく外れた)。7月上旬、アメリカ全土の感染者数はいままでになく上昇(1日に5万人!)。フロリダ、テキサス、アリゾナ州では、感染者が激増し、カリフォルニア州はレストラン、バーの営業を停止し、1ヶ月前に逆戻りした。ニュ-ヨークは感染率が高い州からの移動を禁止した。
今日(7/19)のNY市のコロナウィルス感染者データ:感染者合計:221,419人、新感染者:298人、死者合計:23,400人、新死者:12人
7/11、ニューヨークは3月以降初めて、コロナウィルスでの死者が0になったが、油断は禁物。大勢の若者たちがクイーンズのスタンウェイ・ストリートやロングアイランドシティなどでマスクなしでたむろっている。
https://gothamist.com/food/videos-astorias-steinway-street-has-become-party-street-queens
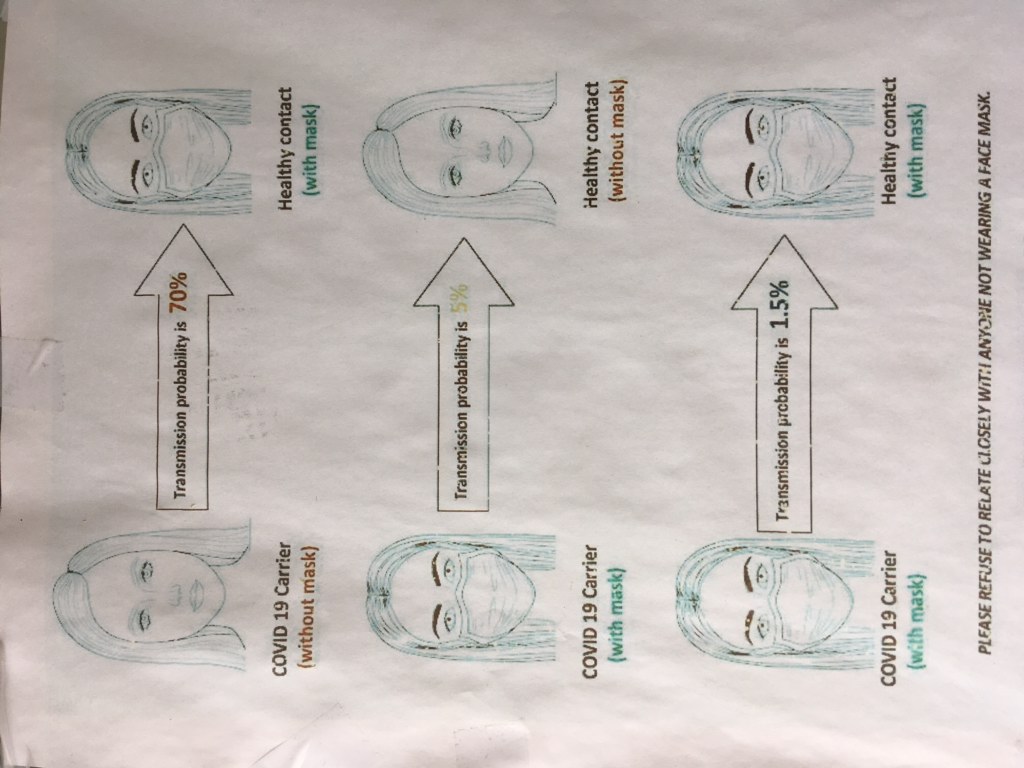
自分は感染していないだろうと誰でも思いたいが、実際は無症状患者もたくさんいるはず、私みたいに。私は6月にアンチボディ検査、7月にPCR検査を受けた。アンチボディは陰性で、PCRは陽性という結果だった。ん、いまコロナにかかっているじゃないか!
とはいっても無症状だったので、まったく気がつかず。熱も無いし、味覚も嗅覚もあるが、かかっているというならそうなのだろう。慌てて隔離生活に入る。隔離生活は、基本家で隔離されるのだが、必要あれば、ニューヨーク市がホテルを用意してくれる(3食付き)。毎日(14日間)ニューヨーク市から電話がかかってきて「今日の調子はどうか」、「誰かに会ったか」、「どこにも外出しなかったか」などいろいろ質問される。「何かあれば、すぐこの番号に電話して」と緊急の電話番号を渡されるなど、いたれり尽くせり。だから、NYは感染者が減っているのだろう。
私も家にいるしかない。やりたいことができないのは辛いが、いまはオンラインでミーティングしたり、友だちや家族に頻繁に電話したり、リモートでできることを探すしかない。バー経営者の友だちは2週間に一回テストを受けているという。人と顔を合わす仕事だから、自分がかかっているかどうか知っておく義務がある、と。自分がかかるのはまだいいが、周りの人に知らない間にうつしてしまうのが一番怖い。持病のある、年老いた親と住んでいる人に会う可能性もあるからだ。
20日からニューヨークは第4段階に入る。動植物園の営業や映画・テレビ制作、無観客でのスポーツイベントが可能になる。一方で美術館や店内飲食など屋内の活動は引き続き制限する。その代わり、レストランの野外飲食はレイバーディから10月末まで延期され、テーブルを並べられる歩行者天国が、40ヶ所追加された。
https://gothamist.com/food/nyc-adds-40-new-open-streets-outdoor-dining-extends-open-restaurants-october
チェルシーマーケットも木曜日から日曜日までと日程制限はあるが、先週末から再開し、ハイラインも予約制でオープンしている。ニューヨークは人が多いから、何かあれば、すぐに感染者は増えるだろう。みんなが自覚し、健全な世のなかになることを祈る。私も自宅待機を続けるしかない。








