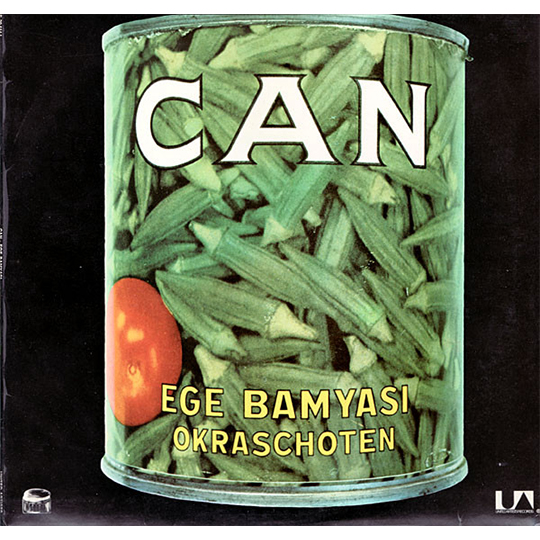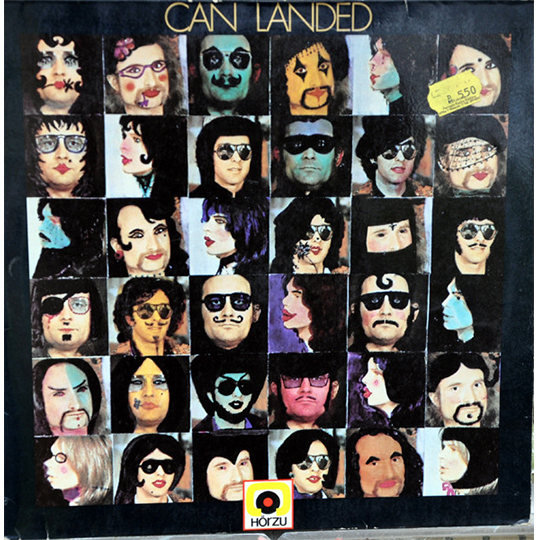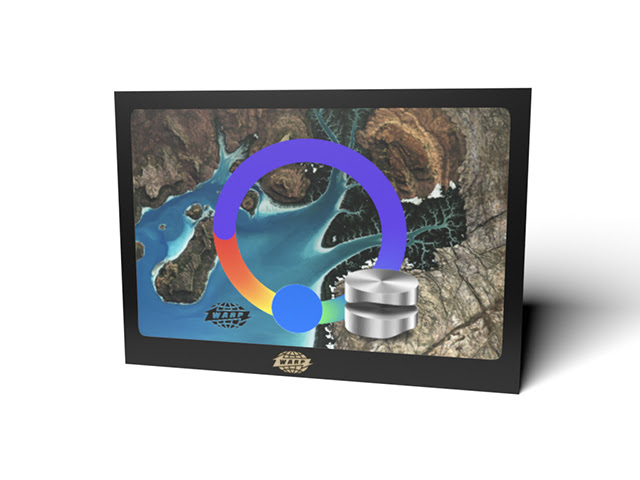2020年、中止になったフェスのひとつ〈Rainbow Disco Club〉。当日(https://www.ele-king.net/review/live/007571/)は、配信という手段でダンス・ミュージック好きを喜ばせてくれたことがもう遠い昔のように感じられる。あまりにも、もう、あまりにもいろんなことがあったからね、今年は。
で、そのときの放送をこのお正月に無料配信すると、RDC主催者が発表した。以下、主催者からのメッセージ。
https://rainbowdiscoclub.zaiko.io/e/RerunofSomewhereUnderTheRainbow
激動とも言える2020年も残す所あと僅かとなりました。
今年は新型コロナウイルスの世界的パンデミックにより、多くの方が様々な面で疲弊する年になったかと思います。
ご存知の通り、我々Rainbow Disc Clubも伊豆や世界各地での公演の中止を余儀なくされ、精神的にも経済的にも非常に苦しい年となりました。
しかし、そのような中にも今までは無意識のうちに遠ざけていた感覚に、気付けたことも多かったように思えます。
今までは想像できなかった人の辛さ、苦悩について考える時間を持てたこと。
日常の小さな変化、家族や友人の些細な気遣いに、大きな幸せを感じたり。
オンラインでの開催となったRDC 2020 。
あの日、私たちは離れた場所で、それぞれのやり方でパーティーに参加しましたが、大切な部分は確実に繋がっていると感じました。
アーティストたちの素晴らしいパフォーマンスとともに、SNSでのやり取りや投稿も強く思い出されます。
ダンサーたちはテキストや写真となって確かにダンスフロアを形成していました。!
何度でもお礼を言わせてください、本当にありがとうございました。
あと数日で2020年は終わり、新しい年がやってきます。我々は来るべき、2021年のために、RDC 2020をZAIKOさんの協力のもとに、1月2日 12:00より無料で再放送いたします。
なぜお正月なのか? 2020年ではなく、2021年のために年が明けてから、新しい気持ちの中で皆さんにまた会いたいと考えたからです。
途中で初詣に行ったり、おせちを食べたり、友達とZOOMを繋いで新年の挨拶をしたり、それぞれが迎えるお正月の中で、 #rainbowdicoclub 一緒の時間を過ごせたらこれほど嬉しいことはありません。
寒く不安な日が続きますが、どうか健康にお気をつけてお過ごしください。
2021年、ダンスフロアでの再会を楽しみにしております。
-
There are only a few days left in the turbulent year of 2020.
We assume that many of you are exhausted in various ways due to the global pandemic.
As you know, Rainbow Disco Club were forced to cancel the festival in Izu and parties around the world, which put us in very difficult condition both mentally and financially.
However, even in such a situation, we could become aware of important things that we unconsciously ignored before. Having time to think about the pain and suffering of people that we rarely think about before.
We could feel great happiness in small changes in daily life and little care of families and friends.
RDC 2020 was held online. That day, we attended the party in different ways, far away, but we felt connected with the wonderful performances of the artists. We vividly remember the exchanges and posts on social media.
All of you made the dance floor virtually through posting comments and pictures. How can we ever say thank you enough for the loves you shared.
We decided to rebroadcast RDC 2020 "somewhere under the rainbow" with free of charge from 12:00 (JST, GMT-9) on January 2nd in 2021, with the cooperation of ZAIKO, for the new year to come.
Why did we choose the New Year? Because we wanted to see you all again with a new feeling of 2021. It would be great if we could spend time together with #rainbowdicoclub during the New Year.
There are still cold and uneasy days to come, but please be extra careful and stay healthy.
We very much look forward to seeing you all again on the dance floor in 2021.