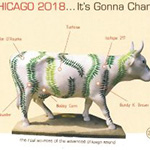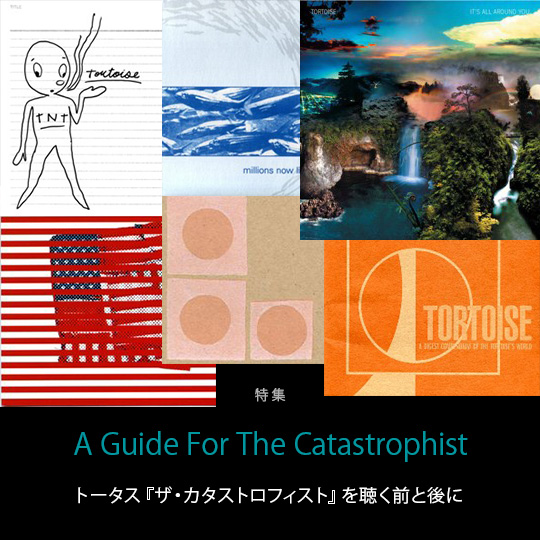MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Tortoise- The Catastrophist

まずジャケットがいい。それはいまのトータスが、トータス以上でも以下でもないことを簡潔に言い当てる合成写真であり、そこには「ポストロックのオリジネイター」なる称賛あるいはレッテルをゆるりと剥がしてしまう絶妙な脱力感と余裕が漂っている。前作からの6年半のブランクの間に僕が何度か観たライヴでも同様で、メンバー5人が楽器を入れ変えつつハイレベルなアンサンブルを構築していく様はもはやたんなる前提であって、方法論自体は少なくともその場では大した問題ではなく、その瞬間に立ち上がる総体としてのトータスこそがすべてだというような説得力があった。何らかのメッセージもわかりやすいカタルシスもないが、ただ音が――緻密なアンサンブルの「結論」ばかりがおもしろいのである。
ただ、トータスのライヴを観るたびに笑ってしまうのは、『スタンダーズ』収録の“セネカ”をメンバーがステージ前方に並んで手拍子を煽るのだが(いやべつに煽ってないのかもしれないが)、そのリズムが難しくて観客が即座にはついていけない瞬間である。何度か繰り返すうちに手拍子は揃っていくのだが、そうしたパフォーマンス、言い換えれば彼らなりの「サービス」がある種の複雑さだった時期はたぶんにあって、とくにリズムの実験とテクノロジーのより入り組んだ内面化に取り組んでいたゼロ年代のトータスないしはポストロックを、その受容において必要以上に敷居の高いものにしていたようにも思う。たとえばバトルスのようなバンドがゼロ年代後半にその「高度さ」を称賛されはじめたときにこそ、ユーモアを前面に出したことを思い出してもいいかもしれない。そして、トータスのそもそもの魅力とはけっして高度さだけではなかったはずだ。
結果的には6年半のブランクがいい熟成期間となったのだろうか、『ザ・カタストロフィスト』にはトータスによるトータスに対する気負いはほとんど聞こえてこない。わたしたちはここで襟を正してポストロックをありがたがらなくてもいい。すんなりとジャズの要素が流れ出してくるタイトル・トラックのオープニングからして『TNT』の時代にワープすることができるし、リズムもずいぶんシンプルだ。もちろんバンドの20年に渡る音の冒険の成果はここで繊細に折り重なっているのだろうが、そうしたものがすっと奥に引っ込むような懐の深さがあって、たとえば“ザ・クリアリング・フィルズ”を聴くとミニマルなリズムのなかに奇妙な立体感を持ったダブ処理が聞こえてくるのだが、それ以上に時間間隔と平衡感覚が攪乱されるような陶酔感が心地いい。シンセやギターが柔らかな叙情を醸すメロディ、素朴にも思えるほどすっと流れていくドラミング。先行シングルの“ゲシープ”には彼ららしいクラウトロックに影響された緩やかなグルーヴ感覚があるし、ミニマルと彼らの重要な出自のひとつであるハードコアが奇妙に出会う“シェイク・ハンズ・ウィズ・デンジャー”の理知的な獰猛さにも痺れる。
2曲のヴォーカル・トラックも現在のバンドの軽やかな姿勢が表れているのだろう。デイヴィッド・エセックス“ロック・オン”のカヴァーにおける思いがけないファンクと色気、そしてヨ・ラ・テンゴのジョージア・ハブレイがマイクを取る“ヤンダー・ブルー”のメロウなチルアウト……。メランコリックなラスト2曲へとアルバムが向かうときには、ただただそこに流れる緩やかな時間に身を任せることができる。
すなわちそれこそがトータスらしさだと言えるだろう。トータスはおよそロックが持っていた大仰な意味性を解体したが、トータスそのものに強い意味、ある種の信仰を与えられつつあったいまだからこそ、それ自体を知的に異化してみせている。90年代のトータスを聴くときのように、リラックスしてここに何の物語性を見出さなくてもいい。ややこしい方程式を手放してもいい。トータスの音の結論にこそ没入することのできる、20年越しの見事な解がここにはある。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE