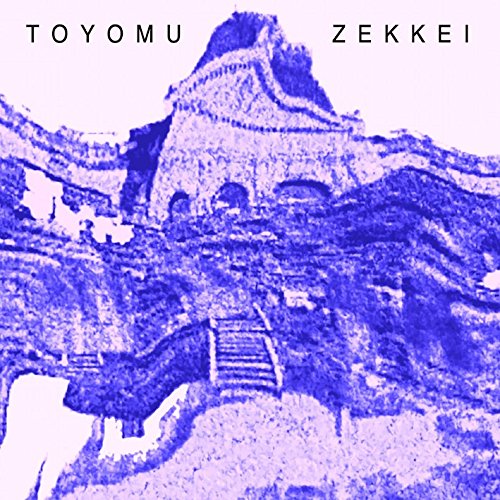2010年代の先端に位置する電子音楽/電子音響の分母はクラブ・ミュージックである。だが、その分母は明確な実態を認識できる「分母」ではない。そうではなく壊れたJPEG画像のように、なにがしかの「グリッチ」(それは音響的ノイズに限ることではない。インターネット以降の環境における情報量の無限の増大とそれに伴う極度のローカル化によって、われわれの無意識や共通認識がすでにグリッチしているからだ)によって存在が破損している「分母」なのである。
いうまでもなく、90年代以降の「クラブ・ミュージック」とは、70年代までの「ロック」と同じく、ポップ/ミュージックにおける重要な分母だったわけだから、それが00年代的なエクスペリメンタル・ミュージックに流れ込んできてもまったく不思議ではないし、電子音による生成という側面から考えれば、むしろ当然の帰結なのだが、問題はわれわれの分母=現実が崩壊しつつある状況を(それが音楽という感覚にもっとも作用しやすいメディアゆえ)、反映「してしまっている」点が何より重要なのだ。少し前に「OPN・アルカ以降」というワードが一時期、頻繁に流通していたが、そこにおいても「破損しかけた分母」の問題が共通している重要なエレメントであったように思う(ゆえに「ミュータント」なのだ)。
それゆえだからこそ、インダストリアルでも、アンビエントでも、ニューエイジなどの10年代的な先端的電子音楽/音響において、分母たるクラブ・ミュージックのエレメントが、どのように「残存しているか」、もしくは「最初からあったのか、否か」という問いは、クリティックやジャーナルにおいても重要な問題に思えるのである。それはジャンル内の正当性を判別する意味ではなく、そのような「共通認識」が、どこまで「壊れているのか」を思考する輪郭線のように機能するからに他ならない。そして、その「壊れている」感覚の根底には21世紀型「恐怖」がある。20世紀型の世界が終わる恐怖。足元が揺らいでいる感覚。それはネガティヴな意味に回収される問題ではない。そうではなく、その破損という「切断」は、逆に「今そのもの」として、私たちに新しい音楽と、その刺激を伝えてくれる。そう、デデキント・カット『$uccessor』のように。
デデキント・カットはリー・バノン(フレッド・ワームズリー)の変名プロジェクトである。1987年生まれの彼は、ヒップホップをベースにしつつ、ジャングルからチルウェイヴ(もはや懐かしい名称だ)まで多様な音楽の要素を、自身の曲やアルバムに反映している。2014年に〈ニンジャ・チューン〉からリリースした『オルタネイト/エンディングス』は、ジャングル・ドラムンベースを全面的に導入したアルバムで話題になったが、2015年に同じく〈ニンジャ・チューン〉からリリースした『パターン・オブ・エクセル』では、一転して、断片的なサウンドをミックス音源のようにコラージュしたアンビエント作品へと変貌、まるで真夏の不穏のようなエクスペリメンタル・ミュージックを展開していたのである。
このデデキント・カット名義、最初のフル・アルバム『$uccessor』は、先の『パターン・オブ・エクセル』の系譜を継ぐアルバムといえる。アンビエントを基調に、ニューエイジ、ジャングル、ノイズ、クラシカルなどのエレメントが交錯し、融解している。いわば、『$uccessor』は、情報がフロウする現代ならではのアンビエント・ミュージックと称することができる(ちなみに3曲め“カンヴァセーションズ・ウィズ・エンジェルズ ”には、DJシャドウが参加している)。じっさい『$uccessor』には多様な音楽のエレメントが横溢し、つながり、そして流れ、独自のアンビエントを生んでいる。当然、彼の出自をみれば分かるように、本作の「分母」にはクラブ・ミュージックがあるのだが(ドラムンベース的な箇所もある)、しかし、やはりこれまた今の先端的音楽としては当然ながら、その「分母」は、すでに融解し、微かな断片のよう存在している。そこでは「音」が廃墟のように壊れかけている。フレッド・ワームズリーは、そのサウンドの断片を「流れ」として、再構成していく。
私には、その残骸の活用・再構成という点こそが、本作に特有の21世紀型の「郷愁」感覚を生んでいるように思えてならない。1987年生まれの若者が生み出す音楽に、不思議な「郷愁」があるということ。それはレコード文化の残骸や廃墟そのものともいえるかもしれないし(アルバム名「successor」という単語は「後任、後継者、相続者、継承者」という意味だ)、真夜中や真夏などの時間が停止した世界への感性ゆえかもしれない。だから「郷愁」は、そのまま「恐怖」に反転しうるのだ。柔らかくシルキーな音色に満ちた本作には、ある特有の「ダークさ」があるのだが、それはこの「郷愁/恐怖」の感覚によって生まれているものではないか。とくに6曲め“☯”から7曲め“5ucc3550r”には、感覚の反転が美しいアンビエントで鳴り響いている。いわば、恐怖と郷愁のアンビエント。2016年から2017年をブリッジするための、とても重要なアルバムである。