コラボ大好きっ子のOPNが次に組む相手はいったい誰なのか、というのは多くの人びとが気にしているところだろう。どうやらその相手は、デヴィッド・バーンになるようである。
去る5月5日にアンジェリーク・キジョーのライヴにゲスト参加して話題を集めたばかりのバーンだが、『ステレオガム』が報じたところによると、彼は来年の初頭に新たなソロ・アルバムをリリースしたいと考えており、すでにワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとコラボをおこなっているという。バーンは先週、ダニエル・ロパティンから送られてきたトラックに歌詞とメロディを書いたそうだ。
バーンはここ10年の間に、セイント・ヴィンセントやファットボーイ・スリム、ブライアン・イーノとのコラボ・アルバムを発表している。他方のOPNは昨年、アノーニやDJアールとコラボをおこなっている。
「OPNã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
もし「近年のエレクトロニック・ミュージックの担い手たちのなかで、OPNやアルカと肩を並べるくらいのタレントは誰か」と問われたなら、僕は迷わずローレル・ヘイローの名を挙げる。『Quarantine』、『Chance Of Rain』、『In Situ』と、作品ごとにスタイルを変えながらしかしつねに唯一無二のサウンドを響かせてきた彼女が、この初夏にニュー・アルバム『Dust』をリリースする。いま彼女が鳴らそうとしているのはいったいどんなサウンドなのか? 彼女は今年の1月に初音ミクにインスパイアされたプロジェクトの新曲も発表しているが、来るべき新作にはそれと関連した要素も含まれているのだろうか? いろいろと疑問は尽きないけれど、クラインやラファウンダも参加していると聞いては、期待しないでいるほうが難しい。『Dust』は6月23日に〈ハイパーダブ〉よりリリース。
ところで、「宅録女子」という言葉、いい加減なんとかならんのだろうか……
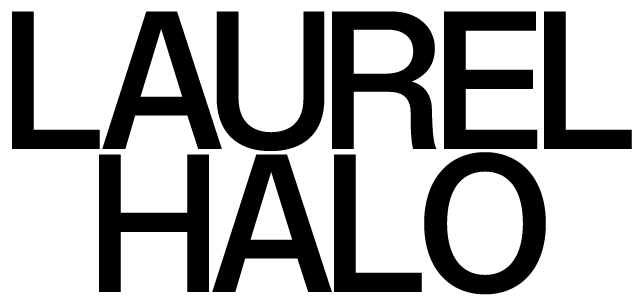
宅録女子から唯一無二の気鋭音楽家へ
〈Hyperdub〉に復帰し完成させた待望の新作『Dust』のリリースを発表!
ジュリア・ホルターやイーライ・ケスラーなど注目の才能が多数参加した注目作から
新曲“Jelly”のミュージック・ビデオを公開!
いきなり英『WIRE』誌のアルバム・オブ・ザ・イヤーを獲得し、主要メディアが絶賛したデビュー・アルバム『Quarantine』やエクスペリメンタル・テクノ作『Chance of Rain』などのアルバムを通し、高度なスキルと独創性を兼ね備えたポスト・インターネット世代の代表的アーティストとして注目を集めるローレル・ヘイローが、2015年に〈Honest Jon’s〉からリリースされたアルバム『In Situ』を経て、再び〈Hyperdub〉に復帰! 会田誠の『切腹女子高生』をアートワークに使用したことも話題となった『Quarantine』以来となるヴォーカル作『Dust』を完成させた。
今回の発表と同時に、昨年〈Warp〉からデビューを果たしたLafawndahとサウス・ロンドンのシンガー兼プロデューサー、Kleinがヴォーカル参加した新曲“Jelly”を公開した。
Laurel Halo - Jelly (Hyperdub 2017)
https://youtu.be/IrjeMN_U1hw
本作の作曲作業は、実験的な科学技術を使った作品、電子音楽やパフォーミング・アーツの発表/研究/作品制作のほか、ワークショップやトークなどをおこなう施設として設立されたメディア&パフォーミング・アーツ・センター(Experimental Media and Performing Arts Center)、通称EMPACでおこなわれている。そこで様々な機材へアクセスを得たローレル・ヘイローは、制作初期段階をひとりでの作業に費やし、終盤では前述のLafawndahと、ニューヨークを拠点にパーカッショニスト兼画家としても知られるEli Keszlerを招き、セッションを重ね、2年間の制作期間を経て完成させた。
より洗練されたソング・ライティングとカットアップ手法、即興を取り入れた電子音が特徴的な本作には、そのほか、Julia Holterや$hit and $hineのCraig Clouse、Zsのメンバーであるサックス奏者、Sam Hillmerのソロ名義Diamond Terrifierなどが参加し、そのハイセンスな人選にも要注目。
参加アーティスト:
Klein
Lafawndah
Michael Salu
Eli Keszler
Craig Clouse ($hit and $hine)
Julia Holter
Max D
Michael Beharie
Diamond Terrifier
ローレル・ヘイローの最新アルバム『Dust』は、6月23日(金)に世界同時リリース! 国内盤にはボーナストラックが追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。iTunesでアルバムを予約すると、公開された“Jelly”がいちはやくダウンロードできる。
 label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
artist: LAUREL HALO
title: DUST
release date: 2017/06/23 FRI ON SALE
国内盤CD BRC-551 定価 ¥2,200(+税)
ボーナストラック追加収録 / 解説書・歌詞対訳封入
iTunes: https://apple.co/2pVIFwG
[TRACKLISTING]
01. Sun to Solar
02. Jelly
03. Koinos
04. Arschkriecher
05. Moontalk
06. Nicht Ohne Risiko
07. Who Won?
08. Like an L
09. Syzygy
10. Do U Ever Happen
11. Buh-bye
+ Bonus Tracks for Japan
言葉は便利だ。とりあえず「OPN/アルカ以降」と言っておけばいい。いやもちろん、OPNとアルカを一緒くたにしてしまうのはいささか乱暴だとは思う。でも、そういう言い方をすることで伝わる何かがあるのもたしかだ。じっさい「OPN/アルカ以降」としか形容しようのないサウンドというものもある。けれど幸か不幸か、まだそういうサウンドを的確に指し示す言葉は発明されていない。ヴェイパーウェイヴだとか、ウィッチハウスだとか、ブロステップだとか、これまでいろいろと言葉は編み出されてきたけれど、こと「OPN/アルカ以降」に関しては、いまだに適切なタグが生み出されていないと言っていいだろう。言葉は便利だけれど、いつも少し遅れている。
そんな「OPN/アルカ以降」という大雑把なくくりのなかで、アッシュ・クーシャと並ぶくらいのポテンシャルを感じさせてくれるのが、このダシキラだ。フォルティDLの主宰するレーベル〈Blueberry Records〉からリリースされた彼のデビュー作「Immolated」は、まさに「OPN/アルカ以降」の王道を行く作品である。
蛾の一属の名称を自身のステージネームとして使用するこの風変わりな男は、本名をエイドリアン・マルテンス(Adrian Martens)と言い、南アフリカ出身で、ニューヨーク在住のプロデューサーだ。ちなみに南アフリカといえば昨年はゴムが話題になったけれど、特にその周辺と接点があるわけではない模様。
「生贄」と題されたこのEPは、全体的に冷たく硬質で、ダークなムードに貫かれている。2曲めの“Caduceus”なんて、イントロからもうktkr感満載である。まさにOPNとアルカが仲良く同居しているかのようなトラックで、ときおり挿入される鋭いサウンドは虫の鳴き声を表現しているようにも聴こえる。4曲め“Sensation”も同じ路線で、インダストリアルな電子音がこれまた虫の鳴き声のように耳に突き刺さる。小さな箱に閉じ込めた虫さんを自らの手でじわじわとなぶり殺しにしている場面の生々しいドキュメントとでも言おうか……『進撃の巨人』の殺戮シーンが好きな人ならきっと気に入るだろう。6曲め“Sanctuary”でも、細かく切り刻まれたサウンドたちがまるで殺されゆく者の悲痛な叫びのように鳴り響いている。
それらの曲とは打って変わって、ブルックリンのシンガーソングライター Embaci がフィーチャーされた先行公開曲“Vipera”では、その神秘的なヴォーカルが支配の実権を握っており、もの悲しげな鍵盤と相まってひと味異なる雰囲気を醸し出している(が、ここでもやはり細かい音響がなんとなく虫の立てる雑音のように聴こえる)。タイトル曲の“Immolated”もノイズとオリエンタルなメロディが奇妙なコミカルさを演出していておもしろい。
しかし、ダシキラというステージネームといい、「Immolated」というタイトルといい、このアートワークといい、彼は虫に対して何か特別な想いを抱いているのだろうか? ググってみると、カマキリの生活環がどうとか、死んでいく昆虫の瞬間がどうといった話がヒットするので、おそらく何かしらコンセプトはあるのだろう。カドゥケウスはヘルメスの杖だし……
ところで虫の第一人者と言えば、個人的には真っ先にミラ・カリックスを思い浮かべるのだけれど、彼は彼女の音楽を聴いたことがあるのだろうか? もしインタヴューする機会に恵まれたら、OPNやアルカについてよりも先に、まず虫について尋ねてみたい。
スペイン語圏の映画が半世紀ぶりに力量を回復しているのに対し、イタリアとフランスの映画はどうにも低調なままである。80年代に似たような地獄を見たイギリスと日本の映画界でさえ見事に息を吹き返したというのに、特にフランス映画は企画性ばかりが目につき、それこそカンヌでパルムドールに輝いたケン・ローチ『わたしは、ダニエル・ブレイク(I, Daniel Blake)』と同じ年にほとんど同じストーリーで、ステファヌ・ブリゼ『ティエリー・トグルドの憂鬱(La loi du marche)』がつくられているにもかかわらず、大した賞は与えられず(セザール賞ではノミネートのみ)、足元で起きている問題に目が向いていないのかとさえ思ってしまう。ポップ・ミュージックも同じくでフレンチ・タッチからエレクトロクラッシュまであれだけ出てきた才能も外国のレーベルに散り果て、次の世代との橋渡しがうまくできなかった結果、フランスのレーベルからリリースされるのはシカゴやデトロイトのプロデューサーの方が多いのではないかと疑ってしまう。オリジナル崇拝が過ぎるというのかなんというか。
ここ数年のエレクトロ・リヴァイヴァルに伴い、いつの間にかDAFスタイルが増殖し、ついでのようにエレクトロクラッシュも呼び戻されている。そんななか、ゼロ年代初頭にエレクトロクラッシュを先導していたブラック・ストロボの初期メンバー、イヴァン・スマッグが活発にリリースを回復させている。ブラック・ストロボのどこからどこまでがイヴァン・スマッグだったのか、同じくキル・ザ・DJもどこまでが彼だったのか、その後はエレクトロ・ハウスのミックスCDを数作まとめただけで、どうも掴みどころのない存在であり続けたものの、アンディ・ウェザオールをダウンサイジングしたような彼の存在感はやはり僕の頭のどこかには残っていたらしい。昨年、〈クラック&スピード〉のティム・パリスと組んでリリースしたイッツ・ア・ファイン・ライン名義のデビュー・アルバムは実のところあまり面白くはなかった。しかし、新たにルパート・クロスとタッグを組んだユニットでは「掴みどころのなさ」をそのままテーマとして凝縮させ、全体としてはミュジーク・コンクレートに現代性を持たせ、半分ぐらいはOPNに対するフランスからの優雅なアンサーを聞かせてくれた。ルパート・クロスの素性はよくわからない。スコットランドの映画音楽家、パトリック・ドイルのアシスタントを務めているようで、なるほど映画音楽に通じる情景描写がスマッグ&クロスの『MA』には溢れている。パトリック・ドイルはカトリーヌ・ドヌーヴの『インドネシア』や、最近ではケイト・ブランシェットの『シンデレラ』などを手掛けている作家。
まずはジャケット・デザインがいい。オフィーリアをアシッド漬けにしたようなイメージ。ヨーロッパ的なオブセッションから表面的な暗さを取り除いている。かといってアメリカ的でもない。なんというか、絶妙のスタンスを感じさせる。オープニングはガムランを思わせる「カーリロン(Carillon)」。オリエンタル・ムードを引きずりながら続いてドローン調の「マイ・ハート・ザ・ビート・スキップド(My Heart The Beat Skipped)」へ。「ワレン(Warren)」ではポルカのような(?)エレクトロのような(?)二拍子のミニマル・ミュージックがインサートされ、ピアノとフィールド・レコーディングを組み合わせた「オンド・デ・チョック(Onde De Choc)」でも伝統と現代性は激しく衝突している。「オステンダ2(Ostende Pt. 2)」や「スロウダイヴィング(Slowdiving)」ではゴングやスペースクラフトといったフレンチ・プログレの最良の成果をアンビエント・ミュージックとして再生、再評価の機運が高いエリアル・カルマやミッシェル・レドルフィなど発掘音源の動向とも重なって見えるものがある(このアルバムの売りは、アデル・ストライプというオフビート・ジェネレイションの小説家による朗読が「コック・オブ・ザ・ノース(Cock Of The North)」でフィーチャーされていることだとあちこちの紹介やらレビューなどには書いてあるんだけれど……誰だ、それは?)。先に「掴みどころがない」と書いたけれど、後半はチル・アウトの道程がそれなりに組まれてはいる。エンディングもシルヴェスター「サムバディ・トゥ・ラヴ・トゥナイト(Somebody To Love Tonight)」のアンビエント・カヴァー。
ここ数年、〈クレクレブーン〉や〈アンチノート〉などフランスから伝わってきたアンダーグラウンド・サウンドは本当に少ない。ジェフ・ミルズによるとフェスなどのイヴェント・レヴェルではテクノはいまフランスが一番面白いともいう。〈ブラザーズ・フロム・ディッフェレント・マザー〉や〈フラジャイル・ムジーク〉といったレーベルの次があるなら、誰か早く伝えて欲しい。
ど、ど、どんと三段重ねのニュースである。アルカが〈Mute〉を離れ、〈XL〉とサインを交わした。そして4月7日にニュー・アルバム『Arca』がリリースされる。それに先駆け新曲“Piel”が公開されたが、そこではなんとアルカ本人が歌っている。
本人によるヴォーカルがフィーチャーされているのは、今回公開されたこの1曲のみなのだろうか。それともアルバム全編にわたってアルカのヴォーカルが導入されているのだろうか。そのあたりの情報はまだ明かされていないが、レーベルの移籍やアルバムのタイトル、あるいは「内面」や「感情」といった本人のコメントから推測するに、来るべきアルカの新作はこれまでとは異なる作風に仕上がっている可能性が高い。
「OPNとは何者なのか」という問いに答えが出ていないのと同様、アルカという現象もいまだ解明されていないと言っていいだろう。しかし今度の新作はもしかすると、「アルカとは何者なのか」という問いにひとつの手がかりを与える内容になっているのではないだろうか。まあ現時点ではまだ何もわからないので、さしあたりは公開された新曲を聴きながらおとなしく待っていよう。
A R C A
奇才アルカが〈XL Recordings〉との契約を発表!
最新アルバム『Arca』を4月7日(金)に世界同時リリース!
ジェシー・カンダによるアートワークと新曲“Piel”を解禁!
“我々の期待を完全に超えている”
- Pitchfork【Best New Track】獲得

Artwork by Jesse Kanda
これは僕の声であり、僕の内面の全てだ。自由に判断してほしい。
闘牛のように、喜びを求める感情の暴力を目撃することになる。
これは、感情のぶつかり合いの模倣的存在が、不自然なほど深く、自己陶酔していく姿なんだ。
- Arca
ベネズエラ出身ロンドン在住の奇才、アルカことアレハンドロ・ゲルシが〈XL Recordings〉と契約し、待望のサード・アルバム『Arca』の4月7日(金)世界同時リリースを発表した。長年のコラボレーターであるヴィジュアル・アーティスト、ジェシー・カンダの手がけるアートワークと、初めて自身の歌声を披露した新曲“Piel”を公開した。『Pitchfork』では早速【Best New Track】を獲得している。
Arca - Piel (Official Audio)
早くからカニエ・ウェストやビョークらがその才能を絶賛し、FKAツイッグスやケレラ、ディーン・ブラントといった新世代アーティストからも絶大な指示を集めるアルカ。セルフタイトル作となった本作『Arca』は、2014年の『Xen』、2015年の『Mutant』に続くサード・アルバムとなり、〈XL Recordings〉からの初作品となる。国内盤CDの詳細は近日発表予定。iTunesでは、アルバムを予約すると公開された“Piel”がいちはやくダウンロードできる。
Arca: Discography
『XEN』2014
『MUTANT』2015
BJORK『VULNICURA』2015
KANYE『YEEZUS』2013
FKA TWIGS『EP2』2013/『LP1』2014
KELERA『HALLUCINOGEN』2015
DEAN BLUNT『THE REDEEMER』2013
BABYFATHER『BBF: HOSTED BY DJ ESCROW』2016
FRANK OCEAN『ENDLESS』2016

label: BEAT RECORDS / XL RECORDINGS
artist: Arca
title: Arca
release date: 2017/04/07 FRI ON SALE
iTunes Store: https://apple.co/2m9K7um
Apple Music: https://apple.co/2l1GBNJ
Tracklisting
01. Piel
02. Anoche
03. Saunter
04. Urchin
05. Reverie
06. Castration
07. Sin Rumbo
08. Coraje
09. Whip
10. Desafío
11. Fugaces
12. Miel
13. Child
14. Saunter (Reprise) *Bonus Track for Japan
ヴィジブル・クロークスは、ポートランドを拠点に活動をするニューエイジ・アンビエント・ユニットである。メンバーは、スペンサー・ドーランとライアン・カーライルのふたり。スペンサー・ドーランは00年代に、プレフューズ以降ともいえるサイケデリックかつトライバルなアブストラクト・エレクトロニカ・ヒップホップをやっていた人で、00年代のエレクトロニカ・リスナーであれば、知る人ぞ知るアーティスト。スペンサー・ドーラン・アンド・ホワイト・サングラシーズ名義の『インナー・サングラシーズ』など愛聴していた方も多いのではないか。
その彼が、〈スリル・ジョッキー〉からのリリースでも知られるドローン・バンド、エターナル・タペストリーのライアンと、このような同時代的なニューエイジ・アンビエントなユニットを結成し、アルバムをリリースしたのだから、まさに時代の変化、人に歴史ありである。
そう、ここ数年(2010年代以降)、いわゆる80年代的なニューエイジ・ミュージックが、エレクトロニカ/ドローン、OPN以降の、新しいアンビエントの源泉として再評価されており、ひとつの潮流を形作っている。そのリヴァイヴァルにおいて大きな影響力を持ったのが、オランダはアムステルダムの〈ミュージック・フロム・メモリー〉であろう。同レーベルは80年代のアンビエント・サウンドを中心とする再発専門のレーベルで、なかでもジジ・マシンを「再発見」した功績は大きい。じじつ、ジジ・マシンのコンピレーション盤『トーク・トゥー・ザ・シー』は日本でも国内盤がリリースされるほど多くのリスナーに届いた。そのピアノとシンセサイザーの電子音を中心とした抒情的で透明で美しい音楽は、現代にニューエイジ・アンビエントという新しいジャンルを作ったといっても過言ではない。まさに「過去」が「今」を作ったのだ。再発レーベルとしては、理想的な成功である。
その〈ミュージック・フロム・メモリー〉がリリースした、唯一の日本人アーティスト・ユニット作品がディップ・イン・ザ・プールの『On Retinae』の12インチ盤であった。ディップ・イン・ザ・プールは、1980年代から活動をしている甲田益也子(ヴォーカル)と木村達司(キーボード)によるユニットで、日本でも根強い人気とファンがいるし、1986年には〈ラフトレード〉からデビューを飾ってはいるが、しかし、それをニューエイジ・アンビエントの文脈と交錯させた〈ミュージック・フロム・メモリー〉のセンスは、やはり素晴らしい(ちなみに香港のプロモ盤がもとになっているらしい)。だが、ふと思い返してみると、日本の80年代は、細野晴臣をはじめ、安易な精神性に回収されない音楽的に優れたニューエイジ/アンビエント的な音楽が多く存在した。それはときにポップであったり、ときに実験的であったりしながら。
ヴィジブル・クロークスのスペンサー・ドーランは、そんな80年代の日本音楽のマニアなのだ。細野晴臣、小野誠彦、清水靖晃らを深く敬愛しているという。彼らの楽曲を用いた「1980年~1986年の日本の音楽」というミックス音源を発表しているほど。当然、ディップ・イン・ザ・プールの音楽も愛聴していたらしい。そして、本作『ルアッサンブラージュ』は、そんな日本的/オリエンタルな旋律やムードが横溢した作品に仕上がっている。そして、先行シングルとしてリリースされた“Valve (Revisited)”は、ディップ・イン・ザ・プールとの共作であり、甲田益也子がヴォイスで参加。アルバム2曲めに収録された“Valve”には甲田益也子が参加しているのだ(ちなみに、“Valve (Revisited)”は国内盤にはボーナス・トラックとして収録)。
ここで思い出すのだが、昨年、戸川純が復活し、ヴァンピリアとの共演盤にしてセルフ・カヴァー・アルバム『わたしが鳴こうホトトギス』をリリースしたことだ。同時期に『戸川純全歌詞解説集――疾風怒濤ときどき晴れ』も刊行されたこともあり、本盤は、かつて戸川マニアのみならず若いファンからも受け入れられ、大いに話題になったが、こちらは「ニッポンの80年代ポップス/ニューウェイブ」再評価における総括のように思えた。
対して、ヴィジブル・クロークスにおける、ディップ・イン・ザ・プール/甲田益也子参加は、たしかに80・90/2010世代の新旧世代の共演なのだが、文脈はやや異なり、ジジ・マシン再評価以降ともいえる近年のニューエイジ/アンビエント文脈にある。先に書いたように、ディップ・イン・ザ・プールがジジ・マシン再評価の流れを生んだ〈ミュージック・フロム・メモリー〉からリイシューされたことも考慮にいれると、ヴィジブル・クロークスがやっていることは、世界的な潮流である「80年代ニューエイジ/アンビエント文脈」の再解釈なのだろう。そこにおいて、日本の80年代的なニューエイジ・アンビエント、そしてそのポップ・ミュージックが重要なレファレンスとなっているわけだ。〈ミュージック・フロム・メモリー〉からのリイシューや、本作におけるディップ・イン・ザ・プールの参加は、その事実を証明しているように思える。
くわえて本作には、ディップ・イン・ザ・プール/甲田益也子のみならず、現行のニューエイジ/アンビエント文脈の重要な電子音楽家がふたり参加している。まず、昨年、〈ドミノ〉からアルバムをリリースしたモーション・グラフィックス。あのコ・ラのサウンド・プロダクションを手掛けたモーション・グラフィックスだが、彼が昨年リリースしたアルバムにも、どこか80年代の坂本龍一を思わせる曲もあった。また、〈シャルター・プレス〉などからアルバムをリリースする現在最重要のシンセスト/電子音楽家Matt Carlsonも、参加しているのだ。
アルバム全体は、ニューエイジ的なムードのなか、現代的な音響工作を駆使し、現実から浮遊するようなオリエンタル・アンビエント・ミュージックを展開する。非現実的でありながら、どこか80年代末期の日本CM音楽のようなポップさを漂わせている。あの極めて80年代的な「日本人による、あえてのオリエタリズム」を、外国人が参照し、実践すること。そのふたつの反転が本作の特徴といえよう。
本作に限らず現在のシンセ・アンビエントは、80年代中期以降の音楽/アンビエントをベースにしつつ、そこに2010年代的な音響を導入し、アップデートしているのだが、本作などは、アルバム全編から「1989年」的な感覚が横溢しているように思える(たとえば、細野晴臣の『オムニ・サイト・シーング』を聴いてみてほしい)。
余談だが、この80年代初期から後期へのシフトは重要なモード・チェンジではないか。それは「バブル感」の反復ともいえる。ちなみに、80年代と一言でいっても、前半と後半では随分と違う。いわゆる日本のバブル経済は1985年のプラザ合意以降のことで、世間的にその実感が伴ってきたのは、「株投資」と「土地転がし」が(一時的に)一般化した80年代末期(1988年~1989年あたり)だったはず。
そう、最近のいくつかの音楽には、この「景気の良かった時代」への憧憬があるように思えるのだ。それこそ大ヒットしたサチモスは、1989年くらいの初期渋谷系(と名付けられる以前。田島貴男在籍時のピチカート・ファイヴ)的なもののYouTube世代からの反復だろう。そういえば、ディップ・イン・ザ・プールの『On Retinae』も1989年だった。
あえていえば、本作(も含め、近年の音楽)は、「景気が良かった時代の音楽を、景気が悪く最悪の政治状況の時にアップデート」することで、「景気が良かった時代への夢想や憧れ」を反転するかたちで実現しようとしているとはいえないか。つまり、30年以上の月日という時が流れ、新鮮な音楽としてレファレンスできる時代になったわけである。
これは、若い世代には80年代という未体験の時代への憧憬も伴うのだろうが、私などがこの種の音楽を聴くと歴史の平行世界に紛れ込んだような不思議な感覚を抱いてしまうのも事実だ。しかしこの感覚が重要なのだ。つまり、リニアに進化する歴史の終わりという意味を、現在の音楽は体現してまっているのだから。これこそポストモダン以降の、アフター・モダンというべきで状況ではないか?
ヴィジブル・クロークスも同様である。逆説的なオリエタリズムの反転。景気の良さへの憧憬。経済の上部構造と下部構造のズレ。その結果としてのニューエイジ・ミュージックのリヴァイヴァル。そこにレイヤーされるOPN以降の精密な電子音楽の現在。
それらの複雑な文脈が交錯しつつも、仕上がりは極めて端正で美しい電子音楽であること。それが本作ヴィジブル・クロークス『ルアッサンブラージュ』なのである。1曲め“Screen”の細やかな水の粒のような美麗な電子音を聴けば、誰の耳も潤されてしまうだろう。
本作は、ニューヨークの名門エクスペリメンタル・レーベル〈RVNG Intl.〉からのリリースだ。つまり文脈といい、リリース・レーベルといい、近年のニューエイジ・アンビエントの潮流における「2017年初頭の総決算」とでも称したい趣のアルバムなのだ。非常に重要な作品に思える。
昨年ベルリンのCTMフェスティヴァルで発表されたローレル・ヘイローの新しいプロジェクト、「スティル・ビー・ヒア(Still Be Here)」。これはクリプトン・フューチャー・メディアのソフトウェア「初音ミク」にインスパイアされたもので、Mari Matsutoya、Darren Johnston、LaTurbo Avedon、Martin Sulzerとの共同プロジェクトとなっている。そのスティル・ビー・ヒアが1月31日、“Until I Make U Smile”および“As You Wish”と題される2曲のMVを公開した。
大きな文化現象となってしまったことで、かえってその勘所が見えづらくなってしまった感のある初音ミク~ボーカロイドだが、近年少しずつ音楽の文脈からそれを捉え直す流れが生まれてきているように思われる。かつてデトロイト・テクノにどっぷり浸かり、OPNことダニエル・ロパティンらと共同作業をおこない、〈ハイパーダブ〉から作品を発表してきたローレル・ヘイローのようなアーティストが、まさにいま初音ミクとがっつり向き合うというのは、何かひとつ大きな突破口になるような気がしてならない。今後の動きに注目である。
アノーニ、怒っています。昨年リリースされたアルバム『Hopelessness』でテロや死刑や環境破壊について激しくかつ流麗に歌い上げ、アメリカという国の希望のなさ=ホープレスネスをあぶり出してみせたアノーニですが、トランプの大統領就任を受け、女性こそが道を変えるというメッセージとともに新曲“Paradise”を公開しました。
まさに「ホープレスネス」という言葉が何度も登場するこの新曲は、3月17日にリリースされる新作EP「Paradise」に収録されます。同EPはアルバムに引き続き、ハドソン・モホークおよびOPNとのコラボレイション作品となっています。
A N O H N I
ブリット・アウォード2017ノミネートも話題のアノーニが
3月リリースの最新EPより、新曲“PARADISE”を公開!
本年度のブリット・アウォード2017にて「ブリティッシュ女性ソロ・アーティスト」部門にノミネートされたアノーニが、最新アルバム『HOPELESSNESS』に続く、最新EP「PARADISE」を3月にリリースすることを発表し、タイトル・トラックを公開した。
ANOHNI: PARADISE
アルバム同様、〈Warp Records〉所属の気鋭プロデューサー、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとハドソン・モホークのふたりとのコラボ作品となっている“PARADISE”には、電子音と政治的な歌詞の衝突を通して、活動家たちの発言をサポートし、ポピュラー音楽に対する既成概念を破壊しようとするアノーニの姿勢が表れている。
本作には、完全未公開の新曲やライヴでのみ披露されている楽曲など計6曲が収録される。

label: Rough Trade
artist: ANOHNI
title: Paradise
release date: 2017/03/17 FRI ON SALE
[TRACKLISTING]
1. In My Dreams
2. Paradise
3. Jesus Will Kill You
4. Enemy
5. Ricochet
6. She Doesn’t Mourn Her Loss
(小川充)
ザ・エックス・エックスはデビュー・アルバムの『エックス・エックス』を2009年に発表して以来、インディ・ロックのあり方を変える存在であったと言える。ギターのロミー・マドリー・クロフトとベースのオリヴァー・シム、そしてドラムの代わりにキーボード/プログラミングのジェームズ・トーマス・スミスという変則的なトリオ編成で、デビュー当初はポスト・ダブステップやベース・ミュージックといった方面からも語られていた。それはジェームズがジェイミー・エックス・エックスという名前でDJ活動もおこない、エレクトロニック・サウンドに大きくコミットしてきたからだ。彼の存在により、ザ・エックス・エックスはインディ・ロックとクラブ・ミュージックを繋ぐ筆頭となった。ザ・エックス・エックスの音楽性そのものを見ると、ダークでメランコリックな色調を帯びたギター・サウンドが軸にあり、英国のロック・バンドに顕著なスタイルを受け継いできたと言える。繊細で今にも壊れそうな儚い魅力はロミーとオリヴァーの歌声にも顕著で、特にロミーの歌はエヴリシング・バット・ザ・ガール(EBTG)のトレイシー・ソーンに通じるところもある。EBTGは一般的にネオアコに分類されるが、スタイル・カウンシル、ワーキング・ウィーク、シャーデーなどとともに1980年代のUKニュー・ウェイヴとジャズ・ダンス・カルチャーを繋ぐ存在でもあった。ジャズやボサノヴァなどを取り入れたノスタルジックなギター・サウンドに、ソーンの淡々としてお世辞にもうまいとは言えない歌は見事にマッチしていたが、それはザ・エックス・エックスにおけるロミーの歌についても言えることだ。EBTGは1990年代半ば以降、ドラムンベースやハウスとエレクトロニックなクラブ・サウンドへと傾倒する場面が見られるのだが、それはベン・ワットがDJカルチャーに開眼し、そうした影響を受けていくことに同調する。こうして見るとジェイミー・エックス・エックスは、EBTGにおけるベン・ワットの存在とかなり被るところもあるのではないだろうか。
ジェイミーのソロ活動を見ると、2011年にギル・スコット=ヘロンの遺作となった『ウィー・アー・ニュー・ヒア』でリワークという形でコラボし、そこではUKガラージやダブステップがサウンドに大きな影をもたらしていた。それから4年後にソロ・アルバムの『イン・カラー』を発表するのだが、そこではハウス・ミュージックをはじめ、よりダンス志向を打ち出したサウンドへと変わっている。ザ・エックス・エックスのセカンド・アルバム『コエグジスト』(2012年)でも、そうしたダンス・サウンドへの接近は一部で見られていたのだが、あくまでギター・サウンドが軸のロック・バンドという形は貫いていた。『イン・カラー』はバンドという制限でできない部分をジェイミー自身が解放した作品で、ダンスという享楽性はその開放感を象徴するものであった。『イン・カラー』にはロミーとオリヴァーも参加しており、ロミーが歌う“ラウド・プレイシズ”はダンス・サウンド特有の高揚感に満ちたもので、これまでのザ・エックス・エックスにはなかった世界だ。ちなみに、この曲はアイドリス・ムハマッドのダンス・クラシック“クドゥ・ヘヴン・エヴァー・ビー・ライク・ディス”の大胆なサンプリングによって作られており、そうした楽曲制作そのものにおいてもジェイミーのDJとしての資質が露わになっている。ロミーとオリヴァーもそうしたジェイミーの姿に感化され、ザ・エックス・エックスの新作『アイ・シー・ユー』は『イン・カラー』の方法論を取り入れながら作られた。
アルバム冒頭の“デンジャラス”は、まるでファンファーレを想起させるようなホーンで幕を開ける。このポジティヴで力強いサウンドは、今までのザ・エックス・エックスの世界とは明らかに異なるもので、大地を踏みしめるようなハウス・ビートは『イン・カラー』の延長に本作があることを示している。彼ら特有のギター・サウンドによる“セイ・サムシング・ラヴィング”にしても、今までの作品にあった密室的な世界とは違い、とても開放的で外向きになっていることがわかる。『アイ・シー・ユー』を作るにあたり、メンバーはシャーデーをよく聴いていたとの逸話を聞いたのだが、確かにシャーデーをバレアリックに解釈すればこうなるのかもしれない。“リップス”のロマンティシズムも、1980年代に一世を風靡したニュー・ロマンティックを彷彿とさせるところがある。UKのメディアは『アイ・シー・ユー』について、「ジョイ・ディヴィジョンがニュー・オーダーになったときを思い起こさせる」と述べている。暗鬱としたゴシック・サウンドのジョイ・ディヴィジョンが、ロマンティシズムを携えたダンス・サウンドのニュー・オーダーへと脱皮したときのダイナミズムは、確かに本作からも感じられるに違いない。アルバム中間の“パフォーマンス”や“レプリカ”などのスロー・ナンバーは、従来のザ・エックス・エックスらしいメランコリックなギター・サウンドである。ただし、“レプリカ”におけるレイドバックしたフィーリングは、UKのゴシック的なものとは違い、バレアリックで開放感に満ちたものだ。インタヴューによるとこの曲は、ツアーでアメリカ滞在時にシアトルからLAまで海沿いを車で移動する中、フリートウッド・マックやビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』をよく聴いていて、そうしたところから着想を得て生まれた曲ということだ。“ブレイヴ・フォー・ユー”も同様に、UKのサウンドとは異なるサイケデリック感覚がある。また“テスト・ミー”のようなアンビエントもある。そして“オン・ホールド”のポップ感覚。ホール&オーツをサンプリングしたこの曲は、トロ・イ・モアとかハウ・トゥ・ドレス・ウェルあたりと同列で聴くことができるナンバーではないだろうか。
EBTG、シャーデー、ニュー・オーダーなどが台頭した1980年代半ば、振り返ると英国の音楽界はとても豊かな時代にあったと言える。1970年代後半のパンクやニュー・ウェイヴを経て、新しいアイデアを持つ者がそれを洗練された形で試していた。当時の英国は鉄の女との異名をとったサッチャー首相の政権下にあったが、サッチャー内閣は不況にあえぐ英国経済を立て直す施策を次々と成功させる一方、国際政治の場面ではフォークランド紛争に見られるように保守的で強固な姿勢を見せていた。彼女の政策には賛否両論があり、政治・経済で英国にかつての輝きを取り戻させたと評価する一方、富裕層の優遇の裏で失業者の増加、格差社会の拡大などの歪みを生んだと指摘する声もある。南アフリカのアパルトヘイト支持に対する批判など、ボブ・ゲルドフやU2のボノを筆頭にミュージシャンには反サッチャーの姿勢を見せる者が多かった。英国の音楽はいつの世も英国社会を映し出し、社会状況と密接な関係にある。そして、閉塞した状況のときほどいい音楽が生まれている。サッチャー政権において労働者階級や貧しい若者が感じた圧迫感や閉塞感が、1980年代の英国音楽を生んだとも言える。ところで、政治・経済的にサッチャーはEUの前身であるEECや欧州為替相場メカニズムのERMには反対の立場をとっており、EUについても強く批判していた(反サッチャー姿勢だったボブ・ゲルドフも、EUに関しては反対論者である)。そして、昨年の英国の国民投票でEUからの脱退が決定し、先日はメイ首相が離脱交渉方針を明らかにした。かたやアメリカ大統領にトランプが就任し、社会・経済は世界的にますます不透明な状況に置かれるのだが、そうした年の頭に『アイ・シー・ユー』がリリースされ、その冒頭が“デンジャラス”のファンファーレというのも、何だかとても象徴的ではないだろうか。
小川充
[[SplitPage]](野田努)
2016年の間違いなく素晴らしいアルバム、ソランジュの『ア・シート・アット・ザ・テーブル』とフランク・オーシャンの『ブロンド』(もう1枚はブラッド・オレンジの『フリータウン・サウンド』)を聴いたとき、ひと昔前で言うところのわりとUKよりの、三田格言うところの最新“加工”が施されたR&Bのようなものを聴いてきたリスナーは、ものすごく入りやすかったんじゃないかと思う。そのアカ抜け方というか……。メインストリームが、それまでアンダーグラウンドが試みてきたこと(チル&BとかOPNとかFKAとかテクノとかいろいろ)を、完全に自分たちのものにしてしまったのがこれらの作品の特徴で、それって、サッカーで言えば金持ちで強いチームが下位のチームの良い選手を引き抜くみたいで個人的には複雑な思いに駆られるのだけれど、しかし、まあ、やはり強いチームは強く、よくできた音楽はよくできていることに変わりはない。悔しいけど。はっきり言えば、今日の音楽シーンでは、そうしたUSものの雑食性が抜群に面白いなかで、そう、音楽におけるUSの文化水準の高さを見せつけられているなかで、ザ・xxは『アイ・シー・ユー』において、UKらしくセンスのいい“加工”が施された音楽としては、ずば抜けた完成度を見せたと言える。
ぼくは、最初に8曲目の“オン・ホールド”を昨年聴いたときに、彼らのそれまでの陰鬱な味を残しながら、ポップな領域にまで高めたその曲に興奮した。ああ、彼らはついにエヴリシング・バット・ザ・ガールの領域にいったんだと思った。木津毅君のインタヴューでも触れられているように、サンプリング・ネタも良い。で、アルバムができてから聴いた1曲目の“デンジャラス”、この冒頭のサンプリングでぐいっとやられ、続くベースラインを聴いた瞬間に、このアルバムは間違いない、と思った。“デンジャラス”と“オン・ホールド”の2曲が収録されているという理由だけでも十分に『アイ・シー・ユー』は2017年のベスト・アルバム候補入りなのはたしかである。
個人的な趣味で言えば、いまでも『イン・カラー』が好みなんですけどね。あのアルバムにはその“加工”において、UKらしいファンクネスが、UKらしいジャマイカがある。「イージー、イージー、オーマゴッシュ(いいじゃん、いいじゃん、なんてこったい)」は、ある意最高の歌詞だった。わかるでしょ。だからパウウェルなのであって、泉智が宇多田ヒカルならぼくは水曜日のカンパネラであり、要するにナンセンスと破壊力に、ただただひたすら飢えているのだ。もっと言えば、スリーフォード・モッズが好きなのも、なにはともあれ、あのユーモアですよ、ユーモア。
そういう意味で言えば、xxのナイーヴさは、薄汚れたぼくには「申し訳ない」と恐縮してしまうのだが、しかしこれは良いアルバムだとつくづく思う。内気でシャイなロンドン子が団結して、ソウルフルな、最新の──という言葉を使うと萩原健太さんに怒られそうなので──レトロではなく、現代に相応しいポップ・ミュージックを完成させたと。USの音楽シーンがプレミア・リーグかスペイン・リーグのようなものになったとはいえ、さすがこれだけ歴史あるUKの音楽シーンがフットボール界におけるオランダ・リーグのようになることはないだろうが……、もとい、そしていまもUKらしい良い音楽を聴きたいと思っている。
野田努
ミュージック・コンクレートや現代音楽にグルーヴを持ち込んでクラブ・ミュージックとして聴かせる発想には飽き飽きしていたというか、初期のDPIやOPNに顕著だった初期衝動を超えるような展開はなく、とくにアカデミックの側がストリートも知ってますよというサインを放っているようなものになってくると、そうした記号性だけでげんなりとしてしまって。踊らない人たちのための踊れないクラブ・ミュージックというジャンルもそれなりに需要はあるのでしょうが、どうも僕には意味がなさ過ぎて。「意味がない」が褒め言葉になるような人たちのことですけど。
初期衝動を超えるような展開。そんなものを待っていたわけではなかった。しかし、聴いてみたらレ・グレイシー(グレイシー家?)がそうだった。ディープ・ハウスのアフリカン・サイエンシィーズとサウンド・アートのアイヒアユー(iHEARu)が組んだアブストラクト・ハウスというのか、なんというのか。彼らが4年間のコラボレイトによって生み出した全7曲は最後まで現代音楽にもダンス・ミュージックにも偏らず、スリリングな定義を歩み続けていく。試行錯誤の後が見える曲は1曲もないので、最初から天才を発揮したのでなければ、初期の音源はばっさり切り捨ててしまったのだろう。と、推測したくなるぐらい「完成形」と呼びたくなるフォームがしっかりと出来上がっている。
アフリカン・サイエンシィーズことエリック・ダグラス・ポーターはディープ・ハウスの王道を歩みながらもサード・アルバムは〈パン〉からリリースしていた。そこにはすでに野心が認められた。ヴァクラのサイケデリック・ハウス・ミュージックをアルバムにまとめて世に出したファイアークラッカーもきっと次を求めていたのだろう。この結びつきだけでも充分である。また20年に及ぶフィールド・レコーディングのキャリアをガエル・セガレン(Gaël Segalen)の名義で『ランジュ・ル・サージュ(L'Ange Le Sage)』としてまとめたばかりのアイヒアユーも新鮮な経験を求めていた時期なのだろう。「命は雑音に満ちている」という考え方をしているのか、『ランジュ・ル・サージュ』自体が非常にグルーヴを感じさせるフィールド・レコーディングなので(ジェフ・ミルズがフィールド・レコーディングをやったらこんな感じか→https://www.youtube.com/watch?v=hlwM8GinaOg)、アフリカン・サイエンシィーズのビート・メイキングも無理にダンス・カルチャーと結びつける必要はなかったに違いない。どこからどこまでがどっちの資質に寄るものなのか、それさえも判然としないところがこのコラボレイションの良さである。男女という組み合わせもどこかで功を奏しているのだろう。
それにしてもキレいな音がたくさん使われている(とくにスティール・パンを多用した「パン」)。そのせいで、ワールド・ミュージックのように聴こえる瞬間も多々ある。「永遠をキャプチャーするためにはワイルドでマッドにやるしかない」と彼らは言う。この過剰さは、しかし、都会から生まれるものだろう(ここまで読んで気になった人はなんとかして“ジ・エントリー・ダンス”を聴いて欲しい)。都会こそが戦争に代わるリチュアルを必要としている。スピのつかないリチュアルを。
