どこまで交友の輪を広げるつもりなのでしょうか。「ともだち100人できるかな」とでも言わんばかりに、またしてもOPNが新たなコラボレイションを仄めかす映像を公開しました。お相手はなんと、FKAツイッグスです。ふたりはそれぞれ、同じ2秒ほどの短い動画をインスタグラムに投稿しています。今後のふたりの動向に注目です。
https://www.instagram.com/p/BEG-PMYDhxq/
https://www.instagram.com/p/BEG-bpSC-rv/
「OPNã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
〈フューチャー・タイムズ〉を運営するマックス・Dと、コ・ラのマシュー・パピッチのユニット、リフテッドの国内盤CDが〈メルティング・ボット〉よりリリースされた。オリジナルはエクスペリメンタル・レーベルとしてほかの追随を許さない〈パン〉から2015年に発表されたアルバムで、しかもCD盤でのリリースは日本のみという快挙。
最初に断言してしまうが、このアルバムは、 ポスト・インターネット以降のアンビエント/ニューエイジ・シーンでも極めて重要なアルバムである。傑作といってもいい。昨年のリリース時は、どこかワン・オートリックス・ポイント・ネヴァー『ガーデン・オブ・デリート』の登場に掻き消されてしまった印象であったが(皮肉なことにOPNの〈ソフトウェア〉から発表されたコ・ラの新譜も素晴らしいアルバムだった)、その騒動がひと段落ついた2016年だからこそ、この作品の真価が伝わりやすい状況になっているように思えるのだ。
さて、ここで事態をわかりやすくするために、あえて単純化してみよう。OPN『ガーデン・オブ・デリート』(以下、『G O D』)よりも、リフテッド『1』は、より「音楽的」である、と。もっとも「音楽の残骸」を庭から拾い集めるように組み上げたOPN『G O D』は、いわば20世紀のポップ音楽の亡霊=ゴースト・ノイズのような作品であり、「音だけのインスタレーション」とでも形容したいアート作品であったのだから、「音楽性の希薄さ」は当然だ。そもそもダニエル・ロパティンは、これまでもそういう作品を作ってきた。また、『G O D』は、聴き手に「語り」の欲望を刺激させ、俯瞰的な意識を持たせることにも成功しているのだが(あたかも「神」のように?)、アートにおいて作品と語り(批評)は共存・共感関係にあるので、これもまた当然のことといえよう。その意味で、ダニエル・ロパティンは確信犯的に『G O D』を世界に向けて送り出した(はずだ)。彼は「いま」という時代に、音楽が生き残るためには、単に「音楽」の領域だけに留まっていてはダメだと直感している(と思う)。『G O D』の成功は、その戦略によるものと思われる。
だが、OPN『G O D』において、確信犯的に切り捨てられた「2010年代以降のアンビエント的な、ニューエイジ的な」音楽の系譜には、「音楽的」進化の余白があることも事実だ。そして、このリフテッド『1』は、その「新しさ」を内包したアルバムなのである。それは何か。これまたザックリと書くと、「2010年代的なアンビエント的な、ニューエイジ的音楽」に、「ジャズのリズム」を分断するように導入することで、「アンビエント+ジャズ」という新たなフォームを生み出している点が、本作特有の「新しさ」である。
もっともコーネリアス・カーデューが参加したAMMなどの例を挙げるまでもなく、実験音楽やアンビエントとジャズの関係はいまに始まったわけではないし、また、カーデューとブライアン・イーノとの関係を踏まえると、実験音楽からアンビエントの移行は必然ですらあったのだろう。
だが本作のおもしろさは、オーセンティックなジャズのリズム(ドラム)を分断するようにトラック上にコンストラクションしている点である。いわゆるジャズ的な和声感は皆無なのだ。上モノは極めて端正なテクノ以降の2010年代的ニューエイジ/アンビエント・ミュージックだ。
そうではなく、『1』で抽出されたジャズ的な要素は、ハイハットとシンバルの非反復的な運動によって生成する音響的なエレメントなのだ。それはビート・キープのため「だけ」に用いられているわけではない。リズムは分断され、ほかの音楽的要素のレイヤーと交錯し、複雑で端正なサウンドを形作っていく。シンバルの音が電子ノイズのように聴こえる瞬間もあるほどだ。
とはいえオーセンティックなジャズのビートも、ほぼベースによってキープされているものだから、これもまた当然の帰結といえる。しかし90年代のクラブジャズ以降における「ジャズ的記号」の援用はリズムではなく、コード感の簡素な流用にあったわけで、本作のリズム主体のジャズの音響エレメントの抽出は確かに新しいのだ。ちなみにリズム面の豊かさは、パーカッションでゲスト参加のジャレミー・ハイマンの功績も大きいだろう(本作の「新しいワールド・ミュージック」感覚は、今後の音楽を考えていく上で重要ではないか)。
アルバム中、7分51秒に及ぶ“ベル・スライド”は、「アンビエント+ジャズ」の総決算ともいえる曲だ。まさにジャズ的/アンビエント的/ニューエイジ的なエクレクティック・サウンドで、まるで仮想空間のリゾート・ホテルのロビーで演奏されているような浮遊感に満ちた電子ラウンジ・ミュージックが展開する。この“ベル・スライド”からアンビエント・ジャイアンツであるジジ・マシンの透明なピアノが響く“シルヴァー”に繋がるのだが、これはニューエイジ/アンビエントの歴史性を意識した構成といえよう。
ジジ・マシンは近年再評価が著しいアンビエント音楽家である。彼が自主制作した『ウィンド』は中古市場において高値で取引されていたが、昨年、アムステルダムの優良アンビエント再発レーベル〈ミュージック・フロム・メモリー〉からようやくリイシューされた。また同レーベルからリリースされていた未発表音源集『トーク・トゥー・ザ・シー』も素晴らしいアルバムで、彼の黄昏の色のアンビエント感を満喫できる作品集であった。現在のニューエイジ/アンビエント・シーンを語る上で、最上級のリスペクトを受ける重要人物である。
本作はその彼に深いリスペクトを捧げている。それほどまでに、この『1』において、ジジのピアノはアルバムの中心で深く、深く、鳴り響いているように聴こえるのだ(ジジ・マシンは続く“ミント”にもギターで参加)。『1』における彼の演奏は、ヒトのいない仮想世界に、不意にヒトによる真に美しい音楽が鳴り響くような感覚をもたらしてくれる。
むろん、ゲストはジジ・マシンだけではない。マックス・Dとマシュー・パピッチは、ジェレミー・ハイマン、ダヴィト・エクルド、ジョーダン・GCZ、そしてモーション・グラフィック=ジョー・ウィリアムズらと共に、アンビエント/電子音楽の「庭」に新しい種を蒔いていく。そう、新しい「音楽」を育てるために。
ここまで書けばわかるだろう。本作が2016年にもう一度、「新譜」としてリリースされる意味、それは『ガーデン・オブ・デリート』的な「音楽の廃墟の庭」に、仮想空間のラウンジ・ミュージック、新しいニューエイジ、海の煌きのようなアンビエント、ジャズのリズム・エレメント、新世代のワールド・ミュージックなどの音楽の種が、すでに「蒔かれていた」ことを実感できる点にある。そう、この2015年作品にこそ、2016年以降の「新しいモダン・アンビエント/モダン・ニューエイジ」の萌芽であった、とはいえないか? そして、〈パン〉主宰のビル・コーリガスのモダニスト的な審美眼にもあらためて唸らされてしまうのだ。
ヒップホップの歴史を紐解けば、ハイプ・ウィリアムスという名前に出会う。ハイプは、ミュージック・ヴィデオにおいてラッパーをローアングルで撮った映像作家で、つまり、ラッパーを必要以上にでっかく見せた作家だ。USヒップホップ史には「ハイプ以前/ハイプ以降」という言葉さえある。UKのディーン・ブラントと名乗る男性とインガ・コープランドと名乗る女性が自分たちのプロジェクト名になぜ彼の名前を選んだのかは、いまところ秘密のままである。名前を盗用するにしても、なぜそれが「ハイプ・ウィリアムス」だったのか……、真っ当に想像していけば、ヒップホップ的映像の型=クリシェを作ったことへのおちょくり、パロディ、たんなるジョーク、シニカルなユーモアだったとなる。クリシェを弄ぶこと、おちょくることは、ディーンとインガのハイプ・ウィリアムスの作品に共通した態度だった。だが、そこにはリスペクトもあるように感じさせてしまうところが、彼らのややこしさでもある。
それはドープでサグなイメージをバラ撒きながら、じつは頭で聴く音楽ということだ。他界した天才フットボーラー/戦術家のヨハン・クライフは、サッカーを足ではなく頭でやった人だった。ハイプ・ウィリアムスにとっての音楽も頭で作るものだった。彼らの音楽は基本インストだが言葉は欠かせないし、言葉は両義的に思えた。そもそも彼らは自身の名前からバイオからすべてをでっち上げて登場したのだから。
ハイプ・ウィリアムス解散(?)後、しばらくディーン・ブラントなる名義で活動を続けていた彼だが、昨年からベイビーファーザー名義を使いはじめている。ほかにも@jesuschrist3000ADHD名義とか……ややこしい。覚えられたくない、というわけではない、覚えられたいけれど通常の覚え方では覚えられたくないということなのだろう。
で、baby fatherとは未婚の父を意味する言葉で、スコットランドのヤング・ファーザーズを意識してなのか、あるいは本当に彼が未婚の父なのかはわからない。とにかく彼は2015年にディーン・ブラント名義で『Babyfather』なるアルバムを〈ハイパーダブ〉から配信のみでリリースすると、配信のみでベイビーファーザー名義の『UK2UK』、2016年の1月にはARCAが参加した曲「Meditation」を〈ハイパーダブ〉からフィジカル・リリース、さらに『Platinum Tears』を無料DLでリリースしている。そしてここに〈ハイパーダブ〉からフィジカル・リリースのアルバムのお出ましである。
「これが私に英国人であることの誇りを与えます(this makes me proud to be British)」という言葉からはじまり、言葉はアルバムのなかで何回も繰り返される。移民の子として生まれ、クラブで働き、苦労しながら俳優になったイドリス・エルバの言葉で、彼にとって(そしてディーン・ブラントにとっても)〝英国人としての誇り〟〝英国人としてのアイデンティティ〟を覚えるのはクラブ・カルチャーであり、音楽というわけだ。ディーン・ブラントにしては、まっすぐなメッセージである。
実際、新作の『BBF』は途中なんどか引き裂かれながらもUKブラック・ダンス・ミュージックのタフさにおいて楽観的な結末へと展開する。ディーン・ブラント名義の、2012年の〈ヒップス・イン・タンクス〉からの作品、2014年の〈ラフ・トレード〉からの作品では、バラードを歌ったり、フォークをやったり、ゲンズブールをへろへろにしたような歌を歌ったりと、わけのわからない方向に走った彼だが、『BBF』の特徴は、彼が明らかにクラブ・カルチャーに寄っていることだ。
ヒップホップ・ビート、レゲエのダンスホール、ブレイクビート、グライム、ゲットー・ミュージック……いかにもUKらしい、初期マッシヴ・アタックのような、UKの雑食的クラブ・カルチャーから聴こえる多彩なビートの数々、そしてベースとメランコリーがある。Micachuが歌う曲は、マッシヴ・アタックにトレーシー・ソーンが参加した“プロテクション”を彷彿させなくもない。ARCAが参加した“Meditation”もリズムはダブ/レゲエだ。ジャマイカ色はところどころに出ていて、アルバムで躍動するリズムからは、移民が作ったUKのストリート・ミュージックへのシンパシーを感じる。アートワークで描かれている、再開発されたロンドンの嫌みったらしいほど高級で美しい光景に消されているロンドンを描いているのだろう。
日本でOPNがこれだけ評価されて、(まあ、OPNにクラブというコンセプトはないので比べるのも間違っているのだけれど、同じ時期に注目されたエレクトロニック・ミュージックとして、しかも欧米ではOPNと同じように高評価だというのに)なぜ日本ではハイプ・ウィリアムスが……ディーン・ブラントが……という思いがぼくにはずっとある。あまりにもUK的な捻くれ方が日本では受けない原因なのだろうか。ライヴにおけるストロボもボディーソニックな音響も、頭を使わせる仕掛けも、ぼくに言わせればハイプ・ウィリアムスのほうが上だった。
まあ、取材を受けるわけではないし、過去の数少ない取材でも嘘ばかりだったし、ディーン・ブラントはわかりづらいアーティストのひとりではあるが、この新作は思いのほかダイレクトに響く。何かの間違いで怪しげなラジオ局の電波をキャッチしてしまった、しかもそのラジオ番組では現代の、最高にハイブリッドなUKダンス・ミュージックがかかっていたと、そんな感じのアルバムで、英国人でなくても楽しめる。ひとりでも多くの人に聴いて欲しい。
1月23日、ファッションブランドのケンゾーがパリ・コレクションにてメンズの新作を発表した。そこでOPNがジャネット・ジャクソンのヒット曲をカヴァーしている。
https://www.facebook.com/nowfashion/videos/10154566478983289/
https://m.nowfashion.com/video-kenzo-menswear-fall-winter-2016-paris-18139
原曲は1989年リリースの「リズム・ネイション」。これまでのOPNにも声に対する意識は垣間見られたが、実際に合唱隊まで従えた曲を公表するのは今回が初めてだろう(因みに合唱隊のアレンジを手掛けたのは、ジェフ・ミルズとの仕事でも知られるパリの作曲家トマ・ルーセル)。キャッチーなR&Bだった原曲がまるで別物のような声楽ドローンへと生まれ変わっており、なるほど、『ファクト』誌が「脱構築」という言葉を使いたくなるのも頷ける。
(ジャネット原曲)
2年前にルトスワフスキの「前奏曲」を独自に解釈してみせたときもそうだったけれど、ここまで大胆に改変してくれるとやはり聴いている方も楽しい。カヴァーたるもの、かくあるべし。今後何らかの形で音源化されることがあるのかどうか、気になるところだ。
2月19日。フォー・テットはOPNの “Sticky Drama” を1時間のロング・ヴァージョンへと仕立て直し、ボイラー・ルームにてストリーミング配信を行った。そのお返しなのか、3月4日にはOPNによるフォー・テット “Evening Side” のエディットが公開されている。まるで往復書簡のようなやりとりだが、もしかしたら今後この二人が本格的にコラボレイトする可能性もあるのかもしれない。
2月29日。テックライフの一員であるDJアールは、OPNと一緒にアルバムを制作していることを明らかにした。ローンチされたばかりの同クルーのレーベル〈テックライフ〉からリリースされる予定とのことだが、アールによれば、ダニエル・ロパティンは彼に自身のレーベルである〈ソフトウェア〉に来て欲しいとまで語ったそうで、今回の共同作業はOPNからの熱烈なアプローチによって始まったものなのではないかと想像させられる。
ともあれ、このふたりの出会いに興奮するリスナーも多いだろう。なぜならこの邂逅が示唆しているのは、「上」も「下」もどちらも面白い音楽が生み出される可能性なのだから。昨年行われたリキッドルームでのライヴでも明らかになったように、OPNの弱点は「下」にある。「下」とはつまりベースやドラム、ビートやリズムのことだ。これまで圧倒的な強度の「上」を呈示し続けてきたOPNが、フットワークすなわち「下」の精鋭とコラボレイトする。これは期待せずにはいられないだろう。
そして、ようやくである。昨年から何度も報じられていたアントニー・ヘガティによる新プロジェクト、アノーニのアルバムが5月6日にリリースされる。この新作でOPNはハドソン・モホークとともにプロダクションを手掛け、全編に渡って参加している。3月9日に公開された “Drone Bomb Me” のMVはナオミ・キャンベルが主演を務めており、アントニーとハドモーとOPNというそもそもなぜ成立したのかよくわからない不思議なトライアングルの緊張感が伝わってくる映像になっている。(小林拓音)
https://itunes.apple.com/us/post/idsa.c9f49974-e62f-11e5-a769-f18b118b72da
ロケーション・サービスは、〈1080P〉からのリリースでも知られるポートランドのR&Bユニット、マジックフェードのマイク・ガルバレクと、ジョシュア・ウォードによるアンビエント・ユニットである。マイク・ガルバレクがギターやシンセ、フットレスベースなどを、ジョシュア・ウォードがハープを担当している。リリースは〈ビール・オン・ザ・ラグ〉。同レーベルの新ラインナップともいえるCDシリーズの一作である。
本作は「OPN以降」の状況を考えるための重要なキーになるように思える。なぜか。それはOPN的な人間以降の世界観を、極めて優雅な音楽性で表現しているからである。このアルバムの楽曲を簡単に表現すれば、「人間絶滅以降の世界で鳴り響くようなアンビエント・フュージョン」ということになるだろうか。透明なシンセサイザー、やわらかく澄んだギター、ハープ。そこから生成する2016年的な無菌/清潔な音楽。
完璧に管理されたオフィスで、それとも病院の無菌ロビーで、もしくはヒトが消滅した世界で稼動しつづけている「施設」で、静かに、環境に溶け込むように、ヒトの感情をいたずらに刺激しないように、もしくは、そんなものなど最初から存在しないように、つまりは美しいヴォイドなBGMのように、ただ、ただ流れているような音楽がここにある。一聴、単にBGM的な作品に聴こえるかもしれないが、そんなことはまったくない。この音楽は美しく、そして異様だ。聴き進むにつれ、誰しもが、どこか人間消滅以降のニヒリティックな感性/コンセプト/美学/思想を感じとってしまうだろう。
本作のアートワークは、そんな「アフター・ヒューマン」なイメージ/コンセプトを象徴している見事なものである(メンバー自身が手がけている)。青い手袋をした「医師」たちが奏でるムード音楽? だが顔のみえない彼らは、本当に人間なのだろうか。それともゾンビや幽霊なのだろうか。人間消滅以降の世界で、人工知能的アンビエント・フュージョンを奏でる「医師」たちとは……?
ともあれアルバム冒頭の“アバイア・トランスファー”の音使いは鮮烈であった。大病院のロビーや、会社のオフィス内で鳴っているような音たち。電話の音、キーボードをタイプする音、何かの通信音、ヒトの声やコップを置く音、ペンを走らせる音などが、美しいシンセサイザーやギターの音などにレイヤーされていく。それらの環境音は、ありがちな「ドローン+フィールド・レコーディング的」な使われ方をしていない。いわば楽曲における重要なサウンドエレメントとして導入されているのである。事実、これらのオフィス的音響は、コンポジションされ、ループし、ヒトの気配、ヒトが動き、働いていた気配を生んでいる。だが、その音響は、いわば天国的なアンビエントのむこうで鳴っているのである。まるで消滅した人間世界の記憶=結晶ように……。
2曲め“ノー・プロジェクションズ”以降は、人間社会の終局以降のような天国的ともいえるアンビエンス/アンビエントな楽曲が、軽やかに、かつ濃密に展開されていくだろう。3曲め“バリーズ”など、サイケデリックな音像に、微かに不穏な空気感も生まれており、フェネスの音楽を思わせもする。ラストの曲“エクセプション・エグザイル”では、再びオフィス音が聴こえてくるのだが、それは即座に消え去り、緊迫感のあるシーケンス・フレーズの反復が楽曲を覆うのだ。
終末以前の人間社会の記憶→人間消滅以降の無人で平穏な世界→人間世界終末のカタストロフィと時間を入れ子構造にしながら展開している構成とでもいうべきか。私は本作を聴きながら、テレンス・マリックの映画『ツリー・オブ・ライフ』を思いだしてしまったほどである。
ヒトが消滅した清潔な世界で鳴り響くアンビエンス/アンビエント。そのような音楽が、「いま=2016年」という時代においては、とても心地よく感じられる。人がいない世界=空虚への憧憬か。これこそニューエイジ・リバイバル以降、人間絶滅以降の世界を射程(=イメージ)に入れたような新しいアンビエント・シーンの動向/鼓動に思えてならない(2本のMVは彼らのアフター・ヒューマンな世界観を見事に表現している。アルバム・ティザー映像は20年前のCGのような建築プレゼンテーション・ビデオのようであり、“バリーズ”のMVは、たぶん、廃墟となった原子力発電所らしき場所を撮影した映像であった)。
本作とともに、カラ・リズ・カバーデール(Kara-Lis Coverdale)の神話的なアンビエントを聴いてみてもよいだろう。人間絶滅以降の新しい世界観のアンビエント・ミュージックの現在が、いっそう浮き彫りになるはずだ。
Four Tet - Evening Side (Oneohtrix Point Never edit)
これはすごいです。昨年リリースされたフォー・テットの2曲入り『Morning/Evening』、その“Evening Side ”をOPNがロング・エディット。あんなに踊れない音楽をやっているOPNがこんなにも桃源郷的なテクノ・トラックに参加しているのがいい。それにしてもOPNの売れっ子ぶりには目を見張るものがある。アントニー話題のプロジェクト、ANOHNIの“4 DEGREES”もプロデュースしているし、しばらく目が離せないです。
Babyfather - Meditation (Prod. by Dean Blunt & Arca) Hyperdub
 ディーン・ブラントのベイビーファザー名義のアルバムは〈ハイパーダブ〉からもうすぐリリース。こちらはARCAをフィーチャーした収録曲で、つい先日ヴァイナルもリリースされている。聴いたことのあるようなないような、斬新なダブ・サウンド。ミックステープも発表しています。彼がeBayに出品した車は希望価格に到達しなかったそうですが、アルバムへの期待も高まります。
ディーン・ブラントのベイビーファザー名義のアルバムは〈ハイパーダブ〉からもうすぐリリース。こちらはARCAをフィーチャーした収録曲で、つい先日ヴァイナルもリリースされている。聴いたことのあるようなないような、斬新なダブ・サウンド。ミックステープも発表しています。彼がeBayに出品した車は希望価格に到達しなかったそうですが、アルバムへの期待も高まります。
Roni Size - Snapshot (Swindle Remix)
ブリストル・ジャングルの王様、ロニ・サイズのクラシックをスウィンドルがリミックスするという。世代を超えたUKハイブリッド・ダンス・ミュージック、格好いいです。
Kero Kero Bonito - Lipslap
最近早くも新作を出したばかりのケンドリック・ラマーがリリック・コンテストをやっているいっぽうで、UKのケロ・ケロ・ボニトときたら……。日本語でもラップする女性ラッパー、サラちゃん擁する3人組、最新曲。電話の「もしもし」、箸で弁当を食べてと……いまトレンディなポップ・ラップ・コメディ。
いま、キミはどのレーベルが好き? 好きなレーベルを3つ挙げよ。80年代や90年代だったら、この問いに容易に答えられた。しかしいまは違う。え、いま、どんなレーベルがあったっけ? これがほとんどの人の反応だろう。
メジャーの音楽産業が売り上げで悪戦苦闘しているいっぽうインディ・シーンといえば、ひと言で言ってカオスである。そもそもインディとは、メジャーの二軍でも売れない人たちでもなく、能動的なメジャーからの自律を意味していたもので、それがゆえの表現の自由度(音楽スタイル、そのハイブリッド、実験、ときには政治性や文学性など)があった。
インディ・ロックなる言葉が有名無実化してからずいぶん久しいが、その文化がなくなったわけではないし、〝自律〟は途中、90年代からクラブ/ダンス・カルチャーにも受け継がれ拡大している。だかだそれも、インターネットの普及にともなってカオスとなった。
先日、ぼくはユーリ・シュリジンのレヴューで、現代のインディ・レーベルの役割や意味のひとつを、ウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動を例に出して説明した。これはもう、デジタルの魔界には足を踏み入れずに、断固として昔ながらの音楽の消費のされ方を墨守し、音楽が評価されることを信じている人たち。現代へのひとつの態度表明だ。ところが、こういうのはもちろん少数派で、多くはデジタルの波にどのように関わるかを考えている。デジタルの世界には、いろんな魑魅魍魎がいるが、たとえばヴェイパーウェイヴのように、過去の音源をスクリューさせる(ゆっくり再生させる)だけで充分に面白いじゃんというムーヴメントは、怪しげなノスタルジーをともなって、音楽を作るとはどういうことなのかという根源的な問いさえもシーンの喉元に突き付けている。
エイフェックス・ツインにもシカゴのジュークにもクラブやダンスがあるが、OPNやジェームス・フェラーロといった連中にはそれがない。あるのはインターネットのカオスである。エイフェックス・ツインは田園を、シカゴのジュークはゲットーの熱気を想起させるが、OPNやフェラーロの音楽に見られるローファイなグリッチとそのアンビエンスは、我々の生活のなかにPCの向こう側が確実に入り込んでいることをあらためて思い知らせてもいる。
向こう側は、たくさんのものが自由に選べるが、同時にたくさんのゴミが、これでもかと言わんばかりのゴミもある。そういうなかにも音楽やレーベルがあり、情報戦、文化闘争(というほどのものかどうかはわからないが終わらない分断化)……が繰り広げられるカオスの世界だ。ジャム・シティのファーストはそのことをじつによく表していたわけだが、ハイパーモダンなビルのレセプションで迷子にならないように、インディ・レーベルは自分のたちの足元をよく見ている。最後にもうひとつ、現代のレーベルの役目の例を挙げておくと、文化紹介ということがある。これが、じつは現代のワールド・ミュージックの拡大の土台である。目利きのレーベルがいろんな国のいろんな音楽を発掘し、紹介する。オマール・ソレイマンなどは、こうした流れから突然脚光を浴びて、欧米で評価された好例だ。
カオスとはいえ、インディ・レーベルは現代も現代なりの文化的な功績をあげている。ただし、状況は、複数の次元において変化が起きている現代では、それらが昔のようにひとつのまとまった勢力になっているとは言い難い。つまり、それを1冊の本にまとめるのは、至難の業。
わりとこの2年ぐらいにものに絞ってあるので、円安によって輸入盤の高騰に拍車がかかってからレコード店には行ってない人もぜひ手にとってください。また、デモテープの送り先で困っている人のために、わかる範囲でレーベルの住所も記載してあるので、電話帳のように使ってくれたら幸いです。
DJノブ、松陽介、マイク・スンダらDJのインタヴュー、浅沼優子のベルリン・コラムなども掲載しております。
きたる6月4日(土)~5(日)、長野県木曽郡木祖村「こだまの森」にておこなわれるTAICOCLUB'16の出演者としてArcaが発表された。これが二度目の来日になるが、もちろんビョークの作品への参加を経て、問題作『ミュータント』リリース後の初めての来日になるので、注目される方も多いだろう。また、エレクトロニック・ミュージックのアクトとしては、すでにOPNの出演もアナウンスされている。
TAICOCLUB'16
2016年6月4日(土)- 6月5日(日)
at 長野県木曽郡木祖村「こだまの森」
出演アーティスト
*- Arca -DJ set (VE)
*- あふりらんぽ (JP)
*- KiNK (BG)
*- LORD ECHO (NZ)
*- LUCKY TAPES (JP)
*- Nozinja (ZA)
*- Oneohtrix Point Never (US)
*- サカナクション (JP)
*- シンリズム (JP)
*- SPECIAL OTHERS (JP)
and more…
MORE INFO: https://taicoclub.com/16/2nd/
チケット販売に関して: https://taicoclub.shop-pro.jp/
遠くから眺めると光ばかりの美しい夜の都市は、寄ればそれがさまざまな要素の過密な集合であることを露呈する。同じように、大雑把な環境で聴けば抒情的なエレクトロニカだと思われるagraphの音楽は、微視的に検分すれば、音響的な配慮をきわめてコンセプチュアルに凝らされた、細密な情報の塊であることが見えてくる。
寄っても寄っても細部がある。それは世界の構造を模写するようでもあり、あるいは音のオープンワールドともたとえられるかもしれない。その意味で、agraphは彼自身がそう述べるように「表現者」ではない。つくる人、だ。
  agraph the shader ビート |
だから、彼が彼自身を「作曲家」と呼ぶのはとてもしっくりくるように思う。エゴを発信するのではなく、世界の構造をつくることを自らの仕事だとする認識。さらには、これはagraphの憧れと矜持とをともに表す肩書きでもあるだろう。作曲家とは、スティーヴ・ライヒなりリュック・フェラーリなり、彼が思いを寄せる先人たちに付せられた呼び方でもあるから。
しかし、そうした偉大な名前や以下語られる愛すべき小難しさにもかかわらず、agraphの音楽は本当に開かれていてポピュラリティがある。この『the shader』は、たとえばフィリップ・グラスの『フォトグラファー』が多くのひとに聴かれたというように、ジャンル意識や予備知識にわずらわされない地点で、ミニマル・ミュージックを更新する。
ポップなものが偉いと言うわけではない。しかし、たとえば“inversion/91”が、そうした彼の中の両極端な嗜好や音楽性をとても高い水準で結びあわせていることに感動せざるをえない。わかりやすいのではなく、普遍性がある。自由でありながら、聴かれるということを考えぬいている。自分の神に正直でありながら、ひとが見えている。「ミュ~コミ+プラス」とインディ・ミュージック誌とにまたがって新譜を語る。そんな若いひと、じっさい他にいるだろうか。
オーディオセットの前で腕組みをして聴けばそれに応えてくれ、雑踏や車中に聴けば、何気なく置かれたバケツさえ、本作の持つ「構造」の上に配置されたものであるかのように感じられる。これを書き終えたら田舎の母親に商品リンクをメールしてあげようと思っている。彼女はきっと「なんやわからんけど、いいわ~」と言ってくれるにちがいない。「なんやわからんけど」が時代を進め、「いいわ~」が時代をなぐさめるだろう。それはオーヴァーグラウンドでもアンダーグラウンドでも変わらない。筆者にとっても本作は2016年のベストだ。
agraph / アグラフ
牛尾憲輔によるソロ・ユニット。2003年、石野卓球との出会いから、電気グルーヴ、石野卓球、DISCO TWINS(DJ TASAKA+KAGAMI)などの制作、ライブでのサポートでキャリアを積む。ソロアーティストとして、2007年に石野卓球のレーベル〈PLATIK〉よりリリースしたコンビレーション・アルバム『GATHERING TRAXX VOL.1』にkensuke ushio名義で参加。
2008年にソロユニット「agraph」としてデビュー・アルバム『a day, phases』をリリース。WIREのサードエリアステージに07年から10年まで4年連続でライヴ出演を果たした他、2010年10月にはアンダーワールドのフロントアクトを務めた。2010年にはセカンド・アルバム『equal』をリリース。2016年2月、サード・アルバム『the shader』が発表される。
■agraphさんのインタヴューってけっこうたくさんネットで読めるんです。なので、基本的なバイオの部分をざっとまとめさせてくださいね。
まず、石野卓球さんにご自身のデモ──イタロ・ディスコを聴いてもらうところからはじまるんですよね。そこでかなり辛い反応をもらって、もっと自分に素直に音をつくらなければと反省・奮起なさる。そしていまの音楽性というか、agraphの始点ともなる“Colours”(コンピ盤『GATHERING TRAXX VOL.1』にkensuke ushio名義で収録)が生まれる。
agraph:はい。
■そして、その「素直」につくった音楽がやがてファースト『a day, phases』(2008年)になり、そこからダンス要素なんかも引いていって、さらに正直に自分の音を追求していく先に、セカンド『equal』(2010年)が形を結んでいく、と。
agraph:はい。
■その追求の過程にはレイ・ハラカミさんであったり、カールステン・ニコライだったり、あるいはエイフェックス・ツインであったり、そういったアーティストへの素朴な憧憬も溶け込んでいるでしょうし、ジョン・ケージからスティーヴ・ライヒ、あるいはマルセル・デュシャンといった人たちの思考なり実験なりの跡が、まさに「graph」として示されている……。
agraph:いやあ、「はい」しか言えないですね。
■すみません、強引に物語みたいにしちゃって。そこまではいろんな記事に共通する部分なんですよね。なので、「はい」と言っていただければひとまず次に進めます(笑)。
agraph:はい。すべて私がやりました(笑)。
僕がこれまで影響を受けてきた要素を俯瞰的に配置することが、今回の作品をつくっていておもしろかったことです。
■ありがとうございます(笑)。では今作はというところですが、すごく部分的な印象かもしれないですけど、冒頭の“reference frame”の声のパートだったり、ラストの“inversion/91”のマレットを使う感じとかライヒっぽいんですけど──
agraph:ああ、マレットを使おうとすると、どうしてもああいうフレーズが出てきてしまうというか。ライヒの印象が骨身に沁みているんですよね。他の曲でも使っている「フェイジング」っていう技法なんかもそうで。
■なるほど、でも今回念頭にあったのはリュック・フェラーリなんだそうですね。
agraph:リュック・フェラーリのほうが大きいですね。ケージであったりライヒであったり、僕がこれまで影響を受けてきた要素を俯瞰的に配置することが、今回の作品をつくっていておもしろかったことです。その配置の仕方とか俯瞰的に見るという行為自体がフェラーリの影響ということになるかもしれない。
■“プレスク・リヤン”だと。
agraph:そうですね。ひとつひとつのメロディとか、あるいは細かいアレンジを追っていくと、それぞれライヒだったりいろいろな影響があると思うんですけど、それはもう一要素に過ぎないというか。
■たしかに、そういう部分もあるというだけですよね。なるほど、ご自身の影響源を意識的に編集してるわけですね。
agraph:そうですね。それからサーストン・ムーアがやった“4分33秒”。あれは音が鳴っている“4分33秒”なんですね。演奏を4分33秒分切り取っているというだけ。つまり、4分33秒っていう枠の中で何かが起きていればいいっていうところまで音楽を俯瞰的に見ているんですよ。そういうことにすごく共感したということもあります。ミュージック・コンクレートみたいなものって、とても現代音楽的なアプローチなんだけど、その構造自体がおもしろいというか。3曲め(“greyscale”)なんて、ラジオ・エディットをつくったりするようなキャッチーなフレーズの出てくる曲ではあるんだけど、それもじつは、そんなフレーズなりメロディがあって、後ろには不穏なテクスチャーが鳴っていて……というパースペクティヴがおもしろいのであって。
そうやって構造をつくると、世界観が立ち上がると思うんですね。……世界観というか、雰囲気というくらいの曖昧なものですけれども、そのかたちをつくりたかったんです。
■なんというか、前作の『equal』について、「イコール」っていうのはバランスなんだというようなことをおっしゃっていましたよね。世界を構成している情報量はものすごいわけだから、人間にはその全部は処理しきれないと。全部受け取ったらパンクしちゃう。でも、どうやったらパンクしないで適度に世界を感知できるのかっていう、その適度さを探るための調節弁がイコールなんだ──強引にまとめると、そういうようなことを説明されていたと思います。
agraph:そうですね。
■で、そうやって世界の情報量を適度に調節することが『equal』の取り組みだったとすれば、いまのお話をうかがう限り、今作はその構造自体を……
agraph:うん、構造自体を把握すること。『equal』について思っていたことはその通りなんだけど、いま言われたような言葉で考えたことがなかったので、なるほどなあって感じですね。今回のアルバムはすごく長い時間をかけた結果、ものすごく細かいことをやれていて、『equal』に比べてずっと情報量も多いと思うんです。メロディを追いきれないし、リズムのパターンに乗りきれないし、コードのプログレッションを把握しきれないと思う。で、そこまで突き放すと、音楽を俯瞰的に見れるんですよね。主観的に歌おうとか踊ろうとか思わないから。そして、そんなふうに前のめりに聴けなくなったときに、構造が見えてくる。そこに世界観が立ち昇る。……と、思うんですよね。今回の制作にあたっては、本当によくリュック・フェラーリを聴いていた時期があったんです。そのときは、意識があるんだかないんだか、寝てるんだか起きてるんだかが曖昧で、ぼやっと視界を把握していたような、すごく説明しづらいリリカルな状況が生まれてきたりしましたね。

inversion/91”……あの曲ができたときに、このアルバムのことがわかった。
agraph:それからもう一点。“inversion/91”っていう曲は、アントニー・ゴームリーっていう彫刻家のつくった「インマーション(IMMERSION)」っていう作品をオマージュしてるんです。日本語では「浸礼」ってタイトルで呼ばれてたりします。コンクリートの塊なんですけど、中に人型の空洞があるんですよ。それで、「浸礼」っていうのはキリスト教の儀式のひとつなので宗教的な意味がある作品なんだとは思うんですが、僕がその作品を見たときに感じたのはもっとちがうことなんですね。その……彫刻って、彫り上げたり作り上げたりするものじゃないですか。たとえば人型であるならば木から削り出したり粘土で練り上げたりする。でもこの作品は、空間をコンクリートで埋めることで空間を削りとる作品なんだなと思ったんですよ。ということは、これは彫り上げ作り上げるという意味での彫刻の概念に、マイナス1を掛けたものだなって。反転してるんですよね。
■あ、「反転(inversion)」ってそういうことですか! うまい。
agraph:そうです。でも同時に、これは彫刻の概念そのものだとも思った。彫刻って何? と問われたときの答え。辞書にこのまま載っていいものだって感じたんです。背理法で考えると、これの反対が彫刻になるっていうことだから。
■なるほど、それで「マイナス1を掛ける」っておっしゃったわけですか。
agarph:そう、絶対値は一緒なんだけど反対側に行っている。だから、逆に、向こうに彫り上げているものが鮮明に見える──というのはただの僕の解釈なので、そんなこと作者はもとより、誰も思ってはいないかもしれないですけども。
で、今回は、音楽に含まれる構造を意識させるっていうことに、最後の曲で行きつけたので、そういうアルバムなのかなと思いました。
■おお、ラストの曲で「反転」ってタイトルを見ちゃうと、つい短絡的に「これまでやってきたことをひっくり返す」みたいな意味かなって想像するんですけど、ひっくり返すんじゃなくて反対側に出っ張るみたいなニュアンスなんですね。
agraph:そう、反対側に出ることで、いままでやってきたことがよく見えるってことです。なんか、狙ったというよりは行きついたという感じで。アルバムのタイトル『the shader』のベースには文学的なコンセプトがあるんですけど、それは同心円状に影響が広がっていくというようなものなんですね。で、その円のエッジの部分に“inversion/91”があったんです。そこまで行きついた……だからあの曲ができたときに、このアルバムのことがわかった。
僕は「表現する」っていう言葉がすごく嫌いで。インタヴューとかで思わず「表現する」って言っちゃって、「つくる」って言い直すんですけど(笑)。
■「同心円状に広がる」というのは、さっきおっしゃっていた、(世界の)構造部分を築くことによって上に表れてくる影響、みたいなことですか。
agraph:そうです。構造っていうのは、いちばんマスな話なのでもちろん大事なんですが、『the shader』っていうタイトルについて、いちばん最初にその言葉の器に入れる水としてあったものは、もうちょっと感覚的なんです。散歩しているときのことだったんですが、ちょうど陽が昇ってきて、そのとき、木についてる葉っぱの、葉脈が透けて見えたんですよ。で、葉が光を隠すことによって、光がそこにあることを理解できるなって思った。「影なすもの」によって光は感知される。それで「影なすもの=the shader」というタイトルにしたんです。同心円状に広がっていく上に、影を成すなにかがあって、それによって構造がわかるという、そういうコンセプトで。まあ、それは文学的な意味においてのことなので、わざわざ言うものでもないんですけど。
■なんか、コウモリって目が見えなくて、超音波をぶつけて、その反響というか跳ね返りでモノがそこにあることを感知するっていいますけれども、agraphさんが物事を理解するやり方自体が、ちょっとそういう独特の傾向をもっておられるみたいに感じますね。今作のコンセプト云々にかかわらず。
agraph:単純に、僕には物理趣味があって。詳しくはないんですけど、そういう本を読むのが好きなんです。統一場理論とか相対性理論とか。そうした世界のありかたみたいなものを読んでいると、ちょっと神秘主義すぎるかもしれないけれど、翻って音楽の場合はどうなのかなって、観測者の立場みたいなものに立って考えてしまう。そうすると、いまソナーに喩えてくださいましたけど、自分は少し引いて、俯瞰したところから物事をつくっていきたいんだろうなって思います。
■agraphさんの音楽は、表面的な音の上ではベッドルーム・ポップに近接するものとして考えることができると思うんですけど、でもベッドルームって、ある意味では自意識の延長みたいな場所じゃないですか。あるいはロックのような音楽も自分の内側からじかにつかみにいくものだったりしますよね。agraphさんはそういうエゴというか、直接的に世界をつかみにいくみたいなことはぜんぜんないわけですか。
agraph:僕は「表現する」っていう言葉がすごく嫌いで。それ、あんまりよくわかんないんですよ。なぜ嫌いかっていうこともよくわかんないんですけど。だから、よくインタヴューとかでも思わず「表現する」って言っちゃって、「つくる」って言い直すんですけど(笑)。
■ああ、なるほど!
agraph:自意識みたいなものを自分で言ったり、「俺はこうなんだ」っていう意識をすることがすごくイヤで。それは思い返せば自分のアート趣味に根ざしていると思うんですけどね。個人的にはまずデュシャンがあって、ジョセフ・コスースがあって、90年代のターナー賞作家たちがある。つまり僕はネオ・コンセプチュアリズムのアーティストが好きなんです。たとえば日本なら2011年以降に顕著だと思うんだけど、リレーション・アートみたいなものが主流にあるじゃないですか。アートにはサジェストがあるべきものだし、90年代以降は、そのサジェストの方向が人間だったり社会だったりに行くものが多く目について。僕、そういうものにまったく興味がないんですよ。コスースとかって、ひとつひとつの物体に対して、その先にあるアイコンを目指していくっていうか、イデアを目指していくじゃないですか。そういうふうに概念自体を語り上げることに興味がある。人間には惹かれないんです。
■ははは! たしかに「表現する」っていうと木から像を彫り上げていくみたいな方向のニュアンスですよね。

サンプリングとコンクレートって、誤用があるんですけど、まったくちがうものなんですよね。絵画と写真くらいちがう。
■ところで、agraphさんはあまりサンプリング・ミュージックというか、ヒップホップ的な方法にはならないですよね? “プレスク・リヤン”というお話も出ましたが、テープ・ミュージックのようなものがイメージされていて。
agraph:意識しているわけじゃないんですが、そんなにサンプリングはやらないんですよ。サンプリングっていう手法を取りはじめたこと自体が最近で。
■前作の中の“a ray”とかはビル・エヴァンスをサンプリングされてますけども、なんというか、ヒップホップのサンプリングとはちょっと発想がちがうような感じがするというか。
agraph:サンプリングとコンクレートって、誤用があるんですけど、まったくちがうものなんですよね。絵画と写真くらいちがう。それで僕の場合、コンクレートでありたいという気持ちが少しあるんです。いわゆるカットアップの手法とかは自分の中にあまりない。……職業柄、たとえば電気グルーヴの仕事をするときに、サンプリングをしたりということはあるので、技術としては知っているんですけど、僕のルーツになくて。
■あはは。
agraph:日本でコンクレートをちゃんとやったり、論じていらっしゃる方として、大友良英さんとか鈴木治行さんがいらっしゃいますよね。僕の通っていた大学には鈴木さんがいらっしゃったんですよ。僕は指導を担当いただいたわけではないんですけど、尊敬も影響もあって、コンクレートについては調べたりもしたんですね。そんなこともあって、音を録る、録音して使うっていうっていうほうに意識が向かなかったんです。
■そうなんですね。加えて、ビートへの意識なんかもそれほど強くはないというか。どちらかというと音響に関心が向かれるという感じなんでしょうか。
agraph:そうですね。ビートっぽいもの、「ステップ」のつくもの、あるいはグライムだったりとか……そういうものはまったく通ってないんですよね。マネージャーさんによく「お前は黒さが足りない」って言われるんですけど(笑)。
■黒さ信仰はありますよね。コンプレックスというか。でもagraphさんは自由でいらっしゃる(笑)。
agraph:いやいや、僕はコンプレックスだらけですよ。だからこうやって難しげなことを言って虚勢を張ってるんですよ(笑)!
いつかもっと何も気にしなくなったときに、きっと「ピー」とか「ガー」とかやっちゃうんだとも思うんです。それをやるために必要な経験はものすごく大きいはず。
■でも、「難しげ」とはいいつつ、agraphさんが目指されているのは一種の快楽性でもあると。他のインタヴューでも読んだんですけどね。それはやっぱり、ミュージシャンとしての目標というか。
agraph:そうですね、ミュージシャンというか、ポピュラー作曲家としての矜持なのかなあと。
■「ポピュラー作曲家」という意識がおありになる?
agraph:あるんですよね。象牙の塔にいるわけじゃないですし。音大閥どころか、ちゃんとした音楽教育を受けているわけでもなくて、憧れているだけなんですよ。いま普通のひとが小難しい現代音楽といって思い浮かべるのは、滅茶苦茶やってるようにみえる曲だと思いますけど、そういうものも書けないし、数学を使ったようなもの、みたいなものも書けないし。自分のできることの範囲でそういうものへの憧れを取り入れて、つくりあげていくというだけなんです。
■よりポピュラリティのあるものを積極的に目指されたいということではなく? 「ポピュラー作曲家」みたいなかたちを意識されるのはなぜなんですかね?
agraph:なぜなんでしょうね。僕はこの5年間、agraphとして音楽をつくっていたので、agraph以外ほとんど何もやっていなかったんですよ。つまりポピュラリティのあることをやらせていただいてたというか。電気グルーヴでもやらせていただいたり、アニメの劇伴だったり、LAMA(中村弘二、フルカワミキ、田渕ひさ子とのバンド)だったりとか。だから、その揺り戻しでもっとマニアックなことをやっていてもおかしくないはずなんですけどね。
■なんでしょう、原体験みたいなものと関係があるとか?
agraph:ああ、TMNETWORKとか。それもそうかもしれないですけどね。
■だって、憧れているものと、目指されているものが、すごいちがってるじゃないですか(笑)。ある面では。
agraph:いやあ、でも、僕が「ピー」とか「ガー」とかってノイズだけ出していたら、こんなふうに取材に来てくれないじゃないですか(笑)。それに、「ピー」「ガー」っていうのは、自分だけでできることなんですよ。だけど、それを一人でやるには自分にはまだ深みがないというか。いまは、より難しい音楽を追求するのと、もっとポピュラリティを持ったものの間にいて、遊んでいたいという感じなんです。僕が今回のアルバムでやったようなことって、一生はやれないと思うんですよ。
でも、いつかもっと何も気にしなくなったときに、きっと「ピー」とか「ガー」とかやっちゃうんだとも思うんです。それをやるために必要な経験はものすごく大きいはず。表面的には、やろうと思えばすぐにやれちゃうことなんですね、それって。でもちがいを出すのはとても難しいんです。そのためにいまは人のできないことをやったりしたい。
■いまは、ポップ・ミュージックという形態を通して他者に出会う、みたいなことでしょうか。しかして、ひとりでやれる「ピー」「ガー」に向かう……。
agraph:そうかもしれないですね。そういう音は、いまは昔よりずっとつくりやすくなっているはずなんですけどね。でも最初からそうしていたら……もしagraphをやっていなかったら、僕は電気グルーヴの裏方ではあったかもしれないけど、ステージでやることはなかったかもしれない。バンドも組まなかったかもしれないし、mitoさんとやることもなかったかもしれないし、劇伴やプロデュース、楽曲提供だってそうです。そういうところの経験は、誰もかれもが持っているものでもないから、おもしろいものにつながるんじゃないかなという期待もあるんです。先の見通しはぜんぜんないので、どうなるかはわからないですけどね(笑)。
agraph - greyscale (video edit)
[[SplitPage]]
普通のポップ・アルバムとして聴ける要素を残したいし、(抒情的なピアノが用いられていることは)ポピュラリティのある作曲家としての矜持なのかもしれないです。
■さて、ではアルバムの話に戻りまして。冒頭の曲のタイトルなんですが、“reference frame”っていうのは何の「基準」なんですか?
agraph:「こういうアルバムですよ」っていう。
■ははは! すごい。
agraph:これからいろんなことを言いますけど、こういうグラフになってますよ、という。x軸とy軸がこう引かれてますよ、基準点はこれですよと。
■なるほど。では、その基準点にピアノが鳴っていることの意味を考えたりとかしていくのは、ちょっとちがいますか?
agraph:なるほど、そこは、配置のひとつというか。今回はひとつひとつの楽器自体にそれほど意味はないんですよね。
■冒頭でピアノが出てきて旋律が奏でられると、つい叙情的なアルバムの幕開けと考えてしまうというか。
agraph:いえいえ、それもそうだと思うし、さっきの快楽性の話もそうですけど、普通のポップ・アルバムとして聴ける要素を残したいし、ポピュラリティのある作曲家としての矜持なのかもしれないです。もちろんどう取っていただいてもかまわないんですけどね。僕自身としては、よくピアノのことを指摘されはするんですが、そんなに意識していないんです。というか、あんまりピアノを弾いていたときの意識自体が残ってないかも。今回、構造のことを考えた記憶はあるんだけど、ひとつひとつの音のことを覚えていないんですよね。
僕はこの5年間のうちに、一度アルバムを放棄しているんですけど──『equal』のつづきになるからやめよう、って思って捨てちゃったものがあるんです。で、今回はそれをコンクレートでいうテープみたいなものとして使ってつくっているんですけど、そうすると5年前の自分のことなんて覚えていないから、本当に再配置という感じだったんですよね。演奏しているときの細かい意識のことは覚えていない。
■ピアノ弾きみたいな意識はないんですね。なるほど。
agraph:いろんなひとに出会う中で、僕よりピアノに思い入れのある人はいっぱいいるなあって思って。じゃあ僕はいっか! と。音に対するフェティシズムはあるので、使っている音はいっぱいあるんですけどね。
同心円状に広がる時間はきっとあると思うんですよね。そうだ、「時間」は今回の裏テーマだったと思います。
■“asymptote”という曲ですけれども、「漸近線」というとこれは「基準」たる“reference frame”に対して漸近していくという?
agraph:“reference frame”でxとyを引いて、ああ漸近していくんだなあという。
■交わらないという。その交わらなさって何のことなんですかね?
agraph:あれは、終わらない曲なんですよ。もちろん時間で切ってますけれどね。そういうふうに極限にいたる、というか。同心円状に広がっていくっていうイメージのお話もしましたけれど、この曲は、その先がどこまでもどこまでも、極限まで行くんだろうなって思ったんですよね。有限ではあるんだけど果てがない……そんな意識をつくっていこうとした曲ですね。
■終わらない時間というのは、なにか、リニアなものとしてのびていくイメージでいいんですか?
agraph:同心円状に広がる時間はきっとあると思うんですよね。そうだ、「時間」は今回の裏テーマだったと思います。音楽って時間芸術であって、時間以外に音楽を特徴づけるものはないというか、時間しか持っていないということが音楽の唯一の特徴だと──僕はそう考えるので。“inversion/91”では時間の使い方に発展や発見があったけど、“asymptote”も「終わらない、極限にいたる」というところで、時間に対する意識が強かったですね。逆に1分くらいの曲もつくってみたいと思ったけど(笑)。
■そういえば終わらないわりに短く切られている。
agraph:「終わらない」と「始まらない」は同じかなと。
抒情的でロマンティックな部分というのはやっぱり要素なんですよね。自分がピアノを弾いているときの気持ちは封入されているんだけど、それはすべてもう息をしていない。
■「すべての要素をドライに配置しただけ」というふうにおっしゃいますが、その語りの中にもしかしたらトリックがあるのかもしれないですけど、でも一方で、もっと普通にドラマチックな、エモーションの幅を感じるようなところもあるんですが。
agraph:それはね、いま思い返すとなんですけど、アンドレアス・グルスキーの、ジャクソン・ポロックの絵を撮った作品があるんですけど、僕はその写真がすごく好きで。ポロックのああいうアクション・ペインティングみたいなものって、すごく熱量をもって描かれるものじゃないですか。関連して、「絵の中にいるときに絵なんか意識しない(=自分が何をしているかなんて意識しない)」っていうような言葉もあったと思うんですけど、そんなふうにつくられるものの、その写真を撮るっていうのはすごい残酷なことだなと思ったんですよね。ポロックの無意識とか、絵の中にいるというすごくエモーショナルな状態をパッケージしてしまう。封をしてしまう。真空にしてしまう。その行為ってすごく力のあることだなと思って。それで、僕の音楽をエモーショナルに聴けるというのは、さっきの話のように、ひとつひとつの要素としてピアノを弾いているし、盛り上げるためにエフェクトを使っているし、叙情的な部分も含んでいるからなんだけど、それを一歩引いてパッケージするということでもあったかもしれない。だから、抒情的でロマンティックな部分というのはやっぱり要素なんですよね。自分がピアノを弾いているときの気持ちは封入されているんだけど、それはすべてもう息をしていない。
■撮られて配置されている。なるほど……こんなふうに作者に解題を求めるのって、はしたないことなのかもしれないですけど、やっぱり聞いておもしろいこともあると思うんですよね。
agraph:いや、僕もなるべく言いたくないんですけどね。文章家じゃないし、伝わり方だっていっぱいあるし。でも音楽雑誌とか批評で自分の評価が辛いと、わー、伝わってなーいって思いますね(笑)。
■あはは!
agraph:傷ついて帰って、枕を濡らすんですよ。
■そんな抒情的なシーンがあったとは(笑)。
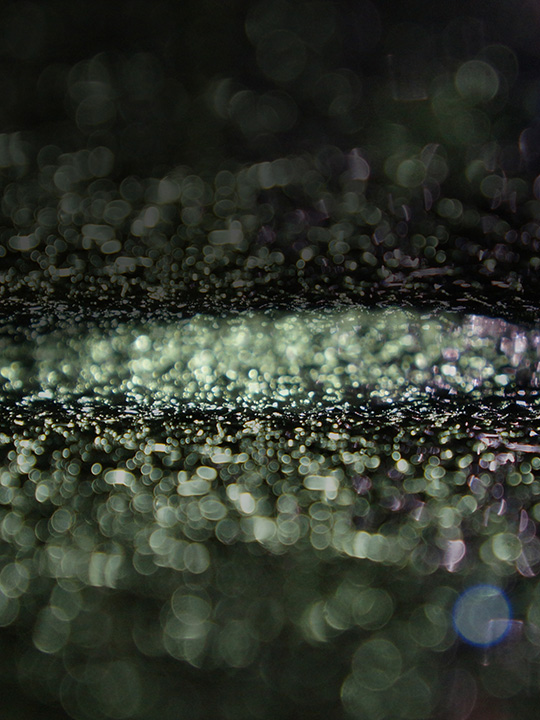
すごく悔しいんですけど、OPNには耳を更新されたという気持ちがあって。
■一方で、部分や要素で聴くと“reference frame”のマレットというか、マリンバみたいな音が出てくる部分は、一瞬OPNみたいになったりもするじゃないですか。
agraph:ギャグですけども(笑)。
■「ニヤッ」て言うとちょっとやな感じですけど、すごい同時代のものが聴こえてうれしいというか。
agraph:すごく悔しいんですけど、OPNには耳を更新されたという気持ちがあって。今回リュック・フェラーリを聴いていた時期とOPNやヴェイパーウェイヴを聴いていた時期があるんですけど、後者については誰もべつにメロディもコードもリズムも聴いていないと思うんですよね。僕自身はそうで。そこに立ちのぼっている湯気のような世界観だけを聴いている。リュック・フェラーリもそうなんです。それから、とくに理由もないままリュック・フェラーリとベーシック・チャンネルを聴いたりもしていたんだけど、ベーシック・チャンネルもそうだしアンディ・ストットもそうだと思って。テクノとかハウスとかも、それからカールステン・ニコライにしても、僕はテクスチャーと世界観を眺めているというか、それが好きだと思って聴いていたんですよね。僕の聴取体験の中では、歌える部分や踊れる部分に惹かれて聴いていたこともあったけど、いまはそういうことがないなと思いました。そういう気づきのきっかけにはなりましたね。
■OPNを似たようなアーティストと分けているのはコンセプチュアルなところかなと思いますね。アルカとかはその点、一時の若さで成立しているものでしかなくて、それが美しくもあるけど圧倒的に弱いというか。
agraph:彼もまた構造的なんだと思うんですよね。一つ一つの要素には、どうしても読み取らなきゃいけないような意味はない。そこには勝手に共感を覚えるんです。アラン・ソーカル事件はご存知ですか? アラン・ソーカルというひとが、ある哲学論文を評論誌に送るんですけど、それは文学とか哲学にすごく難解な数学とか物理とかを結びつけて書かれた、まったくでたらめな意味のないものだったんです。当時はそういうものを結びつけるのが流行っていたので、彼はわざとそういうことをして、そのでたらめさが見破られるかどうか試したわけなんですよ。でも、評論誌には「そういうものを結びつけるのはよくない」という意見に反論する論文としてそれが掲載されてしまったので、ほらやっぱり意味がないじゃないかということになった。……という時代に、まさにフランスの現代思想を数学と結びつけていた急先鋒である女性哲学者がいるんですが、OPNが彼女のことをフェイヴァリットに挙げているのをたまたま見て。僕は彼とも話したんだけど、彼はこの事件のことを知らないと言いはっていた。でも、たぶん嘘じゃないかって(笑)。
■ははは! ええ、だって……
agraph:そう、だって、あんたがやっていることがアラン・ソーカルじゃないか、と。
■いや、お話の途中でオチが見えましたよ。たしかに。
agraph:僕はそこに勝手に共感するんですよね。いや、本当に知らないんだと思うんですが(笑)
■agraphさんご自身がたとえ時代やシーンを意識していなかったとしても、OPNがいたりagraphさんがいたり、それぞれの点が結びたくなってしまうように存在しているんですよ。その意味で時代性のあるアーティストさんなんだと思うんですが。
agraph:いやー、早く見つけてほしいですよ。
ヴェイパーウェイヴは、90年代の文化、っていう具体的な形をテープにしてるんだと思うな。あれは写真に近いんじゃないかな。すごく偽悪的な。
■しかし意外だったのがヴェイパーウェイヴをちゃんと聴いていらっしゃるというところで。いったい、牛尾さんにヴェイパーウェイヴなんて必要なんですか?
agraph:ヴェイパーウェイヴは単純に質感がよかったです。流行った頃は好きでした。もうけっこう経ちますよね。
■でも、あれこそはサンプリング・ミュージックの──
agraph:いや、僕はあれコンクレートだと思う。
■なるほど。とすると、インターネットという環境からの?
agraph:うーん、90年代の文化、っていう具体的な形をテープにしてるんだと思うな。あれは写真に近いんじゃないかな。すごく偽悪的な。
■へえ! 表面的な行為としては、「ネット空間からゴミをたくさん拾ってきてどんどん奇怪なものをつくりました」ってだけのイタズラか遊びみたいなもので、でもそのこと自体が時代の中で批評的な意味を帯びて見えたわけですよね。ただ、ご指摘のように、引っぱってこられるネタがなぜかしら特定の年代や国に固執しているのはたしかで。それで盛り上がったんだという部分も否定できない。
agraph:そうそう。おもしろいんですよ。それに、もっと僕の個人的な趣味嗜好の部分で言うなら、シンセサイザーの音色について発見があったということですね。90年代の前半の音がわりと使われているじゃないですか? 僕は83年生まれなので、ちょうどそのころは意識が芽生えはじめた時期なんです。だから、そういう音がいちばんカッコ悪く感じられる。絶対にさわっちゃいけない音色だったし、シンセサイザーだったんだけど、それを忘れていたところに放たれたカウンター・パンチだったんですよね、ヴェイパーウェイヴは。あの時期「~ウェイヴ」はいっぱいあったけど、僕はそのなかでいちばんおもしろかったかな。在り方が。
■結局ジェイムス・フェラーロとかは現代美術館にまで入りこみましたからね(東京アートミーティングⅥ “TOKYO”──見えない都市を見せる https://www.mot-art-museum.jp/exhibition/TAM6-tokyo.html)。
agraph:そうですよね。それもわかるんですよ。ただ──さっき触れたように、彼らの求めるテープの先が90年代なのだとすれば、きっと、社会だったり文化だったり人類だったり、「ひとの営み」に視座があるじゃないですか。僕の趣味からすれば、そこには興味がないんですよね。
■なるほど、構造と、あとは音だったと。
agraph:リュック・フェラーリは2007年に亡くなっているんですけど、作品はいまも出ているんですよ。それは彼が遺した作品の中に、このテープを使って何かやれっていうようなものがあるようで。たとえばそれで、奥さんであるブリュンヒルド=マイヤー・フェラーリさんが作品をつくられたりしている。その構造と同じかなと思うんです。僕は奥さんも音楽家としてとても好きなんですけどね。
僕は詩に対する理解がまったくないんです。
■ところで、「言葉」っていうレベルにはとくに探求しようという欲求はないんですか? 言葉というか……ライヒとかには、たとえば“テヒリーム”みたいなものがあるわけじゃないですか。ルーツにつながるヘブライ語の中に降りていくというか。今回の作品の中にも声とか言葉を持った部分がありますけど、今後そういうテーマなんかは?
agraph:あれはすごく迷いました。人間を描くのがいやなので、発声をどうしようかなと思って……音楽を規定するときに詩が入ってくるのがすごくいやなんですね。僕は詩に対する理解がまったくないんです。大学ではケージの『サイレンス』の詩を扱ってもいるんですけど、でもやっぱり自分でつくるというのは難しかったですね。セカンドで円城塔さんに文章をお願いしたのは、あの方だったら意味にとらわれない複素数平面を音楽と言葉でつくれるんじゃないかと思ったからで……。なかなか難しいですね。
■そうか、前作には円城さんが添えておられますよね。でも、「詩」というと複雑になりますけど、「言葉」というともうちょっと算数や科学で扱えそうな対象になりませんか。
agraph:それはまだ僕の能力不足ですね。群論的な──言葉が指し示すことができる領域とそうでない領域があるという、そういう複雑系の話から使えるものは出てくるかもしれないですけど、理解も足りないし。
■いやいや、五・七・五・七・七って、もう千何百年も残ってきた韻律ですけど、あれとかをagraphさんが微分積分してくださいよ。
agraph:あれはおもしろいですよね。「タタタタタ・タタタタタタタ・タタタタタ」……。僕は子どものころからああいう韻律をぜんぶ変数にして、たとえば「タタタタタータ」っていうリズムがあったとして、そこに何を入れるのがおもしろいかっていうのを考えていたんですよね。「ハシモトユーホ」とか、入りますね(笑)。韻律っていうものにはすごく興味があるんだけど、でも自分の中ではなかなか解決のつかない要素が多いから、いつかは。
■agraphさんがやってくれないと。楽しみにしていますね!

5年間で、過去3日だけ霧がかかった日に巡り会えて、いまのところその3日は逃さず写真を撮りに行っているんですよ。
■最後に、今作のジャケットについてうかがってもいいでしょうか。アートワークとして用いられているのは、ずばり渋谷です?
agraph:あれは●●●●です。内緒です。
■内緒ですか(笑)。
agraph:特定できるものを何も残したくないんですよね。インタヴューでこんなに話しておいて言うことでもないですが(笑)。「何だろう?」って思ってほしくって。アルバムをつくるときに杖の代わりになるような写真を撮ることがあって、その中の一枚です。
■「何だろう?」って思いましたよ。ご自身で撮られた写真なんですね。
agraph:そうです。
■最近は、アー写ひとつとっても、ミュージシャンがどこの街で写ってたら画になるんだろうというのがわからなくて。渋谷下北ではないし、どこで写ってたとしても「たまたま」というだけで。そもそも地理が何も語らないというか。
agraph:ないですよね。
■あのジャケは、だからといって「どこでもなさ」を表している感じでもなくて。
agraph:この5年間で、過去3日だけ霧がかかった日に巡り会えて、いまのところその3日は逃さず写真を撮りに行っているんですよ。それでたまたま撮れたものなんですが。
■構造の上に霧のように立ち上がる世界っていうイメージにもつながりますね。
agraph:もやっとしたもの。それに、器に注ぐ水が「shader」(=影なすもの)であるという、作品のコンセプトも出せればなと思いました。
■では記事の中でもぜひ数枚ご紹介させてくださいね。本日はありがとうございました。
agraph - the shader(ティザー)
デトロイト・テクノは、複数の位相において起点となり、価値観を更新したという意味において、ターニング・ポイントであり、ビッグバン(はじまり)だった。都市のレポートとしての音楽、都市という牢獄から脱出する術としてのベッドルーム・テクノ、ヨーロッパとアフリカの衝突、ポスト・ブラック・ナショナリズム……、ある意味ではより民主主義的なインディ・シーン、いち個人いちレーベルの現代の先駆けでもあった。
クラフトワークは理解できても「エイフェックス・ツインの音楽はどうしてもわからん」という御人はいまも少なくなく、しかし、その“てんで話にならない”音楽は、この30年間で膨張し、がっつりとひとつの価値体系をモノにしている。その契機となったのが、デトロイト・テクノだ(現代ではさらに新たな価値体系が生まれつつあることは、OPNを聴いている人はうすうす感じているだろうけど、しかしそれはダンス・ミュージックではない)。
とにかく、「これ普通やらないだろ」というときの「普通」に囚われない自由さを、技術よりも先立つものの重要さを「黒い」と表現できるなら、それはエレクトロニック・ミュージックにおけるビバップだったとも言えよう。
あるいはまた、ホアン・アトキンスがエレクトロ、デリック・メイがハウス、URがファンク……と喩えるなら、カイル・ホールのセカンド・アルバムはジャズだ。ジャズのセンスが色を添えている。デトロイトの音楽一家出身で、叔父が高名なジャズ・ピアニストのローランド・ハナ、叔母もミュージシャン(ヴァイオリン奏者)で、母も歌手。彼が10代でありながら大人びたハウスでデビューしたことは、そうした家庭環境も大きく関係しているのだろう。ホールの初期の作品に、「新しく古い世界」という曲があるように、新しさと古さを持ち合わせながら語りかける。古さを温ねることが前進に繫がるという好例である。
それで待望の新作だが、1曲目の“Damn! I'm Feeln Real Close”、ぼくはこれを聴いて、3枚組で5千円以上もする高価な3枚組を買うことに決めた。リズムからはダブステップ以降を感じる。が、全体はメロウなムードに包まれている。ピアノはエリック・サティめいた静謐さを思わせ、ときおり美しいフルートの音色、そしてアシッド・サウンドがカットインされる。前作『ザ・ボート・パーティ』が破壊的とも言えるほどリズミックな躍動を前景化している作品だとしたら、『フロム・ジョイ』は夜のムードをキープしつつ、随所に実験を試みながら、しかし滑らかでメロウに展開するアルバムだ。
“Dervenen”を聴いていると、ステファン・ロバーツの〈Eevo Lute〉レーベルの初期作品を思い出す。エレガントで、ドリーミーで、メロディアスなハウス・ミュージック。曲の後半でシンセサイザーが歌いはじめるような“Wake Up and Dip”、〈Retroactive〉時代のカール・クレイグを思い出さずにはいられない“Strut Garden”、どんなに閉ざされた心でもこじ開けてしまうであろう、ジャズ・ピアノ・ハウスの“Mysterious Lake”。そして、3枚目の裏面つまり最後の曲“Feel Us More”は、本作において3本の指に入る名曲だ。若々しい感性(リズムの組み方、チョップ)、そして古きもの(ハウスにおける美しいメロディ)が絶妙なバランスで展開する。ちなみに今回のアートワーク、どう考えても、初期のデトロイト・テクノの名作を手掛けてきたアブドゥール・ハック直系の感性だよなぁ……。
ハウス・ミュージックから30年以上の年月が流れて、社会もダンス・ミュージックを受け入れるようにはなった。しかし、デトロイト・テクノを起点とする価値体系が広く認められているわけではない。ヨーロッパがいまだにデトロイト・テクノへの思いを馳せるのは、この音楽が、どん底で生まれていることを忘れたくないからである。
