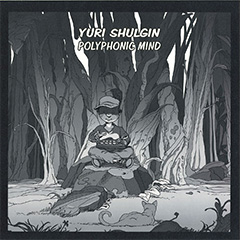MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Yuri Shulgin- Polyphonic Mind
よくアナログ盤は音がいいからという感覚的な話を聞くが、いま現在、12インチのヴァイナルEPなるメディアが意味するところは、90年代(=欧米のインディにとってカジュアルなリリース形態)とも、80年代(=ディスコ目的のリリース形態)とも違っている。高価にはなったが、その意味するところは、19世紀ヴィクトリア朝時代のウィリアム・モリスによるアーツ・アンド・クラフツ運動と似ている。そう、〝量〟に抗する手段である。
いや、〝量〟というよりは、インターネット地獄に抗する手段というべきだろうか。カイル・ホールの素晴らしいアルバムがヴァイナル・オンリーの配信ナシで5千円することも、まったくもってアーツ・アンド・クラフツ運動のコンセプトと重なりはしないか。
ウィリアム・モリスとは、19世紀の大英帝国を代表するデザイナーで、そして貧困を憎む社会主義者だった。イギリスで『資本論』を真っ先に読んだ人物としても知られ、英語版のデザインを手がけてもいる。カール・マルクスの娘とともに社会主義同盟のメンバーとして、ストリートでラジカルな演説をうったほどの人だ。モリスが世界を変えるために試みたアーツ・アンド・クラフツ運動による工芸品は、しかし結果、高価であるがゆえに、彼が味方した労働者に買えるものでなかったという矛盾があった。
だからといって大量生産された安いものばかりを買うことは、職人気質や手工芸というものをこの世界から追放することに加担する。インディ音楽シーンにおいて、いまさらアナログ盤やカセットが重要な意味を持つに至った理由と大いに重なる話だ。そして、Yuri Shulgin(ユーリ・シュリジンと読むのでしょうか。わかる方教えてください)の2年ぶりの新作からは、これが12インチ・ヴァイナルでなければならない理由がよくわかる。デジタルで満足している人には悪いけど、ずば抜けている。そろそろ音楽について語るべきだろう。
ホアン・アトキンスが「ジャズは先生(Jazz Is The Teacher)」なる曲を発表したのは1992年で、いまここでその時代に起きていたことを振り返ってみるのは、Yuri Shulginの新作を絶賛する理由がより見えやすくなるかもしれないが、そうした分析はときにうっとうしくもあるので、まず単刀直入に言うべきことは、このアナログ盤に彫られた4曲すべてに気持ちが揺さぶられる力があるとういこと。計算されながらも、優れた直観による力強い音響と抱擁、個性、美しい逸脱がある。ミスよりも勢い(グルーヴ)を重視しているところもいい。
A面1曲目の“Nothing In The City”の出だしのリズムとコードは、飲んでいるビールを思わず吹き出してしまうほどマッド・マイク直系だが、タメの効いたベースライン、ブレイク、躍動するサックスと美しいソウル・ヴォーカル、華麗なピアノのソロ、これら抑制されたジャズの断片と連続してアシッド・ハウスがミキシングされたとき、まあ、微笑まずにはいられない。ジャズが〝先生〟で、音楽的向上心を意味するなら、アシッド・ハウスとは下々の祝祭へのリスペクトを意味する。
続く“Polyphonic Mind ”を特別なものにしている要素のひとつにもリズムを刻む彼のベースがあり、ヴィブラフォンとサックス、ギターの即興がある。タイトルが言うように、すべての音が“ポリフォニック”に構成される、混然としていて、パワフルで、ハウス・ミュージックが本来持っている猥雑さが根を張るようにある。“Nothing In The City”と同様に、トランペット以外の楽器はすべて彼自身によって演奏されているが、これはフュージョンではないしIDMでもない。1993年のURを継承する音と言えるだろう。
B面の2曲はダブの探求となる。“Livetrackrecording (Dubby) ”はベーシック・チャンネルを彷彿させ、“#1stereo (Analog Jam) ”はアンビエントを展開、こちらの2曲にもアシッド・ハウスとジャズがある。
Yuri Shulginはロシア在住のプロデューサー(ベーシストとしてヴァクラなどの作品に参加している)で、アントン・ザップのレーベル、〈Ethereal Sound〉から2011年にEPを出している。いや、EPしか出していない。Mistanomistaという名義でもイタリアのレーベルから2枚出していて、その2枚と本人名義の3枚すべてがもっと広く賞賛されるべきものだ。本作は2年ぶりの新作になる。彼の音楽は小さなレーベルから発売されたアナログ盤でのみ発表されている。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE