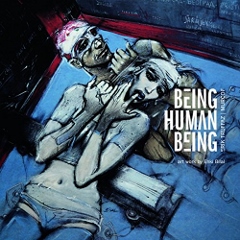MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Vakula- A Voyage To Arcturus
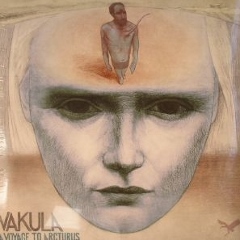
三田格 Feb 20,2015 UP
ブライアン・イーノにベースを足せばジ・オーブ、ジョン・ケージにベースを足せばOPN、テリー・ライリーにベースを足せばジェフ・ミルズで、ペリー&キングスレーにベースを足せばジェントル・ピープル。そう、ニュー・ウェイヴにベースを足せばエレクトロクラッシュで、UKガラージにベースを足せばダブステップと、なんでもベースを足せばクラブ・サウンドに早変わりしてしまう(われながらテキトーだなー)。では、ピンク・フロイ ドにベースを足せば……『アルクトゥールスへの旅』である。TJ・ヘルツによるオブジェクトが19世紀の中編小説「フラットランド」にヒントを得れば、こちらは20世紀初頭にコーンウォールへと引きこもったSF作家の代表作を一大音楽絵巻に仕立て上げた。基本的にはシンセサイザーが波打ちつつも、曲によってはホーンが炸裂し、ギターもソロのリードを弾きまくる。風景は次から次へと移り変わる。まさに「旅」である。(1時間29分40秒)
トーン・ホークやマーク・マッガイアーによるアメリカのクラウトロック・リヴァイヴァルとはやはりどこかが違う。ヨーロッパに特有の淀みがあり、〈デノファリ(Denovali)〉に通じる絶望感も成分としてはしたたかに含まれている。ここまでくるとディープ・ハウスという文脈もさすがに遠のいて、プログレッシヴ・ロックをエレクトロニック・ヴァージョンとして再定義したと捉えるほうがぜんぜん素直だと言える。そういう意味では2000年に再始動したブレインチケットの試みに追従するものとはいえ、全体的な瞑想性の強さでも踏襲している部分は多い。フュージョン的なセンスもまったくといっていいくらい同じ。違いがあるとすれば、それぞれの立場だろうか。ヴァクラはご存知の通り、停戦とは名ばかりの状態が続くウクライナからこの作品を発している。彼が住み、前作のタイトルにも使われたコノトープは軍事的な意味合いの多い場所だという。ヨーロッパで売れなくなった天然ガスを日本に売るため、サハリンと茨城をパイプラインで結ぶという計画がいまも話し合われていると思うと、ウクライナが置かれている立場はまったくの他人事とは行かないだろう。
前人未踏の地へ突き進んでいく勇気を描いた『アルクトゥールスへの旅』は彼の音楽的なチャレンジ精神をトレースするものであると同時に、真実と虚偽やこの世とあの世を超越しようという哲学の書でもある。本人がそこまで意識しているかどうかはわからないけれど、戦争体験を経た水木しげるが『河童の三平』で同じ問いを投げかけていたことを思うと、彼の目の前で起きていることから人間というものについて何かを考えざる得なかったのだろうという推測はどうしても進んでしまう。そして、そのような思索のなかに彼がハウス世代であること、つまりは、プログレッシヴ・ロックの世代にはない若さやわずかな希望を聴き取れるような気がしてしまう。少なくとも〈デノファリ(Denovali)〉にはもはやこのような足掻きさえ感じられないからである。あるいはフランスのトランペット奏者とメキシコのモダン・ミニマルが組んだ『ビーイング・ヒューマン・ビーイング』である。2回めのコラボレイションとなるトラファズとムルコフのセッションはあまりにも絶望感が強く、アルクトゥールスへと旅立つ前にそのまま座り込んでしまう音楽にしか聴こえない。そして、もちろん、それには説得力がある。
エリック・トラファズはジャズにクラブ・ミュージックの要素を持ち込もうとした先駆者のひとりである。初期の代表作となった『ベンディング・ニュー・コーナーズ』(1999)からいきなりラップをフィーチャーし、最後まで一定のテンションを保つ演奏内容はなかなか見事だった。その後もアラブ音楽を取り入れたり、トリップ・ホップをイメ-ジしているようなサウンドと、ここまでやってしまうと果たしてジャズ・ファンは聴くのかなというぐらいの逸脱ぶりを見せたものの、個人的にはどうにも締りのない演奏に成り果てていったという印象が拭えない。ムルコフとのジョイント・アルバム『メキシコ』(2008)はそのような低迷を経て彼がたどりついた新機軸であった。ベーシック・チャンネル・ミー ツ・ジョン・ハッセルとでもいえばいいだろうか。スウィングすることを拒否されたようなビートがストイックに構築され、トランペットはどこか凍りついたように悲しみを掻き立てていく。どちらかというとムルコフの世界観にトラファズが色を添えたものに思えた。
これが6年を経て、もっと複雑な音楽性を表現するものに発展することとなった。リズムは多様性にあふれ、等しく絶望的でありながらも、そこにはさまざまな色合いが認められるような瞬間の連続に成りかわっていったのである。『人間であること』というタイトル=問いはヴァクラとそう遠くにあるものとも思えない。遠くまで行く体力はもうないかもしれないけれど、考える力なら同じかそれ以上だと言いたげでもある。社会が効率を求めれば意味と自由は失われるとマックス・ヴェーバーが予言し、それを回復するのではなく、肯定するところからはじめようといったハーバーマスの言葉を思い出す。
ジャンル的にはまったく異なるものの、『アルクトゥールスへの旅』と『ビーイング・ヒューマン・ビーイング』がどうしても合わせ鏡のように聴こえて仕方がない(ジャケット・デザインが似ていることには、いま、ここまで書いてから気がついた)。悪く言えばヨーロッパ的な観念性は堂々巡りでしかない。しかし、ヨーロッパ的な精神にはそれができることが取り柄だともいえる。ウクライナでまた兵士が4人ほど死んだらしい。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE