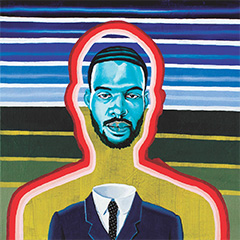MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kyle Hall- From Joy
デトロイト・テクノは、複数の位相において起点となり、価値観を更新したという意味において、ターニング・ポイントであり、ビッグバン(はじまり)だった。都市のレポートとしての音楽、都市という牢獄から脱出する術としてのベッドルーム・テクノ、ヨーロッパとアフリカの衝突、ポスト・ブラック・ナショナリズム……、ある意味ではより民主主義的なインディ・シーン、いち個人いちレーベルの現代の先駆けでもあった。
クラフトワークは理解できても「エイフェックス・ツインの音楽はどうしてもわからん」という御人はいまも少なくなく、しかし、その“てんで話にならない”音楽は、この30年間で膨張し、がっつりとひとつの価値体系をモノにしている。その契機となったのが、デトロイト・テクノだ(現代ではさらに新たな価値体系が生まれつつあることは、OPNを聴いている人はうすうす感じているだろうけど、しかしそれはダンス・ミュージックではない)。
とにかく、「これ普通やらないだろ」というときの「普通」に囚われない自由さを、技術よりも先立つものの重要さを「黒い」と表現できるなら、それはエレクトロニック・ミュージックにおけるビバップだったとも言えよう。
あるいはまた、ホアン・アトキンスがエレクトロ、デリック・メイがハウス、URがファンク……と喩えるなら、カイル・ホールのセカンド・アルバムはジャズだ。ジャズのセンスが色を添えている。デトロイトの音楽一家出身で、叔父が高名なジャズ・ピアニストのローランド・ハナ、叔母もミュージシャン(ヴァイオリン奏者)で、母も歌手。彼が10代でありながら大人びたハウスでデビューしたことは、そうした家庭環境も大きく関係しているのだろう。ホールの初期の作品に、「新しく古い世界」という曲があるように、新しさと古さを持ち合わせながら語りかける。古さを温ねることが前進に繫がるという好例である。
それで待望の新作だが、1曲目の“Damn! I'm Feeln Real Close”、ぼくはこれを聴いて、3枚組で5千円以上もする高価な3枚組を買うことに決めた。リズムからはダブステップ以降を感じる。が、全体はメロウなムードに包まれている。ピアノはエリック・サティめいた静謐さを思わせ、ときおり美しいフルートの音色、そしてアシッド・サウンドがカットインされる。前作『ザ・ボート・パーティ』が破壊的とも言えるほどリズミックな躍動を前景化している作品だとしたら、『フロム・ジョイ』は夜のムードをキープしつつ、随所に実験を試みながら、しかし滑らかでメロウに展開するアルバムだ。
“Dervenen”を聴いていると、ステファン・ロバーツの〈Eevo Lute〉レーベルの初期作品を思い出す。エレガントで、ドリーミーで、メロディアスなハウス・ミュージック。曲の後半でシンセサイザーが歌いはじめるような“Wake Up and Dip”、〈Retroactive〉時代のカール・クレイグを思い出さずにはいられない“Strut Garden”、どんなに閉ざされた心でもこじ開けてしまうであろう、ジャズ・ピアノ・ハウスの“Mysterious Lake”。そして、3枚目の裏面つまり最後の曲“Feel Us More”は、本作において3本の指に入る名曲だ。若々しい感性(リズムの組み方、チョップ)、そして古きもの(ハウスにおける美しいメロディ)が絶妙なバランスで展開する。ちなみに今回のアートワーク、どう考えても、初期のデトロイト・テクノの名作を手掛けてきたアブドゥール・ハック直系の感性だよなぁ……。
ハウス・ミュージックから30年以上の年月が流れて、社会もダンス・ミュージックを受け入れるようにはなった。しかし、デトロイト・テクノを起点とする価値体系が広く認められているわけではない。ヨーロッパがいまだにデトロイト・テクノへの思いを馳せるのは、この音楽が、どん底で生まれていることを忘れたくないからである。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE