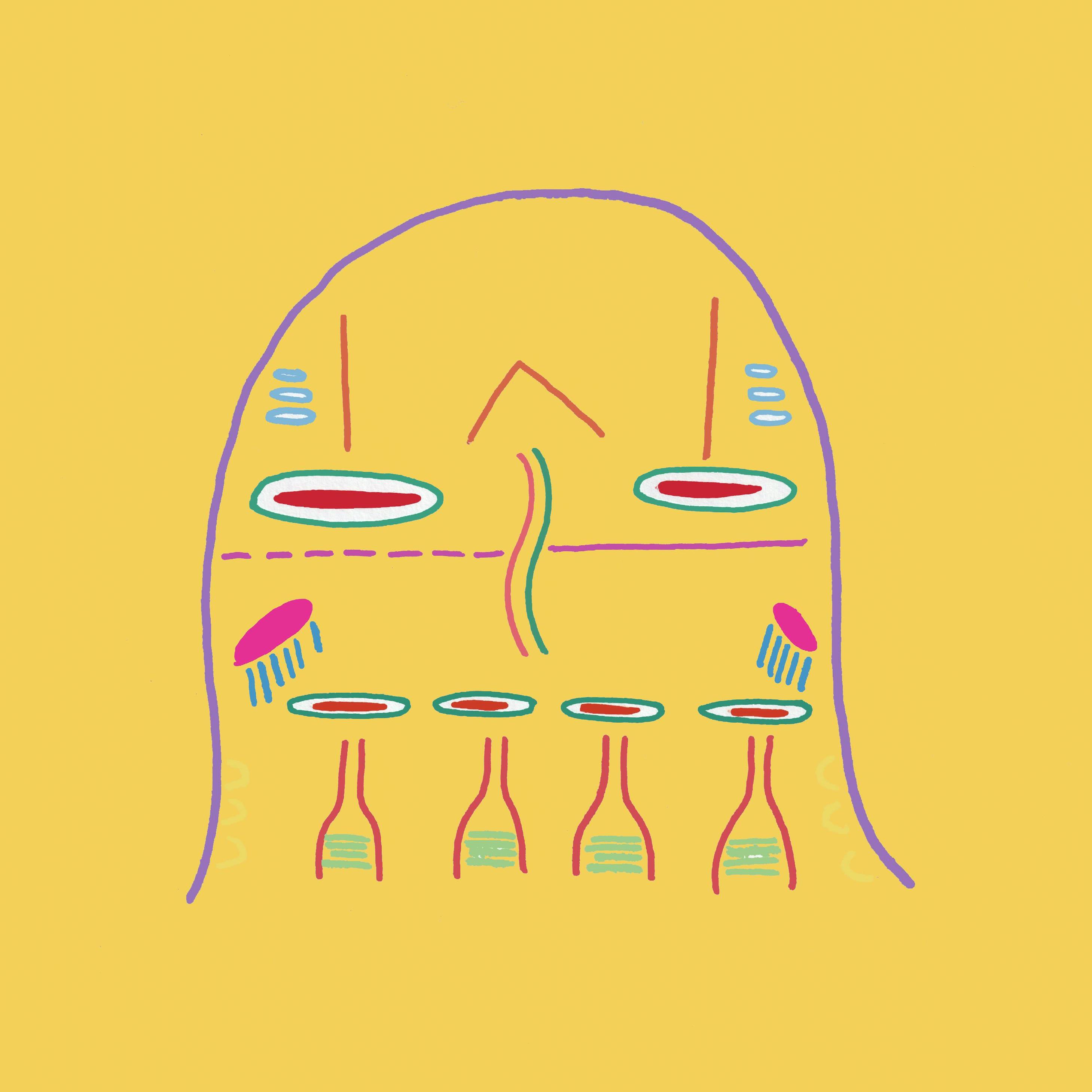つい5年前は本当にベース・ミュージックがブームだったのかと思うほど、最近はベースの存在感がない。ウエイトレスやアフロビートはパーカッションやドラムが曲を推進していくし、食品まつりもジュークからベースを抜いてしまった。OPNに至っては「窓が割れるから」という意味不明な理由でベースを遠ざけている。もちろんドラムン・ベースがダンスホールを取り込み、サンダーキャットも超絶技巧でクラブ・ジャズの改良には余念がない。しかし、パブリック・エナミーが「ベース!」と叫んで30年、ついにあのマジック・ワードがクラブ・ミュージック全体を覆うことはなくなり、必ずしも相撲界が貴乃花を必要としない事態と同じことになっている。ヒトラーが演説するときは土のなかに埋めたスピーカーから低音を出していたように、低音は共同体意識を増強させるものだと言われてきた。ということはクラブ・ミュージックと共同体意識はとっくに乖離し、SNSで結びついた村がたくさん集まったもの(=それは90年代に流行った島宇宙論を踏襲する構造)にクラブ・ミュージックも等しくなったということだろう。フロアでSNSを見ている人は多い。5年前のベース・ミュージックは最後のあがきだったのかもしれないし、孤独を誤魔化すためのニュー・エイジがマルチカルチャリズムを否定し、共同体意識のイミテーションづくりに邁進している現状にも合点が行く。EDMの合言葉はちなみに「フューチャー・ベース」である(大笑い)。
ベースレスのトレンドを決定づけたのはアルカだろう。彼のデビュー作『ゼン』(13)はインダストリアル・リヴァイヴァルを洗練させ、刺々しい感触だけを残して下部構造を捨ててしまったことでステータスをなした。これが様式性として反復・強化され、レイビットやロティックに至る過程はここ数年の白眉だったといっていい。たいていはハードにするか、グラマラスに盛り付けるかで、オリジナルを超えた気分を味わえた。しかし、その本質はファッションであり、それに耐えうるだけのものをアルカは用意していたといえる。「死」を内包したファッションほど強いものはない。ジョイ・ディヴィジョンしかり、ドレクシアしかり。『ゼン』はそうした古典のひとつに数えられる作品になるだろう。
テキサス出身で多摩美を出てから東京で教師をしているというレニック・ベルによる今年、2枚目のアルバム『ターニング・ポインツ』はベースレスの流れにあって、どこかアルカの様式性に反旗を翻し、ベース・ミュージックが持っていたヴァイブレーションへの回帰を促そうと、必要以上にもがき苦しんでいる印象を残す。パーカッションを多用し、曲が進むにつれてビートの叩き方はだんだんとマイク・パラディナスのような暴走状態となり、かえって淀んだ空気を引き立てている。作曲方法はプログラムとインプロヴィゼーションとオープン・ソースを使った自動作曲を混ぜ合わせたアルゴレイヴと呼ばれるもので、ライヴでは二度と同じことが繰り返されないことが特徴だという。そのようにして出来上がったサウンドがオウテカと比較されるのもなるほどで、それはファッションの外側に抜け出したいという衝動を意味しているのだろう、そのような葛藤を共有できるレーベルはむしろ〈パン〉ではないのかと思うけれど、『ターニング・ポインツ』はアイワやジェイ・グラス・ダブスをリリースしてきたカセット・レーベル〈シーグレイヴ(海の墓場)〉からとなった(デビュー・シングルはリー・ギャンブルの〈UIQ〉、デビュー・アルバムはレイビット主催の〈ハルシオン・ヴェイル〉から)。この、痒い所に手が届かないもどかしさは近い将来、何かを生み出すのではないかという予感に満ち、どこか先が読めてしまうアルカ・フォロワーよりも僕には新鮮だし、未完成の魅力がこれでもかと詰まっている。テクニックが向上したら面白くなくなってしまうという可能性もはらんではいるものの、だとしたら、楽しめるのはいまだとも言えるし(ウェルメイドしか聴かないという人には、だからオススメしませんけれど)、“ Splitting”によるビートの躓き具合なんて、期せずしてJ・ディラを乗り越えているとも言える(多分、違うと思うけど)。3月にリリースされた1作目の『ウェイリー(用心深い)』ではまだここまでパーカッションがボカスカ打ち鳴らされることはなかった。ベースで曲を転がすのではなく、パーカッションやドラムでグルーヴを生み出そうとした結果、このようなフリーク・ビートが導き出されることになったのだろう。この先どっちに向かうのかは見当もつかないけれど(自分で『ターニング・ポインツ』といっているぐらいだし)、いい意味で洗練されていけばいいなと思う。
アルゴレイヴについて詳しくは→https://www.renickbell.net/doku.php?id=about