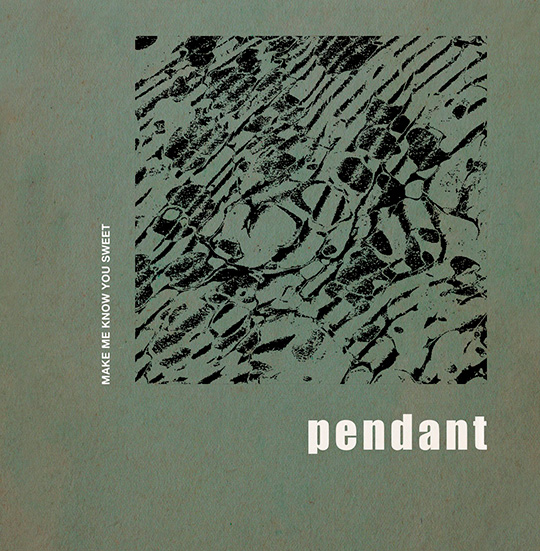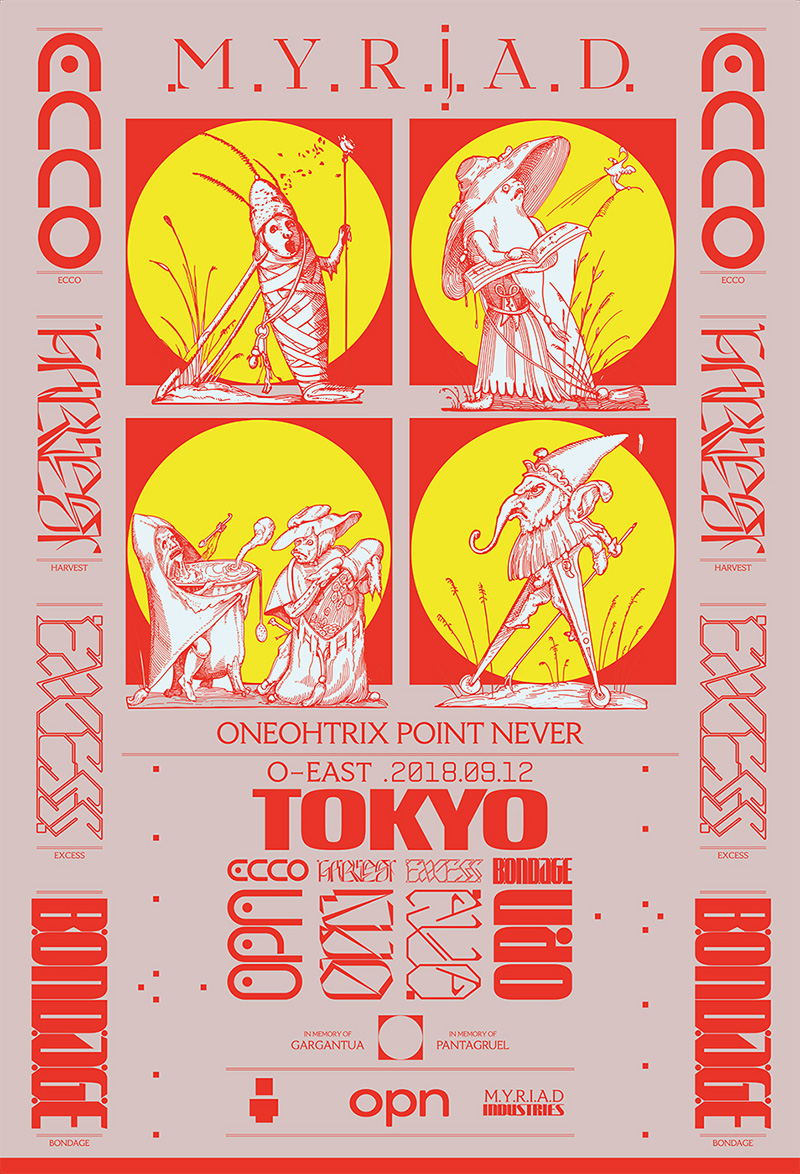いよいよ来週の木曜日からロシアW杯がはじまるかと思うと、いてもたってもいられない。来週末の金、土から日までの3日のあいだがすごい。カタルーニャ人も団結できるのかどうかのスペイン、キリアン・エムバペを擁するフランス、そして知将チッチ率いるブラジル、知将レーヴ率いるドイツのそれぞれの試合が見れるという、もちろんメッシのアルゼンチンも忘れるわけにはいかないし、月曜日には個人的に注目しているベルギーも出てくると。え? 日本代表? やはりここは大島僚太選手に注目でしょうね。
紙エレキングにも少し書いたことだが、今回のロシアW杯はわかりやすい。ドイツを倒すのがどの国か、だ。W杯はいまや戦術の大会などと言われているが(ゆえに直前で監督を変えることは戦術を重視する欧州では考えられないだろう)、ドイツはその最先端でもある。ぼくが子供のころはドイツといえばゲルマン魂の無骨なサッカーという印象だったが、いまやインテリ・サッカーなどとも言われるほど洗練されている。そして、ドイツ相手に前回の地元開催のW杯で1-7という歴史的にもあまりにも無残な敗戦をしたブラジルがチッチ監督の下で蘇生し、リベンジを目論んでいる。ぼくはもちろんブラジルを応援するが、力も技術もあり、根性もあり、幾何学まで取り入れて構築したというドイツ・サッカー(まあ、故障者を抱えていまいち仕上がりが良くないらしいが)をブラジルがどう攻略するのだろう。ついついそのことばかり考えてしまう。まあ、ぼくが考えたところで何も起こるわけでもないのだが。
そしてこのタイミングで、ぼくはブラジル音楽の本の刊行に携わっている。中原仁氏の監修/編集による『21世紀ブラジル音楽ガイド』という、現在進行形のブラジル音楽のディスク・カタログだが、W杯開幕とほぼ同じ時期に入稿がはじまるのだ。つまり世界中がブラジルのサッカーの魅力を再認識してからその本は刊行されると、これがシナリオである。
しかしここまで来るのに長かった。個人的にもいろいろあり、別冊エレキングのジャズ特集があり、紙エレキングのvol.22があった。そのどちらの特集もいま現在の音楽における突出したシーンを知るという意味でじつに有意義なものになったと思う。vol.22に関しては、前々からやりたかったアフロフューチャリズムの特集も実現できた。掲載されているチーノ・アモービのインタヴューは、ある意味OPN以上にハイブローだ(笑)。え? W杯がはじまるのにそれどころじゃないって? いや、たしかにおっしゃる通りだが、おそらくvol.22には、英米の音楽ジャーナリズムに興味がある人にとって、今後音楽について文章を書くうえでの重要な確認事項もあると思うので、観戦の箸休めとしてぜひ手にとっていただければと思います。

5月某日、2週連続で檜原村までサイクリング。梅雨前の初夏の最高のトリップでした。走行中、かぶとむしがぼくの背中にやって来ました。そのうち飛んでいくだろうと思って走っていたのですが……現在は家のベランダで元気にしています。




 photo: Atiba Jefferson
photo: Atiba Jefferson