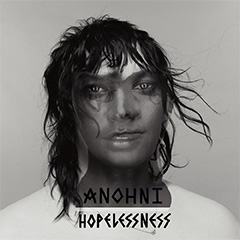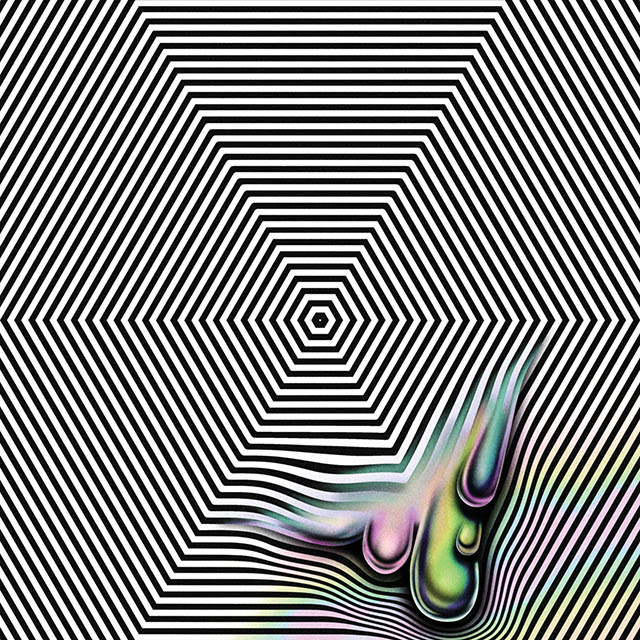MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Anohni- Hopelessness
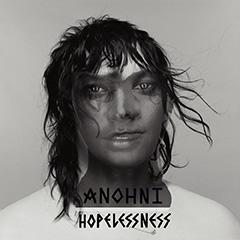
これまでアントニー・アンド・ザ・ジョンソンズ名義などで発表されたアントニー・ヘガティの楽曲は、ギター、ベース、ドラムスを中心とする伝統的なバンド編成であっても不思議な音響性があった。いわばヴェルヴェット・アンダーグラウンド的な空間的な楽器配置を継承するものだと思うのだが、そこにあってアントニーのヴォーカルは浮遊していた。浮遊する非=中心的な存在? それが、アントニー・ヘガティのヴォーカルの魅力のように思える。どこにも属していない感覚とでもいうべきか。
その声は、まるで黄泉の国への旅立ちのように衣装を纏ってもいるようにも聴こえた。この衣装こそが、ジョンソンズのサウンドであったのはいうまでもないが、私はその点においてこそアントニーの音楽が「ロック」の末裔にあると確信している。「ロック」とは「死」へと至る「生」を着飾る衣装=モードの音楽だ。資本主義という死の市場を生きる芸術? しかし「死」への過程はひとつではない。生が複数の層によって成り立っているように、「死」の過程もまた複数的といえる。ゆえに複数の衣装(モード)を身に纏う必然性があるのだ。
「電子音楽」(もしくはパフォーマティヴに未知の音色を探求するという意味で60年代以降の「実験」音楽も加えてもいいだろう)は、ロック史における、衣装(モード)のひとつである。電子音楽(もしくは実験音楽)と「ロック」のマリアージュは多種多様だ。ざっと思い出すだけでも、ピエール・アンリとスプーキー・トゥーズ、ジョン・レノンとオノ・ヨーコ、ロジャー・ウォーターズとロン・ギーシン、トニー・コンラッドとファウスト、ブライアン・イーノとデヴィッド・ボウイ、坂本龍一とデヴィッド・シルヴィアンのコラボレーションなど枚挙に暇がない。テクノからエイフェックス・ツインとフィリップ・グラスのコラボレーションを加えてもよい。さらにはラ・モンテ・ヤングとジョン・ケイルの関係、ザッパにおけるエドガー・ヴァレーズからの影響、シュトックハウゼンに師事したホルガー・シューカイのサウンド、ソニック・ユースの現代音楽への好奇心、レディオヘッドの『キッドA』化などを思い出してみてもよいだろう。
なぜ、これほどに「ロック」は電子音楽や実験音楽を希求するのだろうか。電気楽器による音響の拡張を嗜好する「ロック」と、音響の拡張を志向/思考する「電子音楽」の相性の良さが原因ともいえるだろうし、電子音楽特有の音の抽象性が、「ロック」がもたらす知覚とイメージの拡張に大きな力を発揮しやすいということもあるだろう。いずれにせよ、未知の音色の導入は、それは20世紀後半の「ロック」という商業音楽における、新たな崇高性(のイメージ)を獲得するためのモードであったと思う。そう、「ロック」は常に新しいモード=衣装を刹那に求めるのだ。窃盗の魅惑? それこそまさに「ロック」の魅力ではないか。
そして、アントニー・ヘガティあらためアノーニによる本アルバムもまた電子音楽の現代的なモードを纏っている傑作である。歌詞は、これまで以上にポリティカルだが、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとハドソン・モホークという現代の二大エレクトロニック・ミュージックのプロデューサーを迎えることで、絶望の中の祈りのようなサウンドを実現しているのだ。いまさら、この二人の経歴について書き連ねる必要はないだろうが、これは先に書いたような「ロック」と電子音楽のマリアージュの歴史に、新たな痕跡を残す作品であることは断言できる。
もっともアントニーとワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの録音は本作が最初ではない。2010年にワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが〈エディションズ・メゴ〉よりリリースした『リターナル』からシングルカットされた「リターナル」において、二人は共作している。同曲にアントニーがヴォーカルをつけて歌唱しているのである。むろん、6年の月日が流れた本作は、“リターナル”とは比べ物にならないほどの独創的な構造とテクスチャーを獲得している。“リターナル”のヴォーカル・ヴァージョンは、ピアノを主体とするトラックであったが、本作は、より複雑なエレクトロニック・サウンドに仕上がっていたのだ。また、ポップな享楽性(いわば死への快楽的な希求か?)の獲得には、ハドソン・モホークの存在と楽曲が重要であるのはいうまでもない。
壮大なパイプオルガンのような電子音からはじまる1曲め“ドローン・ボム・ミー”は、アントニーとモホークの共作曲で、崇高なエレクトロニック・サウンドが展開する。まるで死と恐怖に満ちた現代世界への享楽的な哀歌のように響いてくる楽曲だ。2曲め“4ディグリーズ”は、アノーニ、OPN、モホークらの共作。強靭な打撃音とアノーニの絶望を称えた声が重なり、まさに「エレクトロニック・オペラ」とでも称したいほどの唯一無二の楽曲である。
さらには胸締め付けるようなオルガン・コードが堪らない5曲め“アイ・ドント・ラブ・エニモア”から、6曲め“オバマ”、7曲め“ヴァイオレント・メン”と続くアノーニとOPNとの共作は圧巻だ。アノーニのヴォーカルとOPN的なシンセ・アンビエント・サウンド(とビート・プログラミング)が現代の受難曲のように響く。6曲め“オバマ“のアウトロで聴かれる悲痛なピアノ。7曲めのチリチリと乾いた音から溢れ出るような哀しみ……。続く8曲め“ホワイ・ディド・ユー・セパレート・ミー・フロム・ジ・アース?”はモホークとの共作で、まるで天に昇るような解放感のあるトラックに仕上がっている。全曲までとの対比が見事な構成だ。
個人的にはOPNとの共作にして、アルバム・タイトル曲である10曲め“ヘルプレスネス”にもっとも惹かれた。シンセ・アンビエント/ストリングスに、これまで以上に強い息吹を感じるようなアノーニの歌声がレイヤーされ、この世のものとは思えない天国的な音楽的サウンド・スケープが展開されているのだ。
それにしても、本作におけるアノーニの声は、かつてのように浮遊していない。猛烈なサウンドの情報という現実の中で格闘しているようである。その格闘を、過酷な現実への「祈り」から、新しい「崇高性」を獲得するための「闘争」と言いかえてもいいだろう。このような視点(聴点)でアルバムを聴いていくと、本作は、電子音楽とロックの邂逅における「現代の崇高なバロック・ミュージック」といいたい気分にすらなってくる。だが、バロックは地域と歴史を越境する雑多な音楽の交錯点でもあることを忘れてはならない。
晩年のピエール・シェフェールは、自らが生み出したミュージック・コンクレートを「ドレミの外では何もできない」と完全に否定し、「新しい音楽を作る希望を捨てよ」とまで言い放った。そして、それでも残っている音楽が「バロック音楽」と断言する。さらにシェフェールは「西欧音楽で最も崇高とみなされてきたバロック音楽」とまで語り、そして「バロックとはイタリアや中世の音楽のよせ集めから作られた」とも述べていた。よせ集めから生まれる崇高さと新しさ? まさに「ロック」だ。そして、本作には、そのような崇高と猥雑と新しさに満ちた21世紀のバロッキニズムが横溢しているのである(バ/ロック・ミュージック?)。
その意味で、OPNとハドソン・モホークが、アントニー=アノーニとコラボレーションを行ったことは、ロック史において重要な意味を持つと思う。たとえば『ロウ』にブライアン・イーノの参加したことに匹敵するような。いうまでもないが『ロウ』(とくにB面)にもまたバロック的な電子音楽(ロック)である。バロックへの希求。ロックの死、死と生。死の旅路を飾る衣装としての音楽=ロック……ゆえにボウイの死後に本作がリリースされたことは、偶然にせよ偶然を超えた偶然に思えてならない。
黒い星から絶望へ? まさに「世界」が死と恐怖の激動の波に晒されている2016年に世に出るべくして出たアルバムといえよう。そして何よりエレクトロニックのモードを纏いつつも、本作はポップ・ミュージックとしての聴きやすさもあるのだ。電子音と声と和声とノイズによる21世紀のポップ・ミュージック。美しいピアノで終わるモホークとの最終曲“マロウ”を聴き終えたとき、あなたは、現代世界への本当の怒り、そして絶望の果てにある透明な世界を垣間見るだろう。途轍もない傑作が生まれてしまった。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE