昨秋リリースされた『Garden Of Delete』の昂奮も冷めやらぬなか、年明け早々にジャネット・ジャクソンをドローンに仕立て直したかと思えば、ハドソン・モホークとともにアノーニのアルバムをプロデュースしたり、DJアールのアルバムを手伝ったりと、ダニエル・ロパティンの創作意欲は留まるところを知らない。そのOPNがまた新たな動きを見せている。
昨年公開された“Sticky Drama”のMVもなかなか衝撃的な映像だったけれど、このたび公開された“Animals”のMVもまた、観る者に深い思考をうながす内容となっている。近年は過剰な音の堆積でリスナーを圧倒しているOPNだが、彼はもともとアンビエントから出発した音楽家である。そのことを踏まえてこのヴィデオを眺めてみよう。このMVは「ベッドルームとは何か?」という問いを投げかけているんじゃないだろうか?
監督はリック・アルヴァーソン。主演はヴァル・キルマー。以下からどうぞ。
ONEOHTRIX POINT NEVER
ヴァル・キルマー主演の最新映像作品「ANIMALS」を公開

エクスペリメンタル・ミュージックからモダンアート、映画界まで活躍の場を広げ、熱狂的な支持を集めるワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが、2015年に発表し、賞賛を浴びた最新作『Garden of Delete』から、作品の核となる楽曲「Animals」のミュージック・ビデオを公開した。
Oneohtrix Point Never - Animals (Director's Cut)
YouTube:https://youtu.be/1UztCDH2xuQ
公式サイト:https://pointnever.com/animals
Val Kilmer
Directed & Edited by Rick Alverson
Story by Daniel Lopatin & Rick Alverson
Ryan Zacarias - Producer
Drew Bienemann - DP
Alex Kornreich - Steadicam
Julien Janigo - Gaffer
Paulo Arriola - 1st AC
Jess Eisenman - HMU
Dan Finfer - Home Owner
ロサンゼルスで撮影された本映像作品は、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティン原案のストーリーを元に、映像作家リック・アルヴァーソンが監督を務め、映画『トップガン』や『ヒート』、『バットマン・フォーエヴァー』などで知られる俳優ヴァル・キルマーが主演している。
また本作品は、現在ロサンゼルスのアーマンド・ハマー美術館にて開催中のアート展『Ecco: The Videos of Oneohtrix Point Never and Related Works』のオープニング・イベントにて10月18日にプレミア上映された。
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーは、『Garden of Delete』をリリース後も、人気ファッション・ブランド、KENZOのファッション・ショーにて、ジャネット・ジャクソンの「Rhythm Nation」をアレンジした160人による合唱曲を披露し、マーキュリー賞にもノミネートされたアノーニのアルバム『Hopelessness』をハドソン・モホークとともにプロデュースし、ツアーにも参加するなど、ますますその活躍の場を広げている。
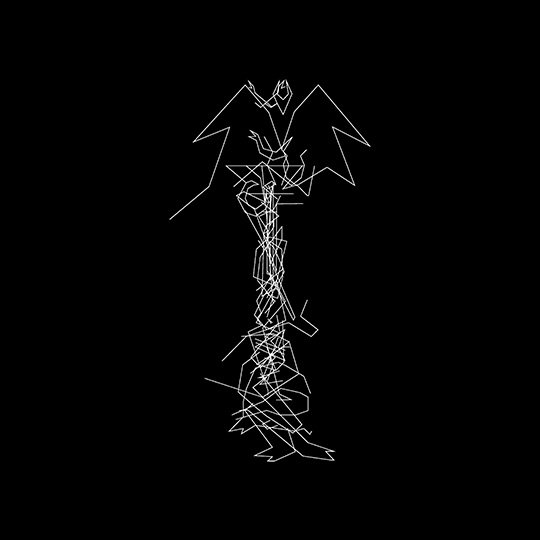
label: WARP RECORDINGS / BEAT RECORDS
artist: ONEOHTRIX POINT NEVER
title: Garden of Delete
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー / ガーデン・オブ・デリート
release date: NOW ON SALE
国内盤CD BRC-486 定価 ¥2,200(+税)
国内盤特典:ボーナストラック追加収録
[ご購入はこちら]
beatkartで購入:https://shop.beatink.com/shopdetail/000000001965/
amazon: https://amzn.to/1NbCrP4
tower records: https://bit.ly/1UodWT0
HMV: https://bit.ly/1LVZJIv
iTunes: https://apple.co/1NOGOj3
Tracklisting
1. Intro
2. Ezra
3. ECCOJAMC1
4. Sticky Drama
5. SDFK
6. Mutant Standard
7. Child of Rage
8. Animals
9. I Bite Through It
10. Freaky Eyes
11. Lift
12. No Good
13. The Knuckleheads (Bonus Track For Japan)





