最新作『Arca』も好評なアルカが、なんと坂本龍一のリミックスを手がけました。原曲は坂本の最新作『async』収録のタイトル・トラック“async”で、このリミックス・ヴァージョンではアルカ本人が歌っております。しかも日本語で。去る7月にはOPNが坂本龍一のリミックスを発表しましたが、今度はアルカということで、現在エレクトロニック・ミュージックの最尖端を走り続けている2巨頭いずれもが坂本龍一と邂逅したということになります。この交差は2017年を象徴する出来事かもしれません。教授のリミックス・アルバム、楽しみですね。
奇才アルカが坂本龍一をリミックス
Ryuichi Sakamoto - “async - Arca Remix" (async Remodels)

ビョークやFKAツイッグス等のプロデューサーとしても知られ、今年〈XL Recordings〉からサード・アルバム『Arca』をリリース、初出演となったフジロックでは、ヴィジュアル・アーティスト、ジェシー・カンダを伴ったAVセットも話題になった他、ビョークのステージにも上がるなど、ますます注目を集めるアルカが、坂本龍一の最新アルバム『async』のタイトル・トラック“async”のリミックス・ワークを公開した。『Arca』でも全面に打ち出された自身の歌声がここでも披露されており、日本語の歌詞が歌われている。
async - Arca Remix (async Remodels)
https://youtu.be/aKxPhAb6OMA
本楽曲は、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが手がけた“Andata (Oneohtrix Point Never Rework)”、アルヴァ・ノトによる“disintegration (Alva Noto Remodel)”、エレクトリック・ユースによる“andata (Electric Youth Remix)”に続いて公開されたもので、その他、コーネリアス、ヨハン・ヨハンソン、モーション・グラフィックス、エレクトリック・ユースなどの参加が明かされている。
Andata (Oneohtrix Point Never Rework)
https://youtu.be/G0p647mDqT0
andata (Electric Youth Remix)
https://youtu.be/6g9LEBYJ1oU
disintegration (Alva Noto Remodel)
https://youtu.be/sxZ9AwIPDa4
早くからカニエ・ウェストやビョークらがその才能を絶賛し、FKAツイッグスやケレラ、ディーン・ブラントといった新世代アーティストからも絶大な指示を集めるアルカ。セルフタイトルとなった本作『Arca』は、2014年の『Xen』、2015年の『Mutant』に続くサード・アルバムとなり、〈XL Recordings〉からの初作品となる。国内盤CDにはボーナス・トラックが追加収録され、解説書が封入される。

label: BEAT RECORDS / XL RECORDINGS
artist: Arca
title: Arca
release date: 2017/04/07 FRI ON SALE
国内盤特典 ボーナス・トラック追加収録 / 解説書封入
XLCDJ834 ¥2,200+税
beatkart: https://shop.beatink.com/shopdetail/000000002153
amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B06WW944RJ/
tower records: https://tower.jp/item/4458674/
hmv: https://bit.ly/2l2yjdp
iTunes Store: https://apple.co/2m9K7um
Apple Music: https://apple.co/2l1GBNJ
[Tracklisting]
01. Piel
02. Anoche
03. Saunter
04. Urchin
05. Reverie
06. Castration
07. Sin Rumbo
08. Coraje
09. Whip
10. Desafío
11. Fugaces
12. Miel
13. Child
14. Saunter (Reprise) *Bonus Track for Japan


 Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
 Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.






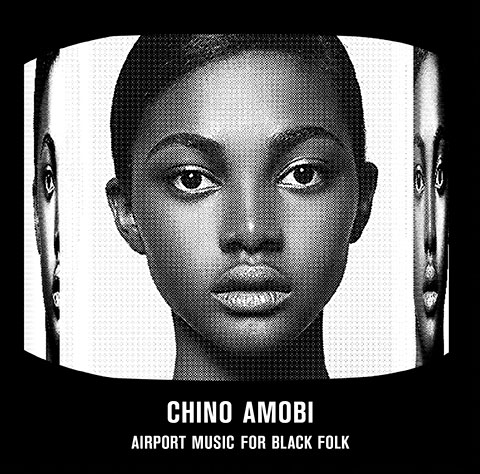
 label: Warp Records / Beat Records
label: Warp Records / Beat Records


