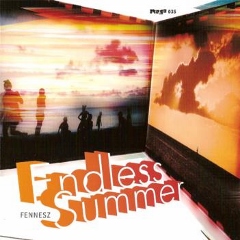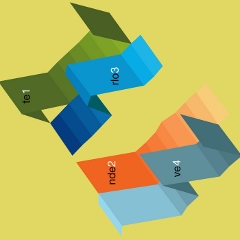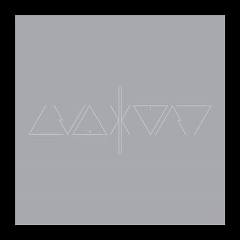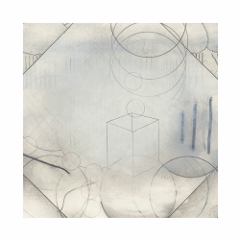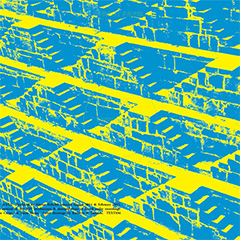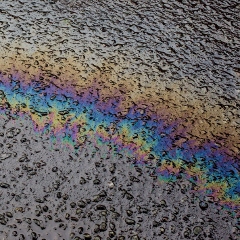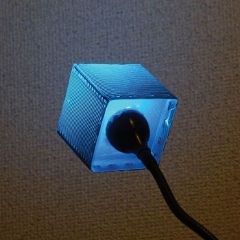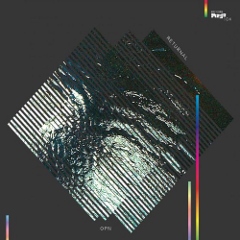今年は、どうも「ロウ」な音の質感が気になっていた。10年代前半のハイレゾリューションな音の横溢から、ザラついたロウな音へのモード・チェンジ。たとえばジェニー・ヴァルのアルバムで聴かれたようなザラついたファットなビートを思い出してもらいたい。もしくは〈アントラクト〉が送り出すイマジナリー・フォーシスなどのアーティストたちの音の質感。または〈ウモール・レックス〉のジェイムス・プレイスのアルバムの淡いノイズ。さらには〈フラウ〉からアルバムをリリースした日本のマッドエッグの壊れゆくビート。そして、〈リーヴィング〉から今年リリースされて作品たち。
もはや説明不要だが〈リーヴィング〉は、OPN以降のアーティストともいえるサリヴァ、新時代のポップ・スターにすらなりつつあるジュリア・ホルター、インターネット以降の世界への嘲笑を一気に引き受けたかのようなD/P/I、モジュラー・シンセ使いで一躍人気のゲド・ゲングラス、ノイズ、ビートの多幸性みなぎるマシューデイヴィッドなど人気アーティストたちを送りだしたできたテン年代の「モダン・ニューエイジ」の潮流を代表するレーベルである。が、本年においては、どこか「ロウ」な質感/気分を持ったアーティストの作品を送り出しているように思えるのだ。とくにディーントーニ・パークスの『テクノセルフ』は、ザラついた質感のロウな激シブなテクノ/ビート・トラックで、まさに2016年のモードを先取り(?)したかのような素晴らしいアルバムであった。
今回取り上げるスマーフィーのアルバムも同様だ。すでに彼女のアルバムは、海外メディア勢の年間ベストにも取り上げられていることからもわかるように、2015年以降のサウンド・アトモスフィアを湛えた傑作といってもよい。メキシコ人である彼女の音は、かの地の空気独特のザラついた質感と蒼穹の青空のような不思議な透明感を持っているように聴こえてくる。
そこに内包された音楽はじつに多種多用である。ジューク以降のリズム感。ザラついたヒップホップなビート。電子音響的なノイズ。空間を自由に伸縮させるような彼女の「声」。まさに音の坩堝といった趣だが、情報過多の暑苦しさはまるでない。トライバルなリズム、ファットなビート、チリチリしたノイズや綺麗なカーテンのようなアンビエントが、彼女の「声」の周辺に空気の粒子のように舞い踊っていくかのような印象を聴き手に与えてくれるからだ。
1曲め“ミッシング2MyBB”で透明なスクリーンの向こうから聴こえてくるような声とトライバルなリズムの交錯が素晴らしい。まるでポスト・インターネット時代のブリジット・フォンテーヌか。シームレスにつながっていく2曲め“サンセット”は、曲名とは裏腹に、リズムと時間が逆回転しながら深海に沈み込んでいるような白昼夢的なインタールード・トラック。つづく3曲め“アクエリアス・リジン”では、砂埃が絡みついたようなビートに亡霊のようなヴォーカリゼーションを聴かせてくれる。そして、分解したビートが再度溶け合うような4曲め“ジャルダン”を経て、5曲め“ウィケッド”では、サウンドの霧の中で美しいメロディラインを歌う(この曲、少しだけ90年代終わりの嶺川貴子を思わせる?)。以降も楽曲もリズムとビートとノイズとヴォイスが舞い踊るように表出しては消えていく。ビートにはジューク以降ともいえる分割感があるが、しかしそれすらもサウンドのレイヤーの中に溶け合っているのだ。ハイレゾでもローファイでもない。美しくも埃っぽい「ロウ」な音の中で……。
そう、ここには「ハイレゾな10年代前半からロウ・サウンドなテン年代へ」という時代のモード・チェンジがたしかにある。本年ギリギリに届いた〈アントラクト〉からリリースされたイゾルデ・タッチのアルバムとともに、2016年にむけての新しい音の蠢きがここにある。