 The Asphodells Ruled By Passion, Destroyed By Lust ROTTERS GOLF CLUB/ビート |
夜だ。雨が窓を強く打っている。以下に掲載するのは偉大なるDJ、アンドリュー・ウェザオールのインタヴューだ。彼はテクノのDJに分類されるが、その音楽にはクラウトロックからポスト・パンクなどが注がれ、その美学にはいかにも英国風のゴシック・スタイルがうかがえる。最新の彼の写真を見ると、19世紀風の趣味がますます際立っているようにも思える。その気持ちも、僕は英国人ではないが、ある程度までは理解できる。
僕は彼と同じ歳なので、世代的な共感もある。パンク、ポスト・パンクからアシッド・ハウス、テクノへと同じ音楽経験をしてきている。この人のお陰で、我々は人生のなかでいろいろな人たちと出会い、話すことができた。ポスト・パンクのリスナーをハウス・ミュージックと結びつけてくれたのはアンドリュー・ウェザオールである。彼が正しい道筋を示してくれたと僕はいまでも思っている。
ちょうどこの取材の最中『テクノ・ディフィニティヴ』というカタログ本のために昔の作品も聴き返したが、全部良かった。彼の新しいプロジェクト、ジ・アスフォデルス名義のアルバム『ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト(情熱に支配され、欲望に滅びる)』も良い。まだ何10回も聴いているわけではないが、きっと後で良く思える気がする。だいたい題名が示唆に富んでいる。以下の彼の発言に出てくるが、彼なりに「人間特有の悲劇」を表しているそうだ。
アンドリュー・ウェザオールはこの取材で、本当に誠実な回答をしてくれたと思う。彼には最初から、ある種日陰の美しさのようなものがあった。古風な親分肌というか、謙虚さのようなものがあったが、今回の取材では、寛容さも身に付けているように僕には感じられた。自分もこうでありたいものだと思う。
俺が音楽の道を選んだ理由のひとつに、競争というくだらないものに関わりたくないという理由があった。俺は自分が野心家ではないと話したが、じつはそうではなくて競争心がないということなんだ。野心はあるが、競争なんてしたくない。「野心はあってもいいけどがんばるな」なんて若い人向けのメッセージとしては最低だな(笑)。
■2009年に『ア・ポックス・オン・ザ・パイオニアズ』を出して以来のアルバムになるんですよね? あれ以降の3年間はあなたにとってどんな時間でしたか?
アンドリュー・ウェザオール:俺は次の構想を練るというようなことはしない。つねに音楽を作り、レコーディングをしている。そして6ヵ月から1年おきにまとまった量の音楽ができあがり、アルバムになる可能性が出てくるわけだ。『ア・ポックス・オン・ザ・パイオニアズ』につづく作品を作っていたけど、それは結局リリースされないね。1年くらいかけて制作に取り組んでいたんだけど、ある法的な事情によってリリースできなくなった。そのときいっしょに制作していた人を解雇したので、それまで作ってきた音楽をリリースするのが複雑になってしまったんだ。
だからこの3年間、レコーディングはつねに続けていた。ただリリースする予定だったものがリリースできなくなったというだけのことだ。俺は音楽制作という仕事をストップすることはないよ。「これからアルバムを作ろう」って具合に取り組むのではなく、つねに音楽を作っている。そしてたいてい、マネージメントのほうから「そろそろアルバムを出す時期なのでは」と言われるから、パソコンに保存してある音楽を確認し、アルバムに収録できそうなものを選んでいき、それをリリースするということになる。
■〈ロッターズ・ゴルフ・クラブ〉からも作品を出しませんでしたよね? それは、先ほどお話しされていた理由からなのでしょうか? それともそれ以外の理由もあったのでしょうか?
AW:さっきの話も一因としてある。それに、ほかのアーティストのレコードをリリースするというのはけっこう責任の重いことでね。音楽業界の現状からして、俺はその責任を負いたくなかった。だから〈ロッターズ・ゴルフ・クラブ〉は、自分の音楽をリリースするためのレーベルになると思う。それは俺の責任だからいいんだ。
俺は最近、〈バード・スケアラー〉という別のレーベルも立ち上げた。そこではほかのアーティストの音楽をリリースしているよ。このレーベルはアナログ・レコードのみ限定300枚のリリースをするためのもので、ダウンロードはなし。あまり責任も重大じゃないし、レコードはすべて売れる。300枚だから1日で売れるんだ。俺は音楽をリリースできるし、アーティストもレコードが何千枚と売れるなどと期待していないから、責任も重くない。
■この3年ものあいだ、あなたのことですから他の名義で作品を出していたんじゃないでしょうか?
AW:いや、ないよ。たとえあったとしても教えない(笑)。だって他の名義で作品を出す意味が失われてしまうだろ?
■ティム・フェアプレイは、『ザ・ボードルームVol.2』にも参加してましたね。彼とはどのように出会って、そしてどのようにジ・アスフォデルスは誕生したのでしょうか?
AW:ティム・フェアプレイと俺は90年代なかごろから2000年代初期まで〈ヘイワイヤー〉というパーティでDJしていて、ティムはそのパーティの常連だったんだ。だから共通の友人もたくさんいた。彼と出会ったのはそんな経緯だね。その後、彼はバッタントというバンドにいて、ギターを担当していた。それから彼は俺の所有するスタジオのひと部屋に移ってきたよ。俺のスタジオは4、5部屋あって、そのひと部屋が空いたから、彼がそこに自分のスタジオを移してきた。だから彼はつねに俺がいる隣の部屋で作業していたのさ。
彼とは長年友だちで、あるときから俺のとなりのスペースで仕事をしていた。そして、俺がエンジニアを必要としているとき、ティムが理想的なパートナーだと気づいた。彼は俺の仕事の仕方もわかってるし、俺が求めているサウンドもわかっている。彼は、俺のキーボードやドラムマシンの好みなんかも知ってる。とても自然な成りゆきで彼と組むことになったよ。そしていっしょに音楽を作るようになった。俺たちの作品はアンドリュー・ウェザオールの作品ではなくいっしょに作ってできあがったものだから、ユニット名が必要だということになって、俺が「ジ・アスフォデルス」という名をつけた。アスフォデルはユリ科の花の名前。ギリシャ神話では「死」や「破壊」を意味する不吉なものとされていた。だが同時にとても美しい花だ。こんなにも美しいものが、悪の象徴とされている。俺はそういう組み合わせが大好きなんだ。
とにかくティムと組んだのは自然な流れからだ。俺がギタリスト、エンジニアを必要としているときにティムがいた。彼は俺の現場につねにいたから自然とそういうふうに発展したんだ。
■あなたからみてティム・フェアプレイのどんなところがいいと思いますか?
AW:ギターがめちゃめちゃうまいところ。それからプログラマー、エンジニアとしての腕もいい。そして何よりも、すごくいいやつだ。音楽、文学、アートの好みがとても近い。これは非常に重要なことだね。
[[SplitPage]]ポップ・カルチャーやトラッシュ・カルチャーが、そのへんの哲学者よりも簡潔に人間のありようについて言及できているのをみると俺はうれしくなってくる。40年代50年代のパルプフィクションもそうだ。路上にいる人びと、通勤中の人びとを魅了するためには、還元主義的で直接的な表現を用いなければいけなかった。
 The Asphodells Ruled By Passion, Destroyed By Lust ROTTERS GOLF CLUB/ビート |
■ジ・アスフォデルスのトラックは、公式には今年あなたが出した3枚組のミックスCDが最初になるのですか?
AW:そうだ。あのCDにはジ・アスフォデルスの曲がふたつある。"ア・ラヴ・フロム・アウター・スペース"とたしか"ロンリー・シティ"だったと思う。初めてレコーディングした曲がこのふたつというわけではないけど、公式リリースとしてはそうだ。俺は〈ア・ラヴ・フロム・アウター・スペース (以下ALFOSと略)〉というパーティをやっていて、この2曲もそのパーティ向けに作られた曲だ。だからよくパーティでかけてたね。
みんなが、「ジ・アスフォデルス」という名前をはじめて見たのはこのミックスCDでだと思う。いまだにジ・アスフォデルスが俺だということを知らない人もいる。CDに記載されてる細かい文字を読まないんだ。よく「ALFOSのあのヴァージョンいいね」と言われるが、俺が「ああ、あれは俺が歌ってるんだ」と言うと驚かれる。「本当に? 本当にお前が歌ってるの?」ってね。細かい文字を読めば俺とティムの名前が載ってるのにね。
■"ア・ラヴ・フロム・アウター・スペース"の最初のヴァージョンはあのミックスCDにも収録されていましたよね。『マスターピース』と今回の『ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト』とはどのような関係にあるのでしょうか?
AW:共通点をひとつ挙げるとすれば、〈ALFOS〉の雰囲気やそこでかけている曲かな。ミッドテンポで、ディスコ、ポスト・パンク、テクノ、ハウスの要素が入っている。俺が作る音楽というのは、無意識的にだけど、俺がいままで35年間聴いてきた音楽が反映されている。俺がいままで聴いてきた音楽は、いいものも悪いものも、俺の骨の一部、音楽的DNAを構成している。俺が作る音楽というのは、俺がいままで聴いてきたものの産物といえるだろうね。
このアルバムのスタート地点として、〈ALFOS〉でかけられるような音楽を作るっていうコンセプトがあり、そこから発展していった。スタート地点はダンスフロアだったが、そこから枝分かれしていったよ。ダンスフロア向けのトラックを曲にしていくことによってそのトラックが聴く側にとってよりおもしろいものになる。そういうフロア向けのトラック集というのももちろんいいが、俺はたまに曲が聴きたくなるんだ。だから、アルバムのなかに〈ALFOS〉向けではない曲を入れることによって、作品をダンスフロアから少し遠ざけたのさ。
■『ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト』はじつにあなたらしいタイトルですが、同時にいままでにない直球な言葉表現を使ってきましたね。そのココロは何でしょう?
AW:『ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト(情熱に支配され、欲望に滅びる)』というのは、俺に言わせると、人間特有の悲劇を表現する6単語なんだ。人間を前進させるのは情熱だ。新しいものに対する情熱、向上心に対する情熱......だけどときどきその情熱の方向性を間違えて、権力に対する欲望や金に対する欲望と化してしまう。それが結果として我々を滅ぼすことになる、というね。どこでこの表現を見つけたかというと、じつは見つけたのはティムなんだが、ティムはB級映画やホラー映画が大好きで、70年代のゲイ・ポルノ映画のポスターを持っていた。その映画には古代ローマ時代の剣闘士が登場するんだけど、ポスターのいちばん下に、「ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト」と書かれていてね。それを見て最高だと思ったんだ。
ポップ・カルチャーやトラッシュ・カルチャーが、そのへんの哲学者よりも簡潔に人間のありようについて言及できているのをみると俺はうれしくなってくる。40年代50年代のパルプ・フィクションなんかもそうだ。路上にいる人々、通勤中の人びとを魅了するためには、還元主義的で直接的な表現を用いなければいけなかった。それと同じ意味で、直接的に簡潔に書くというのは、着飾った文章を書くことよりも難しいのかもしれない。だからダシール・ハメットのような作家は偉大だと思う。人間のありようを一文で表現できるから。
誤解しないでほしいんだが、俺は着飾った文書の本を1冊まるごと読むのも大好きだ。俺は19世紀末から20世紀初めのヨーロッパ小説が好きで、その文体には着飾った文章や長々しい説明も多い。だが同時に、気のきいた言い回しとか、安っぽい格言とかも大好きなんだ。自分で気に入ったものは書きとめておくね。1冊の本になるくらいの量があるよ。小説や映画などからピック・アップするんだ。とにかくアルバムのタイトルは人間のありようについての哲学的な言及だが、ゲイ・ポルノ映画のキャッチ・コピーでもあるというわけだ。受け取り方は人次第さ。
■たしかに今回のアルバムにはパッションとラストを感じました。何がきっかけでそうなったのでしょうか?
AW:おもしろいことに、俺の音楽はそう捉えられることが多いらしい。先日、『CSI』という警察モノのテレビ番組を見ていたら、俺の音楽が使われていたんだが、それがSMかなんかのセックス・クラブみたいな場所でかかっている音楽として使われていたんだ。ほかにも人から「お前の音楽は情熱的でセクシーでいかがわしい雰囲気がある」とよく言われる。なんでだろうな? よくわからないけど、たんに俺がいかがわしいやつなのかもしれない(爆笑)。
でも、そういう雰囲気の音楽が好きだからだと思うよ。この35年間、もっとも心を動かされたのはそういう音楽だったんだ。情熱的な音楽。自分たちのやっていることに対して情熱を感じて音楽を作っている人たちの音楽さ。自分の音楽について「パッションを強く感じる」と言われたらそれは最高の褒め言葉だと思うよ。意識的にそういうものを作っているのではないし、先も言ったようにそれは35年間の経験からにじみ出るものだ。恋に落ち、恋に冷め、誰かを愛し、誰かを愛するのをやめる、誰かに愛されなくなる......人間の人生経験は、芸術経験と同じくらい大切なものだ。俺は音楽を25年間作り続けているから、自らの音楽というものを極めてやろうという決意を持っている。君に、さまざまな音楽を聴かせて、当時の俺がどの地点にいて、どんな精神状態だったかというのをひとつひとつ説明していくこともできるよ。当時の俺は調子がよかったとか。アルバムをかけて、振り返ってみれば、この作品を作っていたときは俺の精神は崩壊する直前だった、とか(笑)。
でもそれも情熱なんだ。悪い方に向けられた情熱だが、情熱に変わりない。俺は音楽に対して情熱を持っている。だから25年間続けていられる。そしてときに音楽に対して欲望もある。それはまたあるときに俺を破滅へと追い込む(笑)。
とにかく、自分の信条にそった音楽を作っていれば、聴いた人にそれが自然と伝わると思う。だから俺の音楽はパッションやラストが感じられると言ってくれるのは俺にとっては最高の褒め言葉だ。
そのとき俺たちの頭のなかにはソフト・セルの"セイ・ハロー・ウェイヴ・グッドバイ"がかかっていた。そして俺は、「マーク・アーモンドに電話してヴォーカルを歌ってもらおう」なんてことを考えてた。俺がもっと金持ちで大きなレコード会社と契約していたら、そう言っていると思うけどね。そういう無意識的なソフト・セルへの愛がこめられている。
 The Asphodells Ruled By Passion, Destroyed By Lust ROTTERS GOLF CLUB/ビート |
■『マスターピース』もそうでしたが、あなたのこれまでの人生で愛した音が詰まっていると、『ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト』でも感じました。テクノ風ですが、よく聴くとロックンロールのグルーヴもあるし、ダブもあるし、ベースやギター、ヴォーカルにはこの10年あなたが追求してきたサウンドがある。セイバース・オブ・パラダイス、トゥー・ローン・スウォーズメンのときと比較した場合、ジ・アスフォデルスでのあなたは、音楽的なアプローチにおいて、どこが違っているのでしょう?
AW:音楽的なアプローチにおいてはあまり違いはない。最終的な結果が違うだけだ。先も話したように、俺は毎日スタジオに出勤して音楽を作る。もちろん海外へ出かけるときや休みを取りたいときは別だが、それ以外は俺は毎日ふつうに音楽の仕事をしているんだ。それをこの25年間やってきた。アプローチに変わりはないよ。俺は音楽制作という過程を楽しんでやっている。そして芸術を作ることによろこびを感じる。絵を書くのが楽しいと感じるように音楽を作るのが楽しい。あまり最終的な結果にはこだわらずに、プロセスを楽しんでいる。
ただ、セイバース・オブ・パラダイスとしてやっていたのは15年前のことだ。当然ながらいまの俺は当時の俺とはまったく違う。あれから20年間分の音楽を聴き、20年間分の人生経験やスタジオでの経験を積んだ。25年間の見習い期間をようやく終えた気分だよ。そしてようやく仕事のやり方がわかってきた感じだ。いま俺が作っている音楽は、俺の頭の中に25年前からあったサウンドだ。25年前、俺は頭のなかにあるサウンドを表現する技術力を持っていなかった。音楽を25年間やり続けて、スタジオでいろいろなことを学んでいくと、そういうことができるようになる。頭のなかにあるサウンドを、具体的な形にして最終的な作品として作りだすことができるのさ。
どの媒体でもそうだが、頭にあるイメージを実際の形にして表現するのは、長い訓練と勉強が必要だ。ただ、俺はけっして学問的にやれといっているのではない。自然に身につけていけばいいと思う。俺だってこの25年間、パソコンのマニュアルやドラムマシンのマニュアルばかりを読んできたわけじゃない。俺の身体的な技術は、ほかのエンジニアに比べるとそこまでいいものではないから、エンジニアを起用するけど、いまではエンジニアに、どのようなサウンドをイメージしているかを技術的に伝えることができる。以前は曖昧な表現でしか自分のイメージしたサウンドを伝えることができなかったからね。
■人間的にはどのように変化したと思いますか? 歳を重ねて見えてきたことはありますか?
AW:かなり落ちついた人間になったと思う。いまでは自分の地位が確立されたから、自分の作品がなかなかいいものであると自分でも信じられるようになったね。俺は長年、不安を感じていた。俺は若いころから注目を浴びて、多くの人から自分の作品がとれだけ素晴らしいかを聞かされていた。それがかえって俺を不信にさせた。俺の音楽キャリアの最初の5~6年はすさまじいスピードで進んでいった。そして俺は防御的になった。誰かが俺の正体を見破るんじゃないかと恐れていたんだ。「あいつは郊外出身の、服屋の店員だった男だ」ってね。
俺自身、俺のデキは、他人の俺に対する評価よりもよくないと思っていたんだ。でもそれが20年や25年続いていると、証明すべきものがなくなってくる。それはある意味、すでに証明されてきたからだ。25年後もその場に居つづけているということ自体が証明になっているということだ。それに気づいたときには、肩の荷が下りた気がしたよ。もちろんそれは徐々に気づいていくもので、いまでも疑問に思うときはある。もちろんその疑問を感じるのはいいことで、それがあるから前進できる。それを感じなくなったら、もう音楽はやっていないだろう。いまの俺は95%の満足感と5%の疑問で成り立っている。その5%があるから俺は前進しつづける。
とにかく、人間的にはより自信がつき、傲慢さが減ったと思う。もう証明するものはないと感じると同時にいまの立場を当然のものとしてはとらえてはいない。証明すべきものは、じつを言うとまだあるんだ。この先、25年間築き上げてきたものをそのままの状態かそれ以上にキープすることだ。俺は野心的な人間じゃないんだ。とくに目標もゴールもない。いまの状態で幸せだ(笑)。自分の仕事は大好きだし、俺のスタジオは家とはべつの場所にある。だから毎日、俺は家を出てそこへ仕事をしに行かなければいけないようにしている。俺は若い頃に家を飛び出してから、自分で仕事をして生き抜いていかなければいけないとわかっていた。その考えがいまでも身についているから、音楽を作るということに関しても毎日仕事に行くのと同じように考えている。
よく、「芸術」を生業としている人がそれを「仕事」と称すると、それを聞いた人はおかしな印象を受ける。芸術に対して屈辱的な言い方だと感じるようだ。芸術は仕事ではなく、神秘的な行為のように考えている人が多い。けど実際はそんなことはない。俺にとっては仕事だ。俺が大好きな仕事だ。だから俺のいまの立場でこの仕事をつづけられていることに対してとてもうれしく感じている。べつに昇進しようとがんばっていない。もちろんいい音楽を作ろうという野心はある。だけど、競争心はないんだ。俺が音楽の道を選んだ理由のひとつに、そういった競争というくだらないものに関わりたくないという理由があった。
さっきも俺は自分が野心家ではないと話したが、じつはそうではなくて競争心がないということなんだ。野心はあるが、競争なんてしたくない。「野心はあってもいいけどがんばるな」なんて若い人向けのメッセージとしては最低だな(笑)。
■いや、最高ですよ。今日の日本では、いちど痛い目に遭っているのにかかわらず、さらに追い打ちをかけるように競争と自立が主張されはじめています。「がんばるな」は良いメッセージでしょう(笑)。そういえば、少し前のあなたの写真を見ると、ヴィンテージなファッションを着て、古いレコードや楽器を持っています。それはちょっとしたアンビヴァレントなユーモアに見えますよね。あなたが古いモノが好きだということと、現代社会へのちょっとした皮肉というか。
AW:いやその通りだよ。当然皮肉も少し混じっている。ただ、俺はテクノロジーにとくに感嘆させられないというだけだ。現代のありように対してとくに素晴らしいことだとは思っていない。たしかに60~70年間で人間は空中飛行から、月に上陸するという宇宙飛行まで可能にした。そういうことに対してはたしかに近代の人間の可能性というものに感心するが、最新のテクノロジー機器をすべて持つ必要性は感じない。テクノロジーは俺にとってはツールだ。自分に必要ないツールは家に置いておく必要がないのと同じことだ。たとえば木を切り倒すためのノコギリは俺は持っていない――必要ないからだ。ある時期まで俺にとってパソコンは絶対不可欠のものではなかった。だが、契約書を確認するのに、わざわざ会社に出向かなくてもいいとか、仕事をする上で便利なもの、時間や経費を削減するものだということがわかった。だからパソコンを買っていまはパソコンを使っている。ライブラリーとして使うときもあるし、仕事に使うときもある。
それがはたして常識なのか皮肉なのかはわからないけど、俺のテクノロジーに対するアプローチはそんなところだ。自分の人生をよりよくすると思ったら使う。俺はiPhoneを持ってない。車のなかからメールする必要もないし、つねに自分のオフィスと連絡が取れる状態にする必要性も感じないからだ。『ニンジャフルーツ』とかいうゲームをする必要もないし、アングリーバードを投げる必要もない(笑)。iPhoneに対してステイトメントがあるとかいうのではなくて、俺には必要ないと言っているだけだ。
よく、人は俺のテクノロジーに対するアプローチを見て最初はそれを疑問に思う。「こんなにたくさんのプログラムを見逃してるよ」とか言うけど、しばらく話していると彼らは「たしかに、こういうのがなかったら俺の人生はずっといまよりもシンプルになっているな」と認める。俺は来年で50になるから、もし俺がいま18だったらもう少し違っていたかもしれない。それでも、俺が18のころを振り返ってもやはり同じだったと思う。俺はティーネイジャーの頃からそういうガジェットといったものに興味がなかった。読書に興味があった。誰かのスクリーンを見つめるよりも、自分の想像力に興味があった。それはある種の傲慢かもしれないが、それがテクノロジーに対する俺の意見だ。
俺のスタイルはたしかにユーモアが含まれていると思う。それが君に伝わってうれしい。俺が近代の生活に立ち向かっている、と思っている人も多い。俺はヴィクトリア朝やエドワード朝の衣装の美的感覚が好きなだけだ。むかしから俺は、19世紀末あたりのエドワード朝のスタイルが好きだった。だからその時代の格好をするし、テクノロジーはとくに必要性を感じないから使わないというだけだ。けど、そのふたつを合わせて、100年前の格好をして古い楽器を持っている写真を撮ったら誤解されても仕方ないね。
これはステートメントというよりは、美学の話だよ。芸術の民主化というのはいい面もあるが悪い面もある。あらゆる人が芸術に触れることができるというのはとてもいいことだと思う。ただそのアクセスのよさを利用する人間が出てくる。そうすると、膨大な量の中途半端な芸術がこの世に広まってしまう。中途半端な芸術は、悪い芸術よりもさらにひどい。悪い作品なら、話し合って何が悪いと議論できる。中途半端な芸術は誰に何のメリットももたらさない。いま、そういった中途半端な芸術がインターネットを通じて出回りすぎていると感じるよ。それがよくない面だね。インターネットについて批判するのはこれくらいにしておこうか。とにかく、俺は、ライフスタイルや服装に関しては現代の美学よりも100年前の美学を好む。そうは言っても家にパソコンはあるし、100年前の暮らしをしているわけでもない。ふたつの時代のいいところをとっているだけだ。気分によって過去に戻ったり未来へ行ったりしているよ。
俺は若いころから注目を浴びて、多くの人から自分の作品がとれだけ素晴らしいかを聞かされていた。それがかえって俺を不信にさせた。俺の音楽キャリアの最初の5~6年はすさまじいスピードで進んでいった。そして俺は防御的になった。誰かが俺の正体を見破るんじゃないかと恐れていたんだ。「あいつは郊外出身の、服屋の店員だった男だ」ってね。
 The Asphodells Ruled By Passion, Destroyed By Lust ROTTERS GOLF CLUB/ビート |
■あなたのようなレコード愛があるDJは、PC中心になった現代のDJスタイルを複雑な感情で見ていると思いますが、最近ではむしろ若い世代がデータにうんざりしてレコードを作ったりしていますよね。あなたはそういう動きをどう見ていますか? USのアンダーグラウンドなシーンでは、ヴァイナルとカセットしか出さないレーベルもありますよね。
AW:それは自然なことなんだ。それも『ルールド・バイ・パッション、デストロイド・バイ・ラスト』に当てはまる。たとえば、子どもは段ボール箱ひとつで楽しく遊べてしまう。それをお城に見立てて遊んだりしている。そこに親がクリスマス・プレゼントで新しいおもちゃを与える。子どもは興奮し、新しいおもちゃで1日ほど遊ぶ。だけど、きっと2日後にその子は再び段ボール箱でお城ごっこをして遊んでいるだろうね。結局、人間とはそんな生き物で、新しいものには情熱を感じ欲望を感じる。だが十中八九、もともとあったものでじゅうぶんだった、という結論に達するのさ。むしろ、もともとあったものの方がよかったということも多い。とくに芸術――音楽やヴィジュアル・アート――の分野においては、いままで完璧であったものを、よりクイックで簡単なもので以前のものほどよくないものに置き換えてしまった。それに最近になってみんな気づいてきたんだと思う。
シンセの場合もそうだ。当初、シンセのソフトウェアが出たときはみんな夢中になった。このプラグインがあるから、もうシンセは必要ない、と言っていた。それから5年後のみんなの感想はこうだった「これはいいけど、実際のシンセよりも音がよくないし、いじっていてシンセほど楽しくない」。そしてシンセを買い直していた。だから当初100ドルで買えたシンセがいまでは1000ドルになっている。われわれの時代の人間は新しいものに飛びつく。だが、その後に以前使っていたものの方がよかったと気づくんだ。それは人間性というものだからしかたない。同じことがレコードとデータでも起こっているということだと思うよ。
俺はべつにパソコンで音楽を作ってもいいと思う。大切なのはどう聴こえるかだ。ロー・レゾリューションのMP3の音楽は、俺にとって爪で黒板をひっかくのと同じように聴こえるが、レコードを録音してパソコンに取り込み、それをWAVファイルで再生しているのなら、問題ない。手法は何でもいいんだ。大事なのは最終的なサウンド、もしくは仕上がりだ。パソコンでアートを作ってもいいと思う。そのアートがパソコン以外の世界でも存在できると感じられることができるならね。それが最近のアートの問題だ。現実味に欠ける。パソコンのなかでしか存在しないものに感じられる。たとえそれをプリントアウトしても、スピーカーで再生して聴いたりしても、パソコンの世界でしか生きられないものに感じてしまう。
俺が好きな音楽は、たとえパソコンで作られたとしても何らかの雰囲気が感じられるものだ。どこかでレコーディングされた感じ。どこかで描かれた、撮影された感じ。そういう雰囲気を持つ芸術に興味がある。そういったことを若い人も同じように感じているのだと思う。よく若い人が俺にアドヴァイスを求めてくる。「音楽を作ったけど、音がフラットに聴こえる。どうしたらもっと生き生きとしたものにできるのか?」と。レコーディングもちゃんとやっているし、音自体も悪くない。けどフラットに聴こえる。俺はこう訊く。「パソコンから一度取り出したか?」、そうすると、していない、と言う。だから、こうアドヴァイスする。「古いテープ・レコーダーを買ってテープ・サチュレイションしてみればいい。音楽に少し息を吹き込んでから、再びパソコンに取り込めばいい」、人びとはそういうやり方に気づきはじめているのだと思う。
俺はパソコンもアナログ機材も両方使う。アナログ機材をひとつ使うだけで、サウンドをパソコンの世界から引き離して、現実性といういち面を与えることができる。そのサウンドはパソコン以外の、外の世界を経験して再びパソコンの世界に戻っていった。最近の芸術の多くはそれがされていない。現実の世界を経験していないんだよ。
■詩人ジョン・ベッチェマンがどんな人か、あなたなりに紹介してください。
AW:彼はイギリスの詩人で、20世紀のはじめに生まれて、1980年代に亡くなったと記憶している。とてもイギリス人らしい詩人で、イギリスの郊外や田舎など、とても心地よく見える情景についての詩を書いた。同時に彼には狡猾で鋭いウィットがあり、イギリスの上品で礼儀正しい生活態度は、皮をはがすと、かなりめちゃくちゃで腐敗していることを知っていた。イギリス人にジョン・ベッチェマンというと、みんな「イギリス人すぎる。ベタだ」と言ってうんざりするだろう。ジョン・ベッチェマンはイギリス人のステレオタイプを詩にしてきた人だよ。
だけど、アルバムの"レイト・フラワリング・ラスト"はとてもダークな詩で、詩の内容は、ふたりの元恋人同士が酒の勢いでヤるために再会する、という話だ。かなりダークでいかがわしいだろ? 俺はそういうイギリスらしさに惹かれるんだ。とくにヴィクトリア朝、エドワード朝の時代はイギリスは歴史的にも最高潮に達して非常に礼儀正しく上品だった。だが、その裏では、あらゆる種類のいかがわしいことがおこなわれ、ダークな部分がたくさんあった。当時は非常に整った社会で、イギリスは礼儀正しく上品とされていたが、表面を取り除いてみると、当時のイギリスは非常にダークな世界だったということがわかる。俺はジョン・ベッチェマンのそういうところに惹かれる。彼は桂冠詩人にもなった人だ。年代は忘れてしまったけど、とにかく彼の描くイギリスの二面性というものに惹かれるね。
■あなたはいろいろなスタイルのDJパーティを企画してきましたよね。『フロム・ザ・ダブル・ゴーン・チャペル』の頃は、50年代のロックンロールをかけるパーティをパブでやっていました。たしかダウンテンポの曲だけのパーティをやっているという噂を聞いたこともあります。この3年のあいだ、何かこの手のユニークなテーマのイヴェントも続けていたのでしょうか?
AW:それが〈ALFOS〉だよ。ダウンテンポばかりというか、BPM90あたりからはじめて、120BPMくらいまで持っていくんだ。3年くらい前、古い友人のショーン・ジョンストンといっしょに車でいろいろなギグに行った。そこでミッドテンポというか、少しディスコっぽくてポスト・パンクっぽい、テクノなのかハウスなのかわからない音楽にたくさん出会った。それからそういう音楽を自分たちで探して、お互いにかけたりして、ついに「こういう音楽をかけるイヴェントをやろう」という話になった。
でも、最近はみんなもう少し速めBPMが好みだからちょっと難しいかもしれないと思った。だから規模は小さめではじめよう、と言ってパブの地下でイヴェントをはじめた。キャパは100人くらい。それが2年半前くらいにはじまって、いまはみんながイヴェントのコンセプトを理解するようになってきた。3枚セットのCD『マスターピース』は、〈ALFOS〉に行ったらどんなサウンドが聴けるかというのを表現したものだ。最近はヨーロッパの各地でも〈ALFOS〉をやっているよ。イヴェントはオールナイトでやる。10時からはじまって、朝4時に終わる。もしくは12時からはじめて6時に終わる。ひと晩かけてイヴェントをやるのが大事なんだ。テンポの変化もゆっくりだから、クラウドがイヴェントの雰囲気を理解してそれにとけこむまで時間がかかる。魔法がかかるまでには時間がかかるのさ。秘薬が効くにはたくさんのミックスを必要とする。これがいまの俺のメインのプロジェクトだ。いまでもロカビリーのDJセットやテクノのセット、ハウスのセットをたまにやったりもするが、〈ALFOS〉がメインだよ。
■ちょっとロカビリー風の"ワン・ミニッツ・サイレンス"では何について歌っているんでしょうか?
AW:俺とティムはクラスターというドイツのバンドにはまっているんだけど、そのバンドの時代の特有のリズムというものがある。クラウトロックやグラム・ロックのリズムだ。俺たちはとくにそこにはまっていて、この曲を作っていたときにクラスターを聴いていたんだと思うよ。俺たちは曲を作るとき、いつもリズムとベースから入る。ドラムとベースだ。そのときもたしかティムがリズムをプログラムして、俺がベースラインを書いた。そこから曲を作り込んでいくんだ。
曲の内容について、俺はふだんあまり話したくないんだけど、この曲は多少政治的な意味を持った曲なんだ。具体名称は出さないが、ある女性が悲劇を経験した。それに対して彼女は、政府にその行為を正式に認めることを求めていた。要は、彼女の家族がテロ攻撃の被害者となった。政治的な話になってしまうから、どの国のどちら側ということは伏せておく。彼女が求めていたものは、被害者の亡くなった記念日に自分の国で1分間の沈黙を得るということだった。ただそれだけだ。その記事を読んだときに、それだけを望んでいる人もいるのだ、と気づいた。多くの人は富や名声を望む。だが、彼女が望んだものは、遺族を思うために国民にだまってもらい、静かな時間を1分間だけくれ、ということだった。それを読んで感動したんだ。だから曲の内容はそういうことだ。
俺はこういうふうに、新聞の記事をとって曲にする、ということはあまりしない。まじめになりすぎてしまうし、他人の苦しみや政治的な動きをポップ・ソングにしてしまうのはどうかと思う。価値を落としてしまう可能性がある。彼女の経験をエレクトロなアルバムの曲にしたことによって、その価値を落としていなければいいと願うよ。
「芸術」を生業としている人がそれを「仕事」と称すると、それを聞いた人はおかしな印象を受ける。芸術に対して屈辱的な言い方だと感じるようだ。芸術は仕事ではなく、神秘的な行為のように考えている人が多い。けど実際はそんなことはない。俺にとっては仕事だ。俺が大好きな仕事だ。
 The Asphodells Ruled By Passion, Destroyed By Lust ROTTERS GOLF CLUB/ビート |
■"ザ・クワイエット・ディグニティ・オブ・アンウィットネスト・ライヴズ"からはちょっとバレアリックな、80年代末のようなピースなアトモスフィアを感じます。何からこの曲はインスピレーションを得たのでしょうか?
AW:ティムがはじめエレクトロっぽいビートを作ったから、俺がそれにベースラインを書いたんだ。もともとはダブのトラックにする予定だったと思う。だから聴いてみるとダブ寄りのサウンドになっているよ。そこから曲が発展して、俺がキーボードをのせたからよりポップな感じになった。そしてティムがさらにパートを加えていく。そのとき俺たちの頭のなかにはソフト・セルの"セイ・ハロー・ウェイヴ・グッドバイ"がかかっていた。無意識的にね。そして俺は、「マーク・アーモンドに電話してヴォーカルを歌ってもらおう」なんてことを考えてた。俺がもっと金持ちで大きなレコード会社と契約していたら、たしかにそう言っていると思うけどね。そういう無意識的なソフト・セルへの愛がこめられている。ニュー・オーダーのアルバム『パワー、コラプション&ライズ(権力の美学)』の要素も入っている。それも80年代中旬な感じがする一因かもしれない。
でも最初からそういうのを意識して作ってるのではなくて、曲ができあがってから、ほかの人に「この曲は○○に似ているね」と指摘される。アルバムのすべての曲はドラムとベースラインが基本で、そこから作り上げられている。そこから曲がどう発展するのかはわからない。それがアナログ・シンセを使うよろこびでもある。すべての曲はドラムとベースラインからはじまり、シンセなどを使って、「ジャム」しながらできあがっていく。「ジャム」という表現はつまらないしロックっぽいから本当は使いたくないんだが、プロセスとしてはそういうことになる。
バンドがギターやドラムを使って徐々に曲を書いていく作業と同じように、俺たちも自然なセッションをしながら曲を作っていく。作っている曲は電子音楽だけど、手法は基本的な作曲の手法だ。お互いにパーツを作って、「これはどうかな?」とアイデアを投げ合っていく。ふたり以上の人がいっしょに音楽を作るということはそういうことだ。だから俺はエンジニアといっしょに仕事をするのが好きだし、過剰に独学で習得しようと思わない。アマチュアでいいんだ。エンジニアとのやりとりに楽しみを感じるからだ。エンジニアから学ぶのはおもしろい。
俺は50になるけど、まだ知らないことがあると認めることができるよ。すると人生はいちだんと楽なものになって、学ぶ作業も楽しく感じられる。ひとりでやる作業よりも、共同作業の方が俺にとってはずっと楽しい。最近の電子音楽を作るミュージシャンはひとり作業が好きな人もいるが、俺にとって音楽制作において好きなプロセスは共同作業の部分だ。お互いと競いあうのではなくお互いを笑わせようとする共同作業。もちろん音楽に対する態度は真剣なんだが、たまにはおもしろいことをやる。たとえば、絶対ありえないようなパーツをわざと入れる、とかね。お互いを笑わせるためだけにね。ジ・アスフォデルスはそういうふうに音楽制作をする。たとえダークな音楽を作っていても、意外な要素を入れたりして、お互いをニヤリとさせる。仕事をするにしても、楽しんで仕事をするべきだと思うんだ。会社で座っていても、向こうに座っているやつと冗談を言い合って笑う。それでいいと思う。
■そして、クローザー・トラックの"ア・ラヴ・フロム・アウター・スペース"へとつづきます。80年代末に生まれたA.R. ケインのこの曲もある種の前向きさを感じる曲ですね。この曲についてコメントをお願いします。
AW:"ア・ラヴ・フロム・アウター・スペース"は俺が長年好きな曲だった。A.R. ケインも大好きなバンドだ。イギリスの、少し変わったポスト・パンク・バンドで、"ALFOS"は俺のこれまででいちばんお気に入りのひとつに入る。あの曲には、リリースされてからずっといい思い出が残っていて、俺は曲のファンだったから、そのカヴァー・ヴァージョンは自分の頭のなかにはつねにあったよ。そしてイヴェントをやるときに〈ALFOS〉とつけて、その名前をつけたからにはヴァージョンを作らなければいけないなと思った。
曲はとてもアップ・リフティングな曲だ。俺はそれをバラードにしようなんて思わなかったけど、自分なりのヴァージョンを作りたかった。このアルバムに入っているヴァージョンは、『マスターピース』に入っているヴァージョンと少し違う。ストリングスを加えたんだ。そうすると、ハッピーな曲なんだけれど、メランコリックな要素が少し加わる。俺は鬱になったりはしないが、ものがなしい雰囲気は好きだ。メランコリックな感情というのはポジティヴだと思うから、自分が実際にメランコリックでいる状況を好むよ。だから、ハッピーな曲にものがなしさやメランコリックな要素を多少加えるのが好きなのかもしれない。
■DJはどのくらいのペースでやっているのでしょうか?
AW:毎週末だよ。俺の週末は来年の半ばまで空きがない。5年前「DJギグはいつまでもつかな」なんて思っていたけど、いまは(DJ依頼の)電話が鳴りやまないんだ。電話が鳴りやまないからいまでもつづけている。電話が鳴らなくなったらほかのことをすると思うけど、いまのところはやりつづけるよ。とても疲れる仕事だけどDJするのは楽しい。平日の4~5日間はスタジオで仕事をして、金曜と土曜はクラブでDJをすると。とても疲れるよ。だから俺にとっては仕事だね。とても素敵な仕事だとは思う。世界中を旅して、2~3時間ほかの人の音楽をかける。他人にうらやましがられる職業だ。だけど、日曜日に帰宅した俺を見ると、みんな、俺がどんなに働きものかということがみてとれるだろうね。もちろんDJはとても楽しい仕事だよ。
■UKではダブステップ以降のダンス・ミュージックがものすごく大きくなっているとききます。若い子たちはみんなレイヴによく行くそうですが、あなたは現在のUKのダンス・カルチャーをどう見ていますか?
AW:いまの時代、UKのダンス・カルチャーをほかのダンス・カルチャーと切り離すことはできない。アメリカのおかげでダンス・カルチャーは世界的なカルチャーとなり、ポップ・カルチャーとなった。情報が普及するスピードがこんなに速いおかげで、ジャスティン・ビーバーの新曲にはダブステップの要素が入っていたりする。最近はディプロがジャスティン・ビーバーといっしょに仕事をしているらしいじゃないか。アンダーグラウンドからオーバーグラウンドへの移行がすぐにできる現代では、現状をうまく分析することはできないな。
たとえば、誰かが曲を週末にレコーディングしてそれがロンドンのダブステップのクラブで翌週にプレイされ、同じ週の木曜にサウンドクラウドにアップされる。翌週の月曜日には何万人もの人がその曲を聴いている――世界中の映画会社関連の人、レコード会社関連の人、プロデューサーなども含めてだ。そういう人がそれを聴いて「いまロンドンで流行っているのはこれだ。これを使おう」と言ってその要素を自分たちのポップ・ソングに注入する。ダンス・カルチャーがポップ・カルチャーだというのはそういう意味だ。だからダンス・カルチャーに関してはこういうコメントしかできないよ。
それに、俺は自分の道は自分で決めて、その上を歩んでいくことにしている。まわりを見渡してほかに何があるのか、この先何が起こりうるかということを少しは気にするけど、この年になると方向を外れることはない。昔はよくいろんな方面に行っていたよ。ある週はドラムンべースにはまっていたり、翌週は別のことをしていたり......昔はほかの人が何をやっているかということに気を取られ過ぎていた。いまでは自分が好きなもの、やりたいことにしか集中していない。だから他のカルチャーもあまり見ていないんだ。ダブステップを聴いて、いいと思うものがあればそれが誰か探して、そこからさらにいろいろ聴いていくかもしれない。ほかの人のクラブ・カルチャーは視野に入っているけど、いまもっとも集中しているのは、自分がクラブで何をやりたいのかということだね。
■あなたはリミキサーとしてもひとつの道筋を作ってきたと人ですが、ここ最近であなたがリミックスをしたくなるような若いバンドがいたら教えてください。
AW:好きなグループを聴いて「このバンドをリミックスしたい」とはあまり思わないよ。リミックスという行為自体を批判するわけじゃないけど、世のなかにはリミックスが必要ない曲もある。大好きな曲のリミックスを頼まれたが、断った経験は何度もあるさ。オリジナルの曲が好きすぎて、リミックスをしたいと思ってもできないんだ。曲を聴いて、もうこれ以上よくならないと感じたり、反対に、自分が共感できるパートがひとつもない場合、その曲のリミックスはしない。好きな音楽は、リミックスしようと考えるのではなくて、そのままにしておくことが多いかな。
[[SplitPage]]俺はティーネイジャーの頃からそういうガジェットといったものに興味がなかった。読書に興味があった。誰かのスクリーンを見つめるよりも、自分の想像力に興味があった。それはある種の傲慢かもしれないが、それがテクノロジーに対する俺の意見だ。
 The Asphodells Ruled By Passion, Destroyed By Lust ROTTERS GOLF CLUB/ビート |
■では最近であなたを興奮させた音楽作品は何でしょうか?
AW:たくさんありすぎるよ。スタジオを歩き回って見てみよう。最近聴いている音楽が山のように積み上げられているからね。レイランド・カービィというダークなアンビエントを作るミュージシャンがいるが、その人の作品はとても好きだ。ザ・ケアテイカーという名義で活動しているが、彼のアトモスフェリックな音楽は素晴らしい。それから今年リリースされたモダン・ソウルのレコード、ヴェニス・ドーンの『サムシング・アバウト・エイプリル』はアナログ・サウンドが美しい作品で、むかしのソウル・アルバムのようなサウンドだが、それにモダンなダーク・タッチが入っている。今年のリリースで大好きな作品のひとつだね。
渋谷に6階建てのタワーレコードがあるだろう? あそこで、俺はエレクトラグライドのプロモーションとして「今年のベスト10アルバム」を紹介している。だからタワーレコードに行ってみてくれ(笑)。それから、カントリーのアルバムで『カントリー・ファンク:1960-1975』というのも好きだな。『パーソナル・スペース』という80年代のエレクトロニック音楽のコンピレーションも素晴らしい。最近のバンドでトイというバンドがいるけど、トイは好きだよ。リミックスもやった。最近聴いているのはそんなところかな。
■エメラルズやOPNのようなUSの電子音楽なんかは好きですか?
AW:両方好きだよ。とくにエメラルズは好きだね。ギターを使ったサウンドだから、スピリチュアライズドやスペクトラムのようなバンドを彷彿させる。ああいう、チラチラ光るようなメタリックなサウンドは昔から好きだよ。エメラルズの音楽はキーボードやギターを使ってそういうサウンドを表現している。それが良い。さっきの質問の答えにエメラルズも入れてくれよ。
エメラルズのサウンドはパソコンで作っているかもしれないけれど音が生き生きとしている。音に空間が感じられるから好きなんだ。けっしてフラットな音ではない。サウンドを聴くと、アップル・マークの後ろでパソコンをいじっている人のイメージではなく、どこかのスペースでレコーディングされたのだというイメージがわく。実際彼のライブをみると、アップル・マークの裏でパソコンをいじっているんだけどね(笑)。けれど彼の音楽はそれを超越している。
■家でリラックスしたいときには何を聴いていますか?
AW:家ではめったに音楽を聴かないよ。俺は週7日間、1日8時間音楽を聴いていられるという特権を与えられているからね。だから一日中音楽に関わる仕事をして、さらに帰宅して家で音楽を聴くことはあまりない。音楽関連のドキュメンタリー番組をテレビでやっていると観たりはするけど、朝11時に出勤して7時に帰宅するまではずっと音楽を聴いているから、その後にはあまり聴かないんだ。家ではたいていラジオをつけているけどBBCラジオ4で、ドラマ、ドキュメンタリー番組、ディスカッションなどいろいろな内容の番組をやっているチャンネルだね。帰宅した後はそういうことをしている。それか読書。読書していることが多いな。俺はつねに、小説、歴史、芸術に関する3冊をいっしょに置いておいて、それらを気分に合わせて読んでいる。
俺のなかで音楽とリラックスは同じカテゴリーに入らない。もちろん仕事中は椅子に座ってるからリラックスしているけれども、君の言うリラックスは頭のスイッチを切る、ということだと思う。俺は音楽がかかっているときに頭のスイッチを切るということはしないんだ。それがたとえひどい曲であっても「ひどい曲だ、なんだこのひどい曲は?」と思ってしまう(笑)。音楽に対しては、いい悪いという反応が俺のなかで絶対に生まれてしまう。だから音楽とリラックスは別物だ。そして俺はリラックス(頭のスイッチを切る)ということもしない。だから本当は瞑想やヨガなどをやるべきだと思うんだけど、俺の頭のなかはつねに時速160キロで進んでいる(笑)から無理だと思うんだ。
俺はつねに外部からのインプットを必要としている。たとえそれが風呂に10分間入っているときでもだよ。新聞か本か何かしら読んでいる。外出するときは音楽を聴かない。携帯用音楽プレイヤーは持ったことがない。音楽的インプットよりも、外の世界で起こっている情景の方がよほどおもしろい。だけど同じ場所に長い間座っていなければいけない状況のときは必ず本や新聞を持っていくよ。とにかく、音楽とリラックスは俺にとっては別物だけど、音楽でリラックスできるってことは素敵なことだね。
■いまもっとも欲しいものは何でしょうか?
AW:いまもっとも欲しいもの? それはむずかしい質問だね。いまその答えを考えて「いま欲しいものといったら、飲み物かな」と思ったら、ちょうど、スタッフのスコットくんが紅茶を入れて持ってきてくれたんだ。
■願ったり叶ったりですね!
AW:そうなんだ。完璧なタイミングでお茶を持ってきてくれた。欲しいものは手に入ったよ。とにかく、いまの状況をキープして、この仕事をつづけることかな。さっきも話したけど、俺の野心は、野心を持たずにいまの状態と同じところに居つづけるということだ。すでにほどよい量の作品を生み出したし、スタジオもいい感じで動いている。スタジオのスタッフは素晴らしい人たちばかりだ。この10年間で最高の状態になっていると思う。それ以上を願うのは欲ばりなんじゃないかと思う。もちろん世界平和や食料飢饉や飢餓をなくすという願いはあるけれど、個人レヴェルの話をすると、いまやっていることを続けるということになるね。
■なるほど。それではエレグラでお会いしましょう!




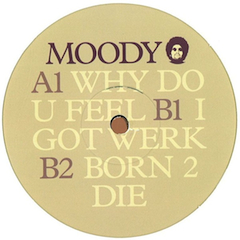








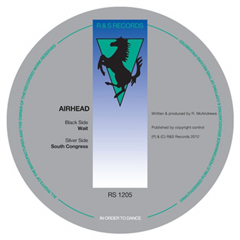





 compuma a.k.a.松永耕一。熊本生まれ。ADS、スマーフ男組として活動後、SPACE MCEE'Z(ロボ宙&ZEN LA ROCK)とのセッション、2011春にはUmi No Yeah!!!のメンバーとして、フランス他5カ国でのヨーロッパ・ツアー等を経て現在へ至る。 DJとしては,日本全国の個性溢れるさまざまな場所、そしてそこでの仲間達と、日々フレッシュでユニークなファンク世界を探求中。各所で話題となっているサウンドスケープな最新ミックスCD『Something In The Air』をリリースしたばかり。5月末には初の選曲を監修したコンピレーションCD『Soup Stock Tokyoの音楽』も〈P-VINE〉より発売予定。さまざまな選曲や音提供に音相談、レコードショップのバイヤーなど、音と音楽にまつわる様々なシーンで幅広く活動中。NEWTONE RECORDS、EL SUR RECORDS所属。SOMETHING ABOUT代表。
compuma a.k.a.松永耕一。熊本生まれ。ADS、スマーフ男組として活動後、SPACE MCEE'Z(ロボ宙&ZEN LA ROCK)とのセッション、2011春にはUmi No Yeah!!!のメンバーとして、フランス他5カ国でのヨーロッパ・ツアー等を経て現在へ至る。 DJとしては,日本全国の個性溢れるさまざまな場所、そしてそこでの仲間達と、日々フレッシュでユニークなファンク世界を探求中。各所で話題となっているサウンドスケープな最新ミックスCD『Something In The Air』をリリースしたばかり。5月末には初の選曲を監修したコンピレーションCD『Soup Stock Tokyoの音楽』も〈P-VINE〉より発売予定。さまざまな選曲や音提供に音相談、レコードショップのバイヤーなど、音と音楽にまつわる様々なシーンで幅広く活動中。NEWTONE RECORDS、EL SUR RECORDS所属。SOMETHING ABOUT代表。