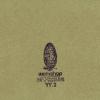MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The Caretaker- Patience (After Sebald)

三田 格 May 09,2012 UP
80年代後半に広く手法として定着したサンプリングは部分から新たな全体を目指したり、再構築することが主な目的だった。言葉を代えていえば、それは「捨てる」ことから始まる作業だったともいえる。ナップスターの登場と前後して、90年代後半にはじまったサンプリングは「捨てる」ことよりも「足す」ことに目新しさがあり、元の曲を違う角度から聴かせる側面を持っていた。マッシュ・アップもそのヴァリエイションといえ、意外な面白さを引き出した例は無数にある。ここでいう「面白さ」とは、つまり、批評性ともいえ、なかではやはり、V/Vm(ヴォリウム・ヴァーサス・マス)が際立って意表をつく発想を展開し続けた。ライオネル・リッチーのラヴ・バラッドにノイズを重ね合わせることで時代遅れのサウンドプロダクションは不明瞭なものとなり、頭の中でアップ・トゥ・デイトされたヴァージョンを想像させてみたり、なかなか次の作品を出さないエイフェックス・ツインの新作を先取りした『ヘルプエイフェックスツイン/3.0』(02)ではリチャード・D・ジェームスが過去にやってきたこととやりそうなことを掛け合わせた全11曲が架空のベスト盤のようにして並べられた。どちらもいじられているのは記憶であり、サンプリングはそれを有効にするための手段として機能している。過去のものを現在に活かすというよりは、捏造記憶を作り出し、過去そのものをサルベージしていくという感じだろうか。
V/Vmことジム・カービイは、しかし、02年に同一のタイトルで2種類の異なる内容で構成された『時々、いいことがある(Sometimes, Good Things Happen)』をリリースした後、ポップ・ミュージックの神話性に限界を見たのか、わりとストレートにヨーロッパの伝統へと立ち返っていく。インダストリアル・ミュージックの原型だと考えられるショスターコビッチの再構築がその分岐点に当たり、シャープで攻撃的だった作風は陰を潜め、以後は悲愴感あふれる作品が洪水のように続くことになる(何よりもヴィジュアルがどんどん重苦しくなっていく)。それこそ、フランコ政権のダメージからスペインが立ち直った象徴として絶賛されたペドロ・アルモドバルが、初期の軽妙洒脱なコメディから、最近は重苦しいヨーロッパの悲劇を扱うようになっていくのと同じコースに乗ったといっていいだろう。アルモドバル監督の最新作『私の、生きる肌』もそれこそギリシア悲劇とどこも変わるところはなかったし、カービイが訴えかける強烈な悲愴感も、そのような悲劇性にエクスタシーを与える以外の何物でもない。
リリース量が下降線を辿っているV/Vmの名義に変わって、このところカービイが力を注いできたのがレイランド・カービイ(裏アンビエントP240)の名義で量産される枯れたアンビエント・ミュージックと、V/Vm以前から現在に至るまでコンスタントにリリースが続いているケアテイカーのそれだろう。30年代のSP盤と降霊会をおこなうためのホーンテッド・ボールルーム(詳しくは→http://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/The_Haunted_Ballroom。アンディ・ウェザオールが題材にした『ホーンテッド・ダンスホール』はこのパロディでしょう)の喧騒を元に独特のアンビエント・ミュージックを作り出してきたケアテイカーは悪趣味なイギリス人たちの心をがっちりと掴んだようで、まさにカルト的な人気を誇り、昨年、英ファクト誌が選ぶアンビエント・アルバムのベスト20に『ア・ステアウェイ・トゥ・ザ・スターズ』(01)も選ばれたほどである(http://www.factmag.com/2011/07/19/20-best-ambient/)。悪趣味なイギリス人たちは、そして、ボビー・ビューソレイユやメインも入れてしまうし......
ケアテイカーの名義では7作目にあたる『ペイシェンス(忍耐)』は、グラント・ジー監督によるドキュメンタリーのサウンドトラック・アルバムで、2004年に交通事故で急逝したドイツの作家、W・G・ゼーバルドを題材にしたものだという(読んだことはない。文章に写真やイラストが組み合わさった独特のフォームで知られているとか。主要作はすべて白水社で訳出)。だからというか、全体にモーンフルで、様々なニュアンスを持った擦過音(やシンセサイザー?)の向こうから微かにピアノの音が聴こえてくるという手法はこれまでとまったく同じ。どこにもクレジットはなく、確かめようがないのだけれど、どれもサンプリングされているのは、おそらく30年代のSP盤なのだろう。ラフマニノフの嬰ハ単調のような曲ばかりよく集めたというか、考えようによっては失われたものを表すノイズと、記憶に関係付けられたピアノのマッシュ・アップと言えないこともない。そして、これがまたピアノしか使われていないせいか、ポスト・クラシカルに聴こえてくるところもマジックではある。インダストリアル・ミュージックがゼロ年代に入って形を変えたものがポスト・クラシカルだと位置づけている僕としては、あまりにも符号が合い過ぎて鼻白んでしまうぐらいなんだけど。
ポスト・クラシカルも、そして、ぜんぜん息が衰えない。アタラクシア、ディクタフォン、タバコニスツ、ソープ&スキンと今年に入ってからも新顔はどんどん増えていく。スフィアン・スティーヴンスが新たに結成したS / S / S (アンチコン)やクラークも新作では作風に取り入れ、デビュー・アルバムが大変な評判を呼んだベルザーリン・カルテットも4年ぶりにセカンド・アルバムをリリース。ケアテイカーのようなアート志向とは違って、スノッブな要素もそれなりに持ち込んだトーマス・ブッカーは、優しく奏でられる弦楽器に奇妙なSEを散りばめることで、トリップ・ミュージックとしても機能できる余地をふんだんに残している(ビートルズ"ア・デイ・イン・ザ・ライフ"のエンディングをザ・KLF『チル・アウト』に混合させたと思って)。完成度ではやはりファーストだろうか。方法論的な変化はなく、ヨーロッパの悲劇があっさりと高貴な恍惚感へと昇華されていく。いささか情緒過多になった分、トリップ度はアップしているので、あとは好みとか気分の問題でしょう。
放射能に消費税、本も売れないし、CDもダメで、夢も希望もないんだから、暗い音楽を聴くしかありませんなー。
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE