MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Les Gracies- Low Doses
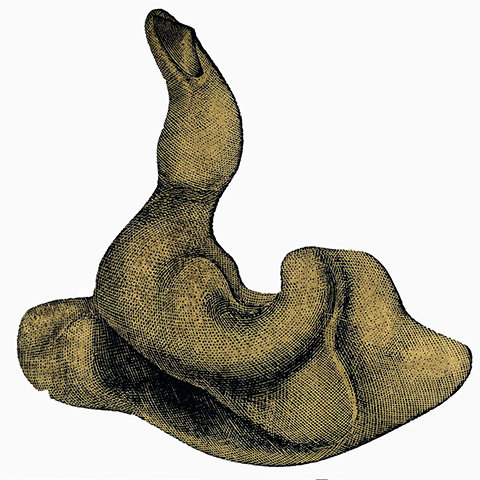
ミュージック・コンクレートや現代音楽にグルーヴを持ち込んでクラブ・ミュージックとして聴かせる発想には飽き飽きしていたというか、初期のDPIやOPNに顕著だった初期衝動を超えるような展開はなく、とくにアカデミックの側がストリートも知ってますよというサインを放っているようなものになってくると、そうした記号性だけでげんなりとしてしまって。踊らない人たちのための踊れないクラブ・ミュージックというジャンルもそれなりに需要はあるのでしょうが、どうも僕には意味がなさ過ぎて。「意味がない」が褒め言葉になるような人たちのことですけど。
初期衝動を超えるような展開。そんなものを待っていたわけではなかった。しかし、聴いてみたらレ・グレイシー(グレイシー家?)がそうだった。ディープ・ハウスのアフリカン・サイエンシィーズとサウンド・アートのアイヒアユー(iHEARu)が組んだアブストラクト・ハウスというのか、なんというのか。彼らが4年間のコラボレイトによって生み出した全7曲は最後まで現代音楽にもダンス・ミュージックにも偏らず、スリリングな定義を歩み続けていく。試行錯誤の後が見える曲は1曲もないので、最初から天才を発揮したのでなければ、初期の音源はばっさり切り捨ててしまったのだろう。と、推測したくなるぐらい「完成形」と呼びたくなるフォームがしっかりと出来上がっている。
アフリカン・サイエンシィーズことエリック・ダグラス・ポーターはディープ・ハウスの王道を歩みながらもサード・アルバムは〈パン〉からリリースしていた。そこにはすでに野心が認められた。ヴァクラのサイケデリック・ハウス・ミュージックをアルバムにまとめて世に出したファイアークラッカーもきっと次を求めていたのだろう。この結びつきだけでも充分である。また20年に及ぶフィールド・レコーディングのキャリアをガエル・セガレン(Gaël Segalen)の名義で『ランジュ・ル・サージュ(L'Ange Le Sage)』としてまとめたばかりのアイヒアユーも新鮮な経験を求めていた時期なのだろう。「命は雑音に満ちている」という考え方をしているのか、『ランジュ・ル・サージュ』自体が非常にグルーヴを感じさせるフィールド・レコーディングなので(ジェフ・ミルズがフィールド・レコーディングをやったらこんな感じか→https://www.youtube.com/watch?v=hlwM8GinaOg)、アフリカン・サイエンシィーズのビート・メイキングも無理にダンス・カルチャーと結びつける必要はなかったに違いない。どこからどこまでがどっちの資質に寄るものなのか、それさえも判然としないところがこのコラボレイションの良さである。男女という組み合わせもどこかで功を奏しているのだろう。
それにしてもキレいな音がたくさん使われている(とくにスティール・パンを多用した「パン」)。そのせいで、ワールド・ミュージックのように聴こえる瞬間も多々ある。「永遠をキャプチャーするためにはワイルドでマッドにやるしかない」と彼らは言う。この過剰さは、しかし、都会から生まれるものだろう(ここまで読んで気になった人はなんとかして“ジ・エントリー・ダンス”を聴いて欲しい)。都会こそが戦争に代わるリチュアルを必要としている。スピのつかないリチュアルを。
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE