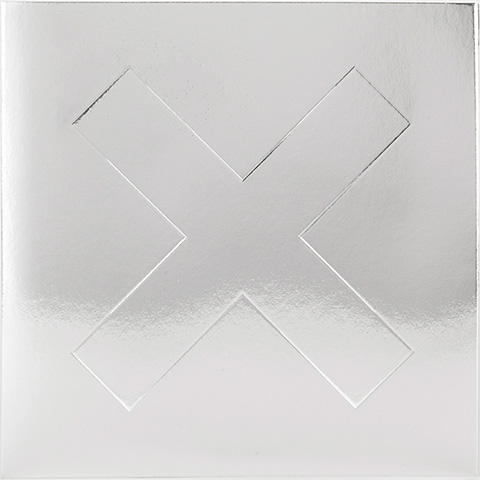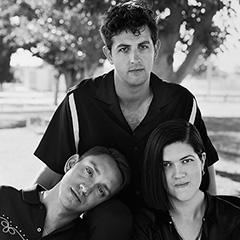MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The xx- I See You
(小川充)
ザ・エックス・エックスはデビュー・アルバムの『エックス・エックス』を2009年に発表して以来、インディ・ロックのあり方を変える存在であったと言える。ギターのロミー・マドリー・クロフトとベースのオリヴァー・シム、そしてドラムの代わりにキーボード/プログラミングのジェームズ・トーマス・スミスという変則的なトリオ編成で、デビュー当初はポスト・ダブステップやベース・ミュージックといった方面からも語られていた。それはジェームズがジェイミー・エックス・エックスという名前でDJ活動もおこない、エレクトロニック・サウンドに大きくコミットしてきたからだ。彼の存在により、ザ・エックス・エックスはインディ・ロックとクラブ・ミュージックを繋ぐ筆頭となった。ザ・エックス・エックスの音楽性そのものを見ると、ダークでメランコリックな色調を帯びたギター・サウンドが軸にあり、英国のロック・バンドに顕著なスタイルを受け継いできたと言える。繊細で今にも壊れそうな儚い魅力はロミーとオリヴァーの歌声にも顕著で、特にロミーの歌はエヴリシング・バット・ザ・ガール(EBTG)のトレイシー・ソーンに通じるところもある。EBTGは一般的にネオアコに分類されるが、スタイル・カウンシル、ワーキング・ウィーク、シャーデーなどとともに1980年代のUKニュー・ウェイヴとジャズ・ダンス・カルチャーを繋ぐ存在でもあった。ジャズやボサノヴァなどを取り入れたノスタルジックなギター・サウンドに、ソーンの淡々としてお世辞にもうまいとは言えない歌は見事にマッチしていたが、それはザ・エックス・エックスにおけるロミーの歌についても言えることだ。EBTGは1990年代半ば以降、ドラムンベースやハウスとエレクトロニックなクラブ・サウンドへと傾倒する場面が見られるのだが、それはベン・ワットがDJカルチャーに開眼し、そうした影響を受けていくことに同調する。こうして見るとジェイミー・エックス・エックスは、EBTGにおけるベン・ワットの存在とかなり被るところもあるのではないだろうか。
ジェイミーのソロ活動を見ると、2011年にギル・スコット=ヘロンの遺作となった『ウィー・アー・ニュー・ヒア』でリワークという形でコラボし、そこではUKガラージやダブステップがサウンドに大きな影をもたらしていた。それから4年後にソロ・アルバムの『イン・カラー』を発表するのだが、そこではハウス・ミュージックをはじめ、よりダンス志向を打ち出したサウンドへと変わっている。ザ・エックス・エックスのセカンド・アルバム『コエグジスト』(2012年)でも、そうしたダンス・サウンドへの接近は一部で見られていたのだが、あくまでギター・サウンドが軸のロック・バンドという形は貫いていた。『イン・カラー』はバンドという制限でできない部分をジェイミー自身が解放した作品で、ダンスという享楽性はその開放感を象徴するものであった。『イン・カラー』にはロミーとオリヴァーも参加しており、ロミーが歌う“ラウド・プレイシズ”はダンス・サウンド特有の高揚感に満ちたもので、これまでのザ・エックス・エックスにはなかった世界だ。ちなみに、この曲はアイドリス・ムハマッドのダンス・クラシック“クドゥ・ヘヴン・エヴァー・ビー・ライク・ディス”の大胆なサンプリングによって作られており、そうした楽曲制作そのものにおいてもジェイミーのDJとしての資質が露わになっている。ロミーとオリヴァーもそうしたジェイミーの姿に感化され、ザ・エックス・エックスの新作『アイ・シー・ユー』は『イン・カラー』の方法論を取り入れながら作られた。
アルバム冒頭の“デンジャラス”は、まるでファンファーレを想起させるようなホーンで幕を開ける。このポジティヴで力強いサウンドは、今までのザ・エックス・エックスの世界とは明らかに異なるもので、大地を踏みしめるようなハウス・ビートは『イン・カラー』の延長に本作があることを示している。彼ら特有のギター・サウンドによる“セイ・サムシング・ラヴィング”にしても、今までの作品にあった密室的な世界とは違い、とても開放的で外向きになっていることがわかる。『アイ・シー・ユー』を作るにあたり、メンバーはシャーデーをよく聴いていたとの逸話を聞いたのだが、確かにシャーデーをバレアリックに解釈すればこうなるのかもしれない。“リップス”のロマンティシズムも、1980年代に一世を風靡したニュー・ロマンティックを彷彿とさせるところがある。UKのメディアは『アイ・シー・ユー』について、「ジョイ・ディヴィジョンがニュー・オーダーになったときを思い起こさせる」と述べている。暗鬱としたゴシック・サウンドのジョイ・ディヴィジョンが、ロマンティシズムを携えたダンス・サウンドのニュー・オーダーへと脱皮したときのダイナミズムは、確かに本作からも感じられるに違いない。アルバム中間の“パフォーマンス”や“レプリカ”などのスロー・ナンバーは、従来のザ・エックス・エックスらしいメランコリックなギター・サウンドである。ただし、“レプリカ”におけるレイドバックしたフィーリングは、UKのゴシック的なものとは違い、バレアリックで開放感に満ちたものだ。インタヴューによるとこの曲は、ツアーでアメリカ滞在時にシアトルからLAまで海沿いを車で移動する中、フリートウッド・マックやビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』をよく聴いていて、そうしたところから着想を得て生まれた曲ということだ。“ブレイヴ・フォー・ユー”も同様に、UKのサウンドとは異なるサイケデリック感覚がある。また“テスト・ミー”のようなアンビエントもある。そして“オン・ホールド”のポップ感覚。ホール&オーツをサンプリングしたこの曲は、トロ・イ・モアとかハウ・トゥ・ドレス・ウェルあたりと同列で聴くことができるナンバーではないだろうか。
EBTG、シャーデー、ニュー・オーダーなどが台頭した1980年代半ば、振り返ると英国の音楽界はとても豊かな時代にあったと言える。1970年代後半のパンクやニュー・ウェイヴを経て、新しいアイデアを持つ者がそれを洗練された形で試していた。当時の英国は鉄の女との異名をとったサッチャー首相の政権下にあったが、サッチャー内閣は不況にあえぐ英国経済を立て直す施策を次々と成功させる一方、国際政治の場面ではフォークランド紛争に見られるように保守的で強固な姿勢を見せていた。彼女の政策には賛否両論があり、政治・経済で英国にかつての輝きを取り戻させたと評価する一方、富裕層の優遇の裏で失業者の増加、格差社会の拡大などの歪みを生んだと指摘する声もある。南アフリカのアパルトヘイト支持に対する批判など、ボブ・ゲルドフやU2のボノを筆頭にミュージシャンには反サッチャーの姿勢を見せる者が多かった。英国の音楽はいつの世も英国社会を映し出し、社会状況と密接な関係にある。そして、閉塞した状況のときほどいい音楽が生まれている。サッチャー政権において労働者階級や貧しい若者が感じた圧迫感や閉塞感が、1980年代の英国音楽を生んだとも言える。ところで、政治・経済的にサッチャーはEUの前身であるEECや欧州為替相場メカニズムのERMには反対の立場をとっており、EUについても強く批判していた(反サッチャー姿勢だったボブ・ゲルドフも、EUに関しては反対論者である)。そして、昨年の英国の国民投票でEUからの脱退が決定し、先日はメイ首相が離脱交渉方針を明らかにした。かたやアメリカ大統領にトランプが就任し、社会・経済は世界的にますます不透明な状況に置かれるのだが、そうした年の頭に『アイ・シー・ユー』がリリースされ、その冒頭が“デンジャラス”のファンファーレというのも、何だかとても象徴的ではないだろうか。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE