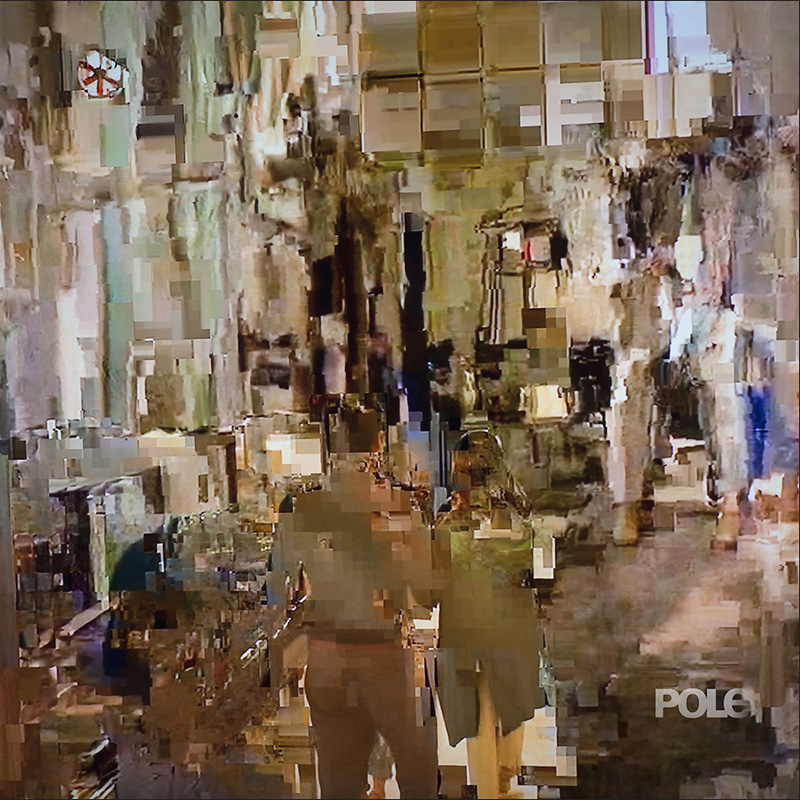MOST READ
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス
- valknee - Ordinary | バルニー
- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- 『成功したオタク』 -
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Solange - A Seat At The Table
- レア盤落札・情報
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
Home > Reviews > Album Reviews > Pole- Fading
ポールことステファン・ベトケ、5年ぶりとなるニュー・アルバムが届きました。これが絶妙な作品です。フワフワと消えては浮かぶウワモノ、淡々と進むのっぺりしたリズム隊。音響感覚にしても、ダブのミニマリズムをさらに突き進めたような、各音の配置が緻密に配慮された、どこまでも淡い存在感。アルバム1枚を再生すると、一筋の空気がゆっくりと流れていく様、それを音楽化したような、実体がなさそうな、幽霊のようなサウンドが通り抜けていきます。しかし、それでいて「鳴っている」存在感はそこにある、という、なんとも絶妙な塩梅でじわりと魅力を放ち、スルメのように……いやスルメのような濃厚な「味」や「香り」があるわけではないのですが、モヤモヤと霧が立ちこめるラスト・トラック “Fading” まで、自己主張の強すぎないそのサウンドが通り過ぎる様を幾度となく確かめたくなる。そんなアルバムとなっています。
ポール、前作からこの5年の間のディスコグラフィーとしては、クラウトロックの奇才、故コンラッド・シュニッツラーのリ “コン” ストラクト・プロジェクト『Con-Struct』に2017年に参加というのがありました(本作と連続性を感じさせる作品で、コンラッド・シュニッツラーのミニマリズムからの本作への影響はあるかも)。こちらはエレクトロニカ~サウンド・アート系のアーティストがそれぞれアルバム1枚分リコンストラクト作品をリリースするプロジェクトでありました。またもうひとつの動きとしては、ダブ・エレクトロニカの金字塔にして、自身の初期連作『1~3』のリマスタリング再・再発をリリースしています。
さて、ご存じのように、彼の本業というか、その出自はマスタリング・エンジニア。本作も彼のそんな出自とそこからくるアーティストのスタンスが結実した作品と言えるでしょう。
現在も大量の作品にマスタリング・エンジニアとしてクレジットされています。もともとはベーシック・チャンネルが設立した〈ダブプレート&マスタリング〉というカッティング/マスタリング・スタジオの技師としてキャリアをスタートさせ、2000年代に入ると独立、ヤン・イェリネックとともにレーベル〈~スケープ〉を、そして自身のマスタリング・スタジオも設立しました。レーベルではバーント・フリードマンやデッドビートらの作品もリリースし、自身の作品も含めて、エレクトロニカ世代におけるベーシック・チャンネル・フォロワーというかエレクトロニック・ダブのひとつの領域を形成します。初期三部作に代表されるそのサウンドはもちろんですが、そのエンジニアとしての「腕」も、シーンに大きな影響を与えたというのは間違いない事実でしょう。それらの音楽性の肝となる、むっちりとした低音再生やエレクトロニカ特有の高い解像度の音像を、最適に製品として成立させるというところで、彼のマスタリング・エンジニアとしての才覚は少なからずシーン形成に一役買ったのではないでしょうか。
そして彼のサウンドとして思い出すのはやはり初期三部作のグリッジ・ノイズを効果的に使った音響的発明でしょう。特に『3』で顕在化した技法ですが、それまでリスニングにおいて邪魔者でしかなかったレコ―ドのクラックル・ノイズを、微細な電子音のグリッジ・ノイズに置き換えて、その音響効果を音楽的要素として聴かせてしまったということです。その手法は、その後、それを再現するプラグインが作られたり、さまざまなアーティストも表現として援用するにいたりました。有名なところではマーク・フィッシャーがその著作でも言及したベリアルやザ・ケアテイカーの作品あたりでしょうか。この手法は、その名義の由来になった4ポール・フィルターが発するノイズ、そこから着想を経たという話になっていますが、デトロイトのプレス工場〈NSC〉でプレスされていた、少々粗めの盤面を持った初期プレスのベーシック・チャンルの作品を再生したときの感覚をふと思い出すサウンドでもあります。
こうした音響的な「ノイズ」を、テクニカルな解釈と再現をもって、ひとつの音楽性として成立させてしまう姿勢、そのあたりはエンジニアならではという感じもします。というか、彼のアーティストとしてのスタイル、根本がそのあたりにあるのではないかと。直系のベーシック・チャンネル・フォロワーでありながら、本家の「謎」と「神秘」すらまとった孤高のサウンドを、エンジニアとして、その技術力でもって解明(もしくはソフトウェアの進化で代替)し、表現として外に開いた存在という印象もあります。技術の民主化というと大げさですがその後大量に発生するベーチャン・フォロアーに道を開いたアーティストという側面は間違いなくあるかと思います。ちょっと話はそれましたが、とにかく彼のアーティストとしての表現に、エンジニアとしての姿勢がかかせないということは確かではないでしょうか。
さて、前置きが長くなりましたが、本作『Fading』は、彼のそんなエンジニア的で、ある音響的要素をアートとして昇華させる姿勢がモロに現れたサウンドではないかと思います。ちなみにプレス資料を引用したとおぼしきレコード店のコメントによれば、本作は彼の母君が煩った認知症、記憶を失いいく、その状況に着想を得て作った作品らしいのですが、それが強固にサウンドのコンセプトになっているわけではないそうです。本作のスタイルは強い表現をすれば、簡素なテクノやダウンテンポのスタイルといったところでしょう。そこにフォーマティヴなミニマル・ダブ的な要素はすでにほとんどありません。音は淡泊なのに視聴後に「なにかがあった、はず」と強烈な印象が残ります。「アレはなんだったのか」という感覚。ある種の不安感がふと好奇心になって、感情をくすぐる音楽という感じでしょうか。それ自体の印象のないことが印象的でもある。だからこそ、再度聴いてしまう、そういうアルバムです。それはあえてさまざまな要素をより簡素に、よりミニマルな要素にしても音楽として成立する、そんなエンジニアリングの方法がとられている、それが本作の肝なのでしょう。
例えば前作『Wald』はリズム・パターンも多彩だったりで、まだどこか「音楽的要素で楽しませてやろう」というリッチな感覚があります。が、本作はそうではありません。また、いままでの作品にあったレゲエ的なベースラインのミニマルな動きと低音の音響的快楽という要素もほとんど本作では使われていない印象があります。ベースラインと言えば、例えば3曲目 “Erinnerung”、4曲目 “Traum”、もしくは7曲目 “Nebelkrähe” あたりで聴けますが、どこかグルーヴを放棄したような、ただその存在を示すだけのような朴訥した表情の音がブーンと「鳴っている」だけ、パーカッションも「鳴っている」だけで、とにかく全体的にサウンドのマナーは平坦な感覚が支配しています。2曲目の “Tangente” あたりが、それでもレゲエ的なミニマルなベースラインを宿していますが、むしろ全体としてはその重心の低さに異質さすら感じます。とはいえ、不思議なことに、アルバム全体にはどこかレゲエ~ダブの存在感は亡霊のように取り憑いていて、これまた聴き返してしまう余韻を生む「謎」の要素とも言えます(とこかコニー・プランクとクラスター、メビウスによるストレンジ・レゲエの名盤『Rastakraut Pasta』を想起させもします)。
思えば初期の『3』は、グリッジ・ノイズを援用し、ミニマル・ダブの亡霊とでも言えそうな、実体を取り除いた、残り香だけの音楽を「聴かす」ことに成功しました。ある意味でエンジニア的な手法の追求による音楽的な価値観の転倒がおこなわれました。本作では、その姿勢がより精密になり、さらに進むことによって「聴かす」ことを可能にしているのではないでしょうか。もはや彼にとってミニマル・ダブのクリシェはおろか、ちょっとしたフックとなるリフも本作では必要ないといった感覚すらあります。彼のエンジニアリングが高次元に結実し、音響の「塩梅」によって、その淡い音楽性を成り立たせている絶妙なサウンド、それが本作の魅力ではないでしょうか。この「なにもなさ」の成立には裏があるのです。
河村祐介
ALBUM REVIEWS
- valknee - Ordinary
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo


 DOMMUNE
DOMMUNE