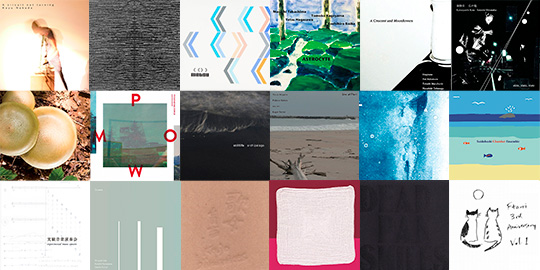MOST READ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- KEIHIN - Chaos and Order
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- 「土」の本
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん
- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定
Home > Columns > 即興音楽の新しい波- ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド
1 ハードウェア・ハッキング
ハードウェア・ハッキングというのは字義通り既成の楽器や電子機器を物理的に改変するという意味で、とりわけ実験音楽/電子音楽の世界で著名な作曲家ニコラス・コリンズによって特有の意味合いが付与されて用いられるようになった。コリンズの言わんとするところを簡潔にまとめた金子智太郎による記事(18)から引用すると、ハードウェア・ハッキングとは「電子工学の専門知識を前提としないDIY電子工作」であり、「コリンズがハードウェア・ハッキングの文化的性格として強調するのは、電子音楽における作曲家と技術者の分離の解消や、デジタル化によって減退した直接性と接触性の回復などである」。要するに必ずしも専門的な技術者ではない演奏家が、自らの手を動かし試行錯誤と実験を繰り返しながら、既成の道具に直接的な改変を施していくことによって新たなサウンドを探し出すのである。コリンズ自身が述べるように、それを「その機器の設計者すら予想しなかった結果を、あらゆる可能性に挑戦する極端な実験主義によって生みだすこと」(19)と言い表すこともできるだろう。そこには既に完成された楽器を使うことでは得られない新奇な音色の探求と、さらにそうした楽器を用いた演奏に要請される新たな身体性の獲得、およびそこから導き出される、これまでになかったような時間的/空間的な構造化への可能性が秘められている。

中田粥 - A circuit not turning
きょうRecords (2017)
Amazon
こうした方向性をもっとも過激に推し進めているひとりとして中田粥の名前を挙げることができる。東京都出身で現在は大阪に拠点を移して活動する中田は、既成のキーボードを解体し、内部の基盤を剥き出しにするとともにその回路に手を加え、独自の音響を紡ぎ出す実践をおこなっている。そうして生み出された楽器を彼は「バグシンセサイザー」と名付け、彼自身はハードウェア・ハッキングではなくリード・ガザラが提唱した「サーキット・ベンディング」の手法の応用であると言い、さらにそれをかつてジョン・ケージがピアノの内部の弦に直接ゴムや金属を挟むことでコンパクトな打楽器アンサンブルとしての音響を生み出した「プリペアド・ピアノ」における内部奏法の延長線上にある実践として捉えている。初期のバグシンセサイザーによる演奏では、自主制作したミニ・アルバムに残されているようにプリセットされた音源が断片的にあらわれていく奇妙な具象性を聴かせていたが、現在はより回路の接触から生まれる電子音響ノイズが強調されたサウンドとなっており、それは『A circuit not turning』で全面的に聴くことができる。一方でライヴでは音響を聴かせるだけではなく、小さな基盤のタワーを構築したりするなど、単なるサウンドの愉しみとしてだけでは終わらない、造形的な視覚要素と空間を生かしたインスタレーション的側面を体験することができる。
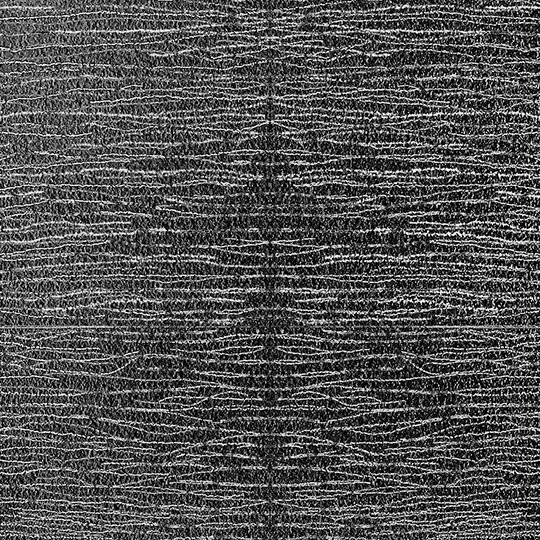
竹下勇馬 - Mechanization
Mignight Circles (2017)
Bandcamp
中田粥とも共演歴が多く、ハッキングという方法論を別の視点から極端に推し進めているもうひとりのミュージシャンとして、竹下勇馬の名前も外せない。中田とふたりで「ZZZT」というデュオ・ユニットを組んでもいる竹下は、エレクトリック・ベースに様々な自作の電子機器を取り付け、自ら「エレクトロベース」と名付けた、これまた奇っ怪な楽器を扱っている。アメリカのトランペット奏者ベン・ニールが「ミュータントランペット」と名付けた改造トランペットを使用していたことを彷彿させるが、ミュータントランペットが既存の音楽を前提とした複数の楽器パートを兼ねる異なる要素の統合を目指すものであったのに対して、エレクトロベースは統合というよりも増殖であり、異なる要素が異物のままに同居することで前提とされる音楽それ自体を問い直しにかけていく。さらにニールがSTEIMという研究所の後ろ盾のもとに楽器を発展させていったことに比すると、あくまでもDIYの精神で改変を施していく竹下の楽器はより自由な音楽へと開かれてもいる。竹下によるベースの改造はいま現在も続いており、一旦でき上がった状態に慣れるとさらにコントロールし難いものへと改変していくというのだからその実験精神は尽きることがない。演奏では通常のベースの弦の響きを織り交ぜ、それを変調するとともに複数の電子音響ノイズを併用するサウンドを生み出しており、『Mechanization』の後半においてその模様を聴くことができる。
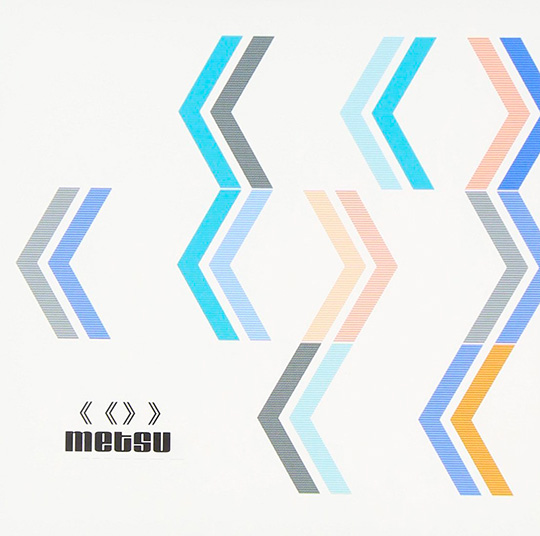
《《》》 - 《《》》
Flood (2015)
Amazon
中田粥と竹下勇馬が、ドラマーの石原雄治、ギタリストの大島輝之とともに結成した《《》》(metsu)によるアルバム『《《》》』では、ハッキングによって生み出されたふたりの楽器が、アコースティックな打楽器とエッジの効いたカッティング・ギターとともに丁々発止のやりとりをする様が収録されている――とはいえハッキングされた楽器から発されるのは肉体的というよりもテクノロジカルなエネルギーであり、レスポンスも即効性があるというよりは不確定的な要素が多く、そこが従来の即興音楽にはない面白さとも言える。このアルバムの3曲めおよび4曲めに参加しているサックス奏者の山田光は、改変こそ施していないものの、マイクロフォンやスピーカーを組み合わせることによって独自の音響をサックスから紡ぎだす演奏を試みてもいる。山田のそうした側面にフォーカスを当てたアルバムはまだ発売されていないものの、ロック・バンド「毛玉」のフロント・マンとしても知られる黒澤勇人とのデュオによる作品が近くリリースされる予定だという。すでにゼロ年代の後半から即興音楽シーンに関わってきた黒澤もまた、集音と増幅を駆使することによって、卓上に寝かせたギターから独自のエレクトロ・アコースティックなサウンドを聴かせる演奏をおこなっている。
このようにハッキングされた楽器からスピーカーを通して発される電子音は、楽器奏者との共演をおこなうことによって、電子音と楽器音が交錯するいわゆるエレクトロ・アコースティック音楽としての様相を呈していく。「エレクトロ・アコースティック」という言葉自体は、狭義には50年代の電子音と具体音を併用したレコード音楽のことを指すが、「音響」のムーヴメントと相俟って90年代以降により広く知られるところとなり、生演奏にエレクトロニクスを取り入れただけの音楽にも適用されるなど、現在では語感の良さも手伝って乱用されているきらいがある。しかし「エレクトロ・アコースティック」という考え方がもたらしたのは単に電子音と生音を併用するということだけではなく、技術の進歩などにより一方にまるで本物の楽器のような音を出す電子音があらわれ、他方には拡張され尽くした特殊奏法――これもひとつの技術革新だ――によってあたかも電子音のようなサウンドを奏でる楽器奏者があらわれ、そうした境界線の曖昧になった電子音/生音が、サウンドの平面上に同等の資格をもって立ちあらわれることによって、電子音や楽器音に歴史的に担わされてきた役割というものを、あらためて問い直す契機になったという点にこそある。そこでは音の発生源がラップトップPCなのかアコースティック楽器なのかといったことよりも、そこに一体どのような音が発生していて、それがどのように聴こえてくるのかということの方に焦点が当てられる。とりわけ「ハードウェア・ハッキング」の流れのなかから導き出されてくるエレクトロ・アコースティック音楽では、電子的なノイズと楽器の非器楽的使用による無形のサウンドが交差する傾向が強く、それを必ずしもハッキングすることのないエレクトロ・アコースティックの実践と関連づけてみることもできるだろう。
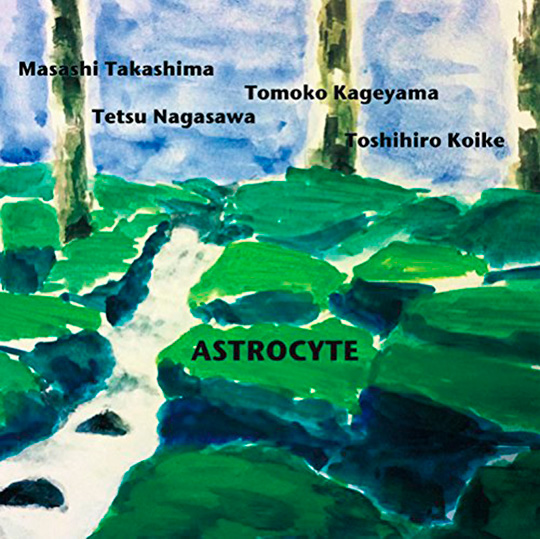
高島正志 / 影山朋子 / 長沢哲 / 古池寿浩
Astrocyte
meenna (2016)
Amazon
山田光のアイデアを取り入れることによって、独自の組み合わせからエレクトロニクス装置を生み出したドラマーの高島正志もまた、サウンドの地平をゆく固有の道を突き進んでいる。「G.I.T.M.」と名付けたその自作装置を取り入れた高島の演奏は、リズムというよりは痙攣するパルスの積み重なりを聴かせ、合奏では往年のスピリチュアル・ジャズのような陶酔感を伴っていく。他方で高島は作曲も手掛けており、そのモチベーションは自由であるはずの即興演奏が陥りがちな定型を脱することという、ギャヴィン・ブライアーズのデレク・ベイリーに対する批判を彷彿させるものがあるが、それでも彼自身はプレイヤーとして即興演奏をおこなう活動を手放してはいない。いわば彼にとっての作曲行為は即興演奏と相互に影響を与え合うような地続きのものとしてあるのだろう。現在は福島県に居住し、アジアン・ミーティング・フェスティバルにも出演したギタリストの荒川淳が郡山市で運営するスペース「studio tissue★box」で主に活動しているものの、都内でライヴをおこなうこともある。先日(5月5日)も高島の作曲作品が、竹下勇馬と石原雄治によるデュオ・ユニット「Tumo」によってリアライズされるライヴがおこなわれるなど、シーンとの交流がみられた。
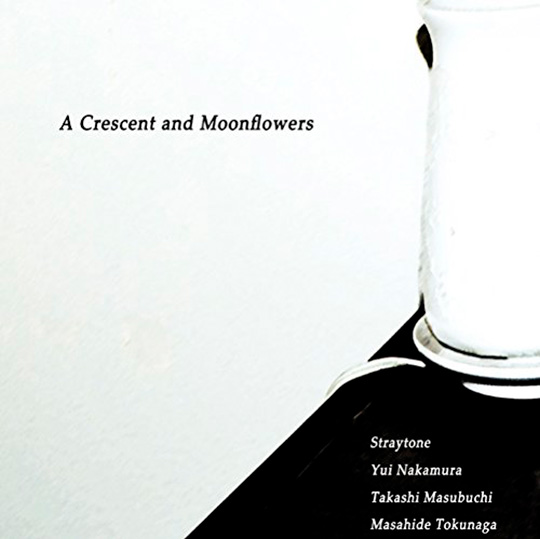
Straytone / 中村ゆい / 増渕顕史 / 徳永将豪
A Crescent and Moonflowers
meenna (2016)
Amazon
エレクトロニクス奏者と楽器奏者の共演から生まれるエレクトロ・アコースティック作品も紹介しておきたい。ミニマル・ドローンな音源の反復から電子音響を変化させていくStraytone、太く豊かな倍音を含んだサウンドを求道的に発し続けるサックス奏者・徳永将豪、12小節という定型を取り外したブルースの音響そのものに焦点を当てるかのようなギターを奏する増渕顕史によるトリオ・セッションと、声というよりも呼吸する気息の物質性をあらわにするヴォイス・パフォーマー中村ゆいが加わったカルテットによるセッションのツー・トラックを収めた『A Crescent and Moonflowers』である。管楽器のようなうねりとプリペアド・ギターのような打楽器的なサウンドを聴かせるStraytoneの演奏は、徳永と増渕による特殊奏法を取り入れた響きと混ざり合い、さらには吉田アミの「ハウリング・ヴォイス」を彷彿させる電子音響的なヴォイスを発する中村ゆいの演奏がそこに重なり合うことで、サウンドそれ自体の地平が開かれていく。そうした音像のなかから、ときおりその楽器の、あるいはその奏者にしか出せない固有の響きが前面に出てくる瞬間に立ち会うとき、サウンドの地平に照準を合わせていた耳に異化作用が施されていくというのも、こうしたセッションならではの愉しみだと言えるだろう。
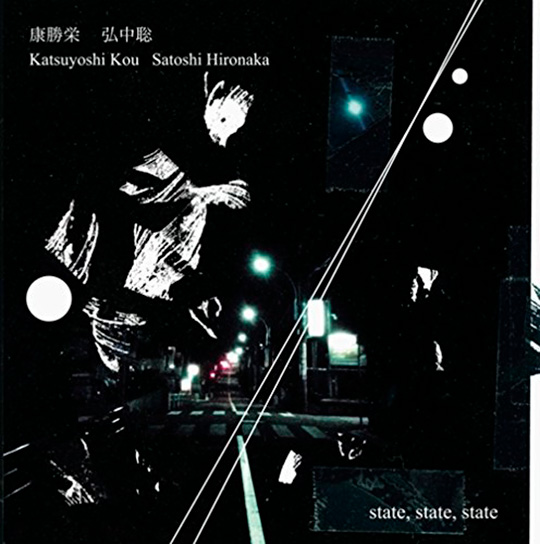
康勝栄 / 弘中聡
state, state, state
ftarri (2012)
Amazon
エレクトロ・アコースティック音楽の可能性を、あくまでも演奏を基礎としながらも、録音芸術として作品化した特筆すべきアルバムとして『state, state, state』も挙げておきたい。MultipleTapを主宰しウェブ雑誌『20hz』を発行するなど、日本のインディペンデントな音楽シーンを精力的に紹介し続け、クライヴ・ベルにも「これらの音楽を取り巻く環境を、特に日本において変えていくという使命を負っている」(20)と評された康勝栄と、変則的で巧妙にデザインされたリズムがラップのフロウを新鮮に聴かせるバンドskillkillsなどで活躍するドラマーの弘中聡によるデュオ作品である。僅かにポスト・プロダクションが施されたデュオ演奏とそれぞれのソロ、そして録音されたままのデュオ演奏が収録された本盤は、エレクトロ・アコースティックという考え方によって演奏をサウンドの地平で捉えられるようになったはずのわたしたちの耳が、それでも音盤上で施される改変によって本来の演奏を想起してしまうということ、しかし手を加えないことが本来の演奏と呼べるものなのかどうかということなどを、スタイリッシュなビートとともに提示している。すでに5年前の作品であり、とりわけ康の現在の活動はギターよりも自作エレクトロニクス装置を用いた演奏をする機会が多くなっているものの、そうした問題提起する射程の深さを伴うこの作品の特異性はまったく古びていない。
註
(18)金子智太郎「ハードウェア・ハッキング」(http://artscape.jp/artword/index.php/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0)
(19)ニコラス・コリンズ『Handmade Electronic Music』(久保田晃弘監訳、船田巧訳、オライリージャパン、2013年)。厳密には、ここでのコリンズの発言はハッキングの一種である「サーキット・ベンディング」について述べられたもの。
(20)クライヴ・ベル、前掲論文。
COLUMNS
- Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns
Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025


 DOMMUNE
DOMMUNE