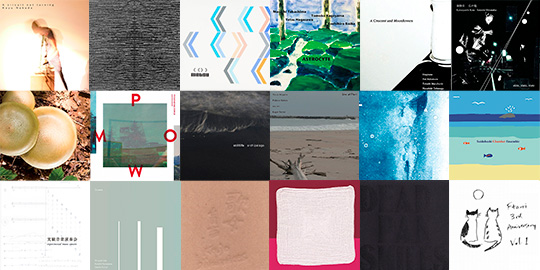MOST READ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- KEIHIN - Chaos and Order
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- 「土」の本
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん
- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定
Home > Columns > 即興音楽の新しい波- ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド
2 ライヴ・インスタレーション
かつてデュオ・ライヴをおこなった川口貴大と大城真は、それを観た米国のとあるレーベル・プロデューサーから「これはインスタレーション系だ」と評されたことがあるという。要するに「こんなものは音楽ではない」という否定的なニュアンスが含まれた評価を受けたのだが、むしろそうした評価を、従来の音楽概念では評価しきれないような、しかしあくまでも音を介した新しいパフォーマンスとの出会いから発された言葉として、ポジティヴに受け止めることもできるだろう。今年の春に出版された大友良英による好著『音楽と美術のあいだ』でも提示されていた、音楽とも美術ともつかないそうした新たな表現領域――あるいは領域から逸脱する表現のありよう――を、しかし美術に基軸を置いた音の展示ではなく、あくまでも音楽の現場で「演奏」としてなされている、いわば「ライヴ・インスタレーション」とも言える実践を眺めることから、その実態を探っていきたい。ここで紹介するミュージシャンたちの多くはアート・スペースに設置されるような音の展示作品も制作しており、いわゆるライヴハウスのような音楽のために設けられた場においても、空間と大きく関わるようなリアルタイムの反応と操作をおこないながら、投げ出された音の行方を見守るという非常に独特な「演奏」をおこなっている。こうした動向については、音楽家/評論家のデイヴィッド・トゥープによって「フェノメノロジスト」という呼称が用いられてもいる(21)。

川口貴大 / ユタカワサキ
Amorphous Spores
Erstwhile Records (2015)
Erstwhile Records
川口貴大はもともとフィールド・レコーディング作品の制作からそのキャリアを出発させながらも、ゼロ年代の半ばにはすでに会場内を歩き回りながら自作の音具を設置していくという特異なパフォーマンスをおこなっていた。『n』に結実するそうした方向性は、その後、大城真、矢代諭史とともに結成したグループ「夏の大△」へと受け継がれるとともに、より演奏に比重を置いた新たな表現を開発していった。複数のヤンキーホーンと音叉、さらには臓器のように伸縮する巨大なビニール袋とスマートフォンの光を用いたパフォーマンスでは、演奏の進行と展開を共演者に対する反応ではなくビニール袋の動きに合わせるという、非常に独特な即興演奏の取り組み方をしている。共演者との相互触発から反応の応酬を聴かせるのではなく、もっと人間の世界から離れた物と物の相互作用を提示するかのような川口のパフォーマンスは、その見た目の異様さもさることながら、どこにでもある日用品の匿名性とは裏腹に、彼にしか生み出せない個性的なサウンドを奏でることにも成功している。ユタカワサキとのデュオ・セッションにポスト・プロダクションを施すことで完成した『Amorphous Spores』で聴くことができるのは、人間の身体的な動作からは切り離されたところにある音響に刻まれた、しかし紛れもない彼の個性である。

大城真
Phenomenal World
hitorri (2014)
Amazon
匿名的かつ個性的なサウンドは大城真が自作した通称「カチカチ」からも聴くことができる。かつてはヴィデオ・フィードバック現象を音楽として提示し、その後も「ウネリオン」と名付けた独自のフィードバックを発生させる楽器を自作するなどしてきた大城は、よりコンパクトに持ち運びの出来る形態として手のひらに収まるサイズの「カチカチ」を生み出した。会場内を歩き回るパフォーマンスは、ともに「夏の大△」で活動する川口貴大の初期の試みを彷彿させるところがあるが、至る所に設置された「カチカチ」が生み出す即物的な音響のアンサンブルがサウンドのモアレを形成するところなどは、独自に取り組んできたフィードバック現象の実践からの形跡を感じさせる。ヴィデオ・フィードバック、ウネリオン、「カチカチ」などを全て収録した、大城の活動の集大成ともいうべき作品が『Phenomenal World』である。彼自身の「現象としての音や、その発生の仕組みへの興味」(22)があらわされている本盤のタイトルからは、現象学を出発点に非人間的なオブジェクトに立脚する哲学を構想するという、グレアム・ハーマンの「オブジェクト指向存在論」を連想させるところがある。ただしそうした現代の思想動向の実体化や反映を彼の音楽に見出すことよりも、まずは様々にあらわれるサウンドに対する興味と驚きが根底にあるのだということには注意しなければならないだろう。
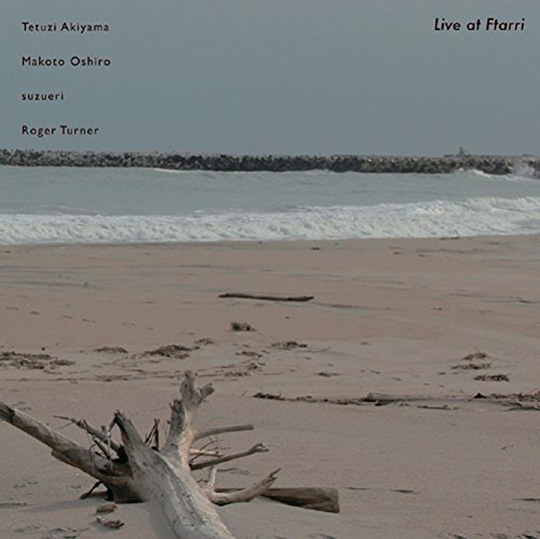
秋山徹次 / 大城真 / すずえり / Roger Turner
Live at Ftarri
meenna (2016)
Amazon
今年の初めにイングランド北西の都市マンチェスターで大城真とともに展示およびライヴをおこなったすずえりの近年の活動にも非常に興味深いものがある。アコースティック・ピアノ、大小のトイピアノ、それにさらに小さな模型のピアノを連結し、「ピアノでピアノを弾く」という実にユニークな展示作品を手掛けるすずえりは、ライヴにおいても複数の「ピアノ」を用いながらそのユニークネスを発揮したパフォーマンスを繰り広げている。会場で何かを制作しようとしているものの、それにしてはあまりにも非合理的で非効率的なプロセスを踏んでいくことが、むしろ自作した音具たちの連関を生み出していくそのパフォーマンスは、従来の演奏概念とはまったく別のところから「即興」の醍醐味を聴かせてくれる。肩肘張らない脱力した佇まいもまた、しかつめらしく状況を見守る即興演奏とは別の緊迫感を生み出していく。残念ながら彼女のこうした側面を捉えた音盤はまだリリースされていないものの――とはいえ、彼女の面白さは音盤にはならないライヴのプロセスにこそあるともいえる。なので反対に、それをどのようにサウンドとして定着するのかは非常に気になるところだ――大城真、秋山徹次、それにロジャー・ターナーとのカルテットによるセッションを収めたアルバム『Live at Ftarri』でその特異な実践を垣間見ることができるだろう。
音盤として残された彼ら/彼女らの実践は、あくまでも変化するサウンドの妙味にその魅力があらわれているわけだが、ライヴや展示においては「装置の実用性や象徴性ではなく、装置同士のネットワークや、物質が人間にもたらす影響」(23)とも言われるような、人間中心主義的な世界を離れた音たちが織り成していく、オブジェクトの相互作用のようなものを形成することの面白味がある。多くの場合ハッキングした自作音具を用いながらも、それをスピーカーから電子音として鳴らすのではなく、あくまでもアコースティックな響きとして空間に配置していくということも、現象する音の環境世界を提示しようとすることと無関係ではないだろう。それは「演奏」というよりも、人間に従属することのない音の発生を、制御不能なままに見届けようとするある種の「聴取」行為とも言える。こうした点から、まったく別の試みであるように思えながらもフィールド・レコーディングという実践との近似性が浮かび上がってくる。フィールド・レコーディングもまた、人間の世界を離れた音の環境を相手取っていく試みだからである。言うまでもなくそれをどのように切り取るのか、すなわち聴取する耳をどこに設定するのかということがフィールド・レコーディングの要であり、それは必ずしも聴くことによって視点を切り取ることが要点ではないインスタレーションの在り方とは異なっている。しかし耳の先で起こる出来事を人間が従属させることはできないのであって、とりわけそうした聴取の実践をライヴ空間でおこなうミュージシャンにあっては、そこでわたしたちが立ち会うこととなるのは出演者たちに同化した耳の視点ではなく、むしろ彼ら/彼女らが聴き、聴こうとし、それでも聴くことの外部へと溢れてしまうような音の生態系であるだろう。

stilllife
archipelago
ftarri (2015)
Amazon
笹島裕樹と津田貴司のふたりによって結成されたstillifeは、フィールド・レコーディングをライヴにおける「演奏」としておこなう非常にユニークなデュオ・ユニットである。彼らのライヴでは、オートハープや木製の笛、音叉、小石、ガラス瓶その他無数の音具と、集音し変調するエレクトロニクス装置などを用いながらも、それらは一般的な音楽の演奏においてホワイト・キャンバスに描かれる絵のようにあるのではなく、むしろその場の環境やライヴをおこなう会場にすでにある様々に彩られたキャンバスを前にして、その背景が決してまっさらな沈黙ではないことを明かすかのように挿入されていく響きとしてある。言うまでもなく、彼らがそこで聴き取ろうとするサウンドは、観客であるわたしたちと同一のものではない。むしろ聴き取ろうとする彼らの「演奏」によって浮かび上がる音の世界が、わたしたちひとりひとりに固有の聴取の位置を与える契機となっていく。しかしだからこそ、彼らの音盤はライヴであらわされる音楽とはまったく別の価値を帯びもする。傑作ファースト・アルバム『夜のカタログ』の翌年にリリースされた『archipelago』では、あたかも電子音楽のような即物性を伴って響く鳥の鳴き声が、最終的にはそれが他ならぬ「鳥の声」という意味にまみれたサウンドでしかなかったということに、思わず気づかせるような工夫が凝らされていて、それは録音作品ならではのstillifeの「耳」の刻みかたとも言えるだろう。
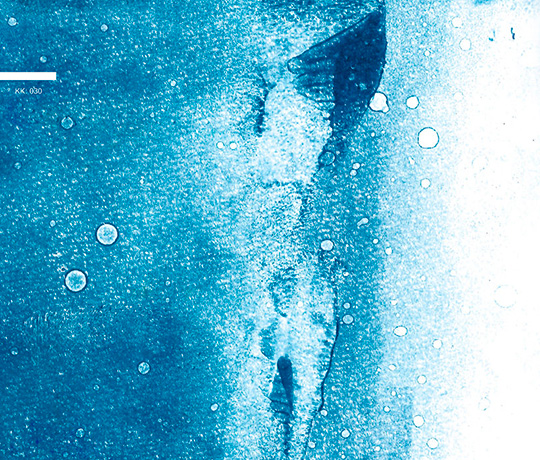
松本一哉
水のかたち
SPEKK (2015)
Amazon
stillifeのメンバーでもある津田貴司と、ベースを用いた特異なドローン/倍音を奏でてきたTAMARUとともに、昨年からは「Les Trois Poires」というグループでも活動をおこないながら、独自のフィールド・レコーディング作品を残しているアーティストとして、打楽器奏者の松本一哉の名前を挙げることもできる。「自分が指揮者になったように音を選んで聴けば、身の回りには常に偶然に作曲された音楽が溢れている」(24)と語る彼が、「偶然のオーケストラに奏者として自分が音を足すことで、全く別の聴き方ができたり、もっと違う楽しみができたり、今まで体感したことのない新しい価値を見出せる」(25)ということを念頭に置いておこなった環境音とのセッションが、『水のかたち』には収められている。全編が「ありのまま」に収録された本盤からは、「波紋音」をはじめとした複数の音具を用いた、水琴窟での数回にわたる演奏から、長野県根羽村に固有の独特な鳴き声を持つ蛙との演奏、梅雨明けに突然訪れるひぐらしとの演奏、あるいは浜辺に打ち寄せる波音との演奏など、水をテーマに様々な場所でおこなわれた「セッション」の記録を聴くことができる。打楽器奏者ならではのリズミカルな演奏もおこなう松本の音楽が、しかしときおり環境音なのか彼の打音なのかわからなくなる瞬間に立ち会うとき、「偶然のオーケストラ」が詩的な方便やケージ主義的な認識論ではなく、極めて具体的なサウンドのありようを指しているのだということがわかる。
註
(21)David Toop “Can SOUND”, The Wire 400, June 2017.
(22)『Phenomenal World』、大城真によるライナーノーツより。
(23)金子智太郎「音の展開2014」(http://artscape.jp/dictionary/newword2014/contents/10101391_18765.html)。なお、同論考では「ハードウェア・ハッキング」がいわゆるサウンド・アートの文脈で取り上げられているものの、本稿では竹下勇馬のようにより演奏の性格が強いアーティストのハッキングの事例を紹介するため、また、川口貴大のようにハッキングをすることはないものの音の展示の性格が強いアーティストを紹介するため、これらを別の項目として立てることにした。
(24)『水のかたち』、松本一哉によるライナーノーツより。
(25)同前。
COLUMNS
- Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns
Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025


 DOMMUNE
DOMMUNE