MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Regulars > チクチクビー、チクチクビー > 第1回 前野健太が自分から語りたがっているようには見えなくて
仕事の場面で誰かを誰かに紹介することは多い。このところ、そのような場面でいきなり自分のことを克明に「説明」する人が増え、いささか面食らっている。え、なんで、それ、いま、必要? ......と思った時にはもう遅い。それは売込みとも違うし、本人に自覚があるのかすら怪しい。とにかく僕からしてみれば突拍子もなく、リアクションがまったく思いつかない。困ったとしかいいようがない。
菊地成孔がフロイトを持ち出した辺りからそれははじまっていたのかもしれない。僕の記憶ではECDがまずはそれを新たなステージに上げ、海猫沢めろんや香山リカがその後に続き、『モーニング・ツー』ではじまった新連載を読むと、西島大介も同じことをはじめようとしているように見える(雨宮処凛や吉田アミもそうなのかな?)。そう、00年代に人気が出た人たちは、なぜかこぞって「自分語り」に手を染めている。西島の連載を指して僕がそういうと、NUの戸塚くんは「そういえば佐々木敦の新書も自伝に読めなくもない」といい、それを聞いていたタキシムが「実際に、次は自伝を書いているようですよ」と会話に割り込んできた。本当かどうかは知らない。すでに自伝として読めなくもない本が書かれているというのだから、それで充分だろう。僕たちはその時、クアトロにいた。31年ぶりに聴いたフューの演奏が終わり、初めて聴く前野健太のステージがはじまる直前ではなかったかと思う。自分探しの90年代から自分語りの00年代へ。『SPA!』の中吊り広告じゃないんだから。
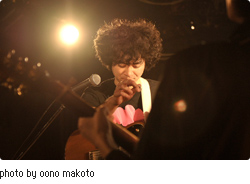 「自分はない」というのが80年代の流行りだった。蓮見重彦の文章からは主体を指し示す指示代名詞が消えてなくなり、思想界というところでは「私は」とか「僕は」と書く人は跡形もいなくなった。例外は粉川哲夫と栗本慎一郎だけで、僕はこの2人にフィリップ・K・ディックについて書いてもらうことにした(『あぶくの城』)。フィリップ・K・ディックの小説もまた主体がはっきりしていないものが多い。『ヴァリス』が4重人格の話ではないかと思うようになったのは、だいぶ後のことだった。
「自分はない」というのが80年代の流行りだった。蓮見重彦の文章からは主体を指し示す指示代名詞が消えてなくなり、思想界というところでは「私は」とか「僕は」と書く人は跡形もいなくなった。例外は粉川哲夫と栗本慎一郎だけで、僕はこの2人にフィリップ・K・ディックについて書いてもらうことにした(『あぶくの城』)。フィリップ・K・ディックの小説もまた主体がはっきりしていないものが多い。『ヴァリス』が4重人格の話ではないかと思うようになったのは、だいぶ後のことだった。
自分について語る人は、だから、あまりいなくなってしまった。それまでは全共闘の昔話が主流だった。その代わりにモノについて語る人が増え、10年も経たないうちに「おたく」というタームが広まった。それもまた異常なことだと認識されることになっても、自分の話をする人が戻ってきたわけではない。合コンで自分のことばかり話す人が嫌われるのと同じようなものだろう。ジャック・ラカンやマリリン・モンローの「自分語り」なら聞きたかった人たちもそれなりにいただろうけれど、どう考えても一般にその流れが戻ってくるとは思えない。自分の話をひとつの例として、ある種の普遍性に還元するんだという意気込みがある場合もあるだろう。マイケル・ジャクスンや『ベンジャミン・バトン』のようにあまりにも特殊な話なので、単なる自分語りとは違うんだと主張する向きもあるだろう。それぞれの動機というものはわからないし、そこまで踏み込む気はない。しかし、それは同時多発的に増え、いまや、僕の会議の席にも押し寄せてきている。少しばかり辟易とさせてもらうことは許してもらえるだろうか。
 ECDも海猫沢めろんも香山リカも西島大介も佐々木敦もすべてに目を通して共通していえることがあれば、この文章も締まったものになるはずだったけれど、しまった......どれも読んでいなかった。とくに友だちのことはあまり詳しく知りたくないということもある。クラブで知り合った人たちとは、いつも、そのように付き合ってきたし、その方がいざとなったら助け合うことは容易だから(ほかではどうなのか知らないけど、クラブで知り合った友人たちはよくわかっていないからむしろ助け合っているとしか思えないことが多い。よく知っていたらとても助ける気にはならないとでもいうように)。そういえば、クアトロのライヴで前野健太がMCで話していた『ライヴ・テープ』を観て、彼が吉祥寺の街を歌いながら歩き続けるシーンはとてもよかったのに(それだけの映画なんだけど)、エンディング近くになって監督が前野健太に歌をはじめた動機を尋ねることですべてが台無しになってしまったような気がした。
ECDも海猫沢めろんも香山リカも西島大介も佐々木敦もすべてに目を通して共通していえることがあれば、この文章も締まったものになるはずだったけれど、しまった......どれも読んでいなかった。とくに友だちのことはあまり詳しく知りたくないということもある。クラブで知り合った人たちとは、いつも、そのように付き合ってきたし、その方がいざとなったら助け合うことは容易だから(ほかではどうなのか知らないけど、クラブで知り合った友人たちはよくわかっていないからむしろ助け合っているとしか思えないことが多い。よく知っていたらとても助ける気にはならないとでもいうように)。そういえば、クアトロのライヴで前野健太がMCで話していた『ライヴ・テープ』を観て、彼が吉祥寺の街を歌いながら歩き続けるシーンはとてもよかったのに(それだけの映画なんだけど)、エンディング近くになって監督が前野健太に歌をはじめた動機を尋ねることですべてが台無しになってしまったような気がした。
彼が歌いながら歩いているシーンはさながら「ひとりサウンドデモ」で、誰ひとり彼のことを振り返らないことや、誰も彼の歌を聴こうとしないために、外に出て大声で歌っているのに引きこもりのように見えてしまうということが世の中との距離感をはっきりと印象付け、それこそテロリストにさえ見えかねなかったのに、彼の個人史がそこで顕わにされることで、その辺にいた人たちとあまり変わらないものに思えてきたのだ。街のなかにあって宙に浮いていた彼の歌を世の中に接着させるもの。それが彼の(強制された)「自分語り」だとしたら、いま、自ら進んで自分語りを行うということは、この世界で無条件に浮いていることに辛さを覚えるようになった人気者たちがどこかに接着されたくて......ま、やめときましょう。どれも読んでもいないし、多分、間違っているし。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE




