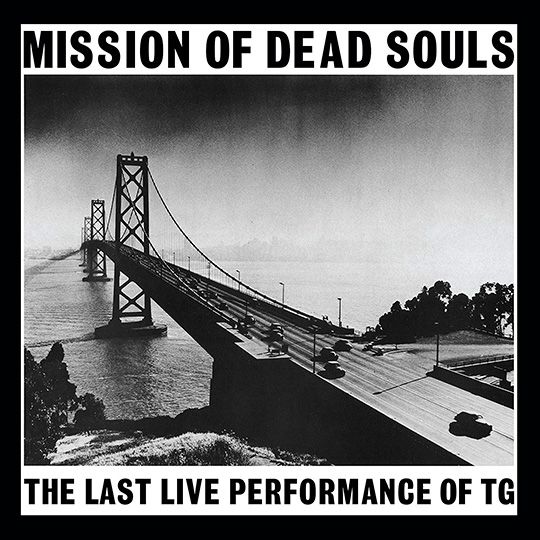MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Interviews > interview with Cosey Fanni Tutti - スロッビング・グリッスルを語る
それがTGであれ、あるいはそれ以外のプロジェクトであれ、わたしたちがこれまでにやってきたことが去ってしまった、それらが自分たちにとって完全な「過去」になってしまったことは一度としてなかったし。
 Throbbing Gristle The Second Annual Report Mute/トラフィック |
 Throbbing Gristle 20 Jazz Funk Greats Mute/トラフィック |
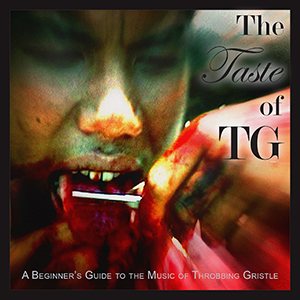 Throbbing Gristle The Taste of TG Mute/トラフィック |
■後に“ヴェリー・フレンドリー”や“スラグ・ベイト” が生まれるような土壌は、60年代末から70年代初頭のロンドンにはあったのでしょうか?
それとも、COUMトランスミッションズやTGのみが突然変異だったのでしょうか?
コージー:まあ、わたしたちはラヴ・ソングは歌わなかったわよね。
■(笑)。「ラヴ&ピース」はTGの味ではなかった、と。
コージー:とにかく、わたしたちは人間のなかにある暗部、よりダークな状態について歌っていた。で、それは愛について歌うのと同じくらい重要なことなのよ。というのも、そうした暗部を抑圧すればするほど、状況はますます悪化していくわけで。それに、かつての70年代イギリスというのは、とにかくダークだったしね。数々の政治的な変動が起きたし、人びとは貧困に苦しんでいて、ストライキも多かった。だから、とてもハードな時期だったわね、あの、60年代終わりの頃から70年代に入っていく、あの頃は非常にハードだった……で、わたしたちはとにかく、自分たちの日常で、そして他の誰もの日常で起きている様々な物事に注意を向けようとしていた、それだけのこと。
■あの頃のバンドあるいはアート集団なりで、当時のあなたたちからしても共感できた、同じようなことをやっていてシンパシーを抱けた、そういう人びとは他にいましたか?
コージー:それはまあ、わたしたちが自分のレーベルを通じてレコードを発表することにした、そういう人たちのことよね。そういう人びとには共感を抱いたし、他にも活動を通じて出会った面々がいた……ただ、そうは言ってもそれはごくごく少数の、小さなサークルではあったんだけどね。正直、そう。
■ええ。
コージー:だから、パンクも当時起きていたわけだけれども、パンク勢とわたしたちとは、非常に性質の違うものだったから。というのも、パンクというのは……あれはこう、なんだかんだ言ったってメインストリーム音楽の一端に属するもので、「レコード契約をモノにしよう、売ろう」云々の思惑が混じる、そういう類いのものだった、というか。わたしたちのやろうとしていたのは、そういうことではなかったし。
■でも、そのパンクの側は、きっと75年、76年あたりのTGの作品や活動ぶりから何らかのインスピレーションを受け取っていたんじゃないでしょうか?
コージー:いいえ、それはないわね。彼らはわたしたちとは別物だったし、彼らの進んでいた方向とわたしたちのそれとは接したことがない、お互いまったく別の道筋をたどっていた。というのも、彼らのやっていたのは要はロックンロールだったんだし、わたしたちがやっていたのはロックンロールとは完全に無縁な何か、だったから。
■ヌード・モデルやストリッパーはぶっちゃけ生活のためにやったのでしょうか? それとも芸術的野心があってのことなのですか?
コージー:あれはとにかく、わたしが自分のアートのために、自分自身に課したプロジェクトだったわ。で……そうね、受け取ったモデル料等々はたしかに役に立ったし、いくつかのプロジェクトの資金、COUM作品に使うアート素材の購入だとかに充てたこともあった。それとか、家賃光熱費etcの一部になったり。だけど、ああした仕事と同時に、わたしは普通の9時5時仕事の職にだって就いたわけだし、そうでもしないと食べていけなかった。それくらい、当時は悪戦苦闘していたから。だから、モデル仕事やストリッパー云々は、まず何よりも第一に、自分のアート・プロジェクトのためにやっていたことだった、と。
それもあったし、第二の要素として、モデル/ストリップ業は定期的な仕事ではなかったし、だからどうがんばっても一定の収入をもたらす職業、生活を支えるだけの収入源にはなりっこなかった。というのも、ヌード・モデルにしたってオーディションを受けなくちゃいけないし、そこで「彼女はこの仕事には不向き、不採用」なんて結果になることだってあるわけで。だから、誰かが「そうだ、自分は裸体モデルになろう!」と思い立ったとしても、その意志だけで募集側がすぐ「それは素晴らしい! じゃあ彼女にこの仕事をあげることにしよう」と反応して「月―金の毎週5日勤務で、○年間あなたを採用します」なんて話にはなりっこない、と。彼らは目的にマッチした特定の体型、特定のタイプの女性を見つけようとしていたんだし。だからあの手の仕事というのは、とてもじゃないけれど、週給/月給単位で自分に生活費をもたらしてくれるような、そういう「安定した職」としてやっていたことではなかった、という。それはどうしたって無理な話。それに、いまと較べてどうなのか? は自分にもわからないけれど、とくにお給料の良い仕事というわけでもなかったしね、当時は。
■ああ、そうだったんですか。
コージー:仕事の内容そのものはいまと同じように複雑だったけれども、でも、別に割のいい仕事ではなかったし。
■いや、当時のあなたはかなりこう、派手でバーレスクめいたこともやっていたわけで、だから結構お金をもらえていたのかな?と感じたんですが、そういうわけではなかった、と。
コージー:いいえ、まったくそういうものではなかったわ(笑)。
■あなたがセックスやセクシャリティといったサブジェクトを扱うようになった経緯について教えて下さい。
コージー:それはまあ、以前のわたしは、コラージュ作品をたくさんやっていたからなのね。そうした作品で、自分のヌード写真が掲載されたセックス雑誌を使ってコラージュをやっていたわけ(※個展でも、アメリカ80年代の『Partner』というハード系ポルノ雑誌に掲載された彼女のヌード・グラビアとインタヴュー記事を用いたコラージュ作が展示されていた)。あそこからだったわね、本格的にセックス/セクシャリティが題材になっていったのは。だから自分でも「よし、これなら自分にも続けられる」と思った、というか。少なくとも自分はあれらのイメージの背後にあるストーリーを理解しているし、ああしたイメージを生み出す経験が実際どういうものかも知っているわけだから。
それに、さっきあなたが言っていたことと少し似ているけれども、「自分をオープンにしてさらけ出す」、ということなのよね。だから、少なくとも自分が実際に体験したことではない限り、その題材を扱うことに意味はないんじゃないか、わたしはそう思っていて。
■ええ。
コージー:で……ただ、自分は嘘はごめんだ、というのか。嘘ではなく真実を、とにかく自分の作品のなかには真実の要素が含まれていなくてはならない、と。それに正直な話、もしもわたしが他の人間のやった仕事──その人間が裸になって撮影されたグラビア写真であれ、何であれ──他者の仕事を使って自分のコラージュ作品をつくろうとするのなら、やっぱり自分はそこで、彼らに対してのリスペクトの念を持ちたいと思う。彼らがどこからやって来て、これまでにどんな体験をくぐってここに至った人なのか、そうした面をちゃんと知りたい。
それに、ヌード写真というのは、当時は興味をそそられる、魅惑的な対象でもあったわけで。というのも、いまのようにインターネットのどこにでも裸体やポルノが氾濫している、そういう時代ではなかったし、そもそもインターネットすら存在しなかったわけで。ああいう雑誌を手に入れるには、裏ルート、セックス・ショップの奥の秘密の部屋に行くしかなかった。だから、あそこにはある種のミステリーも関わっていたし、わたしはそこに興味をそそられもした。
■性産業は犯罪組織とも繫がりがあったわけで、若い女性として、男性の前で裸になる弱い存在として、ああいう世界に入る危険性が怖くはなかったんでしょうか?
コージー:ええ。ただ、あれくらい若い頃だと、逆にそういった面をそこまで深く考えないものでしょう? だから、ああいう年代の人間は「自分はいつまでもこの調子でいける」なんて風に(苦笑)、怖いもの知らずでいられるわけで。けれどもまあ、本当に「これはまずい、ここに来なければよかった」と感じるようなシチュエーションに陥ったら、とにかくその状況をなんとかして切り抜けて、その場から立ち去って自分の安全を確保しようとするんでしょうし。
質問:野田努+坂本麻里子(2017年11月01日)
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE