MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > Low- Ones and Sixes
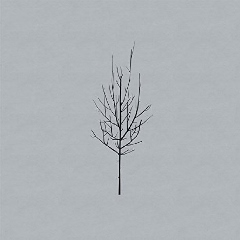
音が震えている。ズン、ズン、ズン……と重いキックの上にザリ、ザリ……とザラつくノイズが重なっていく。オープニング・トラック“ジェントル”をほんの数秒聴くだけで、たとえば簡素に枯れ木が描かれているだけのジャケットにそれ以上付け加えるものがまったくないほど完成されているように、ロウというバンドの美学に引き込まれる。「ロウ」というのはコンセプトだ。低く、深く、もっと下のほうへ……。できるかぎり少ない音と言葉の数で、“ジェントル”は聴き手を甘美に沈みこませる――「こんな風に終わらなくてもいい/でもこれが俺たちの居場所」。
ポストロックというタームがいま再浮上しているのと同じように、スロー・コア、サッド・コアという言葉もチラチラ耳にするようになった。昨年インディ系のロック・メディアが、サッド・コアの源流のひとつレッド・ハウス・ペインターズのマーク・コズレックのプロジェクトであるサン・キル・ムーンをこぞって評価していたこともそうだが、どうも90年代後半からミレニアム前後の音が熱いようだ。リヴァイヴァルの周期が巡ってきたこともあるだろうが、時代の要請もそこにはあるように思える。スフィアン・スティーヴンスがあの寂しげなアルバムを出したように、いまのアメリカではアッパーなものが空々しく響く時期なのだろうか。もちろん、ロウはこの20年間とくに大きなブランクもなく作品の発表を続けてきたバンドであり、彼ら自身はトレンドに左右されることはなかった。が、その間にギャラクシー500のプロデューサーであるクレイマー、スティーヴ・アルビニ、デイヴ・フリッドマンとUSインディのキーマンたちをバックに据えることで、音のボキャブラリーを増やしつつうまく自分たちをアップグレードして生き残り続けてきたイメージがある。
前作『ジ・インヴィジブル・ウェイ』ではウィルコのジェフ・トゥイーディをプロデューサーに迎え、そして通算11作めとなる本作『ワンズ・アンド・シクシズ』ではボン・イヴェールのジャスティン・ヴァーノン周辺のプロデューサーであるBJバートンをフックアップしている。アルバムはジャスティンがウィスコンシンに所有するスタジオ〈エイプリル・ベース〉で録音され、そんなこともあって僕が今夏行ったジャスティン主宰のフェスティヴァル〈オークレア〉にも出演していた。ヴォルケーノ・クワイアでジャスティンがペレと組んだことからもわかるように彼は90年代末からゼロ年代なかば頃のUSインディを地道に支えたバンドを現在フックアップしており、ロウもその動きにうまく合流したということだ。
ただ、サン・キル・ムーンの『ベンジ』がその私小説的な語り口で具象的に悲しみを抽出しているのとは対照的に、『ワンズ・アンド・シクシズ』は描く情景はとことん抽象的だ。いくつかのリレーションシップの齟齬が生み出す掴みどころのない憂うつや倦怠感が、慎重に選び抜かれた音の組み合わせとともに綴られていく。組み合わせ……つまりバンドがその長いキャリアのなかで通過してきた音がきわめて巧妙なやり口で曲に合わせてピックアップされている。浮遊感のあるシンセを漂わせ、アコースティックの柔らかな響きとエレクトロニクスの固い響きを使い分け、透明感のあるウィスパー・ヴォイスとコーラスの底でノイズが地を這う……。明度と彩度は抑えられているが、だからこそ時間をかけてじっくりと染み入って来る叙情がここにはある。“ノー・コンプレンデ”でミミ・パーカーの流麗な歌とあまりにヘヴィな低音が重なるとき、そこには取り返しのないかないほど深いメランコリーが立ち現れ、穏やかなメロディを持つどこかホーリーな響きを持つ“スパニッシュ・トランスレイション”ではアコースティック・サウンドとシンセが天上の響きを演出する。ビーチ・ボーイズのコーラスが降りてくる“ノー・エンド”や“ホワット・パート・オブ・ミー”のようにキャッチーで生き生きとしたポップ・ソングがアルバムのなかではフレッシュに聞こえるが、彼方にノイズがざわめく様はとてもデリケートなバランスを醸している。
9分51秒に渡って激しさと静寂を行き来する“ランドスライド”はまさにロウの本領だが、そこに流れる時間は危険なほどに甘く、快楽的だ。ロウというバンドにおいて、スロー・コアのスローとは実際のテンポのことではなく身体を麻痺させる媚薬のことであり、サッド・コアのサッドとは喜怒哀楽の哀に収まりきらない心地よさや温かさを含んだものである。それは彼らとわたしたちの、秘めごとのような美の戯れとしてそっと差し出されている。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE
