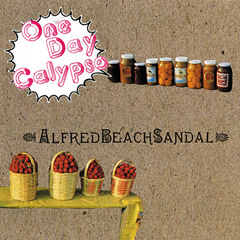MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > Alfred Beach Sandal- One Day Calipso
アルフレッド・ビーチ・サンダル(以下、ABS)の音楽性を説明するとしたら、とりあえずは、シャムキャッツの夏目知幸による「カリブ海のキャプテン・ビーフハート」というコピー以上に的確なものはないだろう。あるいは、元〈ロウ・ライフ〉の浜田淳が編集人を務める『音盤時代』創刊号に二見裕志が寄せていた、70年代後半から80年代前半にかけて、プログレッシヴ・ロックのアーティストたちが、インプットをそれまでのジャズや現代音楽からワールド・ミュージックに、アウトプットを"重く暗い"ものから"軽く明るい"音楽へ切り替えたことについてのテキスト「トロピカル洞、その陰と陽」がそれを代弁してくれる。曰く、「この距離感、遠い異国のフレーズを自前の楽器で奏でることの快楽と違和感がないまぜになった確信のなさが、ぼくにはとても重要に思える。それはぼくの距離感でもあるからだ。照明や家具、さらにはカーテンの柄を変え、BGMの音楽を変えたところで、ぼくの生活は依然としてきのうのままなのだ」。
ABSは北里彰久のソロ・ユニットで、この『いつかの、カリプソ』がデビュー・フルレンスになる。ちなみに、前身のバンド、モグサ・デルタは、サン・シティ・ガールズが『トラウト・マスク・レプリカ』をカヴァーしているような、ノイジーなローファイ・ファンクだったが、本作では、以前までディストートしていたエキゾティシズムへのこだわりを、よりアコースティックに表現することで、解放的な響きを獲得している。しかし、それは、"本物"に近付くのではなく、むしろ、変態性が露になったという意味で、だが。
ただし、北里とドン・ヴァン・ヴリートが違うのは、バックのマジック・バンドが決して奴隷ではないということだ。それどころか、日々、セッションを繰り返し、複数のユニットを掛け持つ彼等のコミュニケーションの残像は、実に健康的なシーンのようなものさえ浮かび上がらせつつある。メンツを順に紹介すると、まずは、スティール・パンとトランペットでMC.sirafu。インディ・ポップ・シーンの顔役として知られるこの髭面の男は、コンテンポラリー・エキゾチカ・ロック・オーケストラこと"cero"や、NRBQとスライ&ザ・ファミリー・ストーンが合体したような"片想い"、中川理沙とのデュオ"うつくしきひかり"等、そのバイオグラフィーを書き出すだけで、ちょっとしたフェスティヴァルのようだ。次に、ベース、ギター、ピアノで伴瀬朝彦。ハートボイルドだが、チャックを閉め忘れているようなチャーミングさもある"アナホールクラブバンド"を率いる他、前述した"片想い"や、フランク・ザッパの意思を受け継ぐ"ホライズン山下宅配便"等、癖のあるバンドに名前を連ねている。そして、ABSのマス・ポップとでも名付けたくなる複雑なサウンドの要を担うドラムは、フリーフォームなプレイで注目を集めている一樂誉志幸。他にはサックスで遠藤里美、トロンボーンで川松桐子も。ちなみに、レーベルはイベント・スペース〈七針〉が運営する〈鳥獣虫魚〉で、八丁堀のオフィス街の地下にある、この、まるでアジトのような空間は、mmm、王舟、oono yuuki、麓健一といったモダン・アシッド・フォーク・ミュージシャンが出入りするライヴ・ハウス、またはスタジオでもあって、本作の楽曲の多くもここでレコーディングされている。コンクリートの下で、南の国を夢見ながら。
それにしても、ceroの『world record』、アナホールクラブバンドの『泥笛』、ヴィデオテープミュージックの『Summer of Death』......と、この周辺で、屈折したエキゾティシズムがリアリティを持ちつつあるのは、一体、どういうことなのだろうか。とりあえず、この、変拍子に乗せて少年のような声で歌われる、何処かの国のいつかの物語は、放射性物質が降り注ぐプールサイドよりも、節電の要請を無視して、寒いぐらいクーラーをかけた部屋がよく似合うのはたしかである。こんな国に、こんな時代に関わりたくないんだ、とばかりに爆音で鳴らすことにしよう。
磯部 涼
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE