MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ryoko Akama - Bruno Duplant - Dominic Lash- Next To Nothing
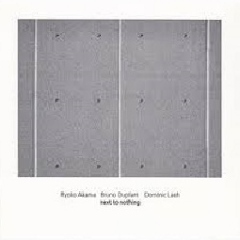
〈アナザー・ティンブレ〉は英国の即興/実験音楽レーベルであり、現在、この種のシーンにおいて大きな存在感を示しているレーベルでもある。その横断領域は広く、即興から電子(電気)ノイズ、現代音楽までも射程に入れており、非常に個性的なレーベル・キュレーションが行われている。
なにしろレーベル初期にはデレク・ベイリーらとミュージック・インプロヴィゼーション・カンパニーで活動したヒュー・デイビスの作品集『パフォーマンス 1969 - 1977』や、音素材を極限まで切り詰め、聴覚/知覚への自覚的なプロセスを浮上させていく静寂の音響・音楽、ヴァンデルヴァイザー楽派の6枚組ボックス・セット『ヴァンデルヴァイザー・アンド・ソー・ヴァイタ―』までもリリースしているのである。また日本のICCで作品が展示された英国の実験音楽家スティーヴン・コーンフォードのアルバム(コラボレーション含む)も多数リリースされている。
そう、いわば即興/実験/作曲の境界線を越えていくようなレーベルなのだ。ある意味ではマイケル・ナイマン著『実験音楽-ケージとその後』の思想を受け継ぐレーベルともいえよう。
昨年2014年もジョン・ティルバリー、フィリップ・トーマスらの演奏によるモートン・フェルドマン『ツゥー・ピアノ・アンド・アザー・ピース 1953-1969』もリリースするなど、即興、ノイズ、電子音楽、現代音楽まで幅広く、かつ大量のリリースを続けていた(個人的にはベルリン・シリーズと銘打ったアーティスト・コラボレーション・シリーズにも注目)。また、英国のエクスペリメンタル・ミュージック・マガジンの老舗『ワイアー』誌の2014年トップ50内に選出されたマグナス・グランベルク率いるスクーゲン『ディスペアズ・ハッド・ガヴァンド・ミー・トゥー・ロング』と、ローレンス・クレイン『チェンバー・ワークス 1992 - 2009』も重要な作品だ。10人の演奏家によるスクーゲン(日本からは中村としまる、笙の石川高が参加)は、コンポジションとインプロヴゼーションを明確なコンセプトとともに両立させ、ローレンス・クレインは室内楽であった。両作とも即興と作曲への境界を越境している。インプロヴィゼーション/コンポジションが同時生成するようなレーベルの新しい志向=思考が明確になってきたのである。
今回紹介するリョーコ・アカマ(VCS3シンセサイザー)、ブルーノ・デュプラント(パーカッション、トーン・ジェネレーター)、ドミニク・ラッシュ (ダブル・ベース、クラリネット、ラップトップ、パーカッション)らによる『ネクスト・トゥ・ナッシング』(2014)もまた純白のミニマリズムでインプロヴィゼーション/コンポジションを越境する素晴らしいアルバムである。まずは各メンバーのことについて簡単に書いておこう。
リョーコ・アカマはAGFらとのユニット(The Lappetites)、カフェ・マシューズ、そしてエリアーヌ・ラディーグ(!)などとのコラボレーションでも知られる電子音楽家(https://www.ryokoakama.com/)。この『ネクスト・トゥ・ナッシング』でリョーコ・アカマが演奏するVCS3は、70年代にキング・クリムゾンやピンク・フロイドなどのプログレ・バンドに導入されたアナログ・シンセサイザーだが、本作では、それら伝説的なバンドの使い方とは異なり、静謐な音の層/霧のような音響が持続している(VCS3は、昨年発表のソロ・アルバム『コード・オブ・サイレンス』でも用いられていた)。
そして、ブルーノ・デュプラントは精力的なリリースを続けるフランス人アーティストで、コントラバス、パーカッション、コンピューターなどを駆使したミニマルな作品/演奏を多数送り出している。自身もレーベル〈リゾーム〉を運営している(https://rhizome-s.blogspot.co.uk/)。ドミニク・ラッシュ はコントラバス奏者。彼は〈アナザー・ティンブレ〉からリリースされているヴァンデルヴァイザー楽派のアントワーヌ・ボイガーの作品『カントル・カルテット』などにも参加している(https://dominiclash.blogspot.jp/)。
インタヴューなどを読むと、このアルバムを主宰したのはどうやらブルーノ・デュプラントのようだ。彼はこれまでもリョーコ・アカマなどとコラボレーションを行ってきたわけだが、その経験を踏まえつつ、さらに新しい音楽を生み出したかったようである。私見だが、このアルバムにおいてはトリオ編成における新しいミニマリズム/アンサンブルを追求しているように思える。
1曲め“ア・フィールド、ネクスト・トゥ・ナッシング”はブルーノ・デュプラントによる曲で、淡い音色の電子音が持続する静謐な楽曲(このトラックが本アルバムのベーシックとなっているのではないか?)。持続とピッチの繊細なコントロール/コンポジションが素晴らしい。2曲め“グレード・ツー”はリョーコ・アカマの曲。透明な持続音に、ベースの点描的な音。鐘のような響き。電子音の層による静謐な音響アンサンブルだ。3曲め“スリー・プレイヤーズ、ノット・トゥギャザー”はドミニク・ラッシュの曲で、鐘のような響きから幕を開ける。日本の雅楽のような持続や、クリッキーなリズムも刻まれていく。そのうえフィールド・レコーディングされた風や空間のような音(多分、電子音主体のノイズではないかと思う)が鳴り響くのだ。この曲では、さらに音の層が増えており、即興/コンポジションのあいだに、音の揺らめきが生まれている。ラスト4曲めは、リョーコ・アカマによる“グレード・ツー・エクステンデッド”だ。電子音響的な高周波のチリチリしたサウンドが持続し、低音部分は震えるような持続をつづける。
ブルーノ・デュプラントは「自分はヴァンデルヴァイザー楽派の音楽家ではない」と語っているが、たぶん、彼の目指すべき音は、サウンドのラディカリズムをミニマリズムとアンサンブルとコラボレーションによって生成していく点にあるのではないか。
静寂と持続の音楽空間を誇る本作は、ほとんどファイル交換によって作り上げられたという。本作では演奏家は、同じ場所・時間で演奏・録音をしていない。しかし実際に会うことなく演奏・録音された本作は、その距離の効果によって独自のサウンドの磁場を形成しているように思えるのだ。反応のアンサンブルではなく、時空間を超えた「応答」のアンサンブル。リアルタイムの反応ではない以上、作曲と即興の境界線は無化していく。
変わりゆく/移ろいゆく音響の饗宴。その古楽の一瞬の響きを引き延ばしたかのような響き。日本の能楽のような静寂と緊張。それは現代音楽的なコンセプチュアルなミニマリズムではなく、音自体の生成に拘る新しいミニマリズムといえよう。90年代と00年代の即興/音響シーンを経由した2010年代の音楽。ポスト・インプロヴィゼーションから新しいミニマリズムへ。そして、その音は、とても澄みきった響きを獲得しているのだ。
最後に。ミニマルなイメージのジャケット写真もブルーノ・デュプラントによるものだという。このアルバムの音楽/音響を象徴する見事なアートワークである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE