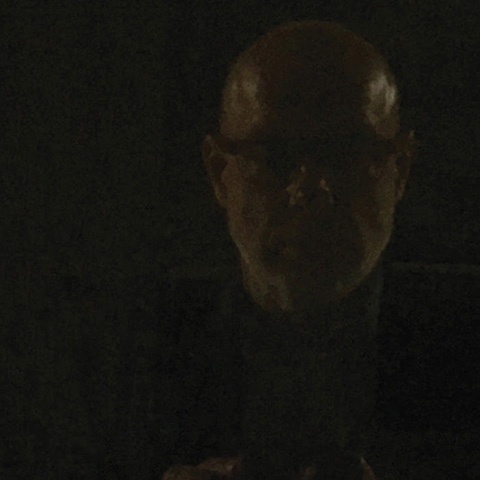MOST READ
- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- valknee - Ordinary | バルニー
- Columns Kamasi Washington 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 | ──カマシ・ワシントンの発言から紐解く、新作『Fearless Movement』の魅力
- interview with D.L 俺のディグったものすべてがファンキーになる | D.L、Dev large、ブッダ・ブランド
- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- 『成功したオタク』 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Kode9 〈ハイパーダブ〉20周年 | 主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- Kamasi Washington ──カマシ・ワシントン6年ぶりのニュー・アルバムにアンドレ3000、ジョージ・クリントン、サンダーキャットら
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
Home > Reviews > Album Reviews > David Byrne- American Utopia
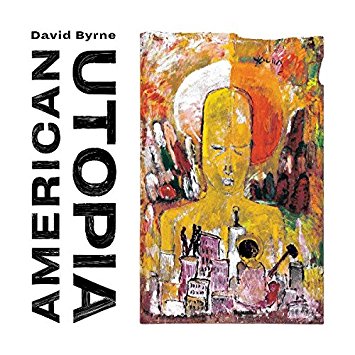
木津毅
1)
かれらがいま深く感じているのは、自分たちは祖国を失いつつある、という思いです。抽象化され一般化された「国民」という考えを政府が振りまき、その結果、ほんとうの祖国が自分たちから奪われている、という思いです。自分たちは、弱者と称される人たちの「身代わりの犠牲者」になっているという意識です。しかも、その弱者たちは「大学出のリベラルなエリートたち」によって甘やかされているという思い込みがあり、それは、かれらのなかに根強く広まっています。そのことが非常にしばしば悲惨な結果をもたらすことになっているわけです。
──ノーム・チョムスキー著 寺島隆吉・美紀子訳『アメリカンドリームの終わり あるいは、富と権力を集中させる10の原理』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)から、「原理10 民衆を孤立させ、周辺化させる」より
ノーム・チョムスキーは現代アメリカ社会について平易に語った新著のなかで、 2016年以降を……ありていに言えばトランプ現象以降を踏まえつつ、格差が生み出した分断をそのように説明している。ここで言う「かれら」はおもにトランプに投票したような低収入の白人労働者のことだ。多くのひとが2016年にぶつかり、いまも向き合っている問題である。「リベラル」とされているものが権力者によってイメージ操作され、それ自体が周縁化を招いているとすれば、いま、「リベラル」は何を言えばいいのか。
ひとまず自分がここで言いたいのは、現在「アメリカン」の冠ほど反語的な響きを有するものはない、ということだ。チョムスキーの同著の原題は『レクイエム・フォー・アメリカン・ドリーム』である。LCDサウンドシステムの昨年のアルバム『アメリカン・ドリーム』がそうであったように、わたしたちが「リベラル」と思っている場所から届けられた『アメリカン・ユートピア』は、「make AMERICA great again」の標語が代表する価値観を反語的に風刺するものだと見なせるだろう。
2)
ブライアン・イーノ「これは、いま、アメリカ人たちが「トランプ当選」という事実に対して感じているのとまったく同じフィーリングなんだろうね。というわけで、我々リベラル派は――リベラルじゃなければ左派でもいいし、中道寄りの左派でも、とにかくまあ、その呼び方はなんでもいいんだけれども、そうした我々全員が、「いま、自分たちはどこにいるのか?」ということをしっかり見つめはじめる必要があるんじゃないか、私はそう思っている。」
──ele-king vol.19、2016年年間ベスト・アルバム号掲載のインタヴューより
3)
『アメリカン・ユートピア』のジャケットを飾る不穏なアートワークはアウトサイダー・アートの画家とされるパーヴィス・ヤングが手がけたものだ。ヤングはマイアミ出身のアフリカン・アメリカンとして70年代の壁画アート・ムーヴメントから影響を受け、アメリカにおける大恐慌時代、消費主義、植民やネイティヴ・アメリカンの窮状などをモチーフにした作品を多く手がけたそうだ。アメリカという巨大な国家(「アメリカン・ユートピア」!)がどこから来たのか、どのような犠牲とともに成り立ってきたかを独特のおどろおどろしい色彩感覚によって執拗に描き続けた作家だと位置づけられている。
4)
マイク・ミルズの映画『20センチュリー・ウーマン』は冒頭で“心配無用のガヴァメント”が流されることからもわかるように、トーキング・ヘッズが非常にアイコニックに引かれている作品である。舞台は1979年の西海岸。明らかにミルズの少年時代の姿が投影された主人公の少年ジェイミーは、同居人でアーティスト志望の年上の女性からラディカル・フェミニズムとパンク・ミュージックを教えられる。なかでもジェイミーのお気に入りはトーキング・ヘッズだ。彼はそのことで近所の不良から「アート・ファグ(アート気取りのカマ野郎)」と罵られるのだが、むしろその蔑称を肯定的に受け入れていく。ミルズは自分の感性を育てたのは70年代の個性的な女性たちであり、フェミニズムであり、アーティなパンク・ミュージックだと宣言し、あらためて感謝と敬愛を捧げている。「アート・ファグ」であることのプライドをそのとき知ったのだと。
だが、タイトルに「20世紀の」と示されているように、そこには回顧的な意味合いが多く含まれている。70年代末のニューウェイヴは多くの少年少女を自由にした、たしかに。だが、それはいまアメリカにおいてどのようなものとして受け継がれているのだろうか。ラディカル・フェミニズムが21世紀において参照され日々更新されているのに対し、では、トーキング・ヘッズは、デヴィッド・バーンは、あるいは「アート・ファグ」はいまも通用するのだろうか?
*
14年ぶりのソロ作である『アメリカン・ユートピア』は、わたしたちが一般的に抱いているデヴィッド・バーン的なイメージを大きく裏切るものではない。当たり前にマルチ・カルチュラルで、多彩なパーカッションで鳴らされる多様なリズムがあり、素っ頓狂なファンクのグルーヴがあり、ソウルフルだがどこか間の抜けた歌があり、それにやっぱり家のことを繰り返し歌っている。ほとんどの曲でブライアン・イーノが関わっていることもあり、イーノ時代のトーキング・ヘッズを彷彿とさせる部分も多々ある。聴いているとその変わらなさに何だか安心してしまうのは、バーン独特のクセのようなものがわたしたちリスナーにも共有されるイディオムとしてすっかり定着しているということだと思う。
14年ぶり、と言ってもバーンは数々のコラボレーションをその間に行っており、なかでもセイント・ヴィンセントやダーティ・プロジェクターズとの共作は、サウンド面でもイメージ面でも、そうした「バーン的なるもの」を大いに頼りにするものであった。21世紀のアーティなインディ・ロック勢にとってバーンはつねに精神的支柱のようなところがあったのだろうし、そうした縦の繋がりが00年代の東海岸における知的なアート・ロックの盛り上がりを大いに担っていた。しかしながら、東海岸の「進歩的な」価値観が存在意義そのものから揺らいでいる2016年以降において、インディ・ロックの優等生たちは訴求力を失っているようにも見える。まさに「大学出のリベラルなエリートたち」の音楽として……。
バーンとイーノは「アメリカン」を冠した作品を世に放つにあたって、徹底してその問題に向き合ったに違いない。『アメリカン・ユートピア』は、そして、バーンの20世紀からの功績を引き継ぎつつ、2010年代の音をふんだんに忍びこませるアルバムとなった。まずは何と言ってもOPNの起用だ。ダニエル・ロパティンは2曲で作曲にクレジットされているほか、別のいくつかの曲でも様々な楽器の演奏、それに「テクスチャー」で参加している。たとえば作曲に関わった“ディス・イズ・ザット”では、『R・プラス・セヴン』に収録されていてもおかしくないような乾いたビート音と美麗なメロディのやり取りが聴けるし、また、“ドッグズ・マインド”や ヒア”で聴けるリヴァービーな打音や繊細なアンビエント的音響にはかなりの部分で貢献しているだろう。あるいはジャム・シティ、あるいはサンファ、あるいはエアヘッド、あるいはトーマス・バートレット、少し意外なところではジャック・ペニャーテ……バーンよりもずっと若いミュージシャンたちが入れ替わり立ち替わり登場し、ポップ・アートの大御所のサウンドに新しい息を吹きかけている。バーンはそのセルフ・イメージやサウンド・シグネチャーを担保しつつ、どうにかそれを今様の響きを持つものとして鳴らそうとする。
いっぽうで更新できていないこともある。本作に女性がひとりも起用されていないことが問題視され、バーン自身がそのことを謝罪したのだ。それこそPCが優先されて無理矢理に多様性が演出されるのもどうかと思うが、これだけ多くのゲスト・ミュージシャンが参加したアルバムに女性がいないというのはさすがに(しかもデヴィッド・バーンの作品としては)不自然だ。彼自身の無自覚な古めかしさがポロっと出てしまったのかもしれない。ただ、バーンは真っ向から反省を綴ったコメントを出した。結果として、新しくなろうとする彼の姿は作品の完成後にも証明されることとなったとも言える。
肝心の「アメリカ」については、はっきりとした政治的モチーフとして表出してはいない。“アイ・ダンス・ライク・ディス”に登場するクレジット・カードに象徴される商業主義、“ガソリン・アンド・ダーティー・シーツ”において繋げられる石油と戦争のイメージ、“Bullet”の銃弾……そこここに現代アメリカが内側に抱える病の描写はあるが、それらはスローガンではなく、ちょうどパーヴィス・ヤングの絵画のように抽象化された風刺画のような形をとる。室内楽とシンセ・ポップを合体させたような本作中もっともチャレンジングなトラック“ドゥーイング・ザ・ライト・シング”は多義的な「正しさ」にこんがらがっているという点でじつに今日的な姿であるし、“エヴリバディーズ・カミング・トゥ・マイ・ハウス”が移民のことを指しているとすれば、「皆が俺の家にやってくる/誰も帰っていくことはない」というのはあまりにも示唆的なフレーズだ。その、どこか不気味さを湛えつつドライヴする情熱的なファンク・ジャムは、実際、アルバムのハイライトである──「皆が俺の家にやってくる/ひとりぼっちになることはない」。
バーンが『アメリカン・ユートピア』で取り組んでいるのは、現在というものに積極的に混乱するということであり、20世紀の「アート・ファグ」の精神を保ちながらも、だからこそ、それをアップデートしようと苦戦することである。迎合してはいない。が、自分自身を時代と照らし合わせて精査しようとしている。「リベラル」なアート・ロックが説得力を失っているとしても、ここでのバーンの姿勢はとても誠実だ──もちろん、ユーモラスでもある。
*
本作を引っさげてコーチェラに出演したバーンのステージを配信で観たが、それがじつにイカしていた。10数人のメンバーが舞台に上がるが(ちゃんと女性のメンバーもいた)、マイクスタンドなど固定の機材はいっさい置かずに、6人ほどの打楽器も含め全員が首から楽器を下げてウロウロしながら演奏する。途中で挿しこまれる妙な寸劇と、合っているのかいないのかよくわからないダンス。デヴィッド・バーン的としか言いようがなかった。ゆるくてシュールな笑い、エキセントリックなのにどこまでもポップな人懐っこさ、キッチュなアート性、アフロやカリビアンを取り入れているのにギクシャクとしたリズム。雑多な人間がそれぞれワチャワチャと統制の取れていない動きをしながら、オリジナルなグルーヴとアンサンブルを生み出そうと共存している。まったく反語ではない「アメリカン・ユートピア」が、そこにはあったような気がした。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- valknee - Ordinary
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo


 DOMMUNE
DOMMUNE