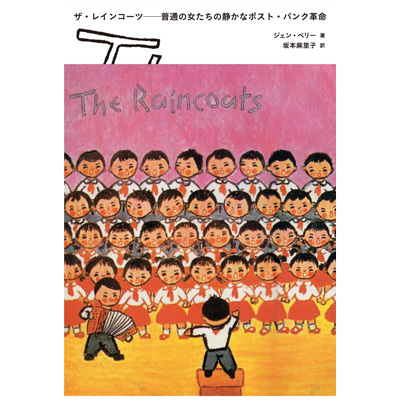MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Gina Birch- I Play My Bass Loud
先週、アフリカ系アメリカ人の友人のひとりと、渋谷のカフェで会った。多忙な弁護士であり、60年代の日本のアンダーグラウンド文化を研究しているこの男は、最近読んだ本では谷崎潤一郎の『痴人の愛』が面白かったそうで、「ナオミの話は、アフロ・アメリカン史のメタファーとしても読めるからね」と言った。批評家グレッグ・テイトは桐野夏生の『OUT』の書評で、「日本という国はアメリカの文化ならなんでも受け入れると聞いているが、その日本でなぜフェミニズムが流行らなかったのかがよくわかった」と書いている。
ぼくがこのアルバムについて書くうえでの問題点はまさにそこにある。間違ってもフェミニストではないし、これまでの人生でフェミニズムに反する行為をしてきたという自覚がある人間がフェミニズムの音楽について語るというのは、普通に考えて偽善者めいているし、自分でも後ろめたさを感じる。本来であればこういう音楽は、野中モモ氏や水越真紀氏のようなフェミニストが書くべきなのだろう。ただ、もしぼくに、少しでも入り込む余地があるとしたら、自分が10代のときに、ザ・レインコーツの大ファンだったということはあるかもしれない。
ザ・レインコーツやザ・スリッツのようなバンド、もしくはデルタ5やヤング・マーブル・ジャイアンツのようなヴォーカリゼーションは、ぼくにとって〈ポスト・パンク〉という言葉から想起されるイメージの多くを占めている。彼女たちは、たとえばアニメや広告などで表象化される必要以上にエロい女の対極にいて、色気を武器にパフォーマンスするシンガーとも100万光年離れていた。まずはその佇まいが、ぼくにはものすごくクールに思えたのだ。
なかでもザ・レインコーツは、圧倒的だった。彼女たちの音楽がもし実験的だったと言えるなら、あの歌いっぷり、あのガチャガチャした演奏は、彼女たちの人生ないしは世界に臨む思想から来ている。それを知ったのは、『ザ・レインコーツ』という本の編集を担当した、けっこう最近のことだったりするのだが、10代だった自分が感じていたのは、同時代のほかの〈ポスト・パンク〉にはない、言うなればオルタナティヴな喜びの感覚だった。男社会とは別のところで彼女たちは楽しんでいる、その感じが、男社会にどっぷりのぼくには最高にクールに思えたのだった。
ザ・レインコーツのベーシスト、ジーナ・バーチは、「私は窓辺でベースを弾いている年老いた白人女」と、資料のなかで言っている。67歳になって初のソロ・アルバムをリリースする彼女はこう続ける。「頭を突き出して、ただでっかく叫びたいだけ。私はベースをでっかく弾く」——これだけで充分にメッセージである。
ジーナのベースは、ダブから大きな影響を受けている。音空間の一要素として、床を這ってグルーヴを創出する。アルバム冒頭の表題曲からまさにそれで、いかにもレインコーツなダブ空間が広がっている。 “Big Mouth” や“Pussy Riot”、 “Digging Down” といった曲においても低音宇宙はストーンと発展し、アナ・ダ・シルヴァの抽象的な電子音が花を添える。その“Pussy Riot” では、「私を黙らせたいのか」と挑発し、「私たちが鎖に繋がれた人たちのために日々闘うことは義務だ」とまで言い切っている。続く、ラジオから流れるオールディーズ風のポップな曲調の、しかし“私は憤怒(I Am Rage)” という曲名の曲では、自分は「憤怒が泡立ち怒りに燃える釜」であると、柔らかくメロディアスに歌っている。
もちろんこのアルバムには、彼女のソロ活動のはじまりを告げた曲、 あの“Feminist Song” が収録されている。
フェミニストかと訊かれたら
私はこう言う
無力なんてクソくらえ
孤独なんてクソくらえ
女を貶める奴らはクソだと権力の座にいる女がいる
しかし多くの女たちは鎖に繋がれ苦役に耐えている過小評価され過小評価され
レイプされ虐待され歴史からはじかれる
だからフェミニストかと訊かれたら
私はこう言う
なぜそうではないのかと
私は都会の女
私は戦士
ザ・レインコーツにあった「喜び」はここにもじゅうぶんにある。が、ジーナ・バーチのソロ・アルバムには、抑えきれない怒りがそこら中にある。ダブの深度がもっとも深い“Digging Down”においても、彼女は怒っている自分を隠さない。そして、アルバムを締める “Let’s Go Crazy” のなかで彼女はより直接的に女たちに呼びかけている。「この狂った時代のために/女の仲間が欲しい/私たちの時代がもうすぐやってくる/私たちの時代がもうすぐやってくる/私たちの時代がもうすぐやってくる/私たちの時代がもうすぐやってくる……」
あらためて、そして謙虚な気持ちで言えば、このアルバムのレヴューの書き手にぼくが相応しくないことはあきらである。が、ここは、偉大なるベル・フックスが言うように「フェミニズムはみんなのもの」ということでお許しいただきたい。確実なところとしては、いちリスナーとして、言うべき言葉をもった音楽特有の力強いものを感じるし、日本がグレッグ・テイトの言う通りなのだとしたら、音楽メディアに関わる人間としてこの作品を紹介するのは、それこそ義務なのだ。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE