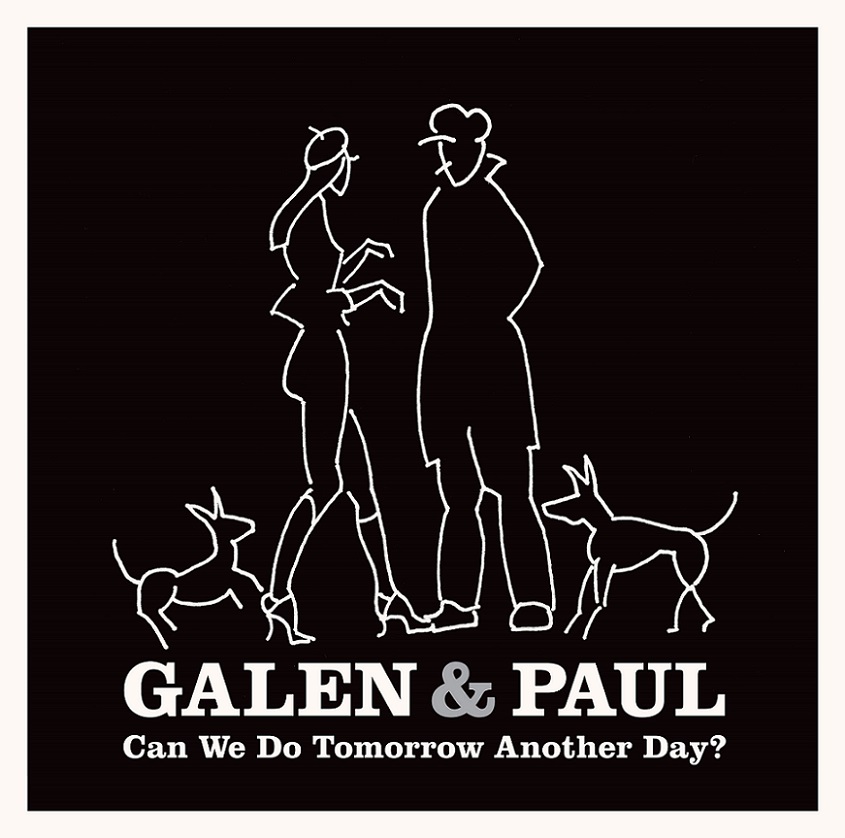MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Galen & Paul- Can We Do Tomorrow Another Day?
自分の10代の頃の憧れだったミュージシャンが、年老いて老害となるのを見るのはつらいものだ。しかしなかには、年齢を重ねながら、昔よりも好きになったミュージシャンもいる。ポール・シムノンは、そんなひとりだ。元ザ・クラッシュのベーシストは2011年6月、グリーンピース活動家のひとりとして、北極圏の石油掘削に反対するキャンペーンのため、はるばる船に乗って、ヨーロッパ最大の石油・ガス会社、ケアン・エナジー社が管理する北極海に面した石油掘削施設へと赴き、石油流出時の対応計画を提出するよう要求した。が、要求は拒否され、抗議者18人は不法占拠の罪で投獄された。こうした一連の政治活動において、また、刑務所のなかでも、シムノンは自分が元ザ・クラッシュのポールであることを言わなかった。シムノンは船内における料理係で、仲間からは「コックのポール」で通っていたそうだ。その彼があのポール・シムノンだとわかったのは、事件が全国ニュースになってからのことだった。
「彼は本当によく働き、通常はコックの休日である日曜日でさえ料理をしていた」と、同行した航海士は『ガーディアン』の取材で答えている。じっさいの話シムノンは料理が得意で、その腕前は刑務所のなかでも発揮されたという。「(刑務所内の)食事があまりにひどかったので、看守にポールが料理をすることに同意してもらった」と、抗議者のひとりも証言している。彼は刑務所で、美味しいベジタリアン料理を作った。
この記事を読んで、いままでスルーしていたハヴァナ3AMを聴かないわけにはいかなかった。ロカビリーにマリアッチ。永遠の音楽。自分のとってのザ・クラッシュというバンドは、高校時代に学校をサボって、静岡から東京まで東海道線で4時間かけて来日公演を見に行ったほどのスーパー・ヒーローだ。もっともその視線はジョー・ストラマーとミック・ジョーンズに集中していたのだけれど。しかし、それから30年の時を経て、ストラマーが歌のなかで訴えていた社会意識の高さを、バンド内でもっとも寡黙だったベーシストがそのさらにうえを行くように継承している事実を知った。デーモン・アルバーンがシムノンといっしょにザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・クイーンを組んだのは、彼の肩書きがたんなる「元ザ・クラッシュ」ではないからだろう。
さて、ここからが本題である。「コックのポール」は、素晴らしいことに、ケヴィン・エアーズの娘の舌も満足させたのである。「人は自分が料理上手だと思いたがるから、どんどんいろいろなものを加えて、シンプルさや新鮮さを奪ってしまう。しかし、ポールのヴォンゴレは完璧だった」と彼女はある取材で答えている。
それにしてもポール・シムノンとケヴィン・エアーズの娘、ギャレン・エアーズがいっしょにアルバムを作るとは、これはこれで面白い話だ。
彼女の父ケヴィン・エアーズは、1960年代後半のUKアンダーグラウンドから生まれたソフト・マシーン(創生期にはデイヴィッド・アレン、ほかロバート・ワイアットがいたことで知られる)のオリジナル・メンバーのひとりで、ピンク・フロイド時代のシド・バレットやティラノザウルス・レックス時代のマーク・ボランのような、UKでは「ソフト・メンズ」と言われる、寛容な子育ての恩恵を受け、成熟した男らしさを拒否した最初の世代に属する人物でもあった。彼の歌声はバリントンだったが、いわば“ストロベリー・フィールズ/イエロー・サブマリン”の系譜というか、『おもちゃの歓び』や『月に撃つ』、『いとしのバナナ』といった初期のソロ・アルバムのタイトルからもその志向がうかがえよう。自由人エアーズは、60年代後半にはUKを離れ、当時のヒッピーたちが目指したスペインのマヨルカ島やイビサ島、モロッコにも住んでいたこともある。(ピンク・フロイドが音楽を手がけた映画『モア』を思い浮かべてしまう)
フランスのコミューンで生まれ、スペインのマヨルカ島で育ったギャレン・エアーズが音楽活動をはじめたのは、大学のためロンドンに移住してからだった。レコード・デビューは2008年で、それはSiskinというバンドの一員としての作品だったが、2018年には最初のソロ・アルバム『Monument』をリリースしている(翌年にはライヴ公演のため来日もしている)。さらに補足すると、2013年の父の死は彼女の音楽への情熱をさらに高めたそうだ。
ギャレンとシムノンとは共通の友人が多く旧知の仲だったが、ことのはじまりはコロナ渦をマヨルカ島で過ごしたシムノンにあった。島の小さな漁村に滞在中、絵を描き、曲作りにも励んだ彼はロンドンに戻ると、自らのアイデアを具現化すべく、エアーズに声をかけた。話は早く、互いに曲を持ち寄って、シムノンが夕食を作っているあいだそれぞれの曲を流し、議論しながらアイデアを発展させていったという。
『Can We Do Tomorrow Another Day?』は、ひとことで言えばレトロ・ポップなアルバムで、レゲエやラテンのフレイヴァーをスパイスに、ここにはデル・シャノン(ビル・ドラモンドがもっとも理想とする歌手)、60年代のフランス・ギャル(渋谷系も聴いた夢見るシャンソン人形)、リー・ヘイズルウッド(ジャーヴィス・コッカーやボビー・ギレスピーも尊敬)&ナンシー・シナトラ(渋谷系にも人気だった60年代ポップ歌手)を参照した痕跡があり、さらにここにはオーガスタス・パブロ(ダブ仙人)のメロディカ、ジェリー・ダマーズのようなオルガンやザ・スペシャルズの “ゴーストタウン”(暗い時代を預言した名曲)を彷彿させる暗いフィーリングもある。古風な質感が特徴で、プロデューサーは大ベテランのトニー・ヴィスコンティ、テクノロジーに頼らずやることがひとつのテーマだった。ちなみにドラマーは、初期のサンズ・オブ・ケメットでも叩いているセバスチャン・ロッチフォードである(良い人選だ)。
ザ・クラッシュのファンにはよく知られている話だが、シムノンは歌がうまいわけではない。が、あの “ガンズ・オブ・ブリクストン” のぶっきらぼうな歌い方で先述したようなポップスをしかも女性といっしょに歌うのは、これはこれで趣がある。しかも彼はこんな歌詞の歌を歌っているのだ。
家をたたんでこの街を出ていく
バイバイと手を振って
家賃がとんでもなく上がってしまった
ここにはもう誰ひとり住んでいない
みんないなくなってしまった
Oh 小さな町よ
心を失ってしまったんだね
“ロンリー・タウン”
音はレトロだが、歌詞はたったいま起きていることを正確に捉えている。ポール・シムノンは自分が昔、パンク・バンドにいたことからまったく逸れていない。我が友よ、ほかにも良い歌詞があるので、これは対訳付きの日本盤で聴いて欲しい。また、考えてみれば、男らしいバンドの代表格でもあったザ・クラッシュの元メンバーがこうして男女のデュオをやるというのも、いまの時代に対応していると言える。
アルバム・タイトルの『私たちは明日をあらたな日として迎えることができるのか?』は、ダブルミーニングではないのだろうか。ひとつは将来への不安を意味し、音楽を聴いていると明日=未来など要らない(no future)と言っているようにも思えてくる。未来の都市、最先端のテクノロジー、いまこの社会が進行していった場合の明日、そこにどんな幸せな夢があるというのか。言っておくけれど、テクノ・ミュージックの始点をデトロイトにするなら、それは安価なテクノロジーで制作された音楽のことで、高価で最先端な環境で作られたそれを意味しない。
好奇心旺盛な20代〜30代のリスナーに、この音楽をゴリ推しするつもりは毛頭ない。だが、憶えておいて欲しいことはある。ザ・クラッシュというパンク・バンドが、偏差値の高そうな連中相手に社会(ときには左翼的なヴィジョン)を語るのではなく、定職にも就かず朝からビールを飲んでいるような連中相手に語っていたこと、それもかなり一生懸命に。そしてバンド内でもっともハンサムだったベーシストは料理が上手で、とくに得意なのは本人いわく「パエリア、スパゲッティ・ヴォンゴレ、マヨルカ島の魚のスープ」……という話はいいとして、革命は必ずしもテレビ(写真)には映らないということを。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE