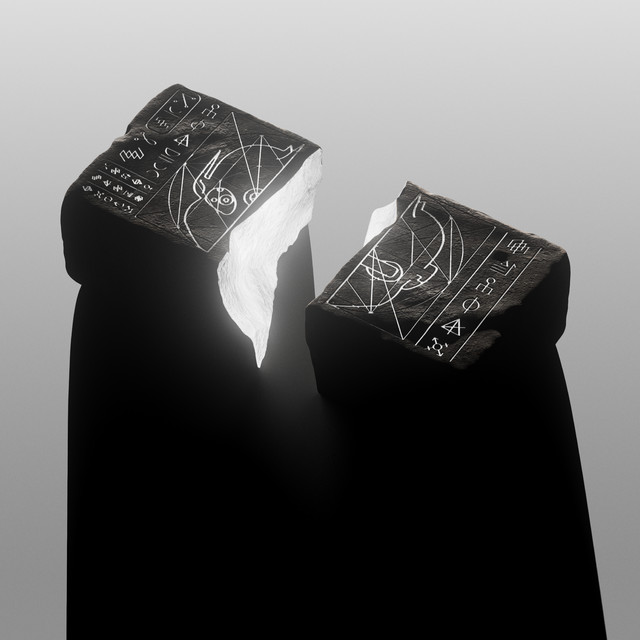MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Lost Souls Of Saturn- Reality
かならずしもロマンティシズムや冒険心、好奇心ばかりが宇宙を目指すとは限らない。サン・ラーがもっともよく体現していたように、地上=現代社会に嫌気がさしている者たちのユートピアのメタファーとしてもそれは機能する。宇宙とはいわば外部だ。X-102の影響だろうか、いきいきとしたダンス・テクノを打ち鳴らすロスト・ソウルズ・オブ・サターン、「土星の失われたソウル」を名乗るデュオもまたそうしたフューチャリズムの可能性に賭ける挑戦者のひと組だ。
メンバーはセス・トロクスラーとフィル・モッファのふたり。この名義としては2017年に〈R&S〉からデビュー、2年後にはセルフ・タイトルのファースト・アルバムを同レーベルから送り出している。が、けして若手というわけではなく、それぞれがすでに短くないキャリアを歩んできている。
00年代から活躍するミシガン州レイクオリオンのトロクスラー(ベルリン拠点との情報もあり)は若くしてDJの才を発揮、2015年の時点で名物シリーズ『DJ-Kicks』を手がけるなどすでに確固たる地位を築いている。デトロイトに住んでいた時期もあったようで、そのときできたつながりだろうか、ヤング・セス(Young Seth)名義で〈FXHE〉のコンピに参加していたりオマー・Sとコラボしていたり。〈Visionquest〉や〈Play It Say It〉、ブラックとヒスパニックのための〈Tuskegee〉といったダンス・レーベルを主宰してもいる。タスキギーとはアラバマ州の市で、活動家のブッカー・T・ワシントンやらローザ・パークスやら悪名高い人体実験やら、合衆国黒人の歴史と切り離せない固有名詞だ。トロクスラーに現代社会にたいする問題意識があることは疑いないだろう。
デュオのもうひとり、フィル・モッファはNYのDJ/プロデューサーである。彼のほうもまたすでに中堅と呼ぶべきキャリアを築いていて、ブッチャ(Butcha)名義はじめさまざまな別名やグループで多くのリリースを重ねている。ようするに、テクノ/ハウスの実力者2名によるコンセプチュアルなユニットがこのLSOSというわけだ。
初っぱなから展開されるスペイシーなシンセに顕著なように、ファースト・アルバムを特徴づけていた宇宙的なムードはこの第二作にもしっかり引き継がれている。ダブ×ジャズ×インド音楽のみごとな折衷を響かせる2曲目 “Scram City” は最初のハイライトだ。ブラック・ミュージックの大いなる遺産を惜しみなく活用するこの曲では、シタールの乱入が宇宙的想像力をブラック以外にひらく役割を果たしている(奏者はラヴィ・シャンカールの最後の弟子だというリシャーブ・シャルマ)。
イーヴン・キックのうえをジェフ・ミルズ風の旋律の反復、加工された声、ヴィデオ・ゲームの効果音のような断片が駆け抜けていく “This Foo” もかっこいい。どこか気だるげなヴォーカルの裏でブロークンビートが暴れまわる “Click” の終盤にはオーガスタス・パブロを想起させるピアニカが仕込まれている。80年代ニューウェイヴっぽい “Mirage” も独特の余韻を与えてくれたりと、いろんな趣向が凝らされたアルバムだ。
ぼくのリスニング能力ではちゃんと歌詞を聴きとれないのが残念だけれど、どうやら本作には反資本主義のテーマが搭載されているらしい。なるほど、たしかに資本主義は奴隷制=人種差別を基盤に発展してきた。だから、その延長線上にある現代社会とは異なる宇宙を想像してみようじゃないか、と。
たいせつなのは、そうした重めの主題をあくまでダンス・ミュージックで探求しているところだろう。テクノやハウスがただ快楽をもたらすだけでなく、世界にたいする違った見方を与えてくれる音楽でもあることをLSOSはあらためて確認させてくれる。多様な電子音楽が生み出されている昨今だからこそ、こうした力強いダンス・テクノがいまなお生きつづけていることを忘れずにいたい。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE