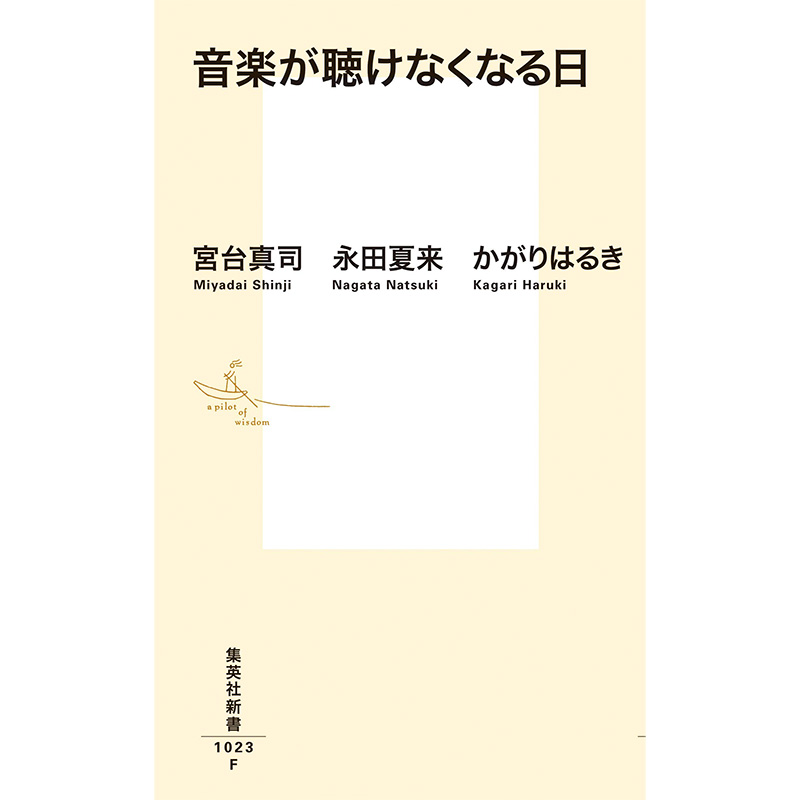MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 音楽が聴けなくなる日- 宮台真司、永田夏来、かがりはるき(著)
ぎょっとするタイトルだ。音楽が聴けなくなる日。それはストリーミングなる形態がはらんでいる大きな問題のひとつで、グローバル企業なりレコード会社なりがひとたび「これは消す」と判断してしまえば、あるいはその運営主体が消滅してしまえば、ぼくたちは音楽を聴くことができなくなる。2019年3月13日のあの日、フィジカル盤を持っておくことの重要性に気づいたひとは少なくなかったのではないだろうか。
社会学者の宮台真司、永田夏希、音楽研究家のかがりはるきによる共著『音楽が聴けなくなる日』は、ピエール瀧の逮捕後に起こったソニーによる電気グルーヴ作品の出荷停止や在庫回収、配信停止に触発されて書かれた本で、その背景や経緯を知るのみならず、「自粛」の奇妙さ・不気味さに気づくためのヒントに満ちあふれている。
いちばん読みやすいのはかがりによる第二章「歴史と証言から振り返る「自粛」」だ。アーティストがパクられたときにその作品などを「自粛」する慣習がいつからはじまったのか、時系列で確認できるようになっている。興味深いのは、起点のひとつが89年の BUCK-TICK に設定され、もうひとつの起点が99年のマッキーに置かれているところ。ご存じのように、89年は昭和天皇が「崩御」した年であり、99年は平成天皇の即位10周年を祝う式典が催された年だ。電グル騒動が発生した2019年もまさに代替わりの年にあたるわけで、「自粛」運動が天皇制とリンクしている可能性をあぶりだしたことは、本書の慧眼のひとつと言える。
その電グル騒動を具体的に追ったのが永田による第一章「音楽が聴けなくなった日」だ。「自粛」運動がとくにポリシーにもとづいて為されたものではないこと、たんに機械的に前例を踏襲しただけのものであること、すなわち思考停止の結果であること、たちの悪い「ことなかれ主義」であることが、社会学の知見を用いつつ丁寧に解き明かされていく。暴力的にまとめてしまえば、ようするにみんな他者の目線を気にしすぎでしょうよ、という話だ。そしてそれこそがいまの日本社会ないしは「(液状化した)近代」(バウマン)の性格でもあるだろう、と。
この章でひとつだけ気になったのが、何度かエクスキューズ的に挿入される「法令を守るのは当たり前のこと」という記述だ。そう書いてしまうと、法令で決まっていることはなんでもかんでも正しいとみなす、現代日本社会のそれこそ「ことなかれ主義」を追認してしまうことになりかねないのではないかしら、とちょっと心配になったのだけれど、その伏線は第三章でしっかり回収されることになる。
先日 Zoomgals のMVへの出演で話題をさらった宮台真司、彼による第三章「アートこそが社会の基本だ」こそ本書の核を為している。法なんてものは統治の必要から制定されているにすぎず、したがって「仕方なく」しぶしぶ従うものであり、間違っても道徳などではない。それに、人間や人間が生み出す芸術や表現はもっと大きなもので、法なんかにはとうていおさまりきらない──ゆえに、悪影響があるとか犯罪者だからといった理由で作品を封印する措置に、合理性は1ミリもない、という話。
と、これまた強引にまとめてしまったが、やはり宮台節──論理展開とそのスピード感──それじたいも、この章の醍醐味だろう。たとえば、作者と作品の関係性について。「作者と作品は別物」というのはよく言われることだけれど、その根拠を彼は、人間が必ずしも主体ではない点にもとめている。表現とは「降りかかってくる」ものであって主体がつくったものではない、ゆえにその主体に貼られたラベルは作品と関係がない──というロジックで、まさしくこれはシュルレアリスムの「オートマティスム」からロラン・バルトの「プンクトゥム」まで、数々の文学的思考によって実践されてきたことだ。
浩瀚な知識と卓越した整理──なんて書くと凡庸なコピーみたくなっちゃうけど、じっさい電グルを出発点に、1万年以上まえの人間の営みまで参照されるからおそろしい。『負債論』にせよ『サピエンス全史』にせよ、ここ10年ほど巨視的な観点から現在の状況をとらえ返す書物が目立つが、宮台もまたその流れに乗っているとも言える。ミクロに考えることに慣れすぎてしまうと見えてこないものは、たしかにある。
正直、彼の天皇主義者的な部分や安倍支持・トランプ支持にはまったく賛同できない。でも、彼が「このクソみたいな社会を変えたい」と本気で思っていることは間違いない。端的に、情熱がある。彼のことをなんとなくのイメージで毛嫌いしているひとはかなり多いと思われるが、しかし宮台はシニカルでもなければニヒルでもない。ストレートに、かなりアツい人間なのだ。地に足がついているというか、研究室で仮説を組み上げるのではなく(いやそれもやってるんだろうけど)、「そんなことまで?」と驚くほど多くの地道な作業を積み重ね、クソに抗おうと奮闘している(電グル騒動にいちはやく反応したのもそうだし、Zoomgals のMVへの出演だってその一例かもしれない)。そしてなにより彼は、その思考を一般に向けて開こうとしている。頭がいいだけの連中ならいくらでもいる。だが閉じないひとはそう多くない。そういう意味で彼は、かつて主流ではなかったテクノを一般の人びとへと開いた電気グルーヴと、共振しているとも言えるだろう。
音楽が聴けなくなる日──彼のような存在がいるかぎり、あるいはあなたがそのような知的営みに手を伸ばすかぎり、けっしてそんな日は訪れないのかもしれない。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE